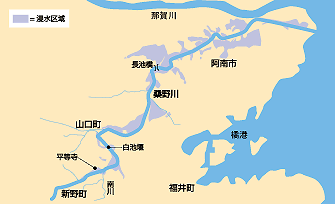平成11年6月29日、徳島県阿南市を流れる桑野川が増水して新野町で越水、住宅街は新聞紙上で「町全体が川になった」と報じられたほど、一面の水浸しとなった。 この日は活発化した梅雨前線の影響により、九州北部や中国・近畿地方など西日本各地で早朝から局地的な集中豪雨となり、徳島県でも午前中から激しい雨に見舞われた。四国霊場第22番札所の平等寺から東に300 mの地点にある新野雨量観測所の観測では、降り始めの29日午前3時から翌30日午前1時までの総雨量が329 mmに達している。人的被害こそなかったものの、市の中心部を通る国道55号が富岡地区で浸水のため通行止めになったのをはじめ、桑野川流域で、床上浸水79棟、床下浸水491棟などの大きな被害を受けた。 約30戸の住宅が床上浸水した新野町では、新野保育所が軒下まで水没してしまった。所長の松田英美さんによれば、「雨は午前9時過ぎから降り始め、わずか15分くらいの間に急に南川の水位が上がりました。大雨・洪水警報が出された午前10時40分、子供たちを迎えに父兄に来てもらったんですが、その時は水がひざ上まで達し始めていました。保護者がすぐに迎えに来られない園児5人と職員15人が、近くの新野市民センターに避難した時には、もうお腹の辺りまで水が来ていました」という。被災後、保育所はすぐには復旧の見通しが立たず休園、園児らはしばらくほかの保育所に通うことになった。 また、新野町旧平等寺橋左岸に住む浜口愛さん宅は川縁からわずか3軒目。堤防を越えた水が流れ込み、床上浸水の被害を受けている。「川の水の増え方はすごく、軽トラックやドラム缶がどんどん上流から流れてくるほどでした。堤防を越えるのは時間の問題と思い、1階の家財道具をできるだけ2階に上げたんですが、案の定、階段の4段目まで浸水。私らもいったんは2階に上がったものの、家ごと流されるかも知れないという不安から平等寺へ避難しようと、大人4人で手を繋いで外に出ました。でも、あまりに水の流れが急で前に進めず、すぐ家に戻りました。家族には年寄りもいたので本当に怖かった」と当時を振り返る。
今回、桑野川の下流に当たる長生町の大原水位観測所では、水位が6.19 mにまで上がり、昭和47年に開設して以来最高の数値を記録している。堤防が危険な状態となる「計画高水位」の6.27 mまで、わずか9 cmという増水量だった。 桑野川流域は、これまで水害とはあまり縁のない地域であった。しかしここ2年間は、降り始めからの総雨量が338 mmを記録した平成10年5月16日の集中豪雨、同じく総雨量が273 mmに達した9月22日の台風7号と相次いで洪水に見舞われ、今回と同規模の被害を受けている。13か月半という短い間に3度も大きな浸水被害を受けたわけだが、いずれも桑野川上流部での川の流下能力をはるかに超える記録的な集中豪雨だったことが大きく災いしたといえる。 しかし流域住民からは、最近、川の流下機能が低下したことを指摘する声も挙がっている。以前も大雨は降ったが、被害はなかった。近年の洪水被害は、川底に溜まった土砂や茂った樹木、雑草のせいで、水が流れにくくなっているからだという。 松田英美・新野保育所長は「30年くらい前までは皆の川という思いが強く、よく奉仕作業で川さらいなどをしていましたが、最近は何もかも税金でやってもらおうと考える人が多くなったように思います。皆で自然を守ろうという意識が薄れてきているのでは」と話している。保育所では、絵本などを使って自然の大切さをまず子供たちに教え、子供を通してその家族にも伝えていきたいとしているが、現状はなかなか難しいようだ。
桑野川の河川改修事業は、県管理区間では9.75 kmについて昭和31年度から開始され、このうち約8 kmについては河床の掘削を残して暫定改修を終えている。残区間の最下流にある農業用取水堰の可動堰化については、地元住民の理解を得るのに時間がかかっていたが、洪水の堰上げによる越水で浸水被害を受けたことから、早急に改築するよう要望が出されてきた。また、改修区間の住民からも早急に河川改修を促進して欲しいという気運が高まってきた。 そうした住民の意向を@んで、平成11年11月、国と県は、平成11年6月規模の洪水に対して再度災害防止の観点から、93億円の予算をもって河川災害復旧等関連事業などを実施することとしている。下流直轄区間については、そのうち52億円で川幅を拡げるなどの改修事業を実施することとした。また県管理区間では、無堤部分の解消と河道掘削の工事に41億円余りを割り当て、おおむね4年間で完成させることを決めた。 この事業に伴い、前出の浜口さん一家は川側の2軒が引堤工事のため移転することになったため、今度は最も堤防の近くに住むことになる。浜口さんは「全く不安がないわけではないが、今までのような心配はしなくて済む。ありがたいこと」と、一日も早い工事の完成を待ち望んでいる。 |
|||||||||||||||||||||||||||