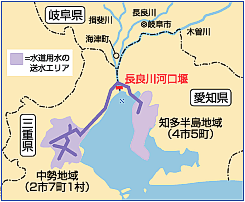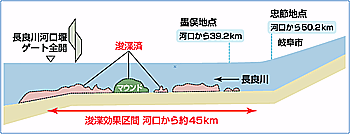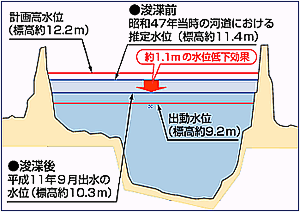|
|
|
|
|
| 岐阜市内では長良川の水が道路に溢れ、約700人が避難した
|
|
|
木曽・長良・揖斐の木曽3川の下流域に行くと、現在も「輪中(輪中堤)」が見られる。江戸時代の人々が、水害から住居や田畑を守るために集落全体を堤防で囲った名残りで、この地域に住む人たちの洪水との闘いの歴史を物語る貴重な資料となっている。
明治時代の河川改修で水害は大幅に軽減されたものの、昭和34年9月の伊勢湾台風では岐阜、愛知、三重の3県で5000人を超す死者・行方不明者を出すなど甚大な被害を受けた。その後も、昭和35年8月には台風11・12号によって、同36年6月には梅雨前線と台風6号によって、同51年9月には台風17号と前線によって、長良川の本堤が決壊し大洪水に見舞われている。
輪中のある下流域はもともと土地が低く、海抜ゼロメートル地帯も多い。水位が上がると水面は家のひさしの高さにまで達するため、いったん破堤すると被害は大きい。
そのためこの地域では、町や村を守る組織として消防団のほかに、水害に対処する水防団が欠かせない存在になっている。輪中の歴史が一目で分かる歴史民俗資料館のある海津町と、その隣の平田町を囲う高須輪中を管轄するのが高須輪中水防団(森正夫団長)だ。
大雨や台風の際には長良川と揖斐川の堤防を監視し、水漏れなど非常事態が発生すると、水防の長い歴史の 中から生み出された昔ながらの工法を駆使して町を守っている。
|
|
| 輪中独自の水防の歴史の中から編み出された「月の輪工法」の訓練をする高須輪中水防団の団員たち
|
|
|
前身は昭和33年に結成された高須輪中水害予防組合で、昭和51年の水害を機に100人を増員、現在207人の団員を抱える大所帯となっている。 水防団には、いざという時のための訓練が欠かせない。「毎年5、6月の末には団員そろって水防演習に参加して、昔から伝わる工法の訓練を受けるんですが、ほとんど欠席者はいない」(森団長)と皆熱心なようだ。
工法は月の輪工法など数十種類もあり、それぞれ異なる機材、道具を使わなければならない。近年は他地域から転入してくる人も少なくなく、工法そのものを知らないため、道具の選び方・使い方など基礎的な訓練がより重要になってきたという。
その長良川に平成7年7月、下流域の住民が待ち望んだ河口堰が完成した。浚渫(河床の掘り下げ)に伴う塩水の逆流防止(治水)と、水道用水・工業用水といった水資源の開発(利水)を目的としたものである。
|
|
| 沿川住民のための治水と利水を目的に平成7年7月に運用を開始した長良川河口堰
|
|
|
河口堰の完成に伴う浚渫の効果は、平成11年9月、台風16号とそれに続く18号の襲来の際に遺憾なく発揮された。台風16号は、日本海に停滞していた前線を刺激し、9月14日から15日にかけて九州から東北南部の広いエリアで大雨を降らせた。岐阜県内でも山間部を中心に局地的な豪雨となり、特に長良川上流域では、14日の日降水量が白鳥町で179
mm、高鷲村で197 mmを記録。降り始めから15日17時までの雨量でも、それぞれ448 mm、527 mmに達している。 このため長良川は大増水し、白鳥町などで堤防決壊や道路・家屋の冠水があったほか、岐阜市内でも川の水位が上昇、長良橋が通行止めになって周辺の約430世帯に避難命令が出るなどしたが、下流域では危険水域まで水位が上昇することはなかった。
森団長は「河口堰が造られ浚渫が終了した後は、それ以前と比べて水位の上がり方が明らかに違っています。我々は経験上、上流の降雨量から下流にどのくらいの影響が出るかが分かるものです。あれだけ大きな被害を出すほどの激しい雨が降れば、今までなら下流も相当な水位に達しているはず。今回もそうでしたが、この2年間は上流でかなり雨が降っても、水位はあまり上がりません」と証言する。
海津町成戸地区の水位計は、水位によって警戒水位・出動水位を示すことができる。しかし、この2年間は一度も警戒水位には至っていないという。
「河道の浚渫で水の流れが良くなったおかげ。平田町、海津町の住民のほとんどがそう思っています」と森団長は言う。 中部地方建設局木曽川上流工事事務所では、雨の降り始めからの長良川の出水状況の調査を進めてきた。同事務所によると、台風16号襲来時の推定最大流量は、河口から39.2
km地点にあたる岐阜県安八郡墨俣町付近で、約5900 m3/s(速報値)となる。これは河口堰が本格運用されて以来最も多い数値で、浚渫前の昭和47年当時の河道との比較では、同じ地点で今回と同じ流量が流れたと仮定すると、約1.1
mの水位低下があったと推定される。 また、墨俣地点の水位が警戒水位を超えた時間で比べると、浚渫前には20時間だったのが、浚渫後は推定で9時間に短縮されていることが分かった。河口堰の整備に伴う浚渫には、このように水位の低下だけでなく、高い水位が継続する時間を短くする効果もあることが実証された。
森団長も「これで我々水防団の責任も軽くなりました」と口元をほころばせるが、同町には揖斐川も流れている。住民にとっては、この川の安全も同様に切実な問題。堤防の強化とともに、上流の新たな徳山ダムの早期完成が待ち望まれている。
|