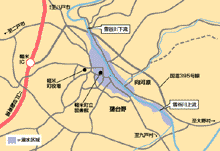|
平成11年10月28日、八戸市同様、岩手県内でも軽米町を中心に家屋の浸水被害などが発生した。年間の降雨量 が1000 mmという全国でも雨の少ない軽米町だが、28日は1日で230
mm、昭和20年に記録した134 mmを2倍近く上回る大雨となった。 このため町の中心部を流れる雪谷川が午前8時過ぎから増水、午後2時過ぎには昭和橋付近で氾濫し、道路は大人の腰の高さまで冠水した。上流から流れ出した大量
の流木などが橋の橋脚に絡まって、流れを塞き止めたためだ。 上流には総貯水量 266万m3の雪谷川ダムがある。これは灌漑と防災のためのダムで、約50年に一度の日降雨量
約122 mmを想定して設計されている。しかし、午前10時頃には貯水能力を超える雨水が流れ込み始め、水はダムを乗り越えて%れ続けた。
|
|
| 水が引いた後の図書館内。1万冊以上の蔵書が被害を受けた |
|
|
|
もともと雪谷川には堤防はなく、川岸ぎりぎりまで住宅や商店が立ち並んでいる。昭和橋に最も近いロ台野地区の住民によると、「10分くらいで背丈まで浸水した。家財道具を運び出す間もなかった」というほど増水のスピードは速かったという。町で唯一の図書館でも、水は見る間に床上40
cmに達し、約3万5000冊の蔵書のうち1万冊以上が水浸しになってしまった。
町の災害対策本部は、28日午前10時15分には約1250世帯に避難勧告を出している。対応そのものは決して遅くはなかったが、増水の速さはそれを上回った。平成10年の大規模山林火災で保水機能が失われたことも、その速さにmがったとの指摘もある。近年、それまであまり自然災害の少なかった地域でも、気象の変化や山の保水力の低下などによって起こる水害が増えているが、雪谷川もこれまでこれ程大規模な氾濫はなかった。今回の被害規模は住家被害で全壊25棟、半壊5棟、床上浸水446棟、床下浸水137棟。公共部門を加えた被害総額は260億1734万円に上り、町の予算の約4年分に匹敵するものとなった。こうした甚大な被害に対し、岩手県では再度災害を防止するため雪谷川の抜本的改修を行うこととしている。
|
|
| 昭和橋に流木などが溜まったため午後2時頃には雪谷川が溢れ、大きな被害を出した向川原地区 |
|
雪谷川の改修は、軽米町の横井内から萩田までの下流部3.69 km区間を河川災害復旧等関連緊急事業として、また、軽米町萩田から九戸村雪屋までの中・上流部14.63
km区間を災害助成事業で実施。併せて護岸21万7000 m2と河道掘削、橋梁25等の工事が、4
ミ 5年という短期間で行われる。下流部は平成14年度、中・上流部は15年度完成予定で、出来上がれば下流部から中流部は30年に一度、上流部は10年に一度の大雨に耐え得る流下能力を持つことになる。
こうした県の取り組みに対し、軽米の住民も「安全な町づくり」への参加に向け積極的に動き出した。その手初めとなったのが、「がんばろう軽米」講演会実行委員会が12月22日、岩手大学の平山健一工学部長を招聘して開催した「10・28豪雨水害の検証とこれからの安全な町づくり」と題する講演会である。講演会は軽米町pta有志や新井田川ネットワークなどが後援し、治水・利水だけでなく、軽米にふさわしい河川のあり方、また、地元住民の意思を正確に伝えるために、工事主体者である県との交渉の進め方などについて話し合われた。
この会の実行委員長を務めた山本賢一さんは、軽米町で最も被害の大きかった向川原地区の住民の1人。今回の改修では、全体で150戸以上の民家が移転することになるが、向川原地区では150戸の住宅のうち山本さんの家を含む80戸が立ち退くことになる。しかし、山本さんたちは「危険と隣り合わせで住むことを考えれば改修はやむを得ない。ただ、川は治水さえできればいいわけでもないので、私たちは復旧プラス将来に希望が持てるような河川改修にして欲しいと考えている。具体的な取り組みはこれからなので、平山先生にも相談しながらいろいろ勉強し、行政と一緒により良い川づくりを進めていきたい」と住民参加の河川改修に意欲的だ。
一方、県側も住民の意見をできるだけ反映させるため、住民代表をはじめ学識経験者、地元有識者から成る「雪谷川河川整備懇談会(仮称)」を平成12年3月中に設置する予定だ。また、これらのハード対策とともに、ソフト面
でも洪水時に迅速な対応ができるように、洪水ハザードマップの作成を支援。きめ細かい避難情報・避難経路、病院などの弱者を含めた避難誘導方法が特に重点的に記載されることになっている。
| stories from disaster
victims |
【被災者体験談】
|
|
|
牧野開発続いた20年
自然と共生できる河川改修を
|
|
|
「がんばろう軽米」講演会実行委員長 山本賢一さん
|
| 雪谷川の氾濫によって軽米町は各所で浸水被害を出しましたが、私が住んでいる向川原は、特に被害が大きかった地区の1つです。我が家はまだ被害の小さいほうでしたが、それでも床上40
cmの浸水に見舞われ、2日間の避難生活を送りました。もともとこの辺りは雨が少なく、水害の少ない地域でした。こんなことは昭和33年の大雨以来の出来事だということです。
私は獣医師で、牛や馬を診るため日々畜産農家を回っていますが、以前からとても気に掛かっていたことがあります。それは、ちょうど20年前私が越してきた頃から雪谷川流域で牧野開発(山を削って牧場にする)が始まり、それ以来、少し雨が多く降ると鉄砲水が出て、小規模な氾濫が起きていたということです。
また近年では、ゴルフ場やスポーツ施 |
設が出来たり、平成10年には大規模な山火事がありました。これら1つ1つは大したことではないかもしれませんが、流域全体で見ると、やはり森林生態系に見られる涵養機能が落ちていると感じざるを得ません。今回の集中豪雨による被害の大きさも、こうしたことと無関係ではないように思われます。
この度、雪谷川の河川改修が行われることが正式に決まりました。住民の安全な暮らしを考えれば、改修はやむを得ないことと考えています。
ただ雪谷川はその90 %以上が軽米町内を流れており、軽米の住民にとってこの川は生活と切っても切れないものです。改修をするにあたっては、自然との共生や住民参加を視野に入れながら進めていただきたいと考えています。 |
|
| |
|