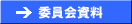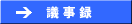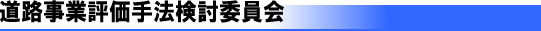
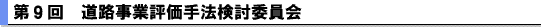
| 日 時 | : | 平成16年5月14日(金)13:00〜14:30 |
| 場 所 | : | 国土交通省4F特別会議室 |
| 議事次第 | : | 1.開会 |
2.議事
| (1) | 道路事業・街路事業に係る総合評価手法について |
| (2) | 高速道路を対象とした総合評価について(報告) |
| (3) | その他 |
|
| 3.閉会 |
|
委 員 長
| ○ |
森地 茂
|
東京大学大学院工学系研究科教授
|
|
|
委員長代理
| |
小林 潔司
|
京都大学大学院工学研究科教授
|
|
|
|
|
|
|
|
|
委 員
| ○ |
林山 泰久
|
東北大学大学院経済学研究科助教授
|
|
|
委 員
| ○ |
山内 弘隆
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
|
|
|
○は出席した委員
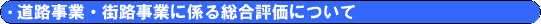
| |
道路事業・街路事業に係る総合評価については、ケーススタディ結果として、平成16年度新規採択事業及び平成15年度再評価実施事業の45路線の分析結果を提示した。なお、今回の分析は途中段階のものであり、今後、指摘のあった意見も踏まえ、さらに分析を深めるべきとされた。
○分析結果について
(委員の主な意見)
| ・ | 評点のバラツキから「有意な差が見られる」と記述されているが、判断基準を明確にする必要がある。正規分布となるのが望ましいのか、一様分布となるのが望ましいのか。 |
| ・ | ヒストグラムについて、バラツキがあるのは必要条件であり、十分条件ではない。有意な差については、例えば実務担当者が指標の結果を何も見ずに感覚として点数をつけた場合と、今回のルールによる点数のバラツキが類似している、等の検証方法があると思われる。 |
| ・ | また、今回のデータのみで判断した場合と、現場の状況を加味した上で判断した場合の差等についても、検証する必要がある。 |
| ・ | 「客観的な効果の確認に基づく指標」について、チェック項目を見ると、主観的なものも含まれている。恣意的になってしまうのではないか。 |
| ・ | 評価結果について、0点〜5点で設定されているが、0点の意味を知りたい。(数字が無い場合や該当しない場合を0点としている旨、事務局より説明。なお、今回の評価では、マイナス評価も有り得るので、0点が必要である旨、事務局より説明) |
○論点2(複数の効果の統合)及び論点5(大項目単位の統合)について
(委員の主な意見)
| ・ | 公共交通の指標では、最大値による評価をしてしまうと、バス/鉄道/空港のうち、バスの影響が6〜7割を占めてしまうことになるが、よいのか。(鉄道[新幹線駅]や空港は、事業箇所の近くに該当するものが存在しないケースが多いため、結果としてバスの影響が大きくなるのは実態であると考えている旨、事務局より説明) |
| ・ | 「最大値」による評価では、最大でなかった他の要因が考慮されないこととなってしまうため、反対である。むしろ合計値等が望ましいのではないか。(一般道路事業の場合、全ての効果を目指すものではない場合が多い。空港近くの事業は空港のためのであり、鉄道駅近くの事業は鉄道のためのものとなる。合計値は、すべての効果が必要となってしまい、却って不公平になってしまうと考えられる旨、事務局より説明。) |
|
○ | 論点3(事業規模による基準化)及び論点4(人口規模による基準化)について |
(委員の主な意見)
| ・ | それぞれの順位相関図を見ると、上位と下位のものは45度線上にあり、事業規模や人口規模で基準化しても大きな影響はないと考えられる。しかし、中間順位ではバラツキが見られる。採択基準はどのあたりを想定しているのか。 |
| ・ | 人口規模による基準化では、通過市町村人口で基準化しているとのことであるが、市町村の周縁部をかすっている場合などはどのように考えているのか。(今回のケーススタディでは、作業量の低減も考慮しているため、行政単位で行った。データ精度が低いことは認識しているが、メッシュデータ等によって精度を上げると、実務の作業量が膨大となってしまう。バランスが大事だと考えている旨、事務局より説明。) |
| ・ | 事業規模による基準化を行う際には、事業費と効果が線形の関係にあるという前提が必要になるのではないか。(異なる事業間では線形の関係にはないかも知れないが、同一事業の中では線形になることが明らかである旨、委員長より説明。) |
| ・ | 順位相関図において、45度線から外れているものについては、どのような種類の事業なのかを分析する必要がある。 |
| ・ | ある程度相関が見られるとして、実際のボーダーを縦線で設定するのか、横線で設定するのかで、順位がばらつくものもあるので、明確に決める必要がある。 |
○事業課・整備局・地方公共団体への意見照会について
(委員の主な意見)
| ・ | 分析を深度化した上で、自治体等への意見照会を行うとのことであるが、今回のケーススタディ事業を対象とするのみでなく、各事業主体個々の対象プロジェクトで検証してもらってはどうか。 |
|
|
|
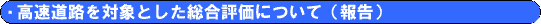
| |
高速道路を対象とした総合評価について、報告書としてのとりまとめを行った旨、事務局より報告が行われた。
提示された報告書は一度持ちかえっていただいた上で、後日意見のある場合は、事務局まで連絡いただくこととなった。
なお今後、意見を踏まえて最終的な報告書として製本することとされた。
(委員の主な意見)
| ・ | 4章で整理されている意見と課題については、2〜3章で示している手法の開発に反映されているものもあるので、その点を明記しておく必要があるのではないか。(4章の冒頭に記述してあるが、別途フロー図を挿入する等、わかりやすくする旨、事務局より報告) |
| ・ | P26〜27に示されている「高速自動車国道の事業評価フロー」は全体の流れを示しているが、今回の検討作業がSTEP3に該当することを明記しておく必要があるのではないか。 |
| ・ | 評価主体は行政であるが、意思決定は国土開発幹線自動車道建設会議(国幹会議)で行われる旨は、明記しておく必要がある。 |
| ・ | 手法の開発について、本委員会での審議内容に基づいている旨、記述されているので、委員リストも入れておいた方が良いのではないか。 |
|
|
|
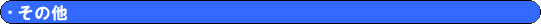
| |
 |
| ・ |
次回委員会の開催については、事務局より各委員の予定を確認して連絡。 |
|  |
以上
|
|
|

All Rights Reserved, Copyright
(C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
|
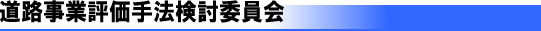
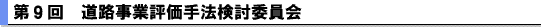
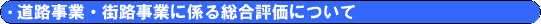
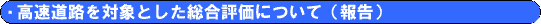
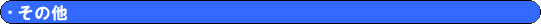

 第10回道路事業評価手法検討委員会
第10回道路事業評価手法検討委員会 第8回道路事業評価手法検討委員会
第8回道路事業評価手法検討委員会 第7回道路事業評価手法検討委員会
第7回道路事業評価手法検討委員会 第6回道路事業評価手法検討委員会
第6回道路事業評価手法検討委員会 第5回道路事業評価手法検討委員会
第5回道路事業評価手法検討委員会 第4回道路事業評価手法検討委員会
第4回道路事業評価手法検討委員会 第3回道路事業評価手法検討委員会
第3回道路事業評価手法検討委員会 第2回道路事業評価手法検討委員会
第2回道路事業評価手法検討委員会 第1回道路事業評価手法検討委員会
第1回道路事業評価手法検討委員会 道路局TOP
道路局TOP