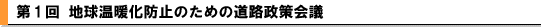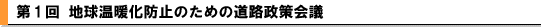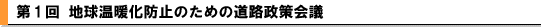
| 日 時 | : | 平成17年4月26日(月)15:00〜17:00 |
| 場 所 | : | 合同庁舎3号館4階特別会議室
|
| 議事次第 | : |
開会
1.主催者挨拶 |
| 2.地球温暖化防止のための道路政策会議 設立趣旨説明 |
| 3.座長挨拶 |
| 4.道路交通におけるCO2排出量の現状について |
(1)京都議定書発効に関する状況について
(2)京都議定書目標達成計画(案)について
(3)自動車交通からのCO2排出の推移について
(4)CO2排出の空間的分布状況について
(5)CO2削減のための道路政策及び効果について
閉会
(配付資料)
資料−1 地球温暖化防止のための道路政策会議設立趣意書
資料−2 道路交通におけるCO2排出の現状について
|
|
配布資料はPDFにて提供しております。 PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。
|
| ○ |
石田 東生(座長)
| |
筑波大学大学院 システム情報工学研究科教授
|
|
|
|
| ○ |
岡部 正彦
| |
(社)日本経済団体連合会 輸送委員会 委員長
|
|
| ○ |
黒田 博史
| |
(社)日本自動車工業会 交通委員会 委員長
|
|
| ○ |
中村 英樹
| |
名古屋大学大学院 工学研究科助教授
|
|
|
|
| ○ |
藤井 聡
| |
東京工業大学大学院 理工学研究科助教授
|
|
|
|
|
|
(敬称略、五十音順)
○は出席した委員
○主な議事概要
(1)データの分析について
| | ・ | 1990〜1997、1997〜2002間のCO2排出量の増減の要因別排出量の分析が必要。 |
| ・ | 三大都市圏以外の地方における効率の悪い地域の原因分析が必要。 |
| ・ | 効果の計測や推計手法についての議論が必要。 |
(2)CO2削減のための方法
ソフト施策
| | ・ | 人の車の使い方や交通行動の視点は重要(ユーザーの視点)。 |
| ・ | 日本人は環境への意識が高い。車の使い方によってCO2が削減されるという意識が低い分、改善の余地も大きい。 |
| ・ | アイドリングストップやエコドライブなどのソフト施策も考えることが必要。 |
| ・ | ロジスティクスでトラック貨物は減少傾向になるだろうから、今後は自家用車をターゲットにする必要がある。その点では、個々のライフスタイルが大きく影響する。自動車学校でエコドライブを教えるというのも対策の1つ。 |
| ・ | 地方に行くと自動車に頼らざるを得なくなる地域もある。公共インフラの整備の度合いを考慮した議論が必要 |
制度など
| | ・ | 環境税の問題も議論すべき。 |
| ・ | 低燃費車の導入の見通しは無視できない |
| ・ | 混雑料金や乗り入れ規制などのソフト施策も考えるべき。 |
| ・ | 現状の道路への満足度はある程度あるものの、交通渋滞の円滑化が最大の関心事。信号等の交通管制は警察の所掌であるが、幅広く議論し、その内容を警察にも伝えていくも1案。 |
(3)施策の進め方について
| | ・ | 焦点を定めないと話が広がりすぎ。 |
| ・ | プライオリティをつけて、どこまでやるのか焦点を決めるべき。 |
| ・ | ソフト、ハード両方が大事。ソフトで短期を考え、ハードで長期を考えるイメージか。意識行動の問題(自発的な行動変化)としてユーザー側の視点に立った検討をする必要がある。 |
| ・ | 2010年までの目標期間との関係もあり、短期施策と長期施策を分けて、両方を取り上げつつ、分けて整理する。 |

All Rights Reserved, Copyright
(C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
|