| 【指標−4】規格の高い道路を使う割合(中間アウトカム指標) |
|
現在の値 | : | 13% |
|
中期的な目標 | : | 平成19年度までに約15%とする |
|
平成15年度の目標 | : | 新たに約210万台キロの交通を自動車専用道路へ転換
(規格の高い道路を使う割合:13%) |
|
本指標については、平成14年度の13%を、平成19年度までに15%とすることを中期的な目標とする。(図4-1)
15%とすることにより、死傷事故数が約2万件/年減少、死者数が約100人/年減少し、CO2排出量も約120万トン/年が削減するものと試算される。
平成15年度は、1日あたり合計約22億台キロの交通量のうち、新たに約210万台キロの交通の自動車専用道路への転換を図ることを目標とする。
|
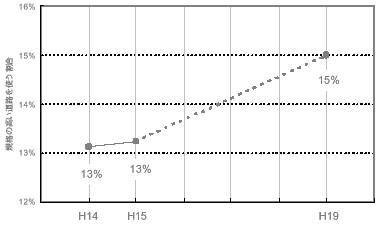
図4−1 指標の現況値と数値目標
|
【指標の定義・位置づけ】
「規格の高い道路を使う割合」は、自動車専用道路を利用する交通の割合を表す指標であり、具体的には、全道路の走行台キロに占める自動車専用道路の走行台キロの割合を表す。(「走行台キロ」とは、区間ごとの交通量と区間延長を掛け合わせた値であり、道路交通の量を表す。)
地域において20〜30%を占める長距離トリップが、事故率が低く走行速度の高い自動車専用道路によって分担されることで、幹線道路・生活道路など本来の役割に見合った機能分化の適正化が図られる。道路の本来の役割に見合った機能分化の適正化の度合いを表す中間アウトカム指標として「規格の高い道路を使う割合」を採用したものである。
【指標の示す目標】
規格の高い道路を使う割合の向上は、長距離トリップを担当する自動車専用道路への適正な機能分化が進展したことを意味する。これにより、都市圏における渋滞解消や環境負荷の軽減、一般道路における交通事故の減少等の様々な効果が期待されるものであり、1%の増加により、死傷事故数が約1万件/年減少、死者数が約50人減少し、CO2排出量も約60万トン/年削減するものと試算される。
1)機能分化されていない日本の道路
日本の「規格の高い道路を使う割合」は約13%と欧米諸国の約20〜30%に比べて著しく低く(図4-2)、さらには都道府県別では約3〜25%と地域間格差が大きいなど、道路(自動車専用道路・幹線道路・生活道路)の機能分化が進んでいないことがわかる。(図4-3、図4-4)
走行速度が高い自動車専用道路は、渋滞解消や環境負荷の軽減の能力が高いほか、死傷事故率がその他の道路に比べ約9分の1と安全な道路である。例えば、仮に「規格の高い道路を使う割合」がドイツ並みの約30%になった場合を試算すると、死者数は約900人の減少、CO2排出量が年間1,100万tの削減など多大な効果が見込まれるが、我が国はこの水準を大幅に下回っている。(図4-5)
自動車専用道路への適正な機能分化が図られていないため、長距離トリップの少なからぬ部分が一般道路を利用しており、渋滞や環境負荷、交通事故を増加させる一因となっている。
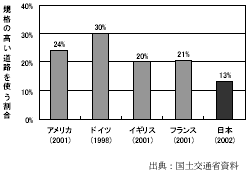 図4−2
図4−2
規格の高い道路を使う割合の諸外国比較
|
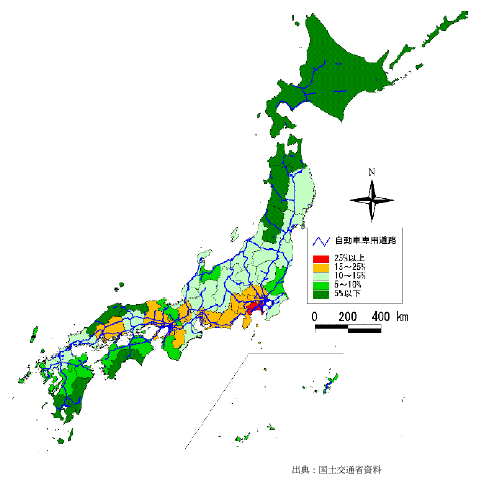
図4−3 都道府県別の規格の高い道路を使う割合
|
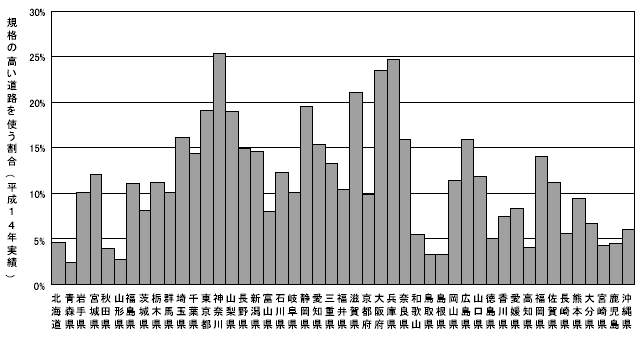 図4−4 都道府県別の規格の高い道路を使う割合
図4−4 都道府県別の規格の高い道路を使う割合
我が国の「規格の高い道路を使う割合」が低いことの理由としては、高規格幹線道路の整備率が最も低い県では25%程度と、地域によっては自動車専用道路ネットワークがまだ不充分であることや、有料でかつ利用料金が高額であるため、利用に障害があることが挙げられる。また、約10kmにも及ぶインターチェンジ間隔の長さなど、自動車専用道路の使い勝手が良くないことも原因である。(図4-6、図4-7)
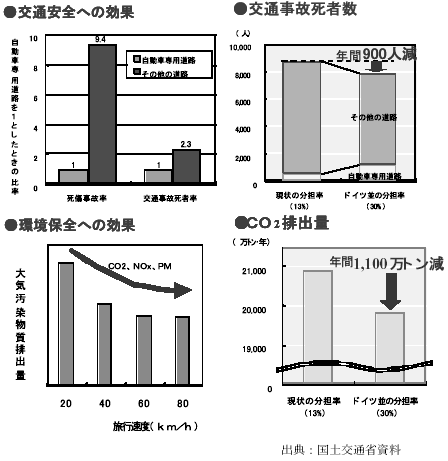
図4−5 規格の高い道路を使う割合の向上に伴う効果
|
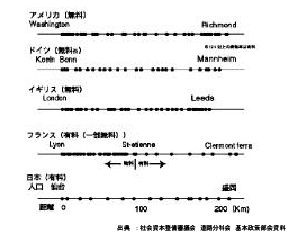
図4−6 諸外国と日本のIC間隔の比較
|
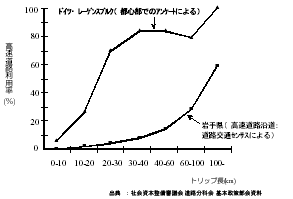
図4−7 トリップ長と高速道路利用率の関係
|
1)まだ不充分な自動車専用道路ネットワークの整備
高規格幹線道路の整備率は約60%、都道府県別では25%にすぎない地域があるなど、地域によってはまだ不充分な道路ネットワークの効果的、効率的な整備を進める。
| 【関連する施策・事業】 | 【関連する平成15年度の主な施策】 |
|
高規格幹線道路・地域高規格道路の整備 | 高規格幹線道路の整備
地域高規格道路の整備
ローカルルールの導入
|
2)諸外国に比べて高額な利用料金の緩和
我が国の高速道路料金は1km当たり24.6円と、無料であるアメリカ・ドイツ・イギリスや、1km当たり8円のフランスに比べて高く、また、画一的な利用料金体系となっていることから多様で弾力的な料金設定に向けた社会実験を実施する。
| 【関連する平成15年度の主な施策】 |
|
有料道路の料金に係る社会実験 |
3)長いインターチェンジ間隔の緩和に向けた検討
我が国の高速道路のインターチェンジ間隔は平均して約10kmに及び、ドイツ等の、高速道路が無料である国々の約2倍と長く、高速道路の使い勝手が悪いことが課題である。
長いインターチェンジ間隔の緩和に向け、ETC(ノンストップ自動料金支払いシステム)を活用した追加インターチェンジの導入に向けた検討など、必要な検討を実施する。
| 【関連する平成15年度の主な施策】 |
|
ETCを活用した追加インターチェンジの導入に向けた検討 |
1)都道府県別規格の高い道路を使う割合
| 区分 | 平成14年度
実績値 |
全道路走行台キロ
百万キロ/日 |
自専道走行台キロ
百万キロ/日 | 平成13年度
実績値 |
| 全国 | 13% | 2,167 | 284
| 13% |
都
道
府
県 | 北海道 | 5% (39) | 115.1(1) |
5.40(19) | 5% (40) |
| 青森県 | 3% (47) | 27.1(31) | 0.69 (45) | 2% (47) |
| 秋田県 | 4% (43) | 27.1(32) | 1.07 (41) | 4% (42) |
| 岩手県 | 10% (25) | 37.0(24) | 3.77 (25) | 10% (25) |
| 山形県 | 3% (46) | 30.7(28) | 0.87 (43) | 3% (45) |
| 宮城県 | 12% (18) | 44.7(21) | 5.41 (18) | 12% (18) |
| 福島県 | 11% (23) | 50.1(16) | 5.57 (16) | 12% (23) |
| 東京都 | 19% (6) |
103.4(3) |
19.80 (3) |
19% (7) |
| 神奈川県 | 25% (1) |
74.2(10) |
18.85 (4) |
26% (1) |
| 千葉県 | 14% (14) | 76.8(8) |
11.10 (9) |
15% (14) |
| 埼玉県 | 16% (8) |
87.9(6) |
14.24 (7) |
17% (9) |
| 茨城県 | 8% (31) | 69.5(11) | 5.66 (15) | 8% (32) |
| 栃木県 | 11% (21) | 48.7(17) | 5.52 (17) | 12% (22) |
| 群馬県 | 10% (27) | 45.8(19) | 4.62 (22) | 10% (27) |
| 長野県 | 15% (12) | 54.1(13) | 8.07 (12) | 15% (12) |
| 山梨県 | 19% (7) |
23.3(37) | 4.44 (24) | 20% (6) |
| 新潟県 | 15% (13) | 60.1(12) | 8.84 (10) |
15% (13) |
| 富山県 | 8% (32) | 26.4(34) | 2.13 (33) | 8% (31) |
| 石川県 | 12% (17) | 26.5(33) | 3.28 (28) | 12% (19) |
| 静岡県 | 20% (5) |
75.5(9) |
14.77 (6) |
20% (5) |
| 岐阜県 | 10% (26) | 52.3(15) | 5.29 (20) | 10% (26) |
| 愛知県 | 15% (11) | 113.1(2) |
17.45 (5) |
16% (11) |
| 三重県 | 13% (16) | 46.3(18) | 6.18 (14) | 14% (16) |
| 滋賀県 | 21% (4) |
34.9(25) | 7.37 (13) | 22% (4) |
| 京都府 | 10% (28) | 32.8(27) | 3.25 (29) | 10% (28) |
| 大阪府 | 23% (3) |
93.6(4) |
21.96 (1) |
24% (3) |
| 兵庫県 | 25% (2) |
88.1(5) |
21.68 (2) |
25% (2) |
| 福井県 | 10% (24) | 22.0 (41) | 2.30 (32) | 11% (24) |
| 奈良県 | 16% (9) |
20.7 (42) | 3.31 (27) | 17% (8) |
| 和歌山県 | 6% (37) | 20.3 (43) | 1.15 (39) | 6% (37) |
| 鳥取県 | 3% (44) | 16.0 (47) | 0.54 (47) | 2% (46) |
| 島根県 | 3% (45) | 19.6 (44) | 0.65 (46) | 3% (43) |
| 岡山県 | 11% (20) | 45.4 (20) | 5.21 (21) | 12% (20) |
| 広島県 | 16% (10) |
53.6 (14) | 8.53 (11) | 16% (10) |
| 山口県 | 12% (19) | 38.2 (23) | 4.54 (23) | 12% (17) |
| 徳島県 | 5% (38) | 19.2 (45) | 0.97 (42) | 5% (38) |
| 香川県 | 8% (33) | 22.3 (40) | 1.68 (35) | 7% (33) |
| 愛媛県 | 8% (30) | 29.6 (29) | 2.52 (31) | 9% (30) |
| 高知県 | 4% (42) | 18.2 (46) | 0.73 (44) | 3% (44) |
| 福岡県 | 14% (15) | 79.1 (7) |
11.13 (8) |
14% (15) |
| 佐賀県 | 11% (22) | 23.2 (38) | 2.62 (30) | 12% (21) |
| 長崎県 | 6% (36) | 24.7 (36) | 1.43 (37) | 6% (35) |
| 熊本県 | 10% (29) | 38.7 (22) | 3.69 (26) | 10% (29) |
| 大分県 | 7% (34) | 29.5 (30) | 2.02 (34) | 7% (34) |
| 宮崎県 | 4% (41) | 24.9 (35) | 1.09 (40) | 5% (39) |
| 鹿児島県 | 5% (40) | 33.7 (26) | 1.56 (36) | 4% (41) |
| 沖縄県 | 6% (35) | 22.6 (39) | 1.35 (38) | 6% (36) |
|
※ | 単位未満四捨五入のため合計が合わないことがある。 |
|
※ | カッコ内は順位、網掛けは上位10位以内の都道府県、下線は下位10位以内の都道府県を示す。 |
|
※ | 「道路交通センサス」(平成11年度)及び国土交通省調査結果(平成13年度及び平成14年度)並びに「陸運統計要覧」(平成13年度)に基づく。 |
All Rights Reserved, Copyright
(C) 2003, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
|