 |
| |
|
|
|
日 時
|
:
|
平成14年3月5日(火) 16:00~17:00
|
|
場 所
|
:
|
経済産業省別館944号会議室
|
|
|
|
|
委 員
|
○
|
残間里江子
|
㈱キャンディッド・コミュニケーションズ゙代表取締役
|
|
|
|
|
委 員
|
○
|
中村 英夫
|
武蔵工業大学教授 (部会長に選出)
|
|
|
委 員
|
|
横島 庄治
|
高崎経済大学教授 (部会長代理に指名)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臨時委員
|
○
|
リチャード・クー
|
㈱野村総合研究所主席研究員
|
|
○は出席した委員
|
| |
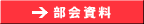 |
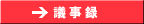
部会資料-2「基本政策部会の運営について(案)」に基づき、委員氏名は○○としています。
|
| |
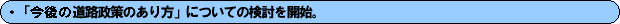
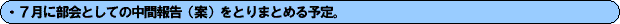
国土交通大臣から、社会資本整備審議会に「新しい課題に対応した道路政策のあり方」について諮問されたことを受け、同審議会道路分科会に「基本政策部会」を設置し、このほど、第1回基本政策部会が開催された。同部会では、月2回のペースで審議を行い、本年7月を目途に中間報告(案)をとりまとめる予定。
|
| |
|
|
| |
|
会議の冒頭、部会長に中村英夫氏(武蔵工業大学教授)が選出された。席上、中村部会長から部会長試案「従来の道路行政からの転換」が提案された。部会長試案では、道路の現状、とりまく情勢変化を認識した上で、道路政策の転換の必要性を指摘している。新たな道路行政の方向性として示された6つのポイントは、以下のとおり。
|
| |
1. |
「量的拡大」重視から、既存のストックの改善と活用を最大限に考慮した「峻別した新規投資と既存施設の有効活用」へ |
| |
2. |
市街地において「車中心」の施策から、自動車利用抑制、生活道路の復権、沿道環境・地球環境の改善も考慮した「歩行者・自転車など生活者重視」の施策へ |
| |
3. |
「道路単独主義」から、鉄道等他の公共交通機関との適切な役割分担を考慮した「インターモーダルな総合的交通システム」の構築へ
|
| |
4. |
「全国一律の"均衡ある発展"」から「地域ブロックを主体とした個性ある地域づくり」の支援へ |
| |
5. |
「事業量確保のための事前評価システム」から「成果を重視する評価システム」へ |
| |
6. |
環境改善、物流効率化、モビリティの向上等の観点に立って、料金を変えるなどの「弾力的な料金政策の導入」へ |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
各委員から出された意見は以下のとおり。
|
| ・ |
都市や安全保障等の観点から量的に不十分な部分もまだ残されているのではないか。
|
| ・ |
既存の道路が十分に活用されているのか。違法駐車によって交通がかなり阻害されている。アメリカには駐車禁止だけでなく、停車禁止(No Stopping Anytime)という考え方もある。停車禁止でかなり容量が増えるはず。 |
| ・ |
現在、道路をつくるのに何十年もかかっているが、何がネックなのか。また、それほど長い間待って完成した道路が本当に利用者のニーズに応えているのか。画一的な基準に基づいて道路をつくるだけでは長期間かけてもニーズに応えられない。 |
| ・ |
道路の定義を見直すべき。どういう使われ方をするのかファンクショナルに定義すべき。また、道路のマネジメントにユーザーをインボルブしていくべき。 |
| ・ |
「官と民」という考え方から「公と個」という考え方へのパラダイムシフトが必要。個人の考え方の中に公的な面をもたないと国としてやっていけない時代に来ている。 |
| ・ |
キーワードは「道路行政の転換」。「転換」のシンボルとなるようなインパクトのある提言を、数を絞って打ち出していくべき。それが全体の流れを変える。 |
| ・ |
一番大事なことは「選別的な重点投資」をどのような観点、どのようなクライテリアで行うのか。それを明確に示すべき。 |
| ・ |
国として道路の整備と管理にどこまで関わっていくかについて方針を持つ必要。 |
| ・ |
これからの時代は、欧米との競争ではなくアジアとの競争。アジアのインフラ整備のスピードは驚異的。その差が国外投資の急激な伸び、国内の衰退につながっている。 |
| ・ |
長期金利が人類史上最低である今こそ競争力確保のためのインフラ投資をするチャンス。マスコミや国民の意見は逆だが、これは道路投資の効果が認知されていないこと、道路工事のイメージが悪すぎることによるのではないか。高いコスト、長期にわたる整備が影響を及ぼしている。 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
部会の議論を一層活発化させるために、その進め方について、以下の方針が合意された。
|
| |
・ |
会議は報道関係者に限り公開とする。 |
| |
・ |
会議資料は、委員ペーパーを基本とする。 |
| |
・ |
会議資料や議事要旨は、速やかに「道路IRサイト」で公開する。 |
| |
・ |
逐次パブリックコメントを実施し、主要な論点については幅広く議論する。 |
| |
・ |
必要に応じ有識者を招き、各界・各地域から意見を聴取する。 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
All Rights Reserved, Copyright
(C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
|