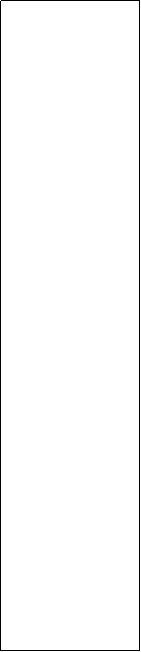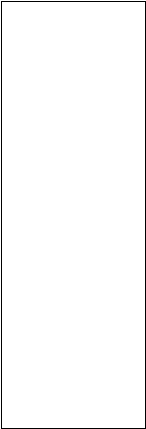�k���s�����v���W�F�N�g���D�v��
��A���D�o�^
�i��j
���J
���D
1�A
�@��
�����J���D���s�����̂Ƃ����v���W�F�N�g�ɂ����āA���D�҂����D������͏o��ہA�K�v�ƂȂ�����͈ȉ��̒ʂ�ł���B
(1)
�v��
�W�F�N�g�R�����傪���������D�g�D�`������ѓ��D�����̋������B
(2) �s�s�v�敔�傪���s�������ݍH���v�拖�B
(3) �s���݈ψ���{�H�Ǘ����傪���s�����{�H����
�ؐ\�����B
(4)
���i
�\���R�������i�@�l���i�����A�v�}�A�\���R�������̎�̓����Əꏊ�A���D�ϑ��Ɋւ�����D�㗝�ϑ��_����܂ށj�B
2�A
���D
�҂����J���D�����߂�v���W�F�N�g�ɂ����āA���D�o�^���s���ہA�K�v�ƂȂ�����͈ȉ��̒ʂ�ł���B
(1) �s�s�v�敔�傪���s�������ݍH����拖�B
(2) �s���݈ψ���{�H�Ǘ����傪���s�����{�H����
�ؐ\�����B
(3) ���i�\���R�������i�@�l���i�����A�v�}�A��
�D�ϑ��Ɋւ�����D�㗝�ϑ��_����܂ށj�B
�i��j
�w��
���D
1�A
�@��
���w�����D���s�����̂Ƃ����v���W�F�N�g�ɂ����āA���D�҂����D������͏o��ہA�K�v�ƂȂ�����͈ȉ��̒ʂ�ł���B
(1)
�v��
�W�F�N�g�R�����傪���������D�g�D�`������ѓ��D�����̋������B
(2)
�s�s
�v�敔�傪���s�������ݍH���v�拖�B
(3) �s���݈ψ���{�H�Ǘ����傪���s�����{�H����
�ؐ\�����B
2�A
���D
�҂��w�����D�����߂�v���W�F�N�g�ɂ����āA���D�o�^���s���ہA�K�v�ƂȂ�����͈ȉ��̒ʂ�ł���B
(1)
�s�s
�v�敔�傪���s�������ݍH���v�拖�B
(2) �s���݈ψ���{�H�Ǘ����傪���s�����{�H����
�ؐ\�����B
�i�O�j
����
����
1�A
�ȉ�
�̏����̂����ꂩ�ɍ��v����ꍇ�A���ڐ����킹�邱�Ƃ��ł���B
(1)
���z
�ʐς�2000�u�ȉ��܂��͓����z��200�����ȉ��̉Ɖ����z����юs���C���t���ݔ��B
(2)
�ꍀ
�ڂ̌_�ϊz��50�����ȉ��܂��̓v���W�F�N�g�̑������z��3000�����ȉ��̊ė��B
(3)
�ꍀ
�ڂ̌_�ϊz��100�����ȉ��܂��̓v���W�F�N�g�̑������z��3000�����ȉ��̐ݔ��B
(4)
����
�����~�܂��͉������ꂽ��A���݂��ĊJ���ꂽ�P���ڍH���ŁA�����Ǝ҂ɕύX���Ȃ��ꍇ�B
(5)
�{�H
�ƎҎ��g�����݁A�g�p����H���ŁA���̋Ǝ҂̎����������H���̗v�������ꍇ�B
(6)
����
���̍H���ɕt�����鏬�K�͍H���܂��͊K�������H���ŁA�����Ǝ҂ɕύX���Ȃ��ꍇ�B
2�A
���D
�҂��o�^���s���ہA�K�v�ƂȂ�����͈ȉ��̒ʂ�ł���B
(1)
���D
�҂���o����\�����B
(2)
�k��
�s�v��ψ���̃v���W�F�N�g���ĕ����B
(3)
�s��
�݈ψ���{�H�Ǘ�����̎{�H���ؐ\�����B
�i�l�j
���D
�҂��{�H���ؐ\��������̂���O�ɐݔ��܂��͊ė��̓��D���s���ꍇ�A�u���W�فv�i�F�s���݈ψ�����̓��D��Ǖ���j�ɐ\�����A���Ă���s���
�Ȃ�Ȃ��B
��A���D�����z����B
�i��j
���J
���D���s���v���W�F�N�g�̏ꍇ�A���D�҂́u���W�ُ��W���v�i�F�s���݈ψ�������D��Ǖ���̐\�������j�ɓ��D�����̌��z��\������B
�i��j
���D
�����͏��W�فu�������v�ɂ��1�K�u�������z�咡�v�i�F�����z�z�[���j
�̃f�B�X�v���C��ʂɂĔ��z����B�������͂���Ɠ����ɓ��D���������ՃZ���^�[���l�b�g���[�N����ь��ݕ����ݍH�����l�b�g���[�N��ɂ����z����B
�i�O�j
���D
�҂�����Ɠ����ɋ�����юw����V���E���s����ɓ��D�����z���悤�Ƃ���ꍇ�́A���D�Ҏ���s�����̂Ƃ��A���W�ُ��W���Ɏw��̐V���E���s
����ɔ��z�������D�����̍T�����o����B
�i�l�j
���D
�����̔��z������D��t�����܂ł͍Œ�5�c�Ɠ��ȏ�Ƃ���B
�O�A���D�҂̊m��
�i��j
���D
��Ƃ͓��D�����ɒ�߂�ꂽ�����ɓ��D�Q����t�葱���s���A���D�҂͌��ՃZ���^�[1�K�������z�咡�ɂĂ��������B
�i��j
�{
�H�A�ݔ��A�ė��Ȃlj��D��Ƃ́A���W�ق̔��s����IC�J�[�h�����Q���Ē�߂�ꂽ���ԓ��Ɏ�t�葱
���s���BIC�J�[�h���Ȃ��A�܂��͐\�����̉��D��Ƃ́A��
�Ƃ̉c�Ƌ�����ю����ؖ����̌��{�A��Ƃ̖@���\�҂̈ϑ��������Q���Ď�t�葱���s���B�������̎Q���ƂȂ�k���ȊO���邢�͊O���̎{�H��Ƃ��Q��
��t�葱���s���ꍇ�́A��Ƃ̉c�Ƌ�����ю����ؖ����̌��{�܂��͍T���i�T���̏ꍇ�͊�Ƃ̌���і@���\�҂̈�ӂ����邱�Ɓj�A��Ƃ̖@��
��\�҂̈ϑ����A�s���݈ψ���֘A����̉��D�����������Q���邱�ƁB
�i�O�j
���D
��Ƃ̎�t�����A���W�ق͓��D�҂ɑ����D�����̗v���ɍ��v����Q����Ƃ̃��X�g�����B
�i�l�j
���D
�҂͎��i�\���R�������Ɋ�Â��A��t���������ׂẲ��D��Ƃɑ����i�R�����s���A���Ȃ��Ƃ�7�Јȏ�̉��D��Ƃ��m�肵�A���D�ɎQ������
��B
�i�܁j
���D
�҂͎��i�R���I����A���i�R���̋L�^�����W�قɒ�o����B
�i�Z�j
���i
�R���ɍ��i�������D��Ƃ�7�Ђɖ����Ȃ��ꍇ�́A���ݍs����Ǖ���̋���
�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�i���j
�w��
���D���s���ꍇ�A���D�҂�3�Јȏ�̎����v��������Ƃɑ����D����
���s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�i���j
��
���A�ݔ����D�Ō��J���D���s���ꍇ�A���D�҂͎��i�\���R�������Ɋ�Â��A��t���������ׂẲ��D��Ƃɑ����i�R�����s���A���Ȃ��Ƃ�4�Јȏ�̉��D��Ƃ��m�肵�A���D�ɎQ������
��B�w�����D���s���ꍇ�́A���D�҂�3�Јȏ�̎����v��������Ƃɑ����D����
���s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�l�A���D����
�i��j
���D
�҂́u���ؐl�����a�����W���W�@�v�i�F���ؐl�����a�����D�@�j��19���ɏ]���ē��D�������N������B
�i��j
���D
�҂����D�������N������ۂɂ́A�ȉ��̖͔͗l�����Q�l�܂��͎g�p���邱�Ƃ��ł���B
1�A
����
���ҏW�́w���ݍH���{�H���W�����͖{�x�B
2�A
�k��
�s�u���ݍH�����W���W�Ǘ��ٌ����v�i�F���ݍH�����D��ǎ������j�ҏW�́w���ݍH���{�H����W�����͖{�x�i2000�N4���j�B
3�A
FIDIC�̌_������Ɋ�Â��ĕҏW���ꂽ���D�����͔�
�l���B
4�A
���E
��s�i�A�W�A�J����s�j�̒����������ɂ�����Z���v���W�F�N�g�̓��D�����͔͗l���iNCB�j�B
�i�O�j
�ė�
���D�����͏��W�ق̒���ė����D�����̖͔͗l�����g�p���邱�Ƃ��ł���B
�i�l�j
�ݔ�
���D�����͏��W�ق̒���ݔ����D�����̖͔͗l�����g�p���邱�Ƃ��ł���B
�i�܁j
���D
�҂͍��Ɣ��W�v��ψ���Ȃ�7���ςɂ��12���߁u�]�W�ψ���a�]�W���@�b�s�K��v�i��
���F���D�]���ψ����ѓ��D�]�����@�Ɋւ���b��K��j�A���ݕ�89���߁u�[�����z�a�s����b�ݎ{�H���{�H���W��
�W�ė��ٖ@�v�i�F�Ɖ����z����юs���C���t���ݔ��H���{�H���D�ė��@�j�ɏ]���āA���D�������ɓ��D�]���̕��@�L����B
�i�Z�j
���D
�҂͏��W�ق̌����A�s���A�ė��A�ݔ��̊e����ɓ��D������͏o��B
�i���j
���D
�������ɍ��Ƃ̖@���A�s���@�K�A�k���s�s���@�K�A�K���̓��e�ɕ������Ȃ����̂�����ꍇ�A���W�ق͉����ӌ����s���A���D�҂͉����ӌ����Ɋ�Â��ē��D
�����ɏC���������A�ēx�͏o��B
�i���j
���W
�ق����D������R��������Ԃ́A�����K�͂̃v���W�F�N�g��7�c�Ɠ��A��K�͂܂��͓���v���W�F�N�g��14�c�Ɠ��Ƃ���B�R�����Ԃ��Ă������ӌ���
�o����Ȃ��ꍇ�́A�͏o�ɓ��ӂ������̂Ƃ݂Ȃ��B���W�ق͎������D�����Ɂu���W�������ď́v�i���D�����̈�j������B
�܁A�J�D�A���D�]������ї��D
�i��j
�J�D
�́A���D�����ɒ�߂�ꂽ���ԂɌ��ՃZ���^�[�J�D���ɂčs���B
�i��j
���D
�҂͓��D�����ɒ�߂�ꂽ�ꏊ�ŁA�J�D���ȑO�ɉ��D��������̂��邱�Ƃ��ł���B�܂��A�J�D�����̒�߂�ꂽ���ԓ��Ɍ��ՃZ���^�[�ɂĉ��D��������̂���
���Ƃ��ł���B
�i�O�j
�J�D
���ɂ́A���D�҂͈ȉ��̏��ނ����Q����B
1�A
����
����̂������D�����B
2�A
�@��
��\�ҁi�܂��͖@���\�҂̈ϑ��l�j�̗L���ȏؖ����B
3�A
���D
����i�i���D����i��ݒ肵�Ă���ꍇ�j�B
�i�l�j �J�D�͓��D�҂ɂ��g�D����A�s������̊ē�
����B
�i�܁j �J�D�ɂ����Ĉȉ��̎����͏��W�قɕۑ����Ȃ�
��Ȃ�Ȃ��B
1�A
���D
�ҁA���D�҂̖@���\�҂̗L���ȏؖ����̃R�s�[�A�@���\�҈ϑ�������т��̗L���ȏؖ����̃R�s�[�i�@���\�҂��㗝�l�Ɉϑ����Q�����Ă���ꍇ�j�B
2�A
���D
����i�i���D����i��ݒ肵�Ă���ꍇ�j�B
3�A
���D
�����̕��{�B
4�A
���D
�҂̎{�H�g�D�\�z�B
5�A
���D
�҂̗\�Z���B
6�A
�J�D
�L�^�̍T���B
�i�Z�j ���D�]���ψ���̐��Ƃ́A���D�҂����D�]��
�ψ����ݒu����ہA���ՃZ���^�[�ɐ݂����Ă���s���݈ψ���܂��͓��D�㗝�@�ւ̓��D�]�����Ɩ��납��A�K�X�I�o�����肷��B������D�v���W�F�N�g
�̓��D�]���̐��Ƃ́A���Ƃ̊֘A�K��Ɋ�Â����D�҂����ڌ��肷�邱�Ƃ��ł���B
�i���j ���D�]���ψ���́A���D�����ɂ�����D�]����
���Ɋ�Â��ĉ��D�����ɑ��R���A��r���s���B
�i���j ���D�]���ψ���͕K�v�ɉ����āA���D�҂ɑ�
���̉��D�����̉��߂����߂邱�Ƃ��ł���B
�i��j ���D�]���ψ���͓��D�]��������A���D�҂ɑ�
�����ʂɂē��D�]�����o���A���D���҂𐄑E����B
�i�\�j ���D�]���I����A���D�҂͓��D�]���ߒ��̋L�^
����ѓ��D�]�������W�قɓ͏o��B
�i�\��j ���D�҂͗��D�Ҋm������15���ȓ��ɓ��D�A���D�̏����ʂɂď��W�ق�
����B���Ɋ܂܂���ȓ��e�͈ȉ��̒ʂ�ł���B
1�A
���D
�͈́A���D�����A���i�R���A�J�D����ѓ��D�]���̉ߒ��A���D�Ҋm��̕��@����ї��R�B
2�A
���D
�����܂��͓��D�������A���D��t�\�A���i�R�������A���D�����A���D�]���ψ���̓��D�]���i���D����i��ݒ肵�Ă���ꍇ�͗��D����i��Y�t�j�A��
�D�҂̉��D�����B
3�A
�H��
���D�㗝�l�Ɉϑ������ꍇ�́A����ɍH�����D�㗝�ϑ��_��Y�t���邱�ƁB
�i�\��j ���W�ق�5�c�Ɠ��ȓ��ɕ����ɑ��ًc���o���Ȃ�
�ꍇ�ɂ́A���D�҂͗��D�҂ɗ��D�ʒm���s���邱�Ƃ��ł���B�܂��A���D���ʂ𗎎D�ł��Ȃ��������ׂẲ��D�҂ɂ��ʒm����B
�Z�A�_��̓͏o
�i��j ���D�҂Ɨ��D�҂́A���D���ʂ̓͏o����30���ȓ��Ɍ_����������i�{�H�A�ė��A�ݔ��_
����܂ށj�B
�i��j �_���������10���ȓ��Ɍ_��̓͏o���s��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
���̍ہA�ȉ��̏���������Ă��邱�ƁB
1�A
�_��
�̐��{�A���{�̂��ׂāB
2�A
�͏o
�o�^���i�o���̌_��Ǘ��҂���т��̐E�ʂ̏؏��ԍ��m�ɂ���j�B
3�A
���D
�ʒm���B
4�A
���D
�����B
5�A
�ϑ�
�l�̎������B
6�A
�_��
�̓͏o���s�����o���̐l������т��̐E�ʂ̏ؖ��B
�i�O�j �_���t����͌_��͏o�ӌ������������s��
��B
�i�l�j �K��ɏ]���A�_���{�ɂ͎�����\��t
����B
���A���̔��z����і₢���킹�T�[�r�X
�i��j ���ՃZ���^�[1�K�ɂ����čH�����D�̏��A��Ƃ⒇��Ǝ҂�
�����Ɋւ�����A�ޗ����i�Ȃǂ̏�z�T�[�r�X���s���B
�i��j ���ՃZ���^�[2�K�̃^�b�`�p�l�����f�B�X�v���C�ɂĂ����Đ�
���@�K�A���D���D�A���W�ق̎��{�\��Ȃǂ̏��₢���킹�T�[�r�X���s���B
�i�O�j ���ՃZ���^�[���l�b�g���[�N���ʂ��āA��
�ݍH������ѓ��D���D�Ɋւ���e��������B
���D���D�菇�t���[�`���[�g
|
��ƒi�K |
���D�� |
���D�� |
�ēǗ����� |
||||||||||||||||
|
�@���A�@�K����ыK��ɏ]���Č��J���D���w�����D
�������肷��B |
|
|
���D���D�ēǗ����傪�͏o������B |
||||||||||||||||
|
���D�҂͓��D�葱������s���ꍇ�A�K��ɏ]�����D
�ēǗ�����ɓ͏o��B���D�葱��㗝�l�Ɉϑ�����ꍇ�́A�㗝�ϑ��_���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
|
|
|
||||||||||||||||
|
���D�҂͋K��ɏ]�����ݍH�������D�����������
��A���D���D�ēǗ�����Ɋ֘A�ؖ����ނ����Q���ē��D�o�^���s���B |
|
|
|
||||||||||||||||
|
���J���D���s���ꍇ�A�L�`���z�s�ꂨ��э��Ƃ܂�
�͒n���̎w�肷��V���E���s���A���l�b�g���[�N�܂��͂��̑��̔}���ʂ��ē��D�����z����B�w�����D�ł́A3�ȏ�̎��������ɕ������鉞�D�҂ɑ����D������
�z����B |
|
|
|
||||||||||||||||
|
���i�\���R���\��������̂���B ���i�\���R�����̗p����ꍇ�A���D�ɎQ������\��
�҂Ɏ��i�\���R�����ނs����B |
|
���D�҂͎��i�\���R�����ނ̗v���ɏ]���Ď��i�\��
�R���\�����ɋL���i�A���̂ɂ�鉞�D�ł���ꍇ�̓����o�[���Ƃɂ��ꂼ��̏��ċL���j���A���t����B ���i�\���R�����ނ�����B |
|
||||||||||||||||
|
���i�������D�\���҂Ɏ��i�\���R�����i�ʒm����
�s����B ���i�������D�\���҂��m�肷��B ���D�\���҂̒�o�������i�\���R���\�����̓��e��
�R���A���͂���B |
|
���i�������D�\���҂͎��i�\���R�����i�ʒm�����
��A�L���Ȏ�̏�ԑ�����B |
|
||||||||||||||||
|
���D���������i�������D�\���҂ɔ̔��܂��͔��s��
��B ���D���D�ēǗ�����ɓ͏o��B ���D�������쐬����B |
|
��̏�ԑ�����B ���D�����̏������J�n�B�֘A������������W��
��B ���D����������B |
���D���D�ēǗ�����͓��D�����̓͏o����
��B |
||||||||||||||||
|
���D�҂�g�D���Ď��n�������s���B |
|
���n���� ���D��������ь���ł̋^��A����͈ȉ��̕��@��
��o���邱�Ƃ��ł���B |
|
||||||||||||||||
|
9�A ���D�\����
�i���^�����j
�������t���A����������B (1)
���ʂɂčs
��
���ʂɂĂ��ׂẲ��D�҂Ɏ���ɑ�����s
���B (2)
���^������
���݂���
�������t���A����������B |
|
(2) ���^�����̑O�ɁA��߂�ꂽ�����܂łɏ��ʂɂĎ�
����o����B ����ɑ��������A��̏�ԑ�����B (1) ���ʂɂčs���B |
|
||||||||||||||||
|
���D�����̉��߁A�C�����s���B ���^�����̏�ɂĉ��s���A���̌㎿��ɑ���
�����ʂɂĉ��D�҂ɔ�������B |
|
���߁A�C������������A��̏�ԑ�����B �̋I�v������A��̏�ԑ�����B |
���D���D�ēǗ�����͓��D�����̉��߁A�C���̓�
�o������B ���D���D�ēǗ�����͉̋I�v�̓͏o����
��B |
||||||||||||||||
|
���D�҂͉��D����������A���������L�^����B �������ߌ�ɓ͂������D������ԋp����B �J�D�܂ʼn��D������K�ɕۊǂ���B |
|
���D�����Ɖ��D�ۏ؋����o����B��̏�ԑ���
��B ���D�������쐬���A���D�ۏ؎葱���s���B �������ߌ�ɓ͂������D�����͕ԋp�����B��̏�
��ԑ�����B |
|
||||||||||||||||
|
���D�҂͊J�D����g�D�A��Â���B |
|
���D�҂͊J�D�ɎQ������B |
|
||||||||||||||||
|
���D�҂͖@���A�@�K�A���̑��̋K��ɏ]�����D�]��
�ψ����ݒu����B |
|
|
|
||||||||||||||||
|
���D�]���ψ���ɂ����D�]�����s���B �E�������̊Ӓ� �E�Z�p���]�� �E���Ɛ��]�� �E���i�R���i����R���j |
|
|
|
||||||||||||||||
|
���D�]������������B���D���҂��m�肵�A���D�]
�������쐬����B |
���D�]���ψ���D�����̓��e�ɂ��ĉ��߂܂���
���ق��s���B |
|
|
||||||||||||||||
|
���D�҂͓��D���D�����쐬���A���D�Ҋm��
����15���ȓ��Ɍ��ݍs����Ǖ���ɓ͏o���s���B |
|
|
���D���D�ēǗ�����͓͏o������B |
||||||||||||||||
|
���D�҂͗��D�҂ɗ��D�ʒm���s����B ���D�҂͗��D�ł��Ȃ��������D�҂ɗ��D���ʒʒm��
�𑗕t���A���D�ۏ؋���Ԋ҂���B |
|
���D�҂͗��D�ʒm������̂���B ���D�ۏ؋�����̂��A��̏�ԑ�����B |
|
||||||||||||||||
|
���D�҂̉��D�ۏ؋���Ԋ҂���B �x���ۏ��葱�A��o����B |
�_��̓͏o���s���B ���D�҂Ɨ��D�҂͌_�ӏ��ɏ�������B |
���s�ۏ��葱�A��o����B ���D�ۏ؋�����̂��A��̏�ԑ�����B |
���D���D�ēǗ�����͓͏o������B |