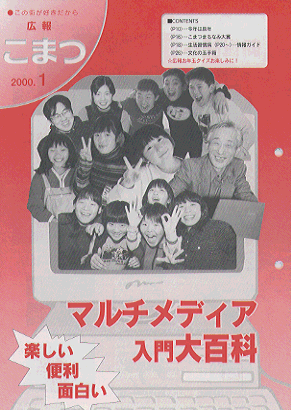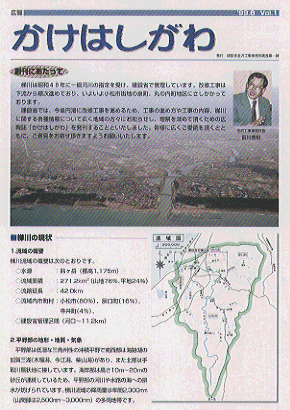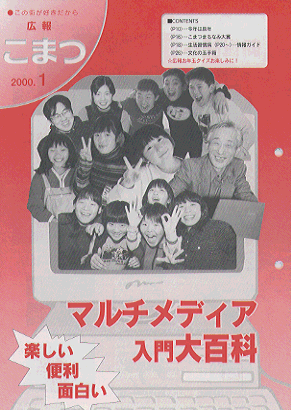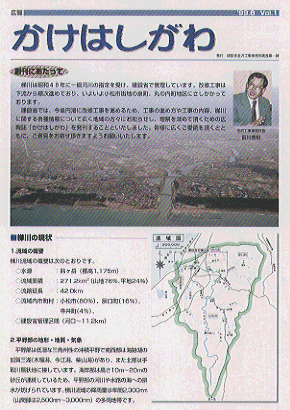建設省では、地域づくりにおいて国民との十分なコミュニケーションを確保していく手法について検討していくため、建設本省の担当者が各地方建設局の担当者と直接意見交換会を行い、その結果出された課題と対応策をとりまとめました。
その報告内容をご紹介致します。
1.各地方建設局における意見交換会の実施
地域づくりを進める際のコミュニケーション手法の確立を目指し、まず第一弾として、実際に国民とコミュニケーションを行う立場にある各地方建設局本局及び各事務所の担当者と本省のコミュニケーション型行政施策担当者が、コミュニケーション推進の方針等について直接議論を行う意見交換会を、平成11年の9月から10月にかけて、合計127名の参加を得て、各地方ブロック(全8ブロック)ごとに実施した。
意見交換会では、一般的に行政が行っているコミュニケーションに対し指摘されている以下のようなテーマを中心にして、地域づくりにおいてコミュニケーションを進める上での課題や工夫、コミュニケーションに求める機能や対象の考え方などについて意見交換を行った。
地域づくりコミュニケーション意見交換会で検討された主なテーマ
1)行政が発信する情報(計画、ビジョン等)を受け取ってもらうため、どうし
たらよいか。
2)広く一般住民の声を吸い上げるためには、どうしたらよいか。
3)行政側の人事異動による継続性確保の課題をどのように補っていけばよい
か。
4)行政や地域の対話を、陳情と苦情だけでなく、双方向の対話として進めてい
くにはどうしたらよいか。
5)市町村と事業関連での対話だけでなく、地域づくり全般での対話を進めてい
くにはどうしたらよいか。
|
2.地域づくりコミュニケーションを推進する上でのポイント
各地方建設局における意見交換会では、様々な角度から住民や地域とのコミュニケーションの改善策や工夫について意見が出された。中でも多く寄せられた意見や、今後取り組んでいくべきと思われる目新しいアイディアに着目して、議論のポイントを整理すると、地域づくりにおけるコミュニケーションを進めていく上では次の3点が重要になってくると考えられる。
(1)コミュニケーションの場づくり
〜日頃からのコミュニケーション〜
(2)組織における情報の共有化
〜人事異動による継続性の欠如の補完〜
(3)広報誌の内容、伝達方法に関する工夫
〜市町村との連携強化〜
|
(1)コミュニケーションの場づくり
〜日頃からのコミュニケーション〜
趣旨:
「一般住民の声が吸い上げられていない」、「市町村とは事業関連でしか付き合いがない」などの問題意識から、日頃から住民との交流を図り、地域住民とのコミュニケーションを図ることを目的として、コミュニケーションの場づくりに努めること
例:
・事務所等の開放(オープンハウス)
・住民交流センター、学べる建設ステーションや砂防博物館等の開設
・現場見学
・出張所、道の駅、資料館等の活用
・ワークショップの開催
事務所内におけるホームページ閲覧専用パソコンの設置、書籍・ビデオの閲覧を通じた情報提供
期待される効果:
・事務所の開放等を通じて意見交換の場を設けることにより、一般住民の声を吸い上げることができる
・コミュニケーションの場を通じて、事業関連のほかにも市町村と意見や情報の交換を行い、連携につなげることができる
事例: コミュニケーションの場づくり
【工事事務所開放】
〜オープンハウス(北勢国道工事事務所)〜
北勢国道工事事務所は、住宅地の中に位置していることから、事務所開設の際に周辺住民の反対に遭った経緯がある。そのため、周辺住民に工事事務所についての理解を深めてもらうために、庁舎を一日開放し、講演会やパネル展示、機器のデモンストレーションを実施して、事業内容の説明をし、住民との交流・親睦を図った。具体的には、パトロールカー、標識車などの建設機械を展示・紹介し、海水の真水化デモや喫茶サービスを行った。地区市民センターや連合自治会と共催し、地元の広報誌や新聞にも載せてもらっている。439名が参加した。
〜オープンハウスとは?〜
オープンハウス(Open House)とは、英語で一般公開、開放という意味で、普段は公開されていない場所を一般の人に開放し、カジュアルな雰囲気の中で業務や活動についての紹介を行ったり、意見交換など行うイベントのこと。アメリカでは、大学や、研究機関、その他公共施設のオープンハウスが多い。日本でも、徐々に使われ始めており、厚木基地、NTT、大阪府立研究所、NECなど多数のオープンハウスの例がある。
(2)組織における情報の共有化
〜人事異動による継続性の欠如の補完〜
趣旨:
「人事異動等により、対話の継続性が図られていない」との問題意識から、地域住民との対話を個々の担当者にとどめるのではなく、情報共有化を通じて、事務所の職員全体で地域とのコミュニケーションを図ること
例:
・グループウェア等を導入し、システム化を図る
・業務日誌等を共有化する
・マニュアルを整備し、ルールや方針を明文化する
・文書の様式を統一し、面談記録や議事録を共有する
期待される効果:
・情報の共有化を通じて、人事異動等に係わらず、組織が継続性をもって地域とのコミュニケーションを図ることができる
(3)広報誌の内容、伝達方法に関する工夫
〜市町村との連携強化〜
趣旨:
「行政側が作成するビジョン等が読んでもらえず、内容が伝わっていない」との問題意識から、住民に事業等に興味・理解を持ってもらうよう、内容や伝達方法などを工夫する
例:
・市町村に広報誌への折り込み配布を依頼する
・事務所の事業内容等を市町村の広報誌に直接掲載してもらう
・テレビやインターネット等の様々な媒体の活用
・読んでもらうだけでなく実際にビジョンを説明
期待される効果:
住民にビジョンや事業内容を伝達することにより、地域とのコミュニケーションを図ることができる
事例: 広報誌の内容、伝達方法に関する工夫
【市町村の広報誌に入れてもらう工夫】
〜金沢工事事務所の事例〜
◆市町村の広報誌に入れてもらうまでの経緯
金沢工事事務所では、現在「かけはしがわ」、「東部環状だより」、「夢職人」、という三種類の広報誌を発行している。
そのうち、小松市周辺住民向けに34,000部発行している「かけはしがわ」は、小松市広報誌の折込で配布されており、市町村の広報誌に入れて配布されている成功事例といえる。
市全体に金沢工事事務所が発信する情報を行き渡らせるためには、市町村の広報誌が一番適しているという考えから小松市にアプローチした。しかし、市の税金で作成している広報誌の紙面に、金沢工事事務所の事業が載ることに対しては、小松市の一部に抵抗感があった。そこで、紙面掲載ではなく、小松市の広報誌へ折り込んで、配布をしてもらうことにした。
◆アカウンタビリティの一環として広報誌を配布
また、金沢工事事務所では、現在建設中の金沢東部環状道路に関連して、「東部環状だより」という広報誌も発行している。市民サイドからは、橋梁下部工事やトンネル工事等が自分たちの周辺で行われているが、国の工事か、県の工事か、よくわからないし、また完成すれば利便性がどうなるのか知らないという声が寄せられていた。
以上の理由によりアカウンタビリティ(説明責任)の一環として、工事周辺の市民を対象(配布世帯数:35,000)として、広報誌「東部環状だより」を新聞折込みにより配布している。
広報誌は、平成11年8月に創刊し、工事が完了するまで、年3回の配布を目標としている。広報誌は、専門用語を極力少なくし、平面図も、航空写真に学校やデパート等身近な施設を記載し、道路がどこに出来るのかをわかりやすく工夫している。
すでに2回配布しているが、地域高規格道路のことをもう少し教えて欲しいと言った電話や、工事はいつまでかかるのかという問い合わせも事務所に来ており、住民からの反応が出てきている。
小松市広報誌「こまつ」に折り込まれている「かけはしがわ」
| 「こまつ」 | | 「かけはしがわ」 |
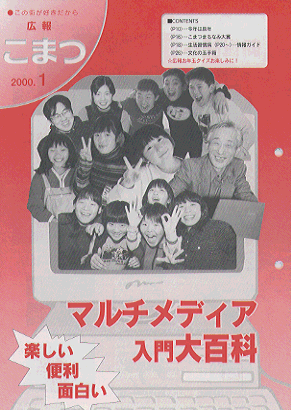 | |
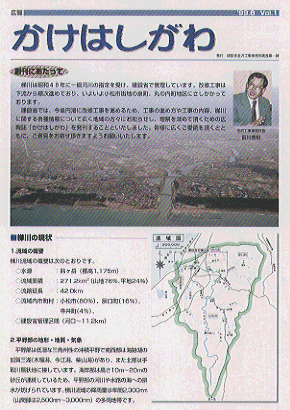 |
[「最新の動き」のページへ戻る]