略 歴
| 昭30 |
北海道生まれ
|
| 昭54 |
中央大商学部卒業 |
| 昭57 |
株式会社アスキー入社、株式会社アスキーマイクロソフト出向 |
| 昭58 |
同社ソフトウェア開発本部次長就任 |
| 昭61 |
マイクロソフト株式会社入社、OEM営業部長就任 |
| 平2 |
同社取締役マーケティング部長就任 |
| 平3 |
同社代表取締役社長に就任 |
| その他 |
| 平6 |
(社)日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会 常任理事に就任 |
| 平7 |
(社)日本能率協会 経営・マーケティング部門評議員に就任 |
| 平10 |
(社福)プロップステーション 理事に就任 |
| 平11 |
(社)経済同友会 幹事に就任 |
|
 |
|
行政で変革が起き始めたのは、情報の非対称性が存在しなくなったからだ。明治以来の行政システムは90年代までは効率が高かった。情報を中央集権的に大量に集め、その結果、ほぼ正しい結論を導きだすことができたからである。
しかし、現在は情報の動きが大きく変化している。
一つは、民間の情報量総量が政府より大きくなったことである。特にマルチナショナルカンパニーの持つ情報収集能力は高い。例えば、建設業界の情報でも世界的に見ると建設省よりマイクロソフト社が国別・会社別の細かい情報を持っている可能性がある。民間の大勢の社員が世界各国でビジネスを通じて様々な情報を直接収集しており、少なくとも情報量はその人数と運用期間の積であるため、建設省よりはるかに多いという事実を理解して欲しい。
もう一つは、いわゆるNPO組織が政府に対して反論可能な情報を持ちはじめ、その人数が行政関係者より多くなったということである。民間の情報にはノイズもあるかもしれないが、行政側はあらゆる情報を整理し対応しなければならないようになってきた。
このように拡大した民間の情報量に対して、相対的に行政の情報量は低下している(下図)。したがって、もはや行政だけでは正しい判断はできない。政府の情報より民間の情報が多い現在、政府の情報だけ公開しても意味がないのだ。
そうではなくて、民間の持つ情報を共有化した方が効率的であろう。事業に反対する団体が根拠とする情報を含め、民間の情報プールをつくり、それを公開してはどうか。
コミュニケーション型行政の意味するところは、官から民への情報公開ということだけではない。民の中の情報を公開することにある。政府と民間が情報を共有し、オープンにするということである。
例えば、建設省のホームページ内に最新の民間の建築、土木技術に関するページにリンクを張り、データベースをつくるのである。最新の情報は建設省のホームページにあり、となれば世界中からアクセスがあるだろう。英語のページへリンクをたくさん貼ると、建設省の「超ドメ」のイメージはずいぶん変わる。大規模プロジェクトを支えている海外に誇れる建築技術等、子供達が「ものを造ること」に興味を持ち、夢を膨らませてくれるような情報を提供出来るようになれば、国民の公共事業を見る目も変わるかも知れない。
ところで、激変の時代に対応して個人が成果をあげていくには、関係の深い業界の人だけではなく、業界を超えて交流することが必要ではないか。つきあいをナローにしすぎないということである。視野を広く持つことで、業界の常識にとらわれず、大胆な判断ができる。そういう意味では、建設省の人も、例えば、運輸省とではなく、通産省や郵政省のテレコム関係者とつきあってみたらどうか。建設省も真面目なだけでは駄目だ。
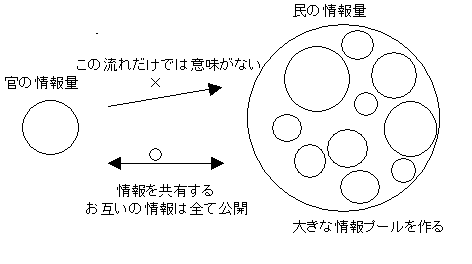
|
|

