(報告:中和正彦=ジャーナリスト)

2日間にわたって開催されたプロップ・ステーションの社会福祉化記念のシンポジウム。延べ300名以上が参加
|
The Challengedとメディアサポート |
社会福祉法人になった「プロップ・ステーション」
| 「ガツン!'99〜夢はもう現実だ!」と題するシンポジウムが4月17、18の両日、神戸で開催された。「チャンレンジド(障害を持つ人を表す最近の米語)を納税者にできる日本」をキャッチフレーズに就労支援活動を展開して来たNPO「プロップ・ステーション」が”社会福祉法人”になったことを記念してのイベントで、メンバーのチャレンジドたちが中心となって企画したという。当日は各界から駆けつけた多彩なシンポジストたちが、それぞれの立場から高齢社会=障害を持つ人が多くなる社会に向けてのポジティブな展望を語り、相互の連携の必要性を確認して話し合っていた。
(報告:中和正彦=ジャーナリスト) |
| |||
2日間にわたって開催されたプロップ・ステーションの社会福祉化記念のシンポジウム。延べ300名以上が参加 | ||||
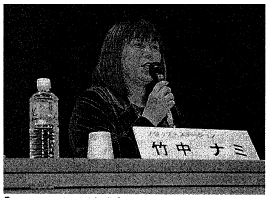
| 前例のない社会福祉法人がなぜ、今生まれたのか プロップ・ステーションは1992年4月の活動開始以来、重い障害を持つ人々に自己実現の道具としてコンピュータ技術を教える一方、彼らが誇りを持って仕事ができる社会システムの構築を提唱して産・学・官・その他の幅広い支援者を集め、インターネットを用いた在宅就労などの先駆的な成功例を次々と生み出してきた。 このプロップ・ステーションの社会福祉法人認可の記念イベントで最初に披露された祝辞は、認可権者である厚生大臣からのものだったが(仁木壮・同省障害者福祉課長代読)、宮下創平厚生大臣はその中でこう述べていた。 「厚生省としましても、これまでの社会福祉法人にはない、このような先駆的な活動を高く評価すると共に、昨年9月に社会福祉法人として認可したところでございます」 この認可は、単にプロップの活動が公益事業と認められたことを意味するだけでなく、障害者をめぐる状況が新たな段階に入ったことを象徴しているようにも思われる。 社会福祉法人には老人ホームや障害児施設などの福祉施設を経営する法人が多いが、そこで思い出されるのは、特別養護老人ホームをめぐる岡光序治元厚生事務次官らの汚職事件である。前例を重んじる行政が事件によって前例の見直しを迫られれば、新規の許認可には前例があっても慎重になったはず。そういう時期に、前例のない活動をするプロップ・ステーションの社会福祉法人申請がパスしたのである。 実は、日本の障害者福祉施策は、理念的にはすでに「施設をつくって保護する」という方向から、「環境を整えて社会参加を支援するという」という方向に移行している。だが、社会一般には、「適切な支援があれば働ける人がたくさんいる」という理解は広まりつつあるものの、まだまだ「障害者は保護すべきで、無理に働かせる必要はない」 | という意識は強い。また、基本的な環境整備や支援はもちろん行政の責任なのだが、多様化する個別的な支援ニーズについては「これからはNPOが担い手になるべき」という市民の自助意識が芽生えつつある一方、まだまだ何事につけて「行政の対応が立ち遅れている」という「行政全面依存の意識も根強い」 こうした中にあって、プロップ・ステーションは社会参加支援型の活動を当事者・関係者の自助意識で展開してきた団体。しかも、施設を基盤とする活動ではなく、コンピュータ&ネットワークを基盤とする活動。つまり、国が進める新しい障害者福祉施策に、一つのモデルを提供するような団体なのである。保護型・箱型の施策で起きた問題の余波が続く中で、このような従来の社会福祉法人にないタイプの団体が同法人として認可されたことは、決して偶然ではないだろう。 一方、プロップ・ステーションの竹中ナミ理事長は、新しくできることになっていたNPO法(営利活動促進法=昨年12月施行)に基づくNPO法人ではなく、社会福祉法人の道を選んだ理由を、次のように述べている。 「私たちの活動には、企業との連携だけでなく、国や自治体との連携が欠かせません。社会福祉法人の申請をしたのは、それを一番しやすい法人だからです」 そのことを物語るかのように、今回のイベントには行政からも多くの参加者があった。
動き出した行政&NPO連携のチャレンジド就労支援 シンポジウムの中で、行政との連携に関して一番新しい具体的な話は、労働省〜羽曳野市(大阪府)〜プロップ・ステーションの連携だった。 本誌5月号の「雇用創出とIT」第4回でも紹介したが、労働省は昨年度の第三次補正予算で500台のパソコンを用意し、障害者の就労支援を行う9つの団体と連携し | ||
「チャレンジドを納税者にできる日本」を訴え、社会福祉法人プロップ・ステーションを牽引する竹中ナミ理事長 | ||||
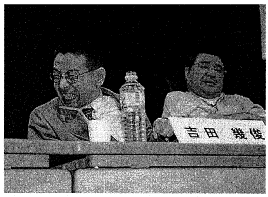
| ||||
このシンポジウムの企画からナビゲートまでを担当した吉田幾俊氏(写真左)。脳性麻痺の彼はデザイナーとして「ガツン!」と夢を現実にした男だ | ||||
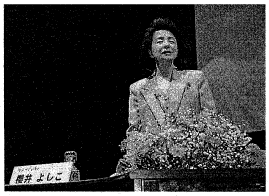
| ||||
チャレンジドの生き方、プロップ・ステーションの役割と期待を丹念な論旨で応援した櫻井よしこさんの記念講演 | ||||
て、実際に障害者にそのパソコンを利用してもらいながら、在宅就労の条件整備のあり方を模索しようとしている。その9団体の1つがプロップ・ステーション。そして、羽曳野市は、独自に障害者・高齢者の在宅就労を支援する体制づくりを模索していた時に今回の労働省の施策と出会い、プロップ・ステーションで腕を磨いたチャレンジドを講師に招いて、労働省給付のパソコンでセミナーを開くことになったということだ。 この話題の出たセッション「高齢社会はチャレンジド社会」の壇上には、村木厚子・労働省障害者雇用対策課長、福谷剛蔵・羽曳野市長、チャレンジド講師の山崎博史さんと貝本充広さんが顔を揃え、それぞれの思いを語った。そこから感じられたのは、組織にしても個人にしても、いい意味で他者を利用している姿だ。行政はプロップ・ステーションのノウハウを利用して施策の実効性の向上を図り、プロップ・ステーションは行政の施策を利用してチャレンジドにチャンスを与え、チャレンジドはプロップ・ステーションを利用して経験を積んでいるいった具合だ。 行政との関連では、高知県・橋本大二郎、宮城県・浅野史郎、兵庫県・貝塚俊民の3知事が竹中さんとの対談ビデオの形で参加し、それぞれの障害者施策を語るという企画もあった。中でも注目を集めたのは浅野知事だ。「チャレンジド・ジャパン・フォーラム」という、プロップ・ステーションの活動に共鳴した各界の第一線の人々が「チャレンジドの在宅就労を可能にする新しい社会システムづくり」を議論する会議体がある。去年8月の第4回に参加して感銘を受けたという浅野知事は、第5回を今年8月21,22の両日、自らが実行委員長になって宮城大学のキャンパスを使って開催すると公表し、会場の人々に来場を訴えた。さらに浅野知事は、2001年の宮城国体を「全国初のバリアフリー国体にする」と宣言。「チャレンジドの方々にもたくさん見に来て欲しいのと同時に、この国体を成功させるために運営側にも加わって欲しい」と訴えた。
チャンスの拡大は 社会の片隅に置かれていた障害者・高齢者が「お客様」として中央に迎えられるようになり、さらに「戦力」としても期待されるようになった。これはいうまでもなく、高齢時代=障害者が増える時代に入っていくのと並行して、情報技術が障害の有無に関係なく活躍できる世界を拡げていくことによる。 プロップ・ステーションにはデジタルアートに取り組んでいるチャレンジドのグループ「バーチャル工房」があり、各人の活動の他にインターネット上でグループワークも行う。 |
今回のイベントではその共同制作の作品が発表されて来場者の注目を集めたが、彼らに製作ツールを提供して支援してきた手嶋雅夫・マクロメディア社長は、「皆さんはすでに、業界のトップレベルの人たちがやっているのと同じことを経験している」と述べ、「自分の中の小宇宙を表現する芸術の方向へいくのか、クライアントの要求に応えるデザインの方向にいくのか、そろそろこの点をよく考える時期にきている」と指摘した。 クリエイターの世界は作品の良し悪しがすべてで、最も障害の有無と関係ない世界かもしれない。だが、最も障害がハンディになりそうな世界も、変わりつつあるようだ。成毛真・マイクロソフト社長は次のようなビジネス環境の変化を紹介した。 「アメリカのマイクロソフトの営業部門では、企業へのテレセールスが伸びたので在宅勤務が増えて、その10%か20%が障害を持った人だそうです。日本でも、5年前だったら『電話ですます気か。顔を出せ』という感じだったと思いますが、最近はリストラが進んだせいか、皆さん忙しそうで、『電話にしてくれ』というケースが出てきているんです」 情報ツールによって多様な働き方が可能になれば、待遇も多様になって成果主義が強まると予想される。また、時間も距離も超えた仕事が可能になることは、究極的には世界全体の中での競争になることを意味する。しかし、プロップ・ステーションの催しでは、チャレンジド本人たちの間にも、その厳しさに対する否定的な雰囲気は感じられない。 話は前後するが、今回のイベントで基調講演を行ったジャーナリストの櫻井よしこさんは、学級崩壊や金融業界の堕落を取り上げて日本社会の問題点を探り、こう述べた。 「結局、どんな人にも競争原理が働いて、自己責任でやっていく社会を作ることが大切なのだと思います。いままで『競争原理』というと、弱者をいじめるようなもののように考えられてきましたが、決してそうではない。むしろ、いままで弱者という枠に閉じ込められて来た人たちにチャンスを開くものなのです」 そして、イベントの最後に朗読されたプロップ所属の中村弘子さん(脳性麻痺で発話にも障害あり)の手記は、何もできなかった自分が2年足らずで仕事をもらえるまでになった喜びを綴り、次のように締めくくられた。 「私たちは多くの事を諦めてきましたが、納税者になることはまだ諦めていません。皆様のお力添えをよろしくお願いいたします」 「チャレンジド」(神から挑戦すべき課題を与えられた者という意味)という言葉を、改めてかみしめた。 |
|
中和正彦 (なかわ・まわひこ) 1960年神奈川県生まれ。明治大学文学部卒。出版社勤務の後、フリー編集者を経て取材執筆活動に専念。障害者支援の問題の他、バブル崩壊後の経済や社会、教育問題を幅広く執筆中。 |

|
|||
| IT産業界として、チャレンジドの在宅就労に注目する第一人者、成毛真マイクロソフト社長も2日間に渡って登壇 | |||

|
|||
|
行政の役割も大きい。羽曳野市の福谷剛蔵市長が取り組みを発言 |
|||
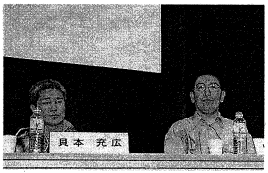
|
|||
|
チャレンジドのワーカーも自信を持って壇上で発言 |
|||
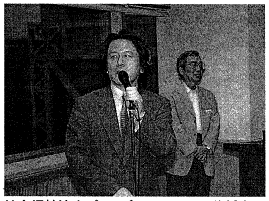
|
|||
|
社会福祉法人プロップ・ステーション後援会の初年度会長の金子郁容:慶應義塾大学大学院教授・慶應幼稚舎舎長。「できることを持ち寄ろう」 |
|||