― 農山漁村地域新生への提言 ―
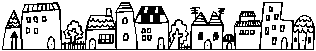
次世紀の地域づくりのあり方検討委員会
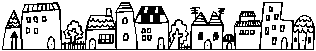
次世紀の地域づくりのあり方検討委員会
Ⅰ目 次
| 1.提言の背景と目的 | ||
| 2.農山漁村地域の長所と問題点 | ||
| 3.農山漁村地域新生に向けて踏まえるべき事項 | ||
| (1)踏まえるべき状況の変化 | ||
| (2)踏まえるべき計画・方針等 | ||
| 1)位置づけ | ||
| 2)社会資本整備上考慮すべき事項 | ||
| 4.農山漁村地域新生の着目点と将来像 | ||
| (1)着目点 | ||
| 1)地域の人々が住み続けられること | ||
| 2)都市地域の人々が農山漁村地域で多様なライフスタイルを実現できること | ||
| 3)安全で魅力ある国土づくりを担うこと | ||
| (2)将来像 | ||
| 1)農山漁村地域の人々が真に豊かさを感じられる地域 | ||
| 2)都市地域の人々が農山漁村地域の人々と連携・交流できる地域 | ||
| 3)個性豊かな多様性のある美しい地域 | ||
| 5.将来像実現の方策 | ||
| (1)方策 | ||
| (2)行政の支援方策 | ||
Ⅱ 全体フロー
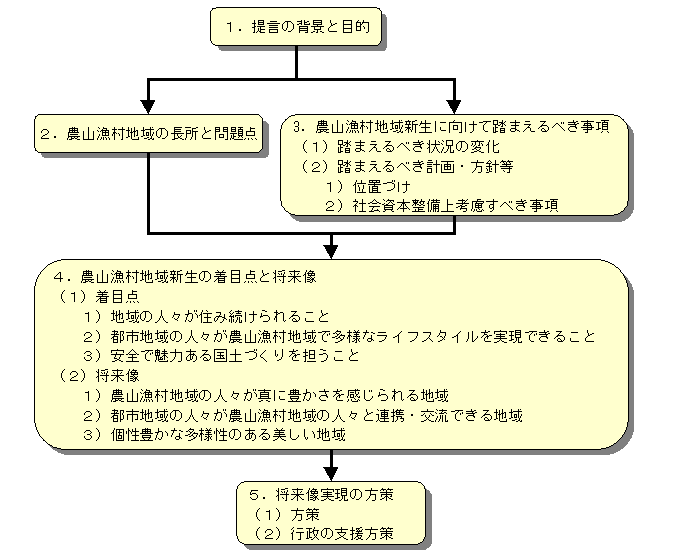
Ⅲ 提 言
1.提言の背景と目的
農山漁村地域は、国土政策において、国民の豊かな暮らしを実現し、さらに21世紀の新たな生活様式を可能とする国土のフロンティアとして、また「多自然居住地域」として位置づけられている。2.農山漁村地域の長所と問題点
しかし、農山漁村地域の現状をみると、過疎化・高齢化の進行、地域活力の低下等、農山漁村地域が抱える問題が深刻化しており、農山漁村地域の活性化は国土づくり・地域づくりの重要な課題となっている。
一方、国民の価値観の変化、ライフスタイルの多様化など、農山漁村地域をめぐる社会経済状況に変化が起きている。また、農山漁村地域を考えていくうえでは、森林の有する公益的機能などの維持や都市地域と農山漁村地域との交流・相互理解の向上がますます重要となってきている。
さらに、地方分権が進展する中で、地域が自ら考え、主体的に地域づくりを行うことが重要になってきており、そのような地域に対して行政は積極的な支援を行うことが期待されている。
このような状況の変化を踏まえ、新しい時代における国土づくり・地域づくりの観点から農山漁村地域のあり方と実現方策を示すことが本提言の目的である。
(1)農山漁村地域の長所
はじめに、農山漁村地域の長所についてみてみることにする。農山漁村地域には次のような長所がある。
①人々の心を和ませる豊かな自然環境や伝統文化
農山漁村地域には、四季それぞれの表情を見せる緑豊かな森林、時には激しくまた時には穏やかな流れをみせる清らかな川、美しい花を咲かせる植物や人々を楽しませてくれる動物など、多様な自然や生物が人々の心を和ませてくれる。②新鮮な農産物、良好な住環境、職住近接などゆとりある生活
また、農山漁村地域には、人々の暮らしと歴史に育まれた豊かな伝統文化が存在している。
このような豊かな自然や伝統文化は、ゆとりやうるおい、心の豊かさを求めるこれからの成熟社会においては何ものにも代えることのできない農山漁村地域の貴重な資源である。
農山漁村地域では、新鮮な農産物や魚介類を安く購入したり、自然環境に囲まれ、広い居住空間に住むことができる、また就業場所と居住場所が近いなど、ゆとりある暮らしを楽しむことが可能である。③相互に交流・助け合う地域コミュニティ
このような農山漁村地域の特性は、日常の暮らしを家族や仲間と楽しんだり、ゆとりやうるおいを求める人々にとっては大きな魅力である。
農山漁村地域には、人口の減少などにより地域社会が大きく変化したにもかかわらず、地域の人々が相互に交流し、助け合う、また、地域の多様な行事や環境維持を共同で行うというような地域扶助システムや地域コミュニティが残っている。(2)農山漁村地域の問題点
このような農山漁村地域のシステムを、新しい時代にふさわしいシステムに変革しながら後世の人々に残し、伝えていくことが重要である。
上述したような長所がある一方で、農山漁村地域には次のような問題点がある。
①少子高齢化・人口減少の進行、労働力の高齢化・後継者不足、若年層の地域外流出による地域活力の低下
農山漁村地域では、高度経済成長期以降、進学や就職等を契機に若者層を中心に人口の流出が進み、少子化ともあいまって、人口減少や高齢化が進行している。特に、学童・児童の減少は顕著であり、将来の農山漁村地域の担い手が少ないという点で大きな懸念がある。②農林漁業の存立が困難、生活の利便性や社会的サービス水準の低さ
また、労働力の高齢化や地域の産業の後継者不足、若年層の地域外流出が進行しており、農山漁村地域の活力の低下を招いている。
我が国の農林漁業は、外国との価格競争などにより存立が厳しい状況に置かれている。③就業機会の不足
また、農山漁村地域は、人口密度が低くものやサービスの需要が少ないことや、生活の利便機能へのアクセス性が低いことなどにより、生活利便性や社会的サービス水準が低くなっている。
若者の定住を促進するためには、若者が所得を得られる就業の場が不可欠であるが、農山漁村地域には農林漁業以外に就業機会が乏しく、それが若者などの定住を促進する上での問題点の一つとなっている。④農山漁村地域の有する個性や多様性の低下・喪失
農山漁村地域には、その地域の歴史や環境の中で形成されてきた多様な言葉や生活様式、文化、産業などが存在し、それらが複合化して地域独自の個性や多様性をつくってきた。⑤集落の崩壊、耕作放棄地の増加等国土の荒廃やそれに伴う国土管理機能の低下
しかし、地域づくりや地域特性等に対する人々の意識の変化、伝統行事や伝統文化等の後継者や担い手の減少などにより、長い年月をかけて培われてきた地域の個性や多様性が失われてきている。
人口の流出や高齢化の進行による集落の崩壊や担い手の減少・高齢化などにより管理されない森林や耕作放棄された農地が増加している。3.農山漁村地域新生に向けて踏まえるべき事項
これら管理されなくなった森林や農地により、国土が荒廃し、国土の保全という観点から問題となっている。
農山漁村地域の長所を生かし問題点を解決しながら、新しい時代にふさわしい農山漁村地域を新生していくためには、次のようなことを踏まえることが必要である。
(1)踏まえるべき状況の変化
今日、農山漁村地域をめぐって次のような状況の変化があらわれていることを的確に踏まえることが望まれる。
①国民の価値観・ライフスタイルの変化
総理府の調査等によると、1970年代後半以降、「心の豊かさ」を重視する国民の割合が「物の豊かさ」を重視する国民の割合を上回り、一定の生活水準を得た現在ではその差は年々拡大している。②農山漁村地域の有する価値を様々な角度から再認識・再評価
また、希望する居住形態として、「自然の豊かな地域に住宅を持ち、都市部まで通勤する」、あるいは「都市部に住宅を持ち、週末や休暇などには自然の豊かな地域に出かける」など、生活の中に自然との関わりを求める志向があり、近年は、省資源や省エネルギー、リサイクルなど環境問題への関心も高まっている。
このような国民の経済的な満足感よりも精神的な満足感を求めている価値観やライフスタイルの変化に着目することが必要である。
農山漁村地域は、食料生産の場、地域の人々の生活の場としての役割だけでなく、豊かな自然環境における国民の憩いの場、野外教育の場、レクリエーションの場としての役割など、多様な役割を果たしており、森林は木材を供給し、自然環境や国土を保全する役割などを果たしている。③地域内外との連携・交流・共生の広まり
このような農山漁村地域の国民的価値を再認識・再評価し、国民の豊かな暮らしを実現する地域づくりを行うことが必要になっている。
今日、人々の生活や経済活動などが広域化し、人々のニーズが多様化・高度化しているなかで、複数の地域が協力して解決すべき課題が増えている。④地域の自立・自主性の尊重
このため、地域内外との連携・交流を進め、異なった個性を持った地域が共生し、発展していくことが地域づくり上の重要な戦略になっている。
また、都市地域と農山漁村地域が相互の課題を克服し共生していくためには、相互交流と相互理解の向上を図っていくことが重要となっている。
今日、地方分権は時代の大きな流れになっており、農山漁村地域の個性や主体性を発揮しつつ、地域づくりを進めていくことが重要になっている。⑤歴史的な日本人の生活文化を再評価このため、地方分権の推進に応じた行政体制の整備・確立を図るとともに、農山漁村地域の自然、歴史、文化などの多様な資源を活用し、住民参加により自主的で創造的な地域づくりを行っていくことが求められる。
日本人は、あたかも山里に住んでいるような生活を味わう茶の湯、盆栽、盆石、俳諧などに示されるように、自然と共生した豊かな文化を創出してきた。⑥生活を支える技術の発展また、園芸が流行した江戸時代には、江戸の面積の6割を占めた武家屋敷の多くに林泉を構えた庭園が設けられ、庭園モザイック都市といわれるように、人々は自然を取り入れた生活を楽しんでいた。
下肥やゴミなどの廃棄物についても、江戸と周辺の農村の間で循環するシステムが形成されており、資源の有効利用が行われていた。
このように、わが国では自然と共生する生活文化や生活システムが形成され、地域は環境への負荷の少ない持続的な発展を遂げてきた。
ゆとりやうるおい、地球環境の保全などが社会の重要なテーマになっている今日、歴史的な日本人の生活文化を再評価し、現代に生かしていくことが必要になっている。
急速に進む情報通信技術の発達により、様々な情報の受発信、オンラインショッピング、遠隔医療、衛星教育、テレワークなどが進展し、社会や人々の暮らしを大きく変えている。(2)踏まえるべき計画・方針等また、高速交通体系の整備により、地域間の移動に要する時間や地域から国際空港へのアクセス時間の短縮が進み、通勤や通学、広域的な地域間の連携と交流、海外との交流などが容易になってきている。
ほかに、環境にやさしい新エネルギー技術、資源のリサイクル技術、福祉・医療・生命関連の技術なども発展している。
1)位置づけ
近年における国の主要な計画・方針である「21世紀の国土のグランドデザイン」及び「経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針」では、今後の国土づくり・地域づくりについて次のように位置づけており、農山漁村地域においてはこれらを踏まえた地域づくりが必要である。
①21世紀の国土のグランドデザイン
中小都市と中山間地域等を含む農山漁村地域等の豊かな自然環境に恵まれた地域を、21世紀の新たな生活様式を可能とする国土のフロンティアとして位置づけるとともに、地域内外の連携を進め、都市的サービスとゆとりある居住環境、豊かな自然を併せて享受できる誇りの持てる自立的な圏域として、「多自然居住地域」を創造するとしている②経済社会のあるべき姿と経済新生の政策方針(第1部 国土計画の基本的考え方/第2章 計画の課題と戦略/第2節 課題達成のための戦略)
東京を頂点とする階層型の国土構造から、個人や地域の自主性、多様性を尊重することにより、効率的で生産性の高い国土構造に転換することと同時に、時間的・空間的ゆとりといった豊かさの増進・持続、国土の安全・安心が実現するとしている。2)社会資本整備上考慮すべき事項(第二部 経済社会のあるべき姿/第1章 多様な知恵の社会/第5節 多様性のある国土)
公共投資基本計画(平成6年10月7日閣議了解)では、都市と比較して相対的に劣っている生活環境の向上に向けて、生活基盤の整備を促進するとなっている。
また、2000年度版建設白書では、人口減少社会を迎え、また循環型社会への移行が喫急の課題となる中で、良いものに手入れ(維持・修繕・改修)を加えながら長く使っていくという、ストック重視の社会を目指すことにより生活の「質」の向上を目指すとしており、今後は、農山漁村地域においても同様の視点を重要するとともに、これまでに蓄積された社会資本を有効に活用していくための方策の充実を図っていくことが必要である。
4.農山漁村地域新生の着目点と将来像
(1)着目点
農山漁村地域の問題点及び踏まえるべき事項に基づき、農山漁村地域新生にあたって次の事項に着目する。
1)地域の人々が住み続けられること
農山漁村地域に居住している人々が誇りをもって地域に住み続けられ、安全で快適に、そして、経済的にも安定し、健康的で、心の豊かさを保てる暮らしを実現すること。
2)都市地域の人々が農山漁村地域で多様なライフスタイルを実現できること
国民の価値観やライフスタイルが変化する中で、農山漁村地域で多様なライフスタイルを実現しようとする人々が増加しており、農山漁村地域の人々と都市地域の人々が共同でこのような状況に対応した地域づくりを行うことにより、都市地域の人々が交流や余暇活動、居住、就業等を実現できること。
3)安全で魅力ある国土づくりを担うこと
多様な自然、長い歴史に育まれた個性豊かな景観や伝統文化、環境と調和した生活文化など、個性豊かで多様性のある美しい農山漁村地域を保全・育成あるいは回復し、安全で魅力ある国土づくりを担っていくこと。
(2)将来像
農山漁村地域新生の着目点を踏まえ、これからのあるべき農山漁村地域の将来像を次のように提案する。
1)農山漁村地域の人々が真に豊かさを感じられる地域
農山漁村地域に暮らす人々が真に生活の豊かさを実感できる地域を創造していくことが重要である。
①安全で快適な生活を享受できる暮らし
(豊かな自然を享受できる暮らし)農山漁村地域には豊かな自然が存在し、澄んだ空気、安全な水などを享受できることが大きな魅力である。
このような豊かな自然の中で、四季折々の自然の変化などを楽しみ、自然に溶け込んだ心豊かな暮らしをすることがこれから重視される必要がある。
(都市では得られない広々とした居住環境での暮らし)②安定した生計を営む暮らし暮らしの場である居住環境についても豊かさが求められており、自然を取り込んだ広々とした居住環境の中で、心豊かな暮らしを実現することが必要である。
(生活基盤、情報通信基盤が整備された暮らし)
都市へのアクセスや地域間の移動を向上させる道路、豊かな水環境を適切に保全する下水道、水と緑に親しみ多様な自然とふれあえる河川、豊かな余暇生活の向上に資する公園などの生活基盤や大量の情報を高速に受発信することが可能な情報通信基盤の整備が重要である。
これらの整備により生活に必要な機能が充実されるとともに、これらの基盤を通じて、これまで得ていたサービス水準が向上したり、オンラインショッピング等の新しいサービスを得る機会が増えるなど、自然豊かな環境の中で快適な暮らしが実現できることが重要である。
(安全が確保された暮らし)
治水対策、土砂災害対策、代替性を考慮した道路などのネットワークの構築、道路防災対策、除雪などの冬期交通確保対策などが推進され、清らかで安全な水の保全が図られるなど、安全で安心できる暮らしの確保が重要である。
(都市的サービスを享受できる利便性の高い暮らし)
周辺の地域や中心都市と連携して、より高い都市機能やサービスを享受できるようにするなど、農山漁村地域に住む人々が快適で利便性の高い暮らしを実現できるようにすることが必要である。
(農林漁業が活性化された暮らし)③健康で安心できる生活を享受できる暮らし消費者のニーズや行動などが多様化する中で、新しいビジネスチャンスが増加しており、販売方法までを考えた消費者志向の付加価値の高いマーケティングを行い、農林漁業の活性化を図っていくことが必要である。
(地域資源と新技術を活用し、地域に立脚した産業が活性化され、就業機会が確保された暮らし)
農山漁村地域には、森林等の自然、歴史、文化などの各種地域資源が賦存しており、新しい科学技術を積極的に取り入れながら地域の多様な資源を複合的に活用し、若者にも魅力のある地域に立脚した新しい産業の創出や地場産業の高度化を図り、就業機会を確保していくことが必要である。
(情報技術(IT)を活用して距離的ハンディキャップを乗り越えて仕事ができる暮らし)
情報通信技術の発達により、距離的ハンディキャップを乗り越えてネットワークを活用しながら自宅などで仕事をすることが可能となりつつあり、農山漁村地域においてもその推進を積極的に図ることが重要である。
(都市への通勤が可能な暮らし)
新幹線や高速道路などの高速交通体系の整備により、農山漁村地域から都市地域への通勤が可能となっており、高速交通体系へのアクセス性の向上などを通じて一層その推進を図っていくことが必要である。
(医療・保健・福祉機能の充実した暮らし)④心の豊かさや地域への誇りを育む暮らし農山漁村地域の人々が健康で安心できる生活を送ることができるよう、周辺地域との連携を推進しながら医療、保健、福祉機能の充実を図ることが必要である。
(相互扶助精神等の地域の豊かな生活文化に根ざした暮らし)2)都市地域の人々が農山漁村地域の人々と連携・交流できる地域農山漁村地域には、相互扶助精神や祭り、季節の行事などの豊かな生活文化が賦存しており、それらを継承・活用していくとともに、時代の変化にふさわしく見直していくことも必要である。
(豊かな心や地域への誇りを育む学校教育や生涯学習の充実した暮らし)
豊かな自然や伝統文化のある農山漁村地域では、子供達の豊かな心と地域への誇りや愛着を育むことができる個性的な学校教育を展開するとともに、都市地域の子供達を積極的に受け入れ、豊かな自然とのふれあいや地域の行事に参加することなどを通じて、子供達の豊かな心と生きる力を育くんでいくことも重要である。
また、学ぶことに対する地域の人々のニーズに応え、生涯学習の充実を図り、生きがいのある暮らしを実現する必要がある。
(地域の人々のコミュニケーションが盛んな暮らし)
地域の行事など多様な機会を通じて積極的に世代間・地区間のコミュニケーションを図り、農山漁村地域の人々の相互理解、地域への認識を深めるとともに、人々の地域への誇りと愛着を醸成していき、人にやさしく、心の豊かさを保てる暮らしを実現していくことが必要である。
経済や社会が大きく変化する中、国民のライフスタイルも多様化しており、農山漁村地域は、都市地域の人々が農山漁村地域の人々と連携・交流し、多様なライフスタイルを実現する地域として発展することが重要である。
①多様な交流の実現
(都市地域の人々が農山漁村地域の人々と多様な交流を実現)②多様な余暇活動の実現都市地域の人々が多様化するニーズやライフスタイルを実現できるよう、農山漁村地域では、都市地域の人々と野外学習や環境教育、産直などの多様な交流を積極的に行い、相互理解を図っていくことが重要である。
(多様な資源を利用した観光、余暇活動の実現)③多様な居住形態の実現人々の自然志向が増大する中、都市地域の人々の農山漁村地域における自然や文化、農林漁業等の体験や創作活動など多様な資源を利用した観光、余暇活動はますます増大することが予想される。
農山漁村地域では、都市地域の人々のニーズを把握し、農山漁村地域の自然、歴史、文化、産業等の様々な資源を活用し、都市地域の人々の期待に応えていくことが重要である。
(保養、レジャー、仕事などを目的とした多様な居住形態の実現)④多様な就業形態の実現人々の価値観が変化する中で、自然の豊かな地域に住宅を持ち、都市地域まで通勤したり、普段は都市地域に住みながら週末や休暇などには自然の豊かな地域で生活することを希望する人々が潜在的に多数存在している。
このように、定住、週末滞在、季節滞在など居住形態に関する都市地域住民のニーズは多様であり、このようなニーズに応えるため、農山漁村地域では、保養、レジャー、仕事などを通じた多様なライフスタイルを育む居住形態を実現することが必要である。
同時に、都市地域の人々は、単に農山漁村地域に居住・滞在するだけでなく、祭りや地域活動、地域コミュニティ等に参加して農山漁村地域の人々と積極的にふれあうことが重要である。
(都市地域の人々が農林漁業等への就業を実現)⑤主体的に社会参加できる地域の実現農山漁村地域における農林漁業就業者の高齢化・後継者の不足が深刻であるが、都市地域では、農林漁業への就業を希望する人々が増加しており、このような人々に対し、情報提供や技術指導等の支援などを行っていきながら、共に働くことができる就業環境をつくりだしていくことが必要である。
(SOHO等ITを活用した新たな就業を実現)
豊かな自然環境の中で情報技術を活用した新たな事業を始めたい人々や、情報技術を活用しながら仕事を集中的に進めたい人々の希望を実現できるよう、農山漁村地域では、都市地域の企業や専門家の協力を得ながら、ITを活用した新たな就業の実現のための環境整備を行っていくことが望まれる。
(農山漁村地域への通勤を実現)
都市地域に定住しながら農山漁村地域へ通勤して、自然の豊かな環境の中で働くことを希望する人々の潜在的なニーズに応えるため、農山漁村地域では就業機会の整備を進めるとともに、都市地域の人々に対する情報提供を行っていくことが重要である。
(ボランティア等に開かれた地域の実現)3)個性豊かな多様性のある美しい地域社会的な問題に無償で積極的に取り組むというボランティア意識が高まっており、農山漁村地域においては、都市地域のボランティアによる多様な活動や基金の創出などが各地で行われている。
今後は、このようなボランティア活動の高揚を踏まえ、ボランティアなどに開かれた地域の実現が重要である。
自然との共生、地域の景観・歴史・文化環境の保全、環境との調和、地域間の連携と交流を重視した、個性豊かな多様性のある美しい農山漁村地域の創造が重要である。
①多様な自然と共生する安全な地域
(様々な機能を有する自然環境が適切に保全・復元された地域)②個性豊かな地域の景観・歴史・文化を大切にする地域農山漁村地域において環境保全上の多様な機能を有する自然環境が、農山漁村地域の人々による努力や都市地域の人々の支援等により適切に保全されるとともに、荒廃した森林や耕作放棄地等が適切に復元されることが望まれる。
(多様な自然を大切にする意識に支えられた地域)
多様な自然を適切に保全していくため、様々な機会を通じて農山漁村地域の人々の自然保全意識を高め、自然保全のための取り組みを推進していくことが必要である。
(景観・歴史・文化が保全された地域)③環境と調和して持続的に発展する地域農山漁村地域には四季折々の表情を見せる美しい自然の景観や人々が暮らしてきた歴史、そして祭り、伝統芸能などの文化が豊富である。これらの景観・歴史・文化はそれぞれの地域の貴重な財産であり、地域全体として保全し、発展させていくことが大切である。
(景観・歴史・文化を大切にする意識に支えられた地域)
農山漁村地域の貴重な景観・歴史・文化を保全・振興するためには、学校教育や生涯学習を通じて、地域の人々が郷土の歴史や文化、そしてそれを保全・振興することの意義を学び、地域文化の後継者として地域文化の保全・振興活動を積極的に行っていくことが必要である。
その際、都市地域へ情報の発信を積極的に行い、農山漁村地域の文化の保全・振興に関心を持つ都市地域の人々の参加を募っていくことも大切である。
(環境にやさしい地域)④国内外との連携・交流が盛んな個性的地域地球環境に負荷を加えず、後世の世代にも負担をかけずに持続的に発展する地域を創出していくため、農山漁村地域では今後も森林などの自然環境を保全し、省エネルギー、バイオマスエネルギーや風力エネルギーなどの自然エネルギーの導入を進め、環境にやさしい地域づくりを行っていくことが望まれる。
また、生ゴミなどの廃棄物を資源として地域内でリサイクルするなど、農山漁村地域が有していた環境と調和した暮らし方を現代的に再生させることも重要であり、その取り組みを推進することが望まれる。
(環境保全意識が醸成された地域)
環境にやさしい農山漁村地域を形成していくため、学校教育や生涯学習を通じて地球環境の現状や環境にやさしい地域づくりの意義、自分の生活と環境保全との関わりなどを学び、地域の人々の環境保全意識を高め、日常生活のレベルで環境保全型の暮らしを行っていくことが重要である。
(外に開かれアイデンティティを有する地域)5.将来像実現の方策
連携・交流を推進するため、農山漁村地域の自然・歴史・文化などの地域資源を評価・活用し、多様な分野で他の地域にはない個性的な地域づくりを行うとともに、国内外に開かれた地域づくりを行っていく必要がある。(人々の連携・交流意識が醸成された地域)
他の地域との連携・交流を推進するためには、連携・交流意識の醸成とともに、農山漁村地域の多様な人々が交流の意義を認識し、それぞれが主体的に取り組むことが重要である。
前述した「農山漁村地域の将来像」を実現するためには、地域自らが責任をもち、主体的に新しい地域づくりを進めていくことが必要である。(1)方 策行政は、そのような地域の人々の取り組みを支援することを基本として施策の展開を行うことが重要である。
1)人々の暮らしの満足度の向上
①住民ニーズに応えた地域づくり
地域づくりにおいては、住民の暮らしの満足度の向上が基本に位置付けられることが必要である。そのためには、住民が何を求めているか、何に困っているかなど、住民のニーズを正確に把握することが必要である。②新しいサービス主体の活用特に、住民の顕在化したニーズだけでなく、潜在化しているニーズを把握し、地域の置かれている状況や経済社会の潮流を踏まえながら、それを実現するための方向性を行政が提案していくことが重要である。
多様化・高度化している住民のニーズを実現するためには、住民、行政、企業などの多様な主体の参加と協力によるサービスの提供が不可欠である。このような多様な主体の参加は、行政のみでは対応しきれなかった分野を補完し、きめ細かなサービス提供を可能とする。③多様な選択肢の提供農山漁村地域においては、従来は行政や第三セクターが主なサービス提供主体であったが、これからは、地域の非営利組織(NPO)や住民組織などの新しいサービス主体の育成・支援・活用が重要である。
農山漁村地域では就業、就学などにおいて選択肢が限られていることが大きな問題であり、それが人口流出の大きな要因の一つとなっていた。2)地域の人々が主体となる自立した地域づくり今後は、多様なサービス主体の活用とITなどの新しい技術の導入・活用により、暮らしの様々な面で選択肢を増やしていくことが望まれる。
①住民主体の地域づくり
計画づくりから運営までの各段階・多様な場面において多様な住民が参加し、行政や非営利組織、企業などと一緒になって地域づくりを行っていくことが重要である。②地域の自立性・自己責任性の明確化そのためには、行政は住民に対して地域づくりに関する情報を公開し、行政と住民が情報を共有することによって地域づくりへの関心を高めるとともに、住民が参加しやすい仕組みをつくることが必要である。
新しい農山漁村地域を創造するためには、地域の将来ビジョンとその実現プロセス・実現方策を明確にし、地域が自立・自己責任の意識を持って多様な主体の参加と連携により、個性的で魅力的な地域づくりを行うことが必要である。③パートナーシップの推進と仕組みづくりそのためには、農山漁村地域の多様な主体が、経済社会の変化や地域づくりの方向性などについて幅広い観点から検討していくことが重要である。
これからは、行政、非営利組織、住民団体、企業など農山漁村地域の多様な主体が地域づくりのパートナーとしてそれぞれの役割を明確化し、お互いに協力しながら個性的な地域の創造を実現していくことが必要である。④地域の人々を導くリーダーシップの強化
近年、各地でパートナーシップの取り組みが進められており、その取り組みのノウハウや仕組みについて情報の収集・学習等を行い、パートナーシップの地域づくりを推進していくことが望まれる。
農山漁村地域の人々が主体となった自立した地域づくりを進めるためには、地域の人々に信頼され、人々の意欲を引き出し、夢を実現する道筋を示すことのできるリーダーが必要であり、特に、地域の代表者である市町村長の果たすべき役割が重要である。3)総合的・計画的な地域づくりまた、これらリーダーシップを発揮できる人々をサポートする体制づくりも重要である。
このためには、地域づくりの各分野、各事業において専門能力を持った人が不可欠であり、専門能力を有する人材の育成・確保が重要である。
①地域の総合的プロデュースの実践
国民や社会のニーズは多様化・高度化するとともに、複合化してきている。今後は分野ごとの個別の取組ではなく、地域の人的・物的・情報資源を総合的に活用し、地域全体として最適化を図っていく地域経営の視点が重要である。②地域づくりを支援するコンサルティング機能の強化・育成
総合的・計画的な地域づくりを推進するためには、プロデューサーとともに、地域づくりに関する様々なアドバイス、コンサルテーションを行う専門家の活用やコンサルティング機能を農山漁村地域の中で強化・育成していくことが必要である。③各種制度を用いた土地利用の整序農山漁村地域におけるコンサルティング機能としては、行政、第三セクターの地域づくり組織、非営利組織、パートナーシップ型の組織など様々なものが想定されるが、地域の状況にふさわしい形態の組織を強化・育成していくことが望ましい。
近年、既存集落周辺や幹線道路の沿道、高速道路のインターチェンジ周辺などにおいて開発行為や建築行為が集積し、用途の無秩序な混在、景観の悪化などが見られる。4)地域資源や地域の暮らし方の再認識と活用「準都市計画区域制度」などの各種制度を用いてこのような行為を規制し、秩序だった美しい農山漁村地域の形成を図っていくことが必要である。
①地域資源の有する価値の認識
環境問題への意識が高まるなかで、風、地熱などは風力エネルギー、地熱エネルギーなど自然エネルギーとして環境への負荷の低減に貢献している。また、森林の有する公益的機能などの維持も重要になってきており、農山漁村地域が有する自然をはじめとする地域資源への人々の関心は高くなっている。②創意工夫を凝らした地域づくりこのような環境保全、公益的機能をはじめとする地域資源の価値を認識し、地域づくりを考えていく上で付加価値あるものとして、これらの積極的な活用を図っていくことが重要である。
農山漁村地域には自然、歴史、文化などの多様な資源が賦存しており、それらは地域の貴重な資源である。地域内外の人々の知恵や助言を得ながら、経済社会の変化を踏まえた新しい視点からこれらを創意工夫して活用することが必要である。③地域の暮らし方や相互扶助システムの見直し・活用農山漁村地域の発展は地域の資源を大切にし、その活用を図ることを通じて達成されるため、創意工夫をこらした地域づくりが重要である。
農山漁村地域には、長い歴史に培われた地域固有の暮らし方や暮らしの工夫・知恵、相互に助け合うシステム、共同で地域環境を管理するシステムなどが残っている。5)情報技術や環境技術等の活用これらの優れた暮らし方や生活の知恵、地域のシステムなどについては、時代の変化にともない必要な見直しを行いつつ積極的に活用するとともに、都市地域へ情報発信していくことが大切である。
①情報技術の活用
情報技術は、農山漁村地域の立地や地形などの面でのハンディを乗り越え、時間的・距離的に自由な活動を行うことを可能としており、情報技術の活用により農山漁村地域は大きく発展する可能性がある。②環境技術等の活用このため、農山漁村地域では、都市地域以上に積極的に情報技術の導入と情報基盤の整備、人々の情報技術の活用能力の向上を図り、地域の人々の生活の向上や産業の振興を図っていくことが重要である。
環境や医療、バイオテクノロジーなどの多様な分野で科学技術が発展しており、農山漁村地域の人々は、地域外の企業、専門家、有識者との情報交流を行い、科学技術の開発動向に細心の注意を払うことが必要である。6)マーケティングの発想と実践農山漁村地域への導入可能な科学技術については、関係者の支援を得ながら積極的に福祉、医療、環境、産業等多様な分野に導入し、地域の人々の福祉や利便性の向上、産業の振興などを図っていくことが必要である。
①マーケティングの発想
今日のように人々のニーズが多様化し市場が細分化している状況では、従来の手法は通用しなくなっている。
このような状況を踏まえ、農山漁村地域の企業はねらうべき市場を明確化したうえで標的顧客のニーズを把握し、顧客が望む商品の開発と提供を行い、顧客満足度を高めるマーケティング発想に立つことが重要である。②産業の振興など多様な分野におけるマーケティングの実践
顧客満足度を高める顧客志向のマーケティングの導入により、農山漁村地域の規模の小さな企業でも独自の市場を獲得し、事業を発展させることが可能となっている。7)暮らしや活動を支える社会資本の整備推進このような顧客志向のマーケティングを、産業振興を図る企業はもとより行政の多様な分野で実践することが必要であり、人材の育成や産業振興を図り、農山漁村地域における雇用の機会を拡大することが望まれる。
①長持ちする社会資本の整備
社会資本がそのストック効果を発揮するためには、適切な維持管理を適時行うことにより、長期に渡って活用されることが必要である。②自然や人にやさしい社会資本整備の推進そのため、ライフサイクルコストを視野に入れ、将来の維持管理をやりやすくしたり、維持・更新のための事業であっても、従来の姿や機能を復旧するばかりでなく、より高いストック効果や生産力効果を持つ社会資本としていく配慮が必要である。
環境重視の高齢社会においては、社会資本は自然や人にやさしいものであることが求められる。③居住環境を支える社会資本整備の推進自然にやさしい社会資本の整備にあたっては、自然環境をできるだけ保全し、環境への影響の回避、軽減、解消に努める必要がある。また、自然の再生やミティゲーションを積極的に推進する必要がある。
人にやさしい社会資本の整備にあたっては、デザインや素材の選定などあらゆる面で高齢者や障害者を始め誰もが使いやすいものにすることが必要である。
農山漁村地域の居住者が快適で安全性・利便性の高い暮らしを実現できるように、道路、河川、砂防、下水道、公園などの生活基盤の整備を推進することが必要である。④連携・交流の活動を支える社会資本整備の推進
これからの地域づくりにおいては他の地域との連携・交流を進め、住民の多様化するニーズへの対応、住民の就業・就学機会の拡大、都市的機能へのアクセス性の向上などを推進することが必要であり、それを支える社会資本の整備が重要な意義をもっている。⑤住民との情報の共有化とコミュニケーション推進の基盤となる社会資本の整備今後は、地域間の連携・交流の促進という観点から幹線道路や、交流の拠点となる道の駅、水辺プラザ等の整備を推進していくことが必要である。
住民主体の地域づくりを進めるためには、地域づくりに関する情報を行政と住民が共有したり、地域の多様な主体間のコミュニケーションを推進することが重要であり、今後は、それを実現するため、インターネット等を用いた情報提供、情報提供施設の整備、交流の場の提供等を推進することが必要である。8)情報の受発信とネットワークづくり
①情報の受発信
都市地域の人々と農山漁村地域の人々が交流・連携し、相互理解を進めるために、また農山漁村地域に不足している情報や知識を都市地域から収集するために、農山漁村地域では都市地域の人々に積極的に地域の情報の発信を行うとともに、都市地域の各種情報を受信し、交流・連携などの地域づくりの取り組みに活用していくことが重要である。②ネットワークづくり
都市地域の人々の深い理解と強力な支援に支えられた地域づくりを行っていくためには、都市の専門家、技術者、有識者、住民など幅広い人々とのネットワークの形成が重要である。9)人材の育成ネットワークの形成のためには、農山漁村地域から都市地域への継続的な情報の発信とともに、多様な人々が参加できる仕組みづくりや地域に関わりを持つ人々に関するデータベースの作成、都市地域の人々に開かれた地域社会の形成を行っていくことが必要である。
①地域の人々の意識の変革
地域に対して誇りを喪失したり、社会の変化に対して人々の意識が変わっていない農山漁村地域が多くみられ、それが地域の活性化の大きな障害となっている。②地域を担う人材の育成このような中で、住民が主体的に地域づくりに参加するためには、地域を変えていこうという意識やこれまで評価されず見捨てられていたものを再評価・再活用していこうとする意識の変革を持続的に行っていくことが必要である。
学校教育や生涯学習を通じて地域の誇りや地域づくりに関する人々の意識を変革していくとともに、具体的な事業を通じて地域の各種事業を担う人材を実践的に育成していくことが重要である。(2)行政の支援方策具体的な事業を通じて人材を育成していく上で重要なことは、首長及び事業責任者の理解と支援であり、地域のトップに立つ人が意欲のある若者達を導き、育てていくことが重要である。
また、男女がともに地域づくりに関する意見を出し、ともに参加できるよう地域の人々の意識を変えていくことや仕組みを整えていくことも重要である。
これまで将来像実現の方策について提案してきたが、行政は次のような支援が必要である。
①地域ニーズを踏まえ、地域の自主性を尊重した支援
人々の暮らしの満足度の向上や、農山漁村地域の人々が主体となった地域づくりを進めていく上では、地域のニーズや意向、地域の自主性を尊重し、多方面での多面的な支援を行うだけでなく、行政と地域の人々が一体となった取り組みを進めていくことも必要である。②自ら考え、主体的に取り組む地域に対する社会資本整備の積極的な支援
自ら考え、主体的に取り組んでいる農山漁村地域へ優先的に社会資本整備を支援するなど、"前進するために努力している地域"を伸ばすことに重点を置いた支援方策の実施が重要である。③農山漁村地域の条件不利を克服するための優先的支援
条件が不利な農山漁村地域の活性化を図るため、行政は地域の活性化へ大きな影響を及ぼす支援を優先的かつ集中的に行い、農山漁村地域が条件不利地域性を克服し、発展の軌道に乗せることを可能とするような方策を実施していくことも今後望まれる。④地域の活性化に大きな効果が期待できる社会資本整備への重点的支援
限られた予算の中で社会資本の整備を効率的・効果的に進めることが重要であり、地域活性化に大きな効果が期待される社会資本の整備に対する重点的支援を行っていくことが必要である。⑤社会資本を活用したイベント等の計画策定への支援
農山漁村地域の活性化を図るためには、農山漁村地域の人々と都市地域の人々が交流するイベントの実施、農山漁村地域の特産物や文化などの提供など、農山漁村地域の多様な主体が連携し、道路、河川、公園などの社会資本を有効に活用していくことが重要である。⑥地域づくりに関する情報の提供と農山漁村地域の人々が利用しやすい相談機能の充実今後は、このような社会資本を活用したイベントなどのソフト事業を実施するための計画策定に対しても行政の支援が必要である。
農山漁村地域においては、地域づくりに関する情報を収集・蓄積・活用することが重要である。⑦行政機関間の連携強化行政は、農山漁村地域の人々が必要とする情報を容易に入手できる情報提供システムと体制を構築するとともに、地域づくりに関する多様な相談に応じられるよう、相談機能を充実していくことが望まれる。
農山漁村地域の活性化に関する施策は多様な機関で実施されており、施策内容は多様である。行政は地域のニーズを的確に把握し、これらの多様な施策をより効果的・効率的に展開するために、関係する行政機関相互の連携と交流を強化していくことが重要である。⑧広域的な連携・交流を推進するための情報や社会資本整備などの面での支援
今後の地域づくりにおいては、周辺の地域をはじめ広範な地域との連携と交流を推進することが重要である。行政においては、農山漁村地域の人々が連携・交流を推進することができるよう、連携・交流の進め方、他の地域に関する情報、連携・交流が成功している地域のノウハウなどに関する情報の積極的な提供、連携・交流をさらに推進しやすくする制度の改善、連携・交流を支える幹線道路や交流拠点などの整備への支援を行っていくことが必要である。
以 上