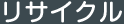建築解体廃棄物リサイクルプログラム
建築解体廃棄物リサイクルプログラム
平成11年10月
建設省
| 目次 |
| ■建築解体廃棄物のリサイクル推進の必要性 | ||
| (1)基本的認識 (2)建設廃棄物の現状 (3)廃棄物をめぐる状況 (4)建築解体廃棄物のリサイクル促進の必要性 |
||
| ■建築解体廃棄物のリサイクルの課題 | ||
| 1.建築物の新設時の課題 (1)短い期間での建築物の更新 (2)設計・建築段階において十分な評価がなされない安全性、解体容易性等 |
||
| 2.建築物の解体時の課題 (1)適正な積算、支払いが行われない解体工事コスト (2)チェックされない解体工事と解体工事業者 (3)依然として大量に排出される建設混合廃棄物 (4)確立されていない解体工事施工技術 |
||
| 3.建築解体廃棄物の再資源化時の課題 (1)再資源化施設の不足 (2)再資源化の困難な建築解体廃棄物 (3)リサイクル産業の現状 |
||
| 4.リサイクル市場の課題 (1)拡大しない再生資源の需要 (2)整備されていない品質基準 (3)リサイクル市場の情報不足 |
||
| ■リサイクルの輪をつなげる戦略 | ||
| ●建設行政の役割 | ||
| ●課題に対する戦略 | ||
| 1.建築物の長寿命化促進等の新設時における戦略 (1)長寿命化技術の開発等と長期使用 (2)設計・計画段階における廃棄物の発生抑制等の技術開発 |
||
| 2.建築物の分別解体促進の戦略 (1)発注者による適正なコスト負担責務の明確化と適正な契約の確保 (2)解体工事チェックシステムの創設と分別解体の実施 (3)解体工事業者の育成等のための制度の創設 (4)解体工事の施工技術基準等の策定と施工技術の開発 |
||
| 3.建築解体廃棄物の再資源化促進の戦略 (1)再資源化責任の明確化 (2)再資源化施設の整備に対する支援 (3)再資源化困難物のリサイクル技術開発 |
||
| 4.リサイクル市場の形成の戦略 (1)再生資材の利用促進 (2)再生資源の利用用途の開拓と再生資材の品質基準の策定 (3)リサイクル材及び再資源化施設の情報交換システムの構築 (4)民間の技術開発に対する支援 |
||
| ●建築解体廃棄物のリサイクルを促進するための法制度化 | ||
| ■公共土木工事におけるリサイクル推進の取り組み | ||
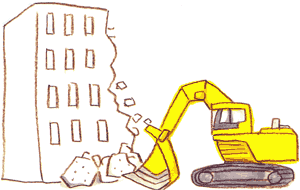 (1)基本的認識
(1)基本的認識建設産業は、全産業の資源利用量の約5割を建設資材として利用している。一方、建設工事に伴い排出される廃棄物(建設廃棄物)は全産業廃棄物の排出量の約2割を占め、最終処分量では約4割を占める。また、厚生省の調査によれば、不法投棄量の約9割が建設廃棄物とされている。
すなわち、建設産業は、資材の利用、廃棄といった面で極めて大きな影響を有する産業であり、このことを建設工事の関係者がしっかりと認識し、建設廃棄物の発生抑制、リサイクルの徹底を図ることが、我が国における資源循環型社会を構築する上で強く求められている。
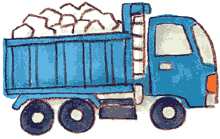 (2)建設廃棄物の現状
(2)建設廃棄物の現状建設廃棄物の約6割が土木工事に伴い排出される土木系廃棄物であり、残りの約4割が建築工事に伴い排出される建築系廃棄物であるが、土木系廃棄物の平成7年度におけるリサイクル率が68%であるのに対して、建築系廃棄物は42%と大きな開きがある。この建築系廃棄物のうち6〜7割が建築解体廃棄物で占められ、さらには、建設廃棄物の不法投棄量の中でも、主に戸建住宅の解体工事に伴い排出される木くずの占める割合が高いと言われている。
この背景として、土木工事は主に公共工事であり、土木工事から大量に発生するコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊のリサイクルについては、公共工事発注者が先導的役割を果たしてきたのに対し、建築工事のうち、その大半を占める民間工事においては、特に解体工事やリサイクルに要するコストに対する理解が得られにくいこと、建築工事が土木工事に比べ一件の解体工事に伴い排出される廃棄物が多種にわたり、かつ各々が少量であるという特色を有することなどもあり、建設業界をはじめとする関係者において、リサイクルはもとより、廃棄物対策全般について責任ある取り組みが必ずしも十分になされてこなかったことがある。
したがって、建設廃棄物の中でも建築解体廃棄物の発生抑制、リサイクルに関する対策が、特に重要な課題となっている。
(3)廃棄物をめぐる状況
厚生省の調査によれば、平成9年3月末時点の最終処分場の残余容量は、首都圏で1.0年分、全国で3.1年分と極めて逼迫している。一方、平成9年12月の廃棄物処理及び清掃に関する法律(以下、「廃掃法」という。)施行令の改正により、従来、安定型最終処分場で処分できた石膏ボードなどが、管理型での処分品目となるなどの見直しが行われた。また、安定型で処分できる品目に関しても、それ以外の品目が混入したり付着したりした場合は、管理型で処分しなければならなくなるなど、安定型処分品目に対する規制・監視の強化が行われた。これらのことにより、既に管理型処分場での処分費用の値上がりが一部の地域で見られる。建築工事から排出される石膏ボードはもとより、建築解体工事から発生される廃棄物が、現状のように混合状態で排出されれば、管理型処分場で処分されることとなる。これにより、管理型処分場の逼迫がますます高まり、その対応が重要な課題となっている。
他方、ダイオキシンに対する規制も、平成9年の廃掃法改正で強化された。さらに、今国会では「ダイオキシン類特別対策措置法」も成立した。ダイオキシンの発生量の大半は廃棄物の焼却により発生している。廃棄物の焼却は、必ずしもリサイクルの促進につながらない。しかし、建設廃棄物のうち、特に建築解体工事から発生する木材は、品質等が劣ることもあり、減量化のため焼却されてきた。今後は、これらの焼却量を削減し、実質的なリサイクルによる減量化が重要な課題となっている。
(4)建築解体廃棄物のリサイクル促進の必要性
建設廃棄物の現状及び廃棄物をめぐる状況でも示したように、建設廃棄物の中でも建築解体工事からの廃棄物対策が重要な課題となっている。
他方、これまでの建築物着工床面積の推移を見ると、昭和40年代以降床面積は急激に増大している。今後、これらの建築物が更新期を迎えることから、建築解体廃棄物の排出量の急激な増大が見込まれる。
このため、建築解体廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進に関する総合的な対策を早急にとりまとめ、それを実現していくことが強く求められている。(なお、このような背景も踏まえ、平成11年3月にダイオキシン対策関係閣僚会議でまとめられた「ダイオキシン対策推進基本指針」においても、建築解体廃棄物の分別・リサイクルの推進の必要性が盛り込まれている。)
■建築解体廃棄物のリサイクルの課題
1.建築物の新設時の課題
(1)短い期間での建築物の更新
我が国では建築物が建築されてから消滅するまでの存続期間は、木造住宅、非木造住宅とも30年から40年程度であり、欧米諸国に比べて極めて使用期間が短い。
この背景として、自然条件の厳しさに加え、住宅等が不足していた高度経済成長期において、性能よりも価格を重視するという選択をしてきたこと及び建築物の更新についても大量生産・大量消費という社会情勢に流されてきたことなどがあげられる。
(2)設計・建築段階において十分な評価がなされない安全性、解体容易性等
また、このようなことから、建築物、建材ともに、設計・建築段階においては、解体や分別のしやすさ、解体廃棄物の再資源化の可能性、解体され廃棄物になった場合の人の健康に対する安全性等に関して必ずしも十分な検討が行われていない。そのため、解体され、廃棄物となる段階においてリサイクル、適正処理が困難になっている状況も見受けられる。
2.建築物の解体時の課題
 (1)適正な積算、支払いが行われない解体工事コスト
(1)適正な積算、支払いが行われない解体工事コスト解体工事や廃棄物処理を適正に行うためには、解体工事業者等に適正なコストが支払われる必要があるが、発注者、元請建設業者は、この認識が必ずしも十分ではない。
さらに、解体工事自体が重層下請け構造になっているため、末端の解体工事業者及び廃棄物処理業者に、適正なコストが支払われていない場合が多い。
一方、解体工事業者と元請建設業者の間では、解体工事と廃棄物処理を一括で契約し、支払いも一括で行う場合が多く、解体工事コストと廃棄物処理コストの内訳が不明確になっている。これらのことも、適正なコストが支払われていないという結果を招いている一因と考えられる。
(2)チェックされない解体工事と解体工事業者
建築工事については、建築基準法に基づき、建築確認申請を通じて、建築物として必要な条件が確保される。
また、建設業を営む者が請負工事額500万円以上の解体工事を行う場合には、建設業の許可が必要になる上、建設業法に基づき工事現場へ技術者を配置するなどにより、適正な施工を確保することが求められている。
しかしながら、解体工事の実施に関しては、許可や確認といった手続きは必要なく、また、戸建住宅解体などの場合、工事金額も500万円を上回ることはほとんどないため、行政等が解体工事の内容やそれを行う業者をチェックをできない現状にあり、結果として解体工事業者の裁量により解体工事が行われ、一部では解体工事業者により、廃棄物の不適正処理が行われていると言われている。
(3)依然として大量に排出される建設混合廃棄物
建築物の解体工事において、コンクリート塊、木くず、ガラス等が分別されないまま大量に排出されている。また、その一部は不法投棄、野焼き等により不適正に処理されている。
これらの事態を招いている要因としては、前述のコスト及び工事のチェック等の問題の他、重機の発達により、ミンチ解体が可能になったことがあげられる。すなわち、これにより解体工事だけを見ると安価なミンチ解体が選択され主流になってきたこと及びその方法が容易なため解体工事業者の過当競争を誘発しミンチ解体にますます拍車がかかってきたこと等から、混合廃棄物の大量排出や一部の不適正処理につながっていると考えられる。
(4)確立されていない解体工事施工技術
リサイクルを促進するためには、分別解体が最も望ましい。
しかし、現在、行われている分別解体の施工技術については、必ずしも統一されたものがなく、その普及も十分とはいえない。
また、近年プレハブ工法、ツーバイフォー工法等様々な工法が普及すると共に、複合建材の使用が多くなっている。これらの建築物について、分別解体を進めリサイクルを促進するためには、その工法、建材等に応じた解体施工技術が必要と考えられるが、その技術は、確立されているという状況にはない。
3.建築解体廃棄物の再資源化時の課題
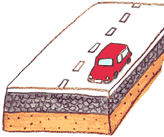 (1)再資源化施設の不足
(1)再資源化施設の不足リサイクルを促進していくため、再資源化施設が必要であるが、その立地状況は、一部の品目を除き、不足したり、地域的に偏在したりしている。また、現在、立地している施設についても、取扱う品目が1品のみというものが大半である。このために、分別解体したとしても、運び込む施設が遠隔であったり、さらには品目毎に異なる施設に持ち込まなければならないといった状況にある。その結果として廃棄物の管理が不十分になったり、持ち込みのための事務が繁雑になるなどリサイクルの実効性を低下させることが懸念されている。
(2)再資源化の困難な建築解体廃棄物
建築解体廃棄物のうち、ガラスくず及び陶器くず、廃プラスチック類については、現状においては分別解体を行っても技術的・経済的に再資源化が困難であり、高度に分別を行わない場合は、管理型処分場での処分が必要になる。また、建築解体廃棄物は、異物が混入しやすく、再資源化の技術が確立されている品目についても再資源化過程における品質管理の面で十分な留意が必要とされている。
 (3)リサイクル産業の現状
(3)リサイクル産業の現状リサイクル産業としての統計は存在しないが、産業廃棄物の中間処理業全体では、1社あたりの平均従業員数は約20人、1社あたりの平均売上高は約5億円であり、中小の企業が大半を占めている。
平成5年度に実施した建設廃棄物の再資源化施設の経営者へのアンケート調査結果によれば、収支が黒字と回答した企業は約3割に過ぎず、リサイクル産業が必ずしも収益性の高い産業ではないことが伺える。
また、企業や施設に対する不信感もあり、企業の経営の状況とあいまって施設立地が進まない要因となっている。
4.リサイクル市場の課題
(1)拡大しない再生資源の需要
建設分野では、舗装工事の路盤材等においてリサイクル材を利用する場合がほとんどであり、再生資材の用途は非常に限られている。
また、建設発生木材の主要用途のひとつである燃料チップは、原油価格の安値安定等により、需要が低迷している。
さらに、コスト面で新材と比べて再生資材が割高になることも、市場が形成されない主要な要因となっている。
このように再生資材の需要見通しが明確でないことが再資源化施設への設備投資意欲を鈍らせている要因にもなっている。
(2)整備されていない品質基準
建設省においては、コンクリート塊を土木資材として公共工事で利用する場合については、発注者として暫定的な品質基準を定めているが、コンクリートを含め、一般的な資材としての規格化はされていない。再生資材の利用に対する心理的な障害もあり、品質基準の不備が利用促進上のネックとなっている。
(3)リサイクル市場の情報不足
現在、リサイクル材は、どこで売られているのか、また、廃棄物はどこで引き取ってもらえるのかといった情報は十分に行き渡っているとはいえず、この点も、リサイクルが進展しない要因となっている。
●建設行政の役割
資源は、自由経済の中では、生産→流通→消費→廃棄の一方通行の流れになりがちである。廃棄物の発生を抑制するとともに、資源循環型社会の構築を目指し、廃棄から再資源化、生産に誘導するという、いわゆる資源循環の輪を形成するには、リサイクル市場が未成熟である我が国の現状においては、排出事業者責任の原則を堅持しつつ、公共が必要な役割を果たす必要がある。また、その際、資源循環の輪をつなげるためには、直接的な排出者だけでなく、生産者などの間接的な排出者も視野に入れて、検討していくことが重要である。
建築解体廃棄物の場合、廃棄物になった段階における適正処理の確保については、廃棄物処理法により不法投棄に対する罰則及びマニュフェストによる管理等の措置がなされている。しかしながら、このことは必ずしも廃棄物の発生抑制や再資源化、さらには生産につながるものではない。
建築解体廃棄物の発生を抑制するとともに、リサイクルを促進し資源循環の輪をつなげるためには、廃棄物処理段階での取り組みのみでは不十分であり、設計・建築・使用、解体及び再資源化段階も含めたライフサイクル全体をとらえることが必要である。このため、各段階における施策を従来より展開している建設行政の積極的な取り組みが不可欠である。
また、施策の展開にあたっては、各段階における関係主体の責任を明確にし、その責任が果たされる仕組みを構築するとともに、その仕組みの実効性を高めるため、再資源化施設の整備及び技術開発などの環境整備の誘導策・支援策を平行して実施することが重要である。
以下の施策は、このような認識のもと、建築解体廃棄物の発生抑制・リサイクルの推進等を進めるため、公共が実施していく施策を中心にとりまとめたものであるが、これとの関連において、市場メカニズムの活用・排出事業者責任の原則といった視点から各段階における関係主体の自主的な取り組みの方向についても示している。
●課題に対する戦略
1.建築物の長寿命化促進等の新設時における戦略
(1)長寿命化技術の開発等と長期使用
建築解体廃棄物の発生抑制を行うことは、最も基本的な取り組みであり、建築物の生産者が長期間使用可能な建築物を生産し、使用者がそれを長期間使用していくことの認識を深め、実行することが重要である。
そのため、長期間使用可能な集合住宅の建設・再生技術や木造住宅の長寿命化・ストック化技術に関する技術開発を推進するとともに、耐久性の高い良質な住宅の供給を促進するため、融資制度の見直しを行う。
また、これらと併せて、建築物の生産にかかる関係者の責任について明確にし、徹底を図る。
(2)設計・計画段階における廃棄物の発生抑制等の技術開発
木造住宅等の建築活動において発生する廃棄物を抑制するための資源循環型の木造構工法・材料部材の開発や、廃棄物処理が容易で環境負荷が少ない木造構工法・材料部材の開発、木造建築物の除却行為そのものを抑制するための技術開発を行う。
2.建築物の分別解体促進の戦略
(1)発注者による適正なコスト負担責務の明確化と適正な契約の確保
発注者は建築解体廃棄物排出の原因者のひとりとして、その発生抑制、リサイクルの促進に努めることが重要である。特に、資源の有効利用と適正な解体が行われるためには、発注者が解体工事及び一定の再資源化コスト等を負担することが必要であり、それらのコスト負担に対する発注者の責務を明確にし、その周知を図る。
また、再資源化を含め適正な解体工事が促進されるよう発注者に対する公的な支援の拡充を要求する。
さらに、解体工事業者や処理業者に適正なコストが支払われるよう、請負契約にあたり、解体工事と廃棄物処理コストをそれぞれ明確にするとともに、元請建設業者が、解体工事及び廃棄物処理を下請等に付する場合においては、解体工事、廃棄物処理を行う業者ごとに契約を締結すること等適正な請負契約がなされるよう徹底する。また、元請建設業者が適正に解体工事や廃棄物処理を行える業者を選定することを徹底するとともに、そのための指針・基準等を作成する。
(2)解体工事チェックシステムの創設と分別解体の実施
適正な解体工事が行われリサイクルが促進されるためには、リサイクル目的に応じた分別解体が行われるようにする必要がある。
このため、分別解体に関する基準を設け、当該基準に基づき分別解体に関する計画を作成し、行政に届け出するとともに、計画に従って、分別解体を実施すること、工事完了後に解体工事完了届を行政に提出することなど新たな制度の創設を検討する。また、これに基づいた解体工事の元請業者の責任を明確化し、その徹底を図る。
また、解体工事の確実な実施が図られるよう、行政機関による監視・指導はもとより、標識の掲示等解体工事の現場を地域に開かれたものにするなどより透明性の高い仕組みの導入について、併せて検討を進める。
(3)解体工事業者の育成等のための制度の創設
解体工事業者の育成及び元請建設業者等による適正な解体工事業者の選定や解体工事の適正な施工の確保のため、解体工事業の登録・閲覧制度、技術者に関する資格者認定制度の創設について検討を進める。
また、ISOの認証制度について普及・啓発を図るなど、解体工事の関係者に対し、自主的な取り組みによる資質の向上を促す。
(4)解体工事の施工技術基準等の策定と施工技術の開発
解体工事における適正な施工を確保し、再資源化を促進するため、解体方法や分別方法などを定めた施工技術基準を定めるとともに、適正な解体工事コストの積算のための積算基準について検討を進める。また、建築物の建材、工法に対応した分別解体に関する技術開発を進める。
さらに、これらの技術開発に対する公的な支援方策を検討する。
3.建築解体廃棄物の再資源化促進の戦略
(1)再資源化責任の明確化
適正に分別解体された建築解体廃棄物の再資源化が促進されるよう、品目ごとの再資源化に関する基準を定めるとともに、これに基づいた解体工事の元請業者の責任を明確化し、その徹底を図る。
(2)再資源化施設の整備に対する支援
今後、特に不足が予測される木材に関する再資源化施設に対する税制・融資等の支援を拡充する。
また、多品種にわたる建築解体廃棄物の管理や適正な再資源化を促進するため、複数の品目を受け入れる再資源化施設に関する税制優遇措置の新設を要求する。
(3)再資源化困難物のリサイクル技術開発
建築解体廃棄物であって、リサイクルが進んでいない廃石膏ボードや廃プラスチック類については、関係省庁・業界と連携し、リサイクルに関する技術開発や回収ルートの検討を進める。
4.リサイクル市場の形成の戦略
(1)再生資材の利用促進
リサイクル材需要の拡大のためには、公共事業での需要創出が有効である。このため、公共事業の実施における再生資材利用計画の策定などによる、より一層の利用の拡大を図る。
さらに、民間においてもリサイクル材の利用が促進されるよう、リサイクル材を利用した場合の融資等での支援制度の創設を要求する。
(2)再生資源の利用用途の開拓と再生資材の品質基準の策定
建築解体廃棄物を再資源化し、再生資材として利用する場合の品質を確保するため、特に発生量が多くリサイクルが低迷している木材等について、新たな利用用途の開拓に関する技術開発を推進する。
また、再生資材の品質基準を策定する。なお、品質基準の策定においては、環境安全性等について十分な検討を行う。
また、関係省庁・業界と連携の上、品質基準の規格化についても検討を進める。
(3)リサイクル材及び再資源化施設の情報交換システムの構築
リサイクル材や再資源化施設についての情報の入手を容易にするため、そのためのデータベースの整備を図るとともに情報交換システムを構築する。
(4)民間の技術開発に対する支援
新たな技術開発とその技術を活用した新たな市場を形成するため、市場性のある実用的なリサイクル技術の開発を民間が主体的に行えるよう、研究委託、助成等により民間の技術開発を直接支援する制度の創設を要求する。
●建築解体廃棄物のリサイクルを促進するための法制度化
建築解体廃棄物の発生抑制、リサイクルを促進するため、解体工事の適正な施工を確保するための手続き等に関し、法制度を含めた具体的な検討を進める。
■公共土木工事における取り組み
本プログラムでは、緊急的な課題である建築解体廃棄物のリサイクル促進のための施策に絞ってとりまとめているが、公共土木工事についても発注者の責任を明確化にし、本プログラムと同様の施策を強力に展開することにより、建設廃棄物の発生抑制、リサイクルを一層推進する。
| ←建設副産物対策の施策・取組みの経緯へ戻る |