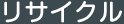再資源化施設・最終処分場の適正な立地に関する研究会
再資源化施設・最終処分場の適正な立地に関する研究会最終報告[概要]
1.検討の背景 建設廃棄物の排出量については、社会資本の更新、住宅等の建替需要の増加に伴い、着実に増加していく見通しである。 建設廃棄物の排出量については、社会資本の更新、住宅等の建替需要の増加に伴い、着実に増加していく見通しである。
これに対しては、まず発生抑制、リサイクルを強化に推進していくことが必要であるが、そのためには建設廃棄物の排出量に見合った再資源化施設が確保されている必要がある。 また、リサイクルを推進しても当面は最終処分される量が相当規模あると見込まれ、最終処分場の確保が必要である。 しかし、近年、環境意識の高まりや不法投棄の多発等により、産業廃棄物や産業廃棄物処理施設に対する国民の不信感が高く、施設設置にめぐる地域紛争が多発し、最終処分場の立地が困難になっている。 この様な状況を避けるため、地域ごとの実状に応じた再資源化施設・最終処分場の計画的な立地が必要である。 以上の背景から再資源化施設及び最終処分場の適正な立地を促進する方策について検討するため、建設省により平成9年12月に「最終処分場等の適正な立地に関する研究会」が設置された。本研究会は平成10年4月に最終処分場の適正な立地の促進に関する検討を中心とした中間報告を公表し、その後有識者へのインタビュー等を通じて検討を深め、また再資源化施設に関する検討結果も加えて、今回最終的な報告をとりまとめられた。 (研究会名称も平成10年12月より「再資源化施設・最終処分場の適正な立地に関する研究会」に改めた。) |
||||||||||||||||||
2.検討の内容 報告では、再資源化施設及び最終処分場ともに、現在あるいは将来的に施設量の不足が予測されるための方策について検討している。 具体的には、立地が円滑に進んでいない現状について、その原因、課題等を洗い出すとともに、官と民の役割分担のあり方を検討した。 また、適正な官民分担による再資源化施設及び最終処分場の計画的な整備を進めていく場合に必要な施策について提案している。 |
||||||||||||||||||
3.再資源化施設・最終処分場の現状と課題 再資源化施設に関する課題として、
最終処分場に関する課題としては、
|
||||||||||||||||||
| 4.再資源化施設・最終処分場の適正な立地及び計画的な施設量の確保に関する公共の役割 再資源化施設・最終処分場は、資源循環型社会の形成及び適正な廃棄物管理に向けて、必要不可欠な施設である。今後も、排出者責任の原則を堅持していくことが重要であるが、施設不足の現状を踏まえれば、官民が適切に役割分担しながら、整備を進めていくことが必要である。そこで、以下の点から、公共の役割を整理した。
|
||||||||||||||||||
| 5.建設廃棄物の再資源化及び最終処分における立地誘導の主体と地域単位の考え方 (1)立地誘導主体の考え方 建設廃棄物は、以下の特性を持つ。
(2)地域単位の考え方 最終処分場を対象にしたシミュレーションを行った結果、経済性からみて、都道府県を概ね地方生活圏に分割した地域単位とすることが適切であることがわかった。 しかし、再資源化施設については、リサイクル材の需要に応じて、最終処分場については、土地利用や廃棄物発生状況に応じて、都道府県を越える地域まで視野に入れ、検討することも重要である。 |
||||||||||||||||||
6.再資源化施設・最終処分場の適正な立地に関する公共が実施すべき具体的内容 再資源化施設・最終処分場は、都道府県が主体となって、立地誘導を行っていくことが合理的である。このためには、建設廃棄物の排出、リサイクル・最終処分までを捉えたマスタープランの策定する必要があり、総合的な方針・目標に加え、最終処分場及び最終処分場の整備の基本的な計画(地域区分、必要施設量、施設候補地、最終処分場の跡地利用方針等)を盛り込む必要がある。 このマスタープランの策定においては、十分な情報のもとでの市町村及び住民との対話を通じた合意形成のプロセスが不可欠である。以下に公共が実施すべき具体的内容を示す。 (1)再資源化施設
|
||||||||||||||||||
| 7.提案の実現に向けて −6つの連携− この報告書の提案を次の6つの連携を通じて、建設副産物への対応体制のネットワーク化を総合的に図ることが必要と考える。
|