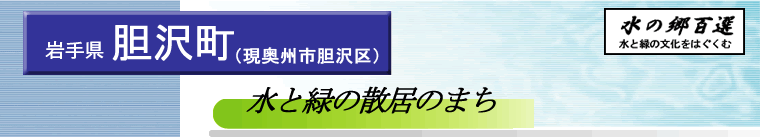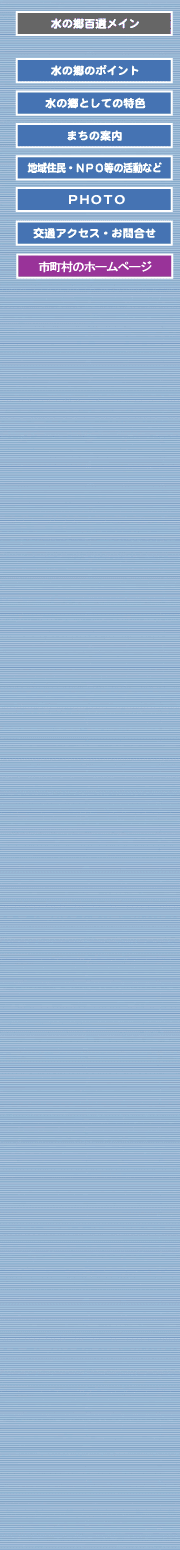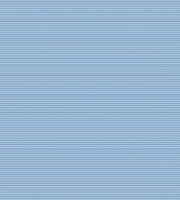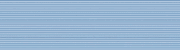| |
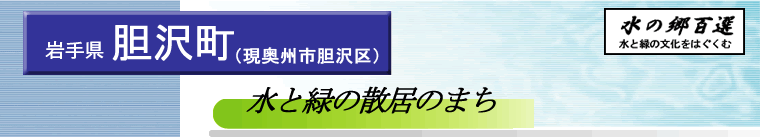 |
| |
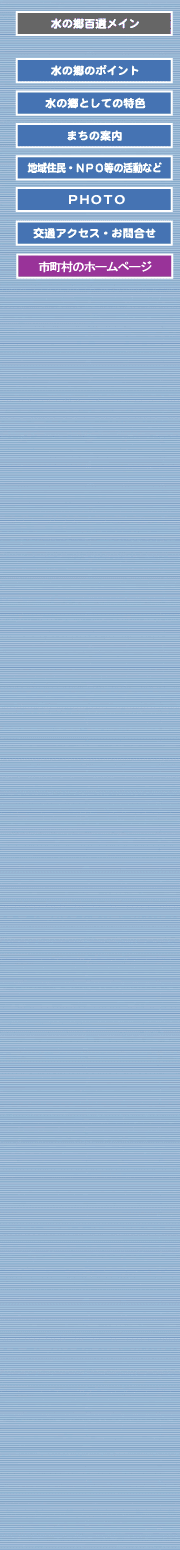
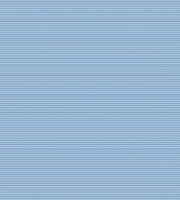
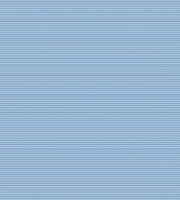
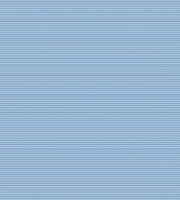
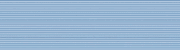 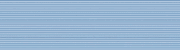 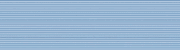 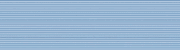
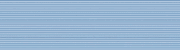
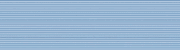 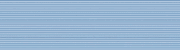 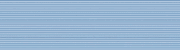 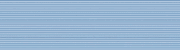 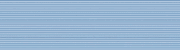 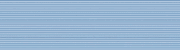 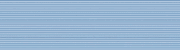 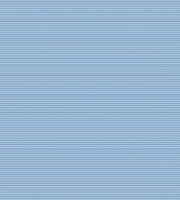 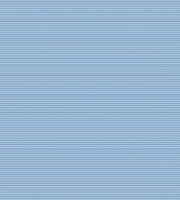
|
|
|
|
|
|
|
● 清らかな水が育んだ美田、その中に民家が点在する
日本のふるさとの原風景「散居(さんきょ)集落」
● 水とのかかわりの歴史を題材にした
手づくり市民劇場「奥州胆沢劇場」
● 日本一の大円筒分水「徳水園(とくすいえん)」
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
今から二千数百年前の弥生時代、胆沢ではすでに米作りが行われていたことが、穂摘みの石包丁の出土によって明らかになっています。この地方は古代、蝦夷の国「日高見(ひたかみ)」と言われ、日本書紀にも「日高見の国は、土地が広大で肥沃である」と記されています。
当地には、古代から農耕文化が栄え、その豊かな国を支配する強大な権力を持った豪族がいたことが、わが国最北端にある前方後円墳「角塚(つのづか)古墳」からも知ることができます。
平安時代には、胆沢地方は平泉の藤原氏繁栄を支える豊かな地として発展しました。
胆沢町(現奥州市胆沢区)の歴史は農耕文化の歴史そのもので、特に、堰の開拓にはさまざまな先人の苦労、壮大なドラマがしのばれます。
江戸時代初期(16世紀はじめ)には仙台伊達藩の直轄領地となり、藩主、後藤寿庵(ごとうじゅあん)らは、かんがい用水の不足を解消するため、寿安堰(じゅあんぜき)を開拓しました。また、それ以前にも茂井羅(もいら)という女性が堰を開削しました。
これらの堰は胆沢平野の美田を潤す大動脈として、今も豊かに水を流し続けています。
明治に入ってからは、当時としては画期的な耕地整理事業が東北で初めて実施されるなど、先人の努力によって現在の田園風景が築かれています。
特に寿安・茂井羅(しげいら)両堰に水を流す日本一の大円筒分水(だいえんとうぶんすい)「徳水園」は、まちのシンボルとなっています。
これら水とのかかわりの歴史・伝説を題材に、脚本から演出、キャスト、スタッフにいたるまで全てが住民の手づくりによる「町民劇場」(現「奥州胆沢劇場」)が昭和60年からはじまりました。ふるさとを素材にした舞台は、住民の暮らしの中に脈々と流れている「水」、「農」の文化を、現在に映し出しています。
現在「石渕ダム」にかわるダムとして「胆沢ダム」の建設が進められています。胆沢ダムは石渕ダムの約9倍の容量を有する日本最大級のロックフィルダムとなり、新世紀の水文化を創造する水がめとして期待されています。
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
◆ まちのみどころ
・ 栗駒(くりこま)国定公園 焼石(やけいし)連峰
・ 徳水園(日本一の大円筒分水)
・ 角塚古墳(国指定史跡)
・ 於呂閇志胆沢川神社(おろへしいさわがわじんじゃ)
(厨子は県指定文化財)
・ 焼石クアパーク ひめかゆ(温泉施設)
・ ひめかゆスキー場
・ 胆沢ダム(建設工事中、H25完成)
|
|
|
|
|
| |
◆◆ 水にかかわる祭り・イベント
・ 水の郷さくらまつり (4月中旬)
・ 徳水園通水式 (4月中旬)
・ 於呂閇志胆沢川神社祭典 (4月29日、9月12日)
・ 全日本農はだてのつどい (2月第2土曜日)
|
|
 |
| |
◆◆◆ 水にかかわる特産品
・ 麺製品 ・ 米菓(せんべい) ・ わら民芸品
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
◆ 主な取組み
(1). 水源地保全活動「22世紀ブナの森づくり」
胆沢川の水質を保全するとともに、北上川(きたかみがわ)水系の上下流域の交流を図りながら、水源地へのブナ苗木の植樹・育樹活動に取り組んでいる。
(2). 北上川河口域ゴミ清掃活動
「海岸清援隊(かいがんせいえんたい)」への参加
下流域での取り組みに対して、上流域団体として参加協力している。
◆◆ 取組みの実施主体
奥州市 ・ エコワークいさわ水の郷 ・ 胆沢平野土地改良区 ・ 北上川流域市町村連携協議会
◆◆◆ その他の参加者
小中学生・高校生、一般市民、北上川流域住民
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
◆ 交通アクセス
http://www.city.oshu.iwate.jp/
icity/browser?ActionCode=content&
ContentID=1139469282102&SiteID=0
◆◆ お問い合せ
〒023-0492
岩手県奥州市胆沢区南都田字加賀谷地270
胆沢総合支所内
奥州市総合政策部企画調整課胆沢ダム振興室
TEL 0197-46-2111
奥州市役所公式サイト
|
|
| |
|
| |
|
|