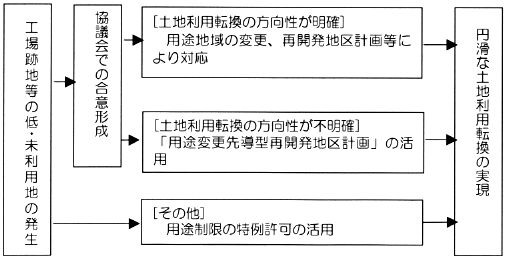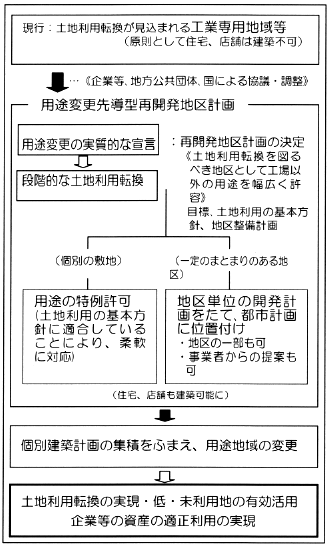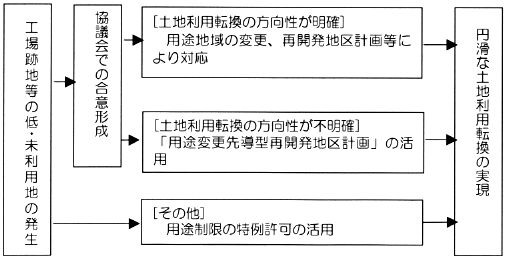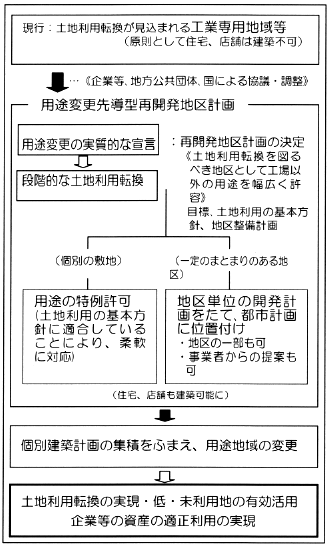大規模な工場跡地等の有効活用にあたっては、周辺地域への影響が大きく地域の将来像が見えないと都市的なポテンシャルや土地利用・道路ネットワーク等の方向が決まらず、なかなか開発に踏み切れません。
地域の将来像の明確化を図るためには、地元市町村等と協働して進めることが重要です。
大規模な低・未利用地の開発は、都市的な見地からその位置付けを明確にして、周辺地域を含めた地域の将来像を見定めることが重要です。そのためには、初期の段階から地元の市町村や県との調整を図り、公民協働で進めることが重要です。
開発にあたっては地域の広域的な位置付けの明確化を図るとともに、周辺地域と調和した土地利用計画や地区内への取付道路と周辺道路体系との整合性等を考慮した計画とすること等が必要です。また、状況に応じて周辺地域を含めた開発・整備が必要となります。また、ある程度計画の方向が固まった段階で、地元市町村のマスタープラン等に位置付けていくことが必要です。さらに、取付道路を都市計画道路として整備する必要がある場合や[方策2]で述べる用途地域等の見直しを行う場合等には、地元市町村の都市計画にこれらを位置付けることが必要です。
一般的な市街地では、都市計画法による用途地域や臨港地区等の指定により、大枠の土地利用が定められており、これにそぐわない用途の建物等の建築はできません。また、暫定的な活用でも不可能な場合があります。
ただし、工場跡地などの低・未利用地の円滑な土地利用転換を促進するために、用途地域の変更の措置等が講じられています。また、用途地域の変更を行う前に、特例によって法規制に合わない建物などの整備を先行させる用途変更先導型再開発地区計画制度も用意されています。
○用途地域の見直しの流れ
- 工場跡地等の有効活用は都市の再構築の観点から推進されます。この場合、土地利用転換の方向性が明らかな場合には用途地域の変更または「①再開発地区計画」の活用が有効です。
- また、土地利用転換の方向が明らかでない場合でも、「②用途変更先導型再開発地区計画制度」の活用により、段階的かつ円滑な土地利用転換が可能となりますので、早い段階から行政に相談すると良いでしょう。
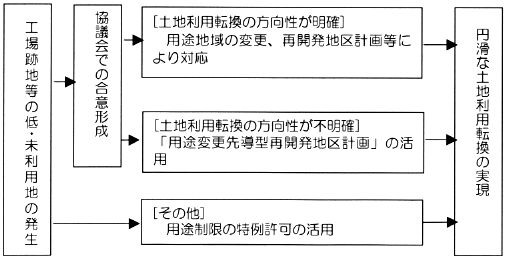
|
①再開発地区計画制度
再開発地区計画制度とは、大規模な低・未利用地の土地利用転換を誘導することにより、良好な市街地の形成による土地の高度利用と都市機能の更新を図るための制度です。
この制度では、都市基盤施設と建築物などの一体的かつ総合的な整備に関する計画に基づいて、容積率制限などの特例措置などが講じられ、事業の熟度に応じて段階的に整備をすすめることが出来ます。
再開発地区計画では、計画の内容に照らしながら一定の良好な建築計画について、容積率制限、斜線制限または用途制限を緩和することができます。
②用途変更先導型再開発地区計画制度
用途変更先導型再開発地区計画制度は、土地利用転換が見込まれる工業専用地域等の工場跡地等で、開発計画が明確に定まらない場合でも、再開発地区計画制度の活用により、用途地域の変更に先行して、幅広い用途の建築を可能とし、段階的かつ円滑な土地利用転換を実現していこうとする制度です。
この制度では、土地利用転換を図るべき地区として幅広い用途を許容するよう、再開発地区計画に区域、目標、土地利用に関する基本方針と再開発地区整備計画を定めた上で、個別の建築計画について、市街地環境に与える影響に配慮しつつ、用途の制限の特例許可等が行われます。全体の大枠を定めた上で、建築できるところから段階的な開発が可能となります。 |
|
(参考)臨港地区及び分区条例の運用
臨港地区は、港湾を管理運営するために都市計画に定められた地区で、用途地域等による用途規制を適用除外とし、分区による構築物の規制が行われています。
これらの用途地域等の見直しは、個別に事情を勘案しながら、必要な範囲で港湾行政と都市行政上の規制を適宜、重層的に適用するものとされています。
| 区 分 |
港湾行政上の規制 |
都市行政上の規制 |
| 都市的
△
▽
港湾的 |
0レベル |
なし |
用途地域等による建築規制
及び必要に応じ地区計画または再開発地区計画による建築規制 |
| Ⅰレベル |
臨港地区による届出・勧告等
(分区を定めない) |
| Ⅱレベル |
臨港地区による届出・勧告等
及び分区条例による用途規制 |
必要に応じ地区計画または再開発地区計画による建築規制 |
| Ⅲレベル |
なし |
0レベル:臨港地区以外の一般的土地利用規制を行う区域
Ⅰレベル:港湾を一体的に管理する必要性から臨港地区に含める必要があるが、相当程度の一般的都市機能を有する土地利用に対応して、分区を定めず、用途規制等による建築規制によるものとし、必要に応じて地区計画等による建築規制を行う区域
Ⅱレベル:臨港地区で、一部に一般的都市機能が含まれることに対応して、分区による港湾の管理運営機能に必要な用途規制を行うが、必要に応じて地区計画等による建築規制を併せて行う区域
Ⅲレベル:臨港地区で分区条例による用途規制を行う区域 |
|