| 建設省都市局区画整理課 | |
| 道路などの公共施設の整備改善、宅地の利用の増進 | |
| 個人、地権者などが設立する組合、地方公共団体、都市基盤整備公団等 | |
| 都市計画区域 | |
| 組合等区画整理補助事業:施行地区の面積が10ha以上(特別の場合は5ha以上) | |
| 調査設計費、移転補償費、公共施設整備費等 | |
換地方式 減歩制度 | |
| 目的や対象地域などによってさまざまな類似制度があります。 例)特定土地区画整理事業…首都圏など大都市地域で比較的小規模な面積でも可能その他敷地整序型土地区画整理事業等 | |
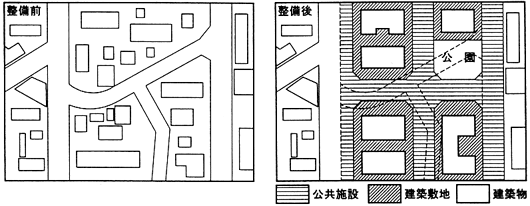 |
| 2.開発リスクの低減 |
開発リスクを低減することは、どのような開発にあたっても基本的な課題となります。特に大規模工場跡地等の開発にあたっては、規模が大きく膨大な投資が必要なこと、市場が未成熟な場合が多いこと、開発企業(土地所有者)が事業経験が少ないことなどの理由により、いかに開発リスクを低減するかが事業化実現への鍵と言えるでしょう。
リスクの低減策は、総合的な事業成立性そのものですが、特に大規模工場跡地の開発の場合には、暫定利用も踏まえた段階的な活用・整備により無理の無い事業計画を立てることが考えられます。また、デベロッパー等の民間企業等をパートナーとして一体的にすすめる方法も有効です。
さらに、資金調達の手法として証券化等の多様な手法も今後、積極的に検討すべきでしょう。
| 方策1 基盤整備への支援措置の活用 |
大規模な低・未利用地では区画道路等の公共施設の整備や敷地の整序が必要となります。また、地区へのアプローチが悪い場合には、幹線道路へ通じる取付道路等の整備も必要となりますが、周辺地区の基盤も同時に整備する必要がある場合には、周辺地区も含めた一体的な「土地区画整理事業」の実施が有効であり、そのため、国等からの補助制度があります。
| 建設省都市局区画整理課 | |
| 道路などの公共施設の整備改善、宅地の利用の増進 | |
| 個人、地権者などが設立する組合、地方公共団体、都市基盤整備公団等 | |
| 都市計画区域 | |
| 組合等区画整理補助事業:施行地区の面積が10ha以上(特別の場合は5ha以上) | |
| 調査設計費、移転補償費、公共施設整備費等 | |
換地方式 減歩制度 | |
| 目的や対象地域などによってさまざまな類似制度があります。 例)特定土地区画整理事業…首都圏など大都市地域で比較的小規模な面積でも可能その他敷地整序型土地区画整理事業等 | |
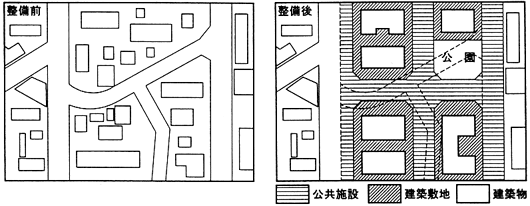 |
| 方策2 暫定利用を含めた段階的な活用 |
現状では地域の開発に対する需要が低かったり、開発規模が大きく一時期の開発では資金的負担も大きすぎる場合は、段階的な開発を進めるべきでしょう。再開発地区計画や土地区画整理事業などの制度や事業も、段階的な整備が可能ですから、無理のない事業計画を検討することが重要です。既存施設や空地部分を利用した暫定利用から始め、当該地区への人の流入状況、消費需要の動向を探ることも考えられます。また、暫定利用する場合は定期借地権制度や定期借家制度(次項参照)を用いることも有効でしょう。
| ケーススタディ:大規模工場跡地等の暫定利用、既存施設の利活用(Y市) |
|
本地区は、工業専用地域に指定され、操業停止により、遊休化とすることが決定されています。また、提案者は、処分等を考えており、事業化により、複数の有効活用や将来の土地利用方向を求められています。以下のような有効活用方針を目標としています。
調査地区の範囲と提案地区 有効活用方針 |
| 方策3 パートナーシップによる事業推進 |
大規模な土地の場合は、資金面やノウハウ面などから自社のみによる開発はリスクが高く、開発が難しい場合があります。このような場合、専門的な知識や資金力のある都市基盤整備公団等の公的機関や民間デベロッパーにパートナーとして事業に参画してもらう方法が有効です。パートナーシップによるまちづくりでは、例えば土地所有者が土地を提供するかわりに、民間デベロッパー等がパートナーとなり資金やノウハウを提供してもらい事業を進めることが考えられます。パートナーには一時的な資金の立替やビル床を一括して買い取ってもらったり、管理運営を委託することも考えられます。また、民間のノウハウを広く活用する方法として、事業コンペ方式*による開発も有効な方法です。
*事業コンペ方式:当該地の開発に深く関与するパートナーを選択する方法で、あらかじめ「土地利用の考え方」「事業の概要」「予算」等を説明し、企画提案その他により決定する。
| 方策4 多様な資金調達手法の検討 |
開発リスクの低減のためには、投資軽減策を検討する必要があります。
投資軽減策としては、資金的な負担がなく、安定的な不動産収入を得るには定期借地法式(事業用借地権)や土地信託方式、等価交換方式等が考えられます。また、等価交換方式では自己使用によるリストラ後の再雇用策等が考えられます
また、新しい資金調達の手法として不動産の証券化を活用することも考えられます。
| 定期借地権とは… |
|
| メリット |
|
| 留意点 |
|
| 適用例等 |
|
| 定期借家権とは… |
|
| メリット |
|
| 留意点 |
|
| 適用例等 |
|
| 不動産の証券化とは… |
|
| メリット |
|
| 留意点 |
|
| 適用例等 |
|
| 事業のイメージ |
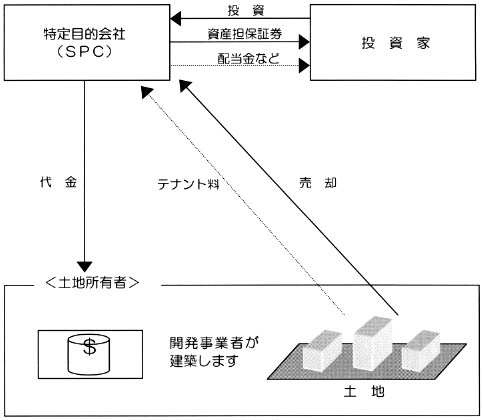 |