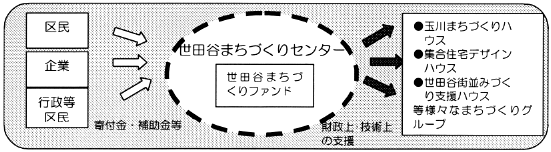
| 1.地域の将来像の共有 |
既成市街地に存在する低・未利用地は、狭小・不整形なものが多く、単独での有効活用が困難な場合が多くなっています。また、道路等の基盤が未整備な密集市街地等に分布する場合も多く、このような低・未利用地の活用にあたっては、住民参加によるまちづくり活動を通じた地域の将来像の共有化と合意形成が前提となります。
| 方策1 住民参加によるまちづくり |
①話し合いの"場" づくり
まちづくりは地域住民が共通の地域の将来像を共有することが重要です。このためには、まず、まちづくりの"話し合いの場"づくりから始めましょう。行政や専門家の協力も受けて、地元のみなさんで検討していくための組織や検討の場を設け、定期的に話し合っていくことが大事でしょう。
はじめは地元有志による「懇談会」から始めて、地元の熟度やまちづくり内容の段階に応じて、「勉強会」や「研究会」、「協議会」など適切な組織化を図ることが重要でしょう。どのような検討組織が望ましいかについては、行政や都市計画コンサルタントなどの専門家に入ってもらって相談すると良いでしょう。いきなり、具体的な事業の話ではなく、最初は自分たちの街を知ることからはじめましょう。街を見直し、良い所、問題個所等を見つけながら、みんなが共有できるまちの将来像を作り上げることが重要です。
このようなまちの将来像づくりや、具体的な計画づくりに対しても様々な助成策があります。
【まちづくり協議会をつくるポイント】
○まちづくり協議会の果たす役割を明確にする
・まちづくりに関する様々な問題について、地域住民と行政の共通認識をもつ
・公開された場で、住民と行政が話し合いを重ね、まちの将来像をもつ
○まちづくり協議会の組織をつくる
まちづくり協議会を組織化する母体となる団体は大きく次の2つがあります。そして、これらの団体の連携、新たにまちづくりの視点を加えた組織のレベルアップ等により、まちづくり協議会を組織化していきます。
・地域コミュニティ等のまとまりを持った団体
(例えば、商店会、自治会、NPO等)
・テーマ別に結成された団体(例えば、地域文化の会、環境を考える会等)
【まちづくり協議会等への支援措置】
まちづくり協議会など話し合いの活動費について、一定の助成をしている自治体もありますので、直接相談すると良いでしょう。
また、まちづくり活動を支援する「まちづくり基金」などもあります。自治体の外郭団体であるまちづくりセンターやまちづくり公社などで運営している場合があります。
■世田谷まちづくりセンター(例)
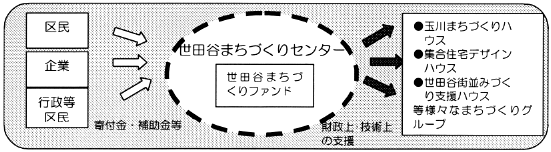
【各段階におけるまちづくり組織の役割】
まちづくりの各段階における話し合いの目的やまちづくりの活動の目標に応じた具体的な手法との関係を以下に整理しています。これらは、基本的な手法であるため、地区の特性やまちづくりの熟度に応じて、具体的な手法を選択・工夫することが重要です。
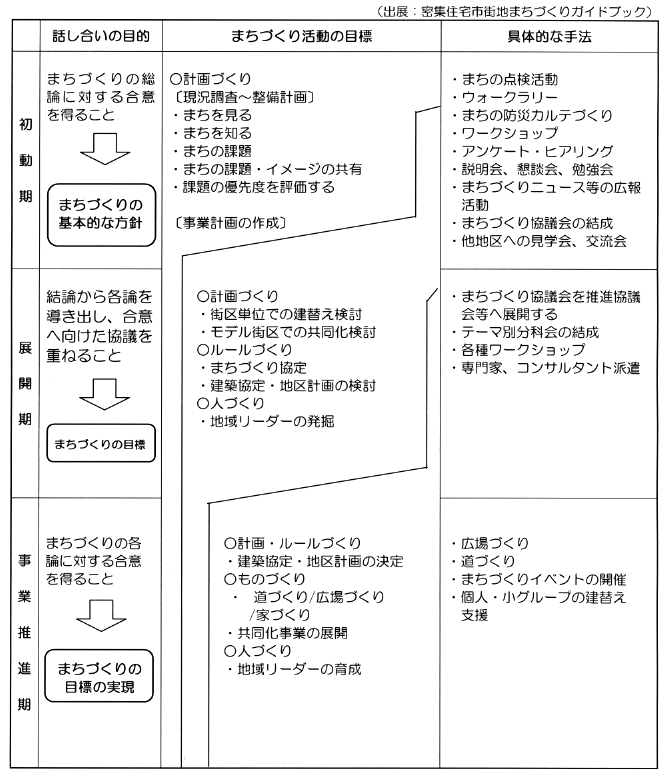
【計画策定段階における支援措置】
地区レベルの整備計画(マスタープラン)を策定する調査や、土地区画整理事業など具体的な事業を行うための調査で国(国土庁、建設省)の補助が受けられる調査があります。
国の補助調査以外にも、各自治体が独自にまちづくりや地域の活性化を図るための調査を行う場合もあります。検討内容や熟度によって活用する調査を行政に相談すると良いでしょう。
■主な国の補助調査
|
《これからのまちづくりの計画を検討する調査》 ・土地利用促進基礎調査策定事業 ・土地利用転換推進計画策定事業 ・まちなみデザイン推進事業 《地区レベルの整備計画(マスタープラン)を検討する調査》 《具体的な事業手法について検討する調査》 |
②まちづくりNPOを活用したまちづくり
財政の逼迫や、市場競争激化のなかで、公平・平等な対応が求められる行政や、利益追求が目的の企業だけでは、市民の多様なニーズに対応できなくなりつつあります。福祉・環境・まちづくりなど、すぐに何とかしなくてはという課題に取り組む自発的な市民活動が活発になってきています。活動理念や目的に賛同・共鳴する市民が自主的にサービスの提供をめざすNPOが、今まさに必要とされています。
| NPOとは… |
|
| メリット |
|
| 留意点 |
|
| 対象分野 |
|
| 低・未利用地での活用方向 |
|
| 主な事例 |
|
諸外国ではCDC(Community Development Center)と呼ばれるNPOが住宅の整備や市街地改善に係る事業を実施しています。今後は、我が国のNPOもまちづくり協議会だけでなく、CDCのように事業を行う主体としての役割を担うことも期待されています。
| 事例紹介:NPOによるまちづくり(東京都大田区 密集住宅地区整備促進協議会) |
|
密集市街地などの小規模低・未利用地において、権利関係が複雑である地区の再開発は、行政では対応しきれず、民間デベロッパーも参入しにくい状況があります。「密集住宅地区整備促進協議会」は、こうした公民のすき間のニーズに応える組織として、97年に設立されました。 【活動の経緯】
|
| 方策2 持続性のあるコミュニティづくり |
木造密集市街地等では少子高齢化の進展や若年層の流出等により、コミュニティバランスの崩壊や地域活力の低下などが多く見られます。
これらの地域では、高齢者対策、子育て等の福祉対策、さらに地元の産業施策等と連動した総合的なまちづくりの促進により、地域コミュニティの再構築が必要となっています。
低・未利用地の活用にあたっても、これらの定住方策とあわせた多様な住宅の供給を図り高齢者や子育て世代の居住継続等のニーズに応えていく必要があります。
| 事例紹介:コレクティブハウジング(神戸市真野地区 真野ふれあい住宅) |
|
|