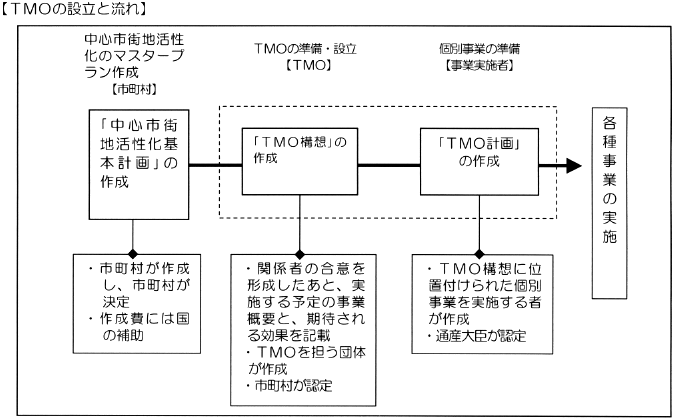
| 1.地域の将来像の共有 |
中心市街地の問題は、様々な問題を抱えています。そこでの大きな問題は、街の将来像が見えないことです。まずは、地域の将来像を明確にするために、地域住民、行政などのまちづくりに係わる人を集めて気運を盛り上げることが必要です。青空駐車場や空店舗などの低・未利用地の存在は、中心市街地の魅力づけにつなげる種地になります。まちづくりの第一歩として、それらを活用してお祭りやイベントなどの周知活動を手始めにすることも考えられます。そうした草の根的な活動から、低・未利用地を活用した事業化に進める過程に至るまで、市民参加によるまちづくりによるまちづくり協議会やTMO、NPOなどのタウン・マネージメント組織を設置し、街の活力を高めることが低・未利用地有効活用の原点となるでしょう。
| 方策1 TMOを活用したまちづくり |
中心市街地活性化法が平成10年に制定され、その要となるTMO(Town Management Organization)は、中心市街地における商業集積の一体的かつ計画的なタウン・マネージメント(まちの運営管理)するとともに、様々な主体が参加するまちの運営を横断的・総合的に調整しプロデュースします。また、施設の建設主体にもなれます。
TMOの事業実施地域は、市町村の中心市街地活性化基本計画で定められますが、TMOが具体的にどのような機関で、どのようなプロジェクトに取り組むかはTMOが策定する構想を市町村が認定することによって決定します。
これらのタウン・マネージメント機能を実現していくためには必要な事業主体は、市町村、商工会、商工会議所、第三セクター、商店街の連合組織、各商店街組合、あるいは市民組織等様々です。そして、その全体を企画・調整するのがTMOになります。
なお、タウン・マネージメント組織は総合力を持つべきであり、NPOなどとTMOを一体化するなどの工夫も必要になりますが、有効活用の方策として期待されています。
【TMOの設立と流れ】
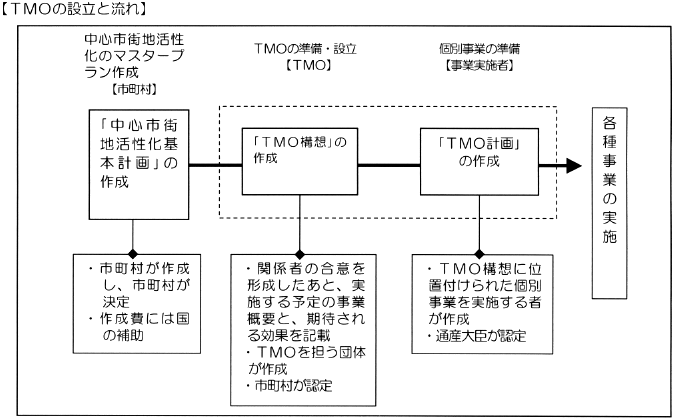
【その他のタウン・マネージメント組織】
| ◆TMC(Town Management Center) まちづくりを運営・管理する主旨で設立する機関であり、TMOと基本的目標は同じです。市街地再開発事業の分野では準備段階から施設の管理・運営を担う主体として支援対象に位置づけられています。 |
| ◆中心市街地整備推進機構 主に公益施設の整備や土地の先行取得などを行う「公益法人」です(中活法第10条)。中心市街地活性化法では、市町村長が「中心市街地整備推進機構」を指定することとなっています。業務内容は、中心市街地の整備改善に関する事業者への情報提供、建築物等を基本計画の内容に即して整備する事業の実施又は参加、整備改善を図るために有効利用できる土地の取得等、調査研究の実施などがあげられます。 中心市街地整備推進機構による公益施設及び面的整備事業の種地など都市機能更新用地の先行取得に対しては、税制上の特例措置が講じられるとともに、都市開発資金制度による低利貸付が活用できることとなっています。 |
| ◆タウン・マネージャー 様々な取り組み主体の仲立ちとして管理・運営を先導する人です。 マネージャーとなる人材には、地元の代表的な商業者や企業経営者、商業や都市整備の分野などまちづくりに造詣の深い専門家、地方公共団体職員などが考えられ、その地域にふさわしい人の登用が望まれます。 例えば、中小企業事業団では、次のような業務内容を予定しています。 ・活性化相談・指導事業(TMOの組織体制整備) ・計画策定、事業実施の指導・助言等(商業ゾーンの方向性、商業機能の整備、共通ソフト事業の実施) |
| 事例紹介1:TMOによるまちづくり組織化(愛知県瀬戸市) |
|
【役 割】 【目 標】 【事業目的】 【設立過程】 【会社概要】 |
| 事例紹介2:TMOによるまちづくり(滋賀県長浜市) |
|
| |||||||||||||||||||||
(参考)中心市街地活性化法
|
|
| 方策2 市民活動やまちづくりNPOなどの活用 |
まちづくりに関連する市民活動やNPOを活用することも低・未利用地の有効活用のひとつと考えられます。例えば、街並みづくり、花・緑・水をいかしたまちづくり、保育環境づくり、子どもたちの参加、高齢化へ対応、環境共生型居住環境づくり、災害復興支援、市民ネットワークづくりなどの多彩なテーマについて研究や提言などを行い、まちづくりを通して実践しています。先述のTMOも新たなまちづくりNPOの一つとして支えられることも考えられますが、非公式の草の根的な会合に始まって徐々に発展させていく様々なNPOの活動は、今後のまちづくり活動の中心的な役割として期待されます。
| 方策3 持続性のあるコミュニティづくり |
中心市街地や木造密集市街地では業務化や若年層の流出等により、夜間人口の減少・少子高齢化等が進み、コミュニティバランスの崩壊が見られます。また、まちの中心部にある商店街では、地元客の減少や高齢化、さらには店舗の郊外立地・大型化等によって衰退し、空洞化が進むとともに街全体の活力が低下しつつあります。
これらの地域で、高齢者対策、子育て等の福祉対策、さらに地元の産業施策等と連動した総合的なまちづくりの促進により、地域コミュニティの再構築が必要となっています。
低・未利用地の活用にあたっても、これらの特定優良賃貸住宅供給促進事業などを活用した定住方策とあわせた多様な街なか住宅の供給を図り、高齢者や子育て世代の居住継続に踏まえ、持続性のあるコミュニティづくりに配慮する必要があります。
○賃貸住宅供給のための主な制度「特定優良賃貸住宅供給促進事業」
この制度は民間の土地所有者などの供給する、良質な賃貸住宅に対して、公社・公益法人が借上げ、もしくは管理することにより、主に中堅所得者の居住の用に供するファミリータイプの賃貸住宅を供給していこうとするものです。
この事業では都道府県知事の認定を受けて供給する賃貸住宅に対して、共同施設整備費や高齢者向け設備設置費等の建設費に対する補助のほかに、家賃対策補助や住宅金融公庫融資等が受けられます。また、高齢者向けの優良賃貸住宅の供給に対しても、ほぼ同様の助成制度(高齢者向け優良賃貸住宅制度(シニア特優賃))が設けられています。
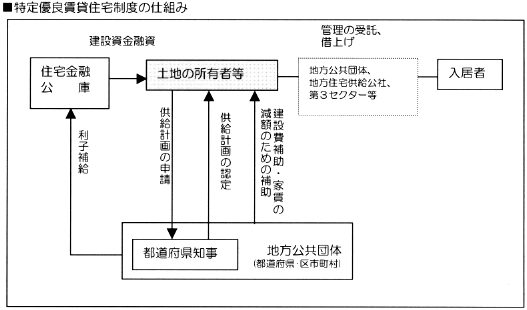
| 事例紹介:「特定優良賃貸住宅、シニア住宅、保育所などの福祉施設の合築」(相模原市 エス・プラザビル) |
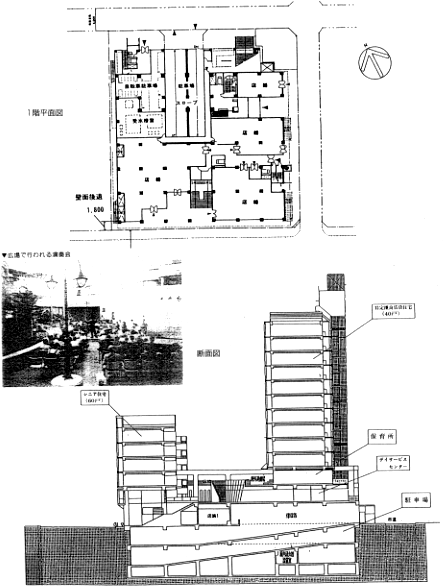 |