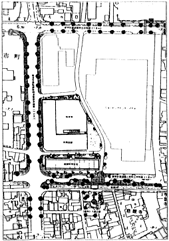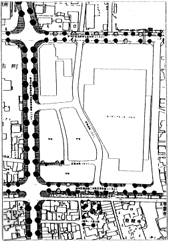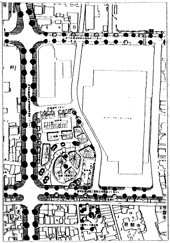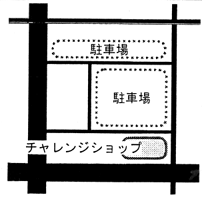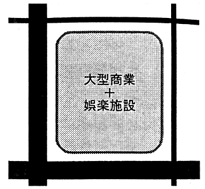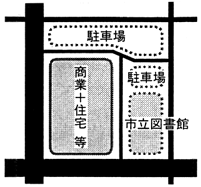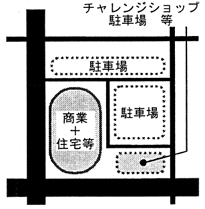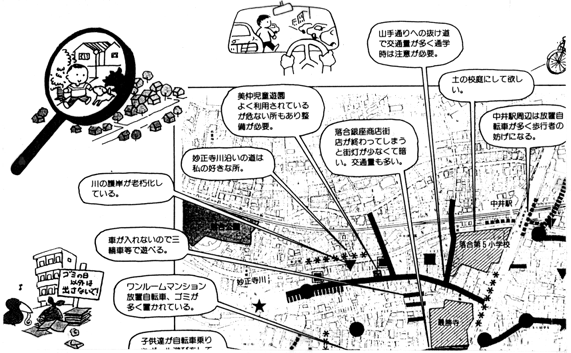| 方策1 賑わいのある魅力的な商業機能など多種多様な立地誘導を図るための活用 |
街なかの商業者など施設を立地させる主体にとって、中心市街地に比べ、郊外部の方が安価で、かつ、まとまった土地が容易に入手可能になり、中心市街地の商店街は寂れて空洞化が起きています。それに対して、利用者並びに消費者である市民の多くは、自家用車によるアクセスの容易な郊外立地型の都市形成に利便性を感じています。
そのために、現在の施設立地ニーズに応え得るような広さや適正な地価、賃料を備えた土地や建物を供給することが必要となります。
まずは、街なか商業を再構築するための低・未利用地の有効活用として、転出してしまった機能の再集積、又は、福祉、新産業育成といった観点から転出した機能に変わる新たな機能の立地導入を図ることが急がれます。
具体的には、以下の視点が考えられます。
○賑わいのある魅力的な商業機能の立地誘導
~街のイメージを強化し"賑わい"をつくる~
・街の接客機能・市民サービスの充実、街の界隈性の演出などによる時間消費型のまちづくりを進める
・空店舗、空地等の活用によるチャレンジショップなどの「呼び水」的な仕掛けづくり
・知識集約型・情報発信型の都市型サービス産業の育成
○都市活動を支える基盤整備の充実
~大きな投資を伴わない環境にやさしい"足"をつくる~
・公共交通機関の充実を図る
(例えば、中心市街地の循環バスや自動車レーン、レンタルサイクルなど自転車利用の利便性向上など)
・拠点的な再開発に合わせた駐車場の整備、既存駐車場のネットワーク化、あるいは自動車の駐車環境の整備に重点をおくなどの街なかの自動車対応を充実させる
○情報の発信
~多種多様な活動を礎とした発信の"仕掛け"をつくる~
・イベントや祭りの実施により、市民全体の交流を支えるオープンスペース、コンベンション機能の充実を図る
・地域コミュニティの歴史・文化・まちづくりなどを地域市民の手で情報発信を図る仕組みづくり
・都市独自のまちづくりへの取り組みそのものを要所に展示し、市民や来街者へアピールすることをはじめとして、中心市街地全体を独自の文化の発信の場となる仕掛けづくり
| ケーススタディ1「商業複合的機能拠点形成」(I市) |
| |
有効利用の考え方 |
導入機能の考え方 |
空間イメージ |
| A―1案 |
・個別建替え+計画タイプ |
・商業(既存商業+新規)+住宅
・道路に面する宅地を店舗として利用し、街区内部は当面駐車場として利用する |
|
| A―2案 |
・敷地共同利用タイプ |
・商業+文化施設(市民ギャラリー)+住宅
・地区内居住者、営業者の現地残留に対応 |
| B案 |
・土地区画整理事業タイプ |
・商業+住宅・大規模地権者は土地の集約化により高度利用を図る |
|
| C―1案 |
・基盤整備+敷地共同利用タイプ |
・商業(小売店舗の集合体)+公益施設+店舗併用住宅
・低層(仮設タイプ)の広場を中心にして店舗を配置する |
|
| C―2案 |
・基盤整備+共同ビル(市街地再開発)タイプ |
・商業(隣接する核店舗と一体化)+公益施設
・共同ビルを建築し構造的に隣接核店舗と接続を図る |
| ケーススタディ2「商業中心拠点としての商業機能の段階的な再編」(T市) |
|
シナリオ1:暫定的な小拠点づくり
(跡地の一部で暫定利用する案)
○地元主体によるチャレンジショップを設置し、商業の活性化を図る(周辺開発時における仮設店舗の設置等の利用も可能)
・跡地部分、現市営駐車場部分は駐車場として利用
(手法)対象部分の定期借地
(用途)チャンレンジショップ、駐車場 等
(債権問題)現状のまま |
|
|
シナリオ2-1:中心市街地の集客・交流拠点づくり
○敷地を最大限に利用し、周辺大型商業の集約により商業核の形成を図り、中心市街地での回遊の拠点形成を図る。
・F百貨店跡地を公的機関に売却
・スズランの用地交換による移転・増床
(手法)第一種市街地再開発事業/(中心市街地集積関連施設整備事業(地域公団の出資支援)等の通産省支援)
(用途)大型商業(百貨店)、映画館、都市型住宅、チャンレンジショップ、駐車場 等
(債権問題)集約・債権放棄 |
|
|
シナリオ2-2:中心市街地の交流拠点づくり①
○中心市街地における滞留時間を長引かせるための環境を商業施設+αの機能の導入を図る
・F百貨店跡地の集約換地により区域設定
・空地部分は駐車場等に活用
(手法)街なか再生土地区画整理事業/第一種市街地再開発事業/(通産省支援)
(用途)商業施設、映画館、都市型住宅、図書館、チャンレンジショップ、駐車場 等
(債権問題)換地による集約・地下構造物の撤去 |
|
|
シナリオ2-3:中心市街地の交流拠点づくり②
○路面型の商業等の配置により、集客の核を形成し、また、都市型住宅の導入を図る
・F百貨店跡地の一部換地により区域設定
・集約された空地において、仮設店舗によるチャレンジショップの導入
(手法)等価での土地交換分合による集約後に第一種市街地再開発事業/(通産省支援)
(用途)低層商業、映画館、都市型住宅、チャンレンジショップ、駐車場 等
(債権問題)一部換地による集約 |
|
| 方策2 地域資源に目を向けた「呼び水」的な促進活動 |
まちづくりに対する市民の意識高揚や気運の醸成を図るために地域資源に目を向けた「呼び水」的な活動を通して低・未利用地を活用することは有効手段の一つです。特に地方都市においては、観光都市や歴史的な街並みを残しているところが多く見られ、地域資源をいかしきれず、まちづくりの策定に苦慮している場合が見られます。まずは、まちづくりの視点から街なかを探検・点検し、まちの課題を市民、地域住民で共有し、街の将来像を掴むことが有効活用になります。
また、国や都道府県においては、市町村のまちづくりに対する取り組みを促進させるためのイベントや表彰制度によって地域資源をいかしたまちづくりの成果を評価しているところも見られます。
- 多分野のリーダー層によるまちづくりワークショップ
- 街にふさわしい色彩環境の研究活動や意向把握
- 模型づくりによりまちの全体像を把握する
- 歴史的・文化的資源を発掘するイベント
- 伝統的な祭りと連携したまちづくりのプロモーション
- 大型店撤退跡地や空店舗などの利活用の検討
- まちづくり事例見学会の実施
- 義務教育・生涯学習におけるまちづくり教育
- まちづくり協定やガイドラインづくり
- 活動内容及び成果を対象としたまちづくり表彰制度
(例えば、都市景観大賞、まちづくりアイデアコンペなど)
| 事例紹介 まちの点検結果(東京都新宿区 上落合地区) |
|
(出典:上落合地区まちづくりニュース)
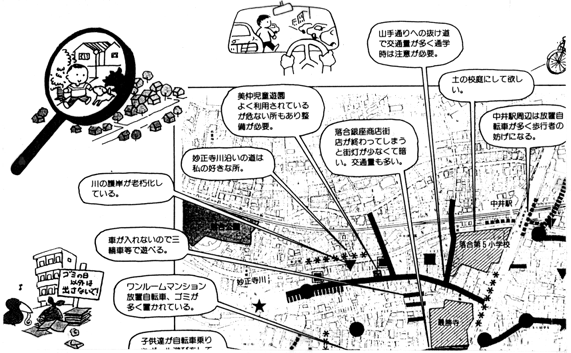
|
①空店舗が目立つ商店街での活性化に向けた空店舗対策
個々に対療法的に対策を練るよりも、面として捉えて商業だけではなく住宅やコミュニティなど総合的にまちとして考えることが重要です。
まちとして、何が不足しているのかとか、どのような業種構成や並びが望ましいのかなどの視点で捉えながら、ニーズややる気のある人に開放するなどして、先ずは一店のシャッターを開けて成功例をつくり、そこから、さらに一店ずつ積み重ねていくことで、全体としての活性化を図る"一店突破"的な方法も考えられます。空き店舗の利用方法として、例えば、SOHO、インキュベーション機能、チャレンジショップなどとして元気な若者に開放することも考えられます。将来的には、大学生の社会体験の場として活用されていくことも考えられます。なお、こうした空き店舗の活用策などをコーディネートする役割がTMOに期待されます。
②街なかから撤退した大型店舗における当面の有効活用策
大型店舗は、廃墟のまま放置するのではなく、できるだけ地域に役立つ再利用が求められます。そこで、スケルトン賃貸として1階は店舗として活用しつつ、上層階などに行政の出張所や福祉施設など公共施設を整備して、高齢化しているまち中での買い物や福祉サービスなど地域に密着しコミュニティに貢献した活用策を図ることも有効でしょう。
または、すぐに再開発で新たな大型建物を建てることを考えるだけではなく、広場として広く開放した活用も有力な候補となり、そうした発想の転換も必要ではないでしょうか。こうした活用策を検討したり、コーディネートする役割もTMOには期待されています。
| 事例紹介 大型店の撤退によるコミュニティ施設の活用(埼玉県羽生市 羽生市民プラザ) |
街なかのショッピングセンター跡地の既存施設を改築し、市民のコミュニティ交流施設として既存施設を利用した事例です。
1階はふれあいスペース、2階は知的・教養スペース、地下1階は文化創造スペースとして、子どもから高齢者まで多くの人が利用しやすい施設となっています。
|
外観写真

|
藍染め体験コーナー(地下1階)

|