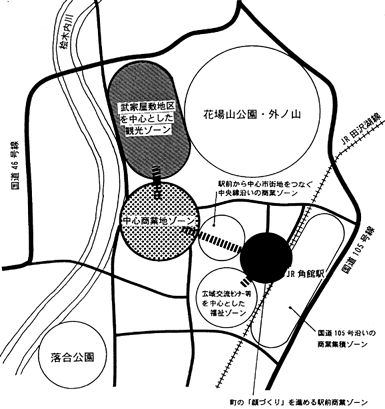1.地区の現況
①人口:14,846人(若者層の減少が出生数の減少に結びつき総人口が減少)
②高齢化率:総人口に占める65歳以上の割合は24.7%(平成10)。平成に入り急速に高齢化が進行している。
③土地利用現況:工場跡地および町有地(都市計画道路事業用地)からなる。更地、および住居系既成市街地から構成されている。
④基盤整備状況:駅前広場、および都市計画道路の一部が整備済み。
⑤法規制状況:用途地域:商業地域400%、第一種住居地域200%
7.土地利用転換計画
■土地利用転換計画図(A案)
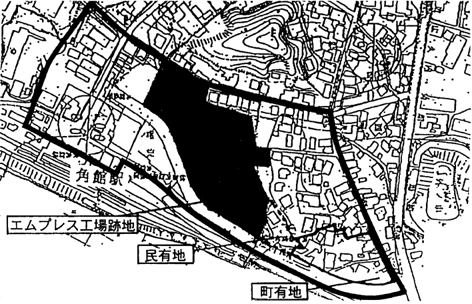
民間用地における開発計画案
- 民間用地(エムプレス工場跡地)のみでの開発計画案
- 既存の都市基盤をそのまま活用し、事業初期段階では、既存工場施設の再利用等による集客施設(ミュージアム)や物販施設の導入を図る。
2.上位・関連計画における地区の位置づけ
- 角館町将来土地利用構想:駅前広場計画に合わせた角館町の「顔」づくり を行う商業地区として位置付けられている。
3.対象地区の課題
- JR秋田新幹線駅前における低未利用地の有効活用
- 開発推進のためのボトルネック解消(土地所有形態、日影規制による制限等)
- 秋田内陸縦貫地域(6町2村)および仙北郡を含んだ広域地域における地域振興のための中核拠点としての役割
4.対象地区の既存調査手法における問題点と課題
- 既存調査なし
(都市計画道路中央線整備事業により、対象地区内での駅前広場整備は完了)
■土地利用転換計画図(B案)

民間用地と町有地の一体利用による開発計画案
- 民間用地(エムプレス工場跡地と調査地区内の町有地等(都市計画道路事業用地)を一体型に利用した開発計画案。
- 町有地(都市計画道路事業用地)と、対象地区に近接する羽後交通バスターミナル用地等(同事業による移転を想定)の交換を行い、対象地区内に交通結節機能を導入する。
5.提案者とのこれまでの協議内容と提案者の意向
- 提案者側は早期の事業化を望んでいるが、町側に対象地区に関する具体的な構想が存在しないため、官民連携型の開発を希望する提案者側との調整が必要である。
6.低・未利用地有効活用の方針
(1)土地利用転換計画の目標と導入機能のメニュー
[目標]
① 街の第一印象を決める「駅前の顔づくり」の推進
② 周辺地域をつなぐ交通ネットワーク機能の拠点づくり
③ 産業の活性化につながるサポート機能の整備
④ 人口減少への対応・地元における雇用の場の確保
[導入機能]
「交流・情報機能」:準都市型ホテル、角館まんがファクトリー・情報館
「産業支援機能」 :物産品販売施設、観光用飲食施設
「交通結節機能」 :観光シャトルバスセンター、大型バス駐車場
「定住促進機能」 :Iターン・Uターン受け入れ用居住施設
(2)有効活用の方針
- 角館町及び周辺エリアにおいて当地区の果たす役割は大きく、開発主体の 組み合わせ等を考慮して、3パターンの土地利用転換計画の策定を行う。
■土地利用転換計画図(B’案)

段階整備を想定した市街地再編計画案
- B案のバリエーションプラン(対象地区内の既成市街地の部分的な再編を行い、開発エリアの区域どりを整形した案)
- 事業ポテンシャルを考慮し、開発区域・時期を二期に分けて想定する。また、必要に応じて区域内に区画道路の整備を想定する。
角館町(中心市街地)における将来的な都市構造の考え