|
2 国鉄経営の問題点
51年度の旅客部門をみると,全体で3,280億円の赤字であるが,その内訳は,新幹線が2,183億円の黒字,在来線が5,463億円の赤字となっている 〔2−2−2表〕。在来線のうち,幹線系線区の赤字は3,568億円〔2-2-3表〕と前年度に比べ減少したが,なおその絶対額は大きなものとなっている。
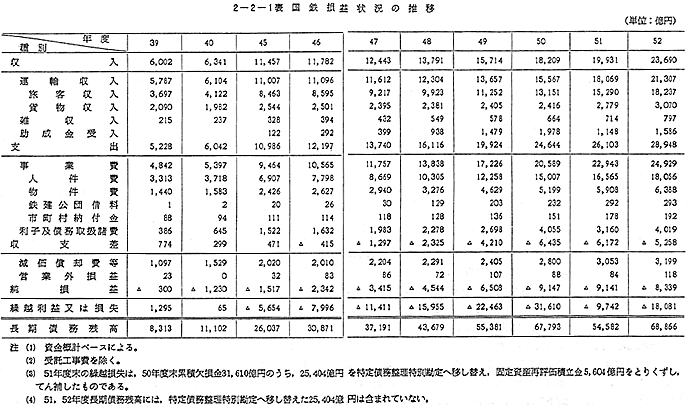
また,地方交通線系線区は,営業係数では幹線系線区と同様に51年度に改善を示しているが,これは,51年11月の運賃改定の結果によるものであり,赤字の絶対額は,1,895億円と前年度に比べ増加しており,悪化の傾向は変っていない。地方交通については,道路整備の進展に伴い,自家用自動車等の他の輸送機関の利用が増加していることから,将来とも地方交通線の利用の増加はあまり期待できないので,今後は,事業運営の効率化や合理化による経費の節減等の経営改善に努めるとともに,運輸政策審議会委員等による国鉄地方交通線問題小委員会の中間報告に示されている特別運賃の設定等の対策についてもさらに検討する必要がある。
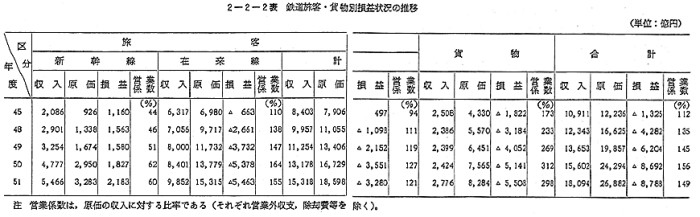
国鉄の貨物輸送は,45年度の624億トンキロをピークとしてその後減少を続け,52年度には406億トンキロとなっているが,輸送量の減少に対応して輸送力の調整が十分に進められなかったため,輸送量と輸送力に大幅な乖離を生じている。
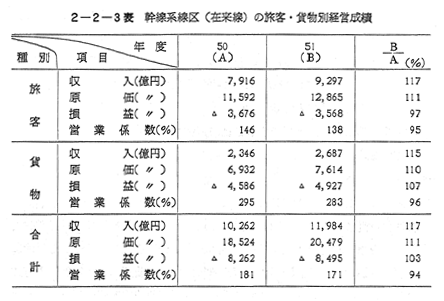
51年度の貨物部門をみると,5,508億円の赤字であり,そのうち幹線系線区の赤字は4,927億円である 〔2−2−2表〕 〔2−2−3表〕。51毎度の国鉄全体の赤字の約60%は貨物部門からのものであり,そのうち幹線系線区が約89%を占めている。このように貨物部門の赤字は国鉄財政悪化の主たる原因となっている。
国鉄は,これまでも作業方式の改善や設備の機械化,近代化など経営の合理化を進めてきたが,52年4月には運輸大臣の承認を受けて「経営改善計画」を策定し,55年度までに,15,000人の要員を縮減することを目途に合理化を進めている。52年暮の国鉄運賃法の一部改正により運賃決定方式の弾力化が図られたが,後述するようにこの運賃決定方式の下では,改定幅が経費の増加額の範囲内に抑えられ,これまで以上に収支が悪化することを防ぐにとどまるものであり,改定増収による収支の改善はあまり期待し得ず,一方,国による助成にも自ら限度があること等から国鉄経営の健全化を達成するためには,国鉄自身が業務全般の見直しを行い,徹底した合理化を進めていくことが従来にも増して極めて重要となっている。特に,今後数年間は相当数の退職者が見込まれるので,退職者の後補充を極力抑制することによって積極的に要員の縮減を推進していく必要がある。
|