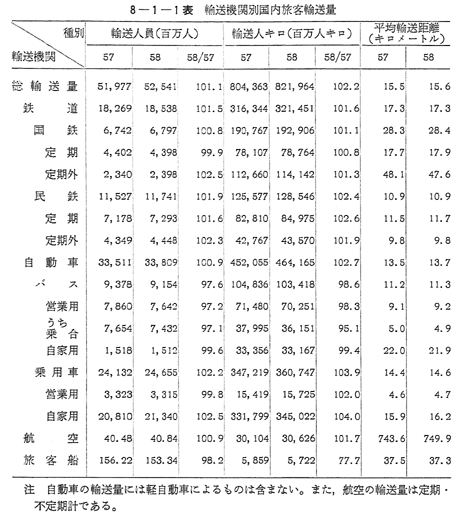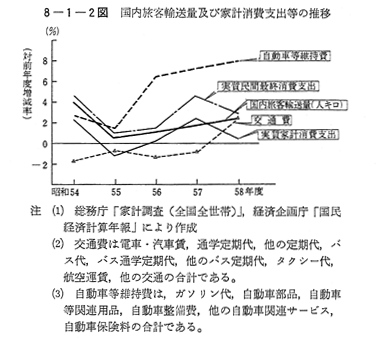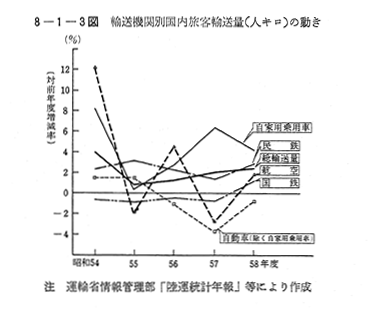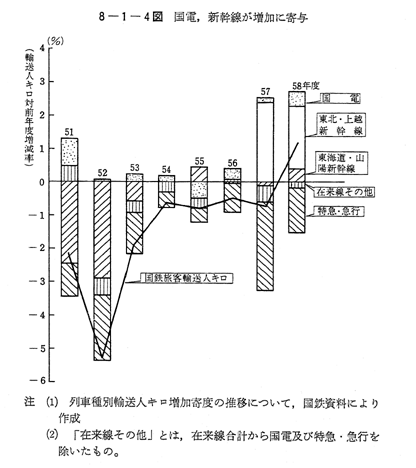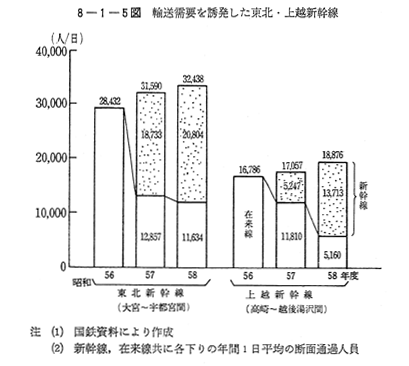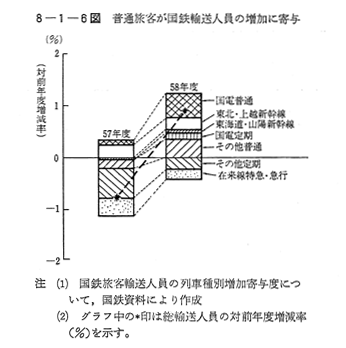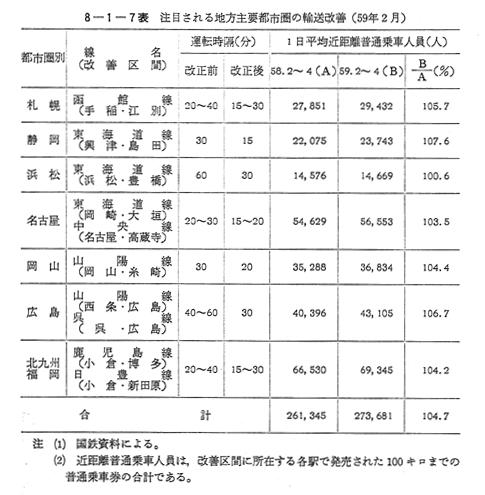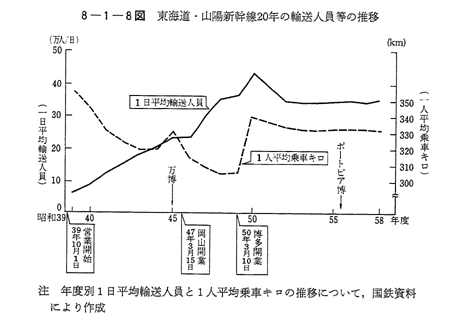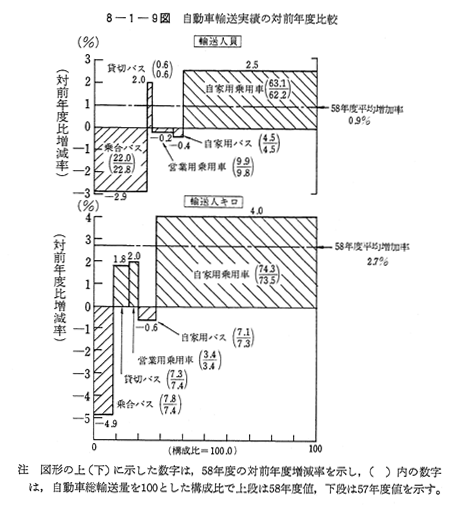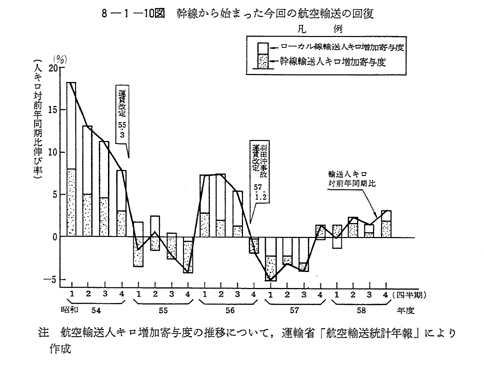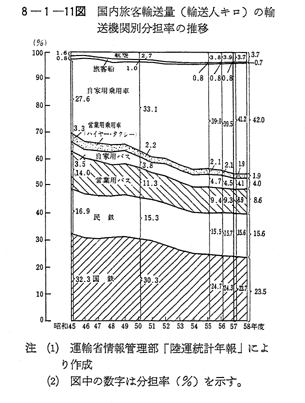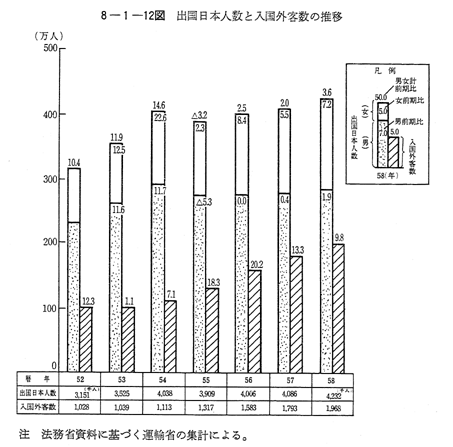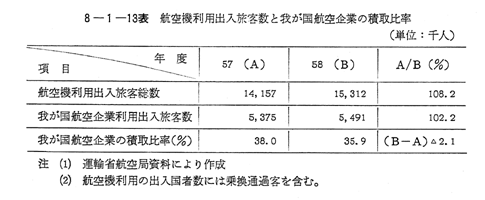|
1 旅客輸送の動向
(1) 国内輸送
ア 58年度の概況
(国内旅客輸送量は輸送人キロで2.2%増)
昭和58年度の国内旅客輸送量は,総輸送人員で525億4,100万人,対前年度比1.1%増,総輸送人キロで8,220億人キロ,同2.2%増であり,人員・人キロともに,前年度の伸び率(それぞれ0.4%増,1.8%増)を上回った 〔8−1−1表〕。
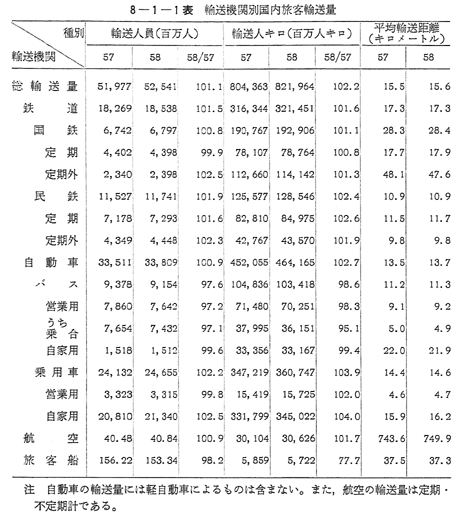
58年度の消費動向をみると 〔8−1−2図〕,実質民間最終消費支出は,年間を通して緩やかな増加傾向を示し,年度全体で2.9%増であった。
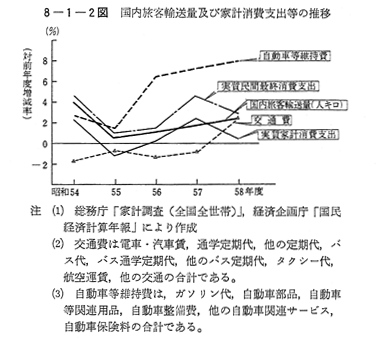
また,全国全世帯(家計調査)の実質消費支出は,四半期ごとに増減のバラツキがみられ,年度全体で0.3%増にとどまった。しかし,消費支出の内容をみると,自動車等維持費は対前年度比8.0%増で,前年度に引き続き高い伸びとなったほか,交通費も同2.1%増となり,53年度以来5年ぶりにプラスに転じた。
また,58年の旅行動向をみると,宿泊数,宿泊旅行回数,延べ旅行人数,消費額等いずれも前年水準を上回った。
58年度の特徴としては,国鉄が輸送人員で7年ぶり,輸送人キロで9年ぶりに増加に転じたこと,航空が2年ぶりに増加となったこと,自家用乗用車が前年度に比べ伸びが鈍化したものの高い伸びを示したこと等があげられる 〔8−1−3図〕。
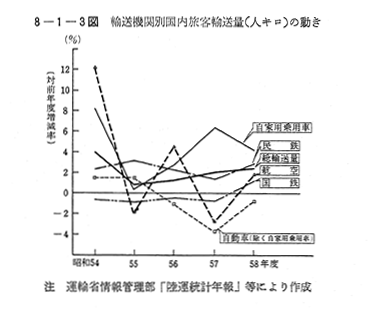
イ 輸送機関別輸送動向
(国鉄旅客減少傾向に歯止め)
国鉄は,輸送人員は対前年度比0.8%増で7年ぶりの増加となり,輸送人キロも同1.1%増で9年ぶりの増加となった。定期は,輸送人員が同0.1%減であったが,1人当たりの平均輸送距離が伸びた結果,輸送人キロでは同0.8%増となった。定期外は,輸送人員で同2.5%増,輸送人キロでは同1.3%増であった。
列車種別にみると,新幹線は,輸送人員は対前年度比12.9%増,輸送人キロ同9.4%増であった。このうち,東海道・山陽新幹線は,57年度のマイナスから輸送人員で同2.2%増,輸送人キロでは同1.7%増といずれも増加となった。また,東北・上越新幹線は,開業が前年度の中途(東北新幹線は6月23日,上越新幹線は11月15日)ということもあって,輸送人員で86.6%増,輸送人キロで78.8%増であった。
在来線の特急・急行は,東北・上越新幹線開業に伴う輸送力減少の影響もあって,輸送人員で同8.4%減,輸送人キロで同7.2%減となったが,前年度の減少率(それぞれ12.0%減,12.4%減)は下回った。
東京・大阪の国電は,定期は,輸送人員で同0.3%増,輸送人キロで同1.3%増,定期外はそれぞれ2.1%増,1.3%増であった。
この結果,国鉄旅客輸送人キロの列車種別増加寄与度は 〔8−1−4図〕のようになり,新幹線及び国電の増加と特急・急行及び在来線その他の減少幅の縮小が58年度の増加につながった。
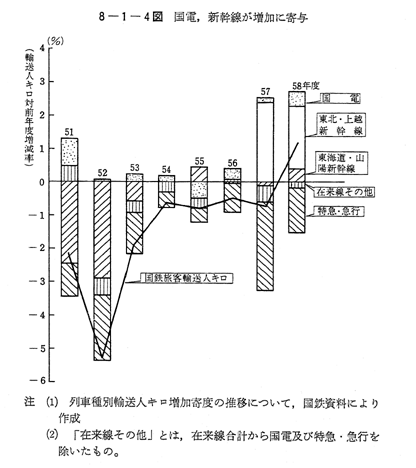
(58年度の増加要因は,東北・上越新幹線の平年度化と運賃改定の見送り)
次に,58年度の国鉄旅客輸送量の増加理由を考えてみると,第1に,東北・上越新幹線の平年度化が上げられる。57年度の中途に開業した東北・上越新幹線は,開業ブームの薄らいだ58年度も好調を持続し,懸念された在来線の落ち込みをもカバーしている 〔8−1−5図〕。
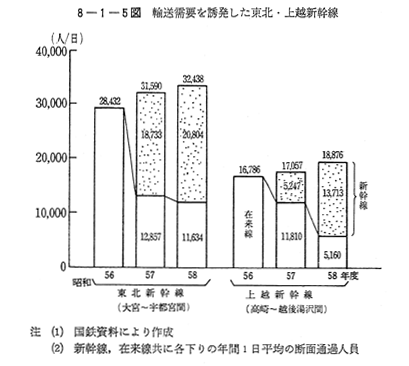
第2に,58年度は53年度から5年間続けて実施した運賃改定を見送ったことによる影響が考えられる。そもそも,運賃改定による輸送量への影響は,定期旅客が概して輸送機関の選択性に乏しく,交通費の会社負担の割合が高いこと等もあって比較的弱いが,普通旅客は交通手段の能動的な選択が可能であるため運賃改定に対して敏感な反応を示すのである。この点を輸送人員ベースでみると, 〔8−1−6図〕のように,58年度は,国電普通,その他普通が大幅に増加している。また,東海道・山陽新幹線が輸送人員,輸送人キロとも3年ぶりに増加に転じたことや,在来線特急・急行の減少幅の縮少等も運賃改定の見送りが影響しているものと思われる。
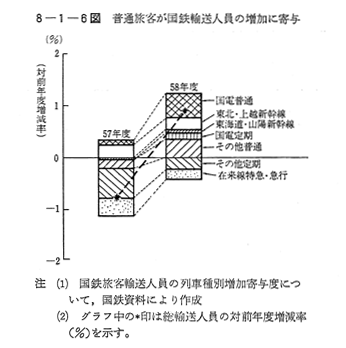
なお,59年2月のダイヤ改正を機に大幅な輸送改善を実施した札幌ほか6地区の輸送動向をみると,これらの地区では国電並みのダイヤを目標に 〔8−1−7表〕のような従来より短編成の列車を等時隔で多数運転した結果,輸送量はいずれも増加していることが注目される。
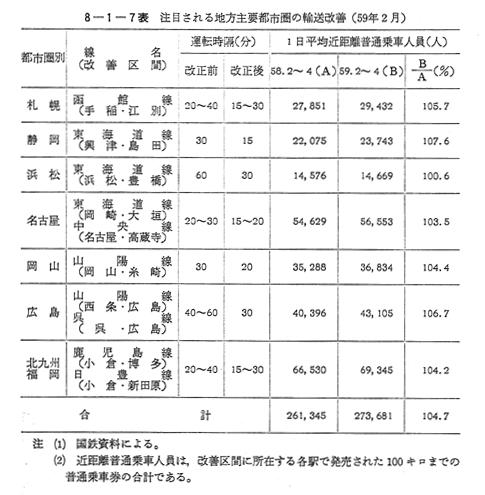
(東海道新幹線は開業後20年を経過)
東海道新幹線は,59年10月1日に開業20周年を迎えた。東京オリンピックが開催された39年に東京・新大阪間553キロメートルを4時間(40年11月から現在の3時間10分に短縮)で結ぶ夢の超特急として営業を開始し,47年には岡山まで,さらに50年には博多まで延長され,延べ輸送人員は20億人を超えたが,この間,乗客死亡事故は皆無であり,世界で最も安全な大量高速輸送機関であるということを証明した。営業収支は,開業3年目から黒字計上を続け,58年度の収入は8,212億円で,これは国鉄旅客収入の33%に相当する。
開業時と現在(59年9月末)の輸送条件を比較すると,営業キロは,開業時の553キロメートルから47年3月の岡山開業,50年3月の博多開業で1,177キロメートルとなり,列車本数(上下計)も1日平均60本から255本となった。この結果,1日当たりの走行キロは,2万9000キロから16万2000キロに増加している。また,駅数も12駅から28駅となっている。
次に,輸送量等の変遷についてみると 〔8−1−8図〕,1日平均の輸送人員は,営業キロの延長,輸送力の増強等に比例して増え続けたが,50年度の43万人をピークに52年度以降は34万人前後に落ち着いている。ちなみに,過去もっとも利用者が多かったのは,50年5月5日の103万人であった。一方,1人平均の乗車キロは,開業時の355キロを最長に,以後短距離化の傾向を示した。しかし,50年の博多開業により再び延長し,以後,現在まで330キロ台で推移している。
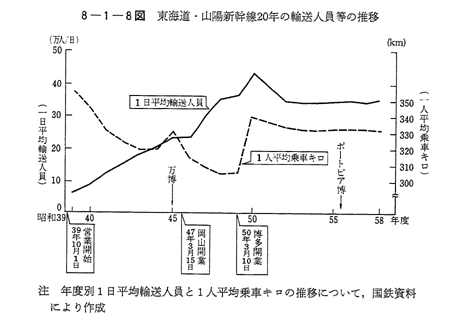
なお,東海道・山陽新幹線利用者の旅行目的別割合をみると(58年10月国鉄調査),用務55.7%,観光18.3%,家事私用16.1%等となっている。
(民鉄は堅調保持)
民鉄は,輸送人員で対前年度比1.9%増,輸送人キロで同2.4%増といずれも前年度の伸び率を上回った。定期は輸送人員で同1.6%増,輸送人キロで同2.6%増,定期外は輸送人員で同2.3%増,輸送人キロで同1.9%増であった。このうち,地下鉄の輸送人員は対前年度比4.3%増,輸送人キロ同5.8%増であり,東京と大阪における地下鉄の輸送人員は東京4.2%増,大阪2.6%増,輸送人キロは東京,大阪ともに5.8%増であった。なお,大手私鉄(14社)の輸送人員は,対前年度比1.0%増,輸送人キロ同1.7%増であった。
(自動車の伸びはやや鈍化)
自動車(軽自動車は含まない。)は,自家用乗用車の伸びが大きく寄与し,輸送人員は対前年度比0.9%増,輸送人キロは同2.7%増であった。バスは,輸送人員,輸送人キロとも前年度水準を下回った。このうち,乗合バスは輸送人員で同2.9%減,輸送人キロで同4.9%減となったが,貸切バスは輸送人員,輸送人キロいずれも増加した。
一方,乗用車は比較的堅調に推移し,輸送人員で同2.2%増,輸送人キロで同3.9%増であった。自家用乗用車は,輸送人員で同2.5%増,輸送人キロは平均輸送距離が伸びたため4.0%増となったものの増加率では前年度(それぞれ2.7%増,6.3%増)を下回った。また,営業用乗用車は,輸送人員で同0.2%減,輸送人キロでは同2.0%の増加となった 〔8−1−9図〕。
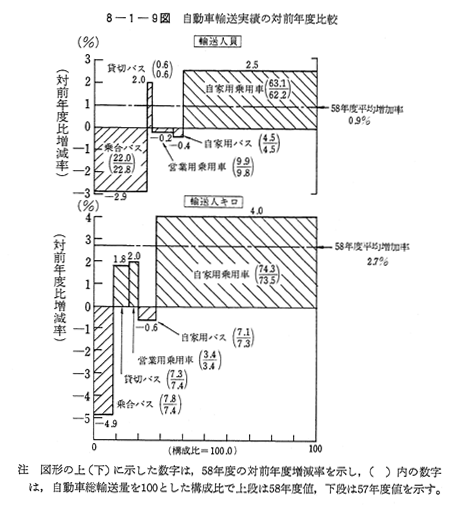
なお,軽自動車による輸送量をみると,58年10月の1か月間で輸送人員は,5億9,483万人,輸送人キロは67億6,800万人キロとなっており,それぞれ登録自動車の輸送量の17.2%,14.2%に相当している。57年10月の輸送量と比較すると,輸送人員で6.5%増,輸送人キロでは12.9%増であった。なお,軽自動車全体の旅客輸送量に占める自家用軽貨物車のシェアは,輸送人員で69.9%,輸送人キロで69.1%,自家用軽乗用車は,それぞれ30.1%,30.9%となっている
(航空は2年ぶりに増加)
航空は,輸送人員は対前年度比0.9%増(幹線同3.2%増,ローカル線同0.5%減),輸送人キロは同1.7%増(幹線同2.8%増,ローカル線同0.7%増)で2年ぶりの増加となった。路線別では,幹線は東京・大阪線(同8.8%増),東京・福岡線(同5.2%増)等のビジネス路線が,また,ローカル線は東京・高知線(同48.6%増),東京・徳島線(同35.8%増)のようにジェット化した路線や東京・広島線(同7.4%増),大阪・仙台線(同19.1%増)のように大型機材が就航した路線での増加が顕著であった。
次に,航空の四半期別輸送動向(輸送人キロ)をみると 〔8−1−10図〕,57年1月の運賃改定,2月の航空機墜落事故,6月の東北新幹線,11月の上越新幹線開業等の影響により,56年度の第4四半期以降4期連続して前年水準を下回ったが,57年度第4四半期から幹線が増加に転じたことにより全体でも増加に転じた。しかし,ローカル線の減少傾向はさらに長びき,58年度の第2四半期から増加となった。その後は,徳島,高知,富山等の地方空港のジェット化,機材の大型化等により増加傾向を続けている。
なお,58年度の座席利用率は,全体で60.9%となり,前年度に比べ0.3ポイント減となった。このうち,幹線は59.8%で0.8ポイント増,ローカル線は上半期の不調が響き,62.0%で1.4ポイントの減少であった。
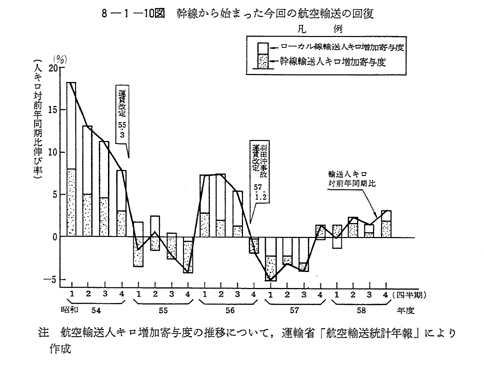
旅客船(一般旅客定期航路,特定旅客定期航路及び旅客不定期航路)は,輸送人員は対前年度比1.8%減,輸送人キロは同2.3%減となり,輸送人員は57年度から,輸送人キロは55年度から減少を続けている。このうち,長距離フェリー(片道の航路距離が300キロメートル以上であって陸上のバイパス的なフェリー)は,輸送人員,輸送人キロとも前年度と同水準であった。
以上のような輸送動向により,58年度の輸送機関別国内旅客輸送人キロ分担率は,自家用乗用車のみが増加し,他の輸送機関は横ばいないし低下している 〔8−1−11図〕。
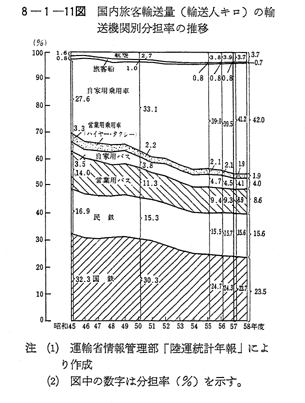
(2) 国際輸送
(国際旅行者は2年ぶりに増加)
1983年の国際旅行者数は、世界観光機関(WTO)の推計によれば、到着数で2億8,648万人、対前年比0.5%増となり2年ぶりの増加となった。これは、旅行者の送出国であり、かつ、世界の国際観光量の85%以上を占めている北アメリカ、ヨーロッパの先進諸国の経済環境がやや好転した結果と考えられる。
(世界の国際航空輸送は人員、人キロとも増加)
国際航空の動き(輸送人員ベース)をみると、国際民間航空機関(ICAO)の統計に基づく定期国際輸送量は、83年は、1億7,192万人、対前年比1.1%増となり、国際線旅行者数の伸び率を上回った。また、輸送人キロは、5,081億人キロで同2.4%増であった。
(出国日本人及び入国外客とも史上最高を記録)
昭和58年の我が国をめぐる国際旅行の動向をみると、出国日本人数は423万人で対前年比3.6%増となり、史上最高を記録した 〔8−1−12図〕。出国日本人数は、55年以降は景気の停滞等から横ばい状態にあったが、最近になって再び増加傾向を示している。
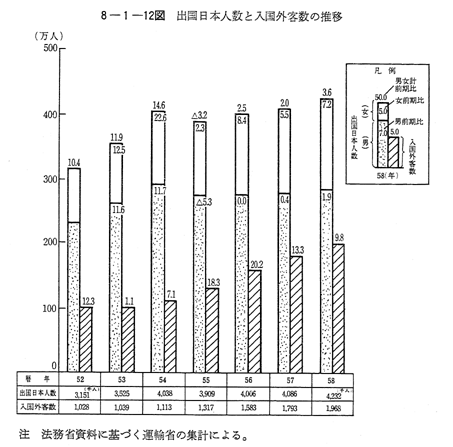
出国日本人を渡航目的別にみると、観光が全体の82.6%を占め、次いで業務関係となっている。
渡航先別では、男女とも第1位は米国(男性の28.7%、女性の44.3%)で、以下、男性は台湾、韓国、香港、女性は香港、台湾、シンガポールの順となっている。
男女別割合は、ほぼ2対1であるが、対前年増加率は、男性の1.9%増に対し、女性は7.2%増となっており、海外渡航者中に占める女性割合は漸増傾向にある。
一方、入国外客数は197万人、対前年比9.8%増となり初めて190万人台を記録した。
入国外客数は,円高を反映して伸び悩んだ53年を除き順調な伸びを示している。これは,世界的な物価上昇傾向の中で,我が国の物価上昇率が諸外国に比べて低かったこと等によると考えられるほか,円が比較的安値で推移したことにより,訪日旅行費用に割安感があったこと,台湾が54年1月から観光目的の海外渡航を自由化したことに加え,韓国においても渡航制限が緩和されてきていること等による。
入国外客を州別にみると,アジア州が98万人(対前年比10.0%増)と全体の50%を占め,次いで北アメリカ州53万人(同11.3%増),ヨーロッパ州36万人(同10.8%増)となっている。このうち,米国が46万人(対前年比12.3%増)と最も多く,次いで台湾37万人(同5.1%増),韓国20万人(同0.9%増),英国(香港在住者等を含む)。17万人(同14.3%増)となっている。
(我が国航空企業による積取比率は減少)
58年度の航空機利用出入国者数(乗換通過客を含む。)は,1,531万人,対前年度比8.2%増であった。このうち我が国航空企業(2社)利用出入旅客数は549万人,同2.2%増であり,我が国航空企業による積取比率は前年度に比べ2.1ポイント減の35.9%となった 〔8−1−13表〕。
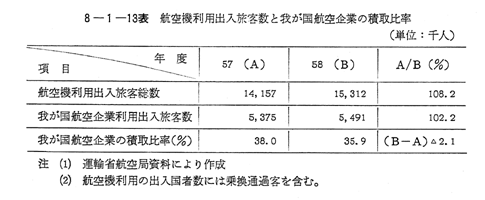
|