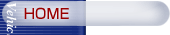|
自動車の用途等の区分について(依命通達) |
| |
|
| |
自車第452号
昭和35年9月6日
自車第793号
昭和39年11月12日
自車第1112号
昭和45年5月14日
自車第280号
昭和48年3月23日
自車第599号
昭和49年10月17日
地技第176号
昭和63年8月4日
地技第144号
平成2年8月2日
自技第256号
平成7年12月28日
自技第65号
平成8年4月15日
国自技第49号
平成13年4月6日 |
|
| |
各地方陸運局長 殿
沖縄総合事務局長 殿 |
| |
自動車局長 |
| |
自動車の用途等の区分について(依命通達) |
| |
道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第14号の自動車(軽自動車を除く。) の用途及び軽自動車(二輪自動車を除く。)の分類は、次のとおり区分して取り扱うこととされたい。
なお、「貨物自動車と乗用車の区分に関する基準について」(昭和29年自車第366号)及び「貨物自動車 と乗用自動車の区別に関する基準の解釈について」(昭和29年自車第436号)は、廃止する。 |
| |
|
| |
1 乗用自動車等
| 1-1 |
乗用自動車等とは、乗車定員10人以下の自動車であって貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。 |
| 2-2 |
乗合自動車等を次のように分類するものとする。
| (1) |
乗用自動車
(2)又は(3)以外の乗用自動車等をいう。 |
| (2) |
貸渡乗用自動車等
道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「運送法施行規則」という。)第52条の規定により許可を受けた乗用自動車等をいう。 |
| (3) |
幼児専用乗用自動車
専ら幼児の運送を目的とする乗用自動車等をいう。 |
|
|
| |
|
| |
2 乗合自動車等
| 1-1 |
乗合自動車等とは、乗車定員11人以上の自動車で貨物自動車等及び特種用途自動車等以外のものをいう。 |
| 2-2 |
乗合自動車等を次のように分類するものとする。
| (1) |
乗合自動車
(2)又は(3)以外の乗合自動車等をいう。 |
| (2) |
貸渡乗合自動車等
運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた乗合自動車等をいう。 |
| (3) |
幼児専用乗合自動車
専ら幼児の運送を目的とする乗合自動車等をいう。 |
|
|
| |
|
| |
3 貨物自動車等
| 3-1 |
貨物自動車等とは、特種用途自動車等以外の自動車であって、次の(1)又は(2)のいずれかを満足するものをいう。
| (1) |
(2)以外の自動車にあっては、次の①及び②を満足すること。
| 1. |
物品積載設備の床面積 |
| |
自動車の物品積載設備(注1)を最大に利用した場合において物品積載設備の床面積(注2)が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2m2)以上あること。
|
| 2. |
構造及び装置 |
| |
当該自動車の構造及び装置が3-1-1又は3-1-2に該当するものであること。 |
|
| (2) |
第五輪荷重を有するけん引自動車であって、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引自動車であって、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によってささえられる構造のものをいう。以下同じ。)をけん引するための連結装置を有すること。 |
|
| 3-1-1 |
次の(1)から(4)までの基準に適合するものであること。
| (1) |
物品積載設備の床面積と乗車設備の床面積
自動車の乗車設備(注3)を最大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。 |
| (2) |
積載貨物の重量と乗車人員の重量
自動車の乗車設備を最大に利用した場合において、残された物品積載設備に積載し得る貨物の重量(注5)が、この場合の乗車設備に乗車し得る人員の重量より大きいこと。 |
| (3) |
物品の積卸口
物品積載設備が屋根及び側壁(簡易な幌によるものであって、その構造上屋根及び側壁と認められないものを除く。)によっておおわれている自動車にあってはその側面又は後面に開口部の縦及び横の有効長さがそれぞれ800mm(軽自動車にあっては、縦600mm横800mm)以上で、かつ、鉛直面(後面の開口部にあっては車両中心線に直角なもの、側面の開口部にあっては車両中心線に平行なものをいう。)への投影面積が0.64m2(軽自動車にあっては、0.48m2)以上の大きさの物品積卸口を備えたものであること。ただし、物品積載設備の上方が開放される構造の自動車で、開口部の床面への投影面積が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2)以上の物品積卸口を備えたものにあっては、この限りでない。
|
| (4) |
隔壁、保護仕切等
自動車の乗車設備と物品積載設備との間に適当な隔壁又は保護仕切等を備えたものであること。ただし、最大積載量500Kg以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品から保護される構造と認められるもの、及び折りたたみ式座席又は脱着式座席(注6)を有する自動車で乗車設備を最大に利用した場合には最大積載量を指定しないものにあってはこの限りでない。
|
|
| 3-1-2 |
次の(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
| (1) |
隔壁等
自動車の運転者席(運転者席と並列の座席を含む。以下「運転者席」という。)の後方がすべて幌で覆われた物品積載装置であって、運転者席と物品積載装置との間に乗車人員が移動できないような完全な隔壁があること。
|
| (2) |
座席
物品積載装置内に設けられた座席は、そのすべてが折りたたみ式又は脱着式の構造のもので、折りたたんだ場合又は取り外した場合に乗車設備が残らず貨物の積載に支障のない構造のものであること。
|
|
| 3-2 |
貨物自動車等を次のように分類するものとする。
| (1) |
貨物自動車
(2)以外の貨物自動車等をいう。 |
| (2) |
貸渡貨物自動車
運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた貨物自動車等をいう |
|
|
| |
|
| |
4 特種用途自動車等
| 4-1 |
特種用途自動車等とは、主たる使用目的が特種である自動車であって、次の(1)から(3)のすべてを満足するものをいう。
| (1) |
主たる使用目的遂行に必要な構造及び装置を有し(注7)、かつ、4-1-1、4-1-2又は4-1-3のいずれか1つに該当するものであること。 |
| (2) |
最大積載量を有する自動車にあっては、自動車の乗車設備と物品積載装置との間には、適当な隔壁又は保護仕切等を備えたものであること。
ただし、最大積載量500Kg以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品から保護される構造と認められるものにあっては、この限りでない。 |
| (3) |
次の 1 から 3 のいずれかに該当する自動車でないこと。
ただし、4-1-1の各車体の形状の自動車にあっては、この限りでない。
| 1. |
型式認証等を受けた自動車(注8)の用途が乗用自動車であって、車体の形状が箱型又は幌型のものであり、かつ、その車枠が改造されていないもの |
| 2. |
型式認証等を受けた自動車の用途が貨物自動車であって、その物品積載設備の荷台部分の2分の1を超える部位が平床荷台、バン型の荷台、ダンプ機能付き荷台、車両運搬用荷台又はコンテナ運搬用荷台であるもの |
| 3. |
型式認証等を受けた自動車の用途が貨物自動車であって、セミトレーラをけん引するための連結装置を有するもの |
|
|
| 4-1-1 |
専ら緊急の用に供するための自動車
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条により指定又は届出された緊急自動車であって、かつ、以下の車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を有するもの
救急車、消防車、警察車、臓器移植用緊急輸送車、保線作業車、検察庁車、
緊急警備車、防衛庁車、電波監視車、公共応急作業車、護送車、血液輸送車、
交通事故調査用緊急車
なお、被けん引車又は二輪車若しくは三輪車であることにより車体の形状の一部が異なる場合については、上記の車体の形状を以下の事例に示すように読み替えて適用する(以下本項において同じ。)。
| 例: |
消防車 → 消防フルトレーラ |
| 救急車 → 救急車二輪 |
| 警察車 → 警察車三輪 |
|
| 4-1-2 |
法令等で特定される事業を遂行するための自動車
使用者の事業が法令等(注9)の規定に基づき特定できるもので、その特定した事業を遂行するために専ら使用する自動車であって、以下の車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を有するもの
給水車、医療防疫車、採血車、軌道兼用車、図書館車、郵便車、
移動電話車、路上試験車、教習車、霊柩車、広報車、放送中継車、
理容・美容車 |
| 4-1-3 |
特種な目的に専ら使用するための自動車
特種な目的に専ら使用するため、次の①から③の全てを満足する自動車
| 1. |
次の(1)から(4)の区分に示す車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を運転者席以外に有していること。 |
| 2. |
乗車設備及び物品積載設備を最大に利用した状態で、水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)に特種な設備を投影した場合の面積(以下「特種な設備の占有する面積」(注10)という。)が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2)以上であること。 |
| 3. |
特種な設備の占有する面積は、運転者席を除く客室の床面積(注11)及び物品積載設備の床面積並びに特種な設備の占有する面積の合計面積の2分の1を超えること。 |
|
| (1) |
特種な物品を運搬するための特種な物品積載設備を有する自動車であって、車体の形状が次に掲げるもの
粉粒体運搬車、タンク車、現金輸送車、アスファルト運搬車、
コンクリートミキサー車、冷蔵冷凍車、活魚運搬車、保温車、
販売車、散水車、塵芥車、糞尿車、ボートトレーラ、オートバイトレーラ、
スノーモービルトレーラ |
| (2) |
患者、車いす利用者等を輸送するための特種な乗車設備を有する自動車であって、車体の形状が次に掲げるもの
患者輸送車、車いす移動車 |
| (3) |
特種な作業を行うための特種な設備を有する自動車であって、車体の形状が次に掲げるもの
消毒車、寝具乾燥車、入浴車、ボイラー車、検査測定車、穴堀建柱車、
ウインチ車、クレーン車、くい打車、コンクリート作業車、コンベア車、
道路作業車、梯子車、ポンプ車、コンプレッサー車、農業作業車、
クレーン用台車、空港作業車、構内作業車、工作車、工業作業車、
レッカー車、写真撮影車、事務室車、加工車、食堂車、清掃車、
電気作業車、電源車、照明車、架線修理車、高所作業車 |
| (4) |
キャンプ又は宣伝活動を行うための特種な設備を有する自動車であって、車体の形状が次に掲げるもの
キャンピング車、放送宣伝車、キャンピングトレーラ |
| 4-2 |
キャンピング車、放送宣伝車、キャンピングトレーラ |
| (1) |
特種用途自動車
(2)以外の特種用途自動車等をいう。 |
| (2) |
貸渡特種用途自動車
運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた特種用途自動車等をいう。 |
|
| |
5 建設機械
建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に掲げる大型特殊自動車をいう。 |
| |
6 自動車の用途等の区分に係る細部取扱い
| (1) |
この通達に規定する自動車の用途等の区分を定量的に判断するに当たって必要な事項は、別途定める(以下「細部取扱通達」という。)。 |
| (2) |
細部取扱通達において、本通達の規定を読み替えて適用する旨の規定がある場合にあっては、細部取扱通達の規定により本通達の規定に適合するものと見なすものとする。 |
|
| |
| 注1 |
物品積載設備 |
| |
運転者席の後方にある物品積載装置(原則として、一般の貨物を積載することを目的としたものであって、物品の積卸しが容易にできる構造のもの。)をいう。 |
|
| |
| 注2 |
物品積載設備の床面積 |
| (1) |
乗車人員の携帯品の積載場所と認められるもの、例えば後部トランク及び屋根上の物品積載装置の床面積は、この場合の物品積載設備の床面積には含めないものとする。 |
| (2) |
タイヤえぐり、蓄電池箱等の占める面積は、物品の積載に支障がない限り物品積載設備の床面積に含めるものとする。 |
| (3) |
物品積載設備の上方開放部の面積が床面積より小さい構造の自動車にあっては、床面からの高さが1m未満の箇所における最小開放部の水平面への投影面積をもって床面積とする。 |
| (4) |
物品積載設備が屋根及び側壁で覆われている自動車、例えばバン型の自動車の類にあっては、室内最高部と床面との中点を含む車室の断面積で大部分の床面に平行なものをもって床面積とする。 |
|
| |
| 注3 |
乗車設備 |
| |
運転者席の後方にある乗車設備をいう。 |
|
| |
| 注4 |
乗車設備の床面積 |
| (1) |
運転者席の後方に設けられた座席の背あて後端から前方(前方を含む。)には物品が積載されない構造の自動車にあっては、運転者席背あて後端(隔壁又は保護用の仕切のあるものにあってはその後端。)から最後部座席の最後端までの大部分の床面に平行な距離に室内幅を乗じたものを床面積とする。
|
| (2) |
運転者席の後方に設けられた座席の前方又は側方に物品が積載される構造の自動車(この場合、積載物品により安全な乗車が妨げられないよう、座席の前方又は側方に保護仕切等が必要である。)にあっては、座席の床面への投影面積をもって床面積とする。ただし、次の床面は乗車設備の床面積に含める。
| (イ) |
座席の前縁から250mmまでの床面(補助座席にあっては、座席を含む幅400mm、奥行650mmの床面) |
| (ロ) |
乗車設備の一部として使用されることが明らかな床面。例えば保護仕切で囲まれた床面又は乗車する人員の通路と認められる床面等。 |
|
|
| |
| 注5 |
積載し得る貨物の重量 |
| (1) |
物品積載設備内に折りたたみ式又は脱着式の座席を備えた自動車にあっては、物品積載設備を最大に利用した場合の最大積載量を指定する際に、最大積載量の基となる重量から乗車設備を最大に利用した場合の乗車設備乗車出来る人員の重量(脱着式の座席を備えた自動車にあっては、乗車設備を最大に利用した場合の乗車設備に乗車出来る人員の重量と脱着式の座席の重量との和)を減じた重量をいう。
|
| (2) |
物品積載設備内に折りたたみ式及び脱着式の座席がなく、物品積載設備と乗車設備とが明確に区分された自動車にあっては、最大積載量を指定する際に最大積載量の基となる重量をいう。
|
|
| |
| 注6 |
脱着式座席 |
| |
脱着して使用することを目的とした座席であり、工具等を用いることなく、容易に脱着ができ、かつ、確実に装着ができる構造の座席をいう。 |
|
| |
| 注7 |
主たる使用目的遂行に必要な構造及び装置を有し |
| |
車枠又は車体に、特種な目的遂行のための設備(「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け自技第234号、自整第262号)の指定部品は、「特種な目的遂行のための設備」には該当しないものとする。)がボルト、リベット、接着剤又は溶接により確実に固定されているものをいう。
なお、蝶ねじ類、テープ類、ロープ類、針金類、その他これらに類するもので取り付けられた設備は、確実に固定されているものに該当しないものとする。 |
|
| |
| 注8 |
型式認証等を受けた自動車 |
| (1) |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第75条第1項の規定によりその型式について指定されたもの |
| (2) |
「自動車型式認証実施要領について(依命通達)」(平成10年11月12日付け自審第1252号)別添2「新型自動車取扱要領」により新型自動車として届け出された型式のもの
|
| (3) |
「輸入自動車特別取扱制度について(依命通達)」(平成10年11月12日付け自審第1255号)別紙「輸入自動車特別取扱要領」により輸入自動車特別取扱自動車として届け出された型式のもの
|
| (4) |
「並行輸入自動車取扱要領について」(平成9年3月31日付け自技第61号)別添「並行輸入自動車取扱要領」(以下「並行輸入自動車取扱要領」という。)に基づく並行輸入自動車であって、並行輸入自動車取扱要領により届出自動車との関連を判断するにあたり、上記(1)から(3)の型式と比較して同一又は関連ありと判断したもの
|
|
| |
| 注9 |
法令等 |
| |
法律、政令、府令、省令及びこれらの規定に基づく告示並びに地方自治体が定める条例をいう。 |
|
| |
| 注10 |
特種な設備の占有する面積 |
| (1) |
車体の形状毎に別途定める構造上の要件に適合する設備を基準面に投影した場合の面積をいう。 |
| (2) |
次の各号のいずれかに該当する部位及び当該部位に設けられた設備の基準面への投影面積は、特種な設備の占有する面積には含めないものとする。
| 1. |
乗車人員の携帯品の積載箇所と認められるところ(トランク、ラゲッジスペース、インストルメント・パネル、グローブボックス、トレイ、ルーフ・ラック等の各種ラック類 等) |
| 2. |
乗車装置の座席 |
| 3. |
乗車装置の座席の上方又は下方(背あての角度が可変する座席にあっては、背あての角度は背あての支点をとおる垂直な面と背あてのなす角度は後方に30度(30度に保持できない場合は、30度に最も近い角度)とした場合の床面への投影面、座席が前後、左右に可変又は回転する場合は、可変又は回転した状態で保持できるすべての位置における床面への投影面、折りたたみ式座席又は脱着式座席にあっては、当該座席を乗車設備として利用したときの床面への投影面、これらの機能を併せ持った座席にあっては、これらの要件のうち、該当するものすべてを組み合わせた状態における床面への投影面とする。)
|
| 4. |
乗車装置の座席の前縁から前方250mmまでの床面(座席が前後、左右に可変、回転、折りたたみ式又は脱着式である場合にあっては、当該座席を利用できるすべての位置において、座席の前縁から前方250mmまでの床面)
|
| 5. |
特種な設備を基準面に投影した場合の部位と、物品積載設備を基準面に投影した場合の部位が重なる部位 |
| 6. |
当該自動車の修理等に使用する工具等を収納する荷箱 |
| 7. |
いかなる名称によるかを問わず、①から⑥と類似する部位 |
|
|
| |
| 注11 |
運転者席を除く客室の床面積 |
| (1) |
運転者席の背あて後端(隔壁又は保護用の仕切のある場合にあっては、その後端)から乗車設備の最後部座席までを含む客室の後端(乗車設備の最後部座席より後方に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有する場合にあっては、乗車設備の最後部座席の背あて後端(隔壁又は保護用の仕切がある場合には、その前端))までの車両中心線上における大部分の床面に平行な距離に室内幅を乗じたものを客室の床面積とする。
この場合において、運転者席が前後に可変する座席にあっては、座席の位置は最後端とし、運転者席の背あての角度が可変する座席にあっては、背あての角度は背あての支点をとおる垂直な面と背あてとのなす角度は後方に30度(30度に保持できない場合は、30度に最も近い角度)とする。
また、乗車設備の側方等に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有する場合にあっては、上記にかかわらず、乗車設備の座席の床面への投影面積をもって客室の床面積とすることができる。
この場合において、次の床面は客室の床面積に含むものとする。
| (イ) |
座席の前縁から250mmまでの床面(幅400mm、奥行400mm未満の補助座席にあっては、座席を含む幅400mm、奥行650mmの床面) |
| (ロ) |
乗車装置の一部として使用されることが明らかな床面。例えば保護仕切で囲まれた床面又は乗車する人員の通路と認められる床面等 |
|
| (2) |
タイヤえぐり等の占める面積は、安全な乗車に支障がない限り、客室の床面積に含めるものとする。 |
| (3) |
客室の室内幅(乗車設備の側方等に物品積載設備又は特種な目的に専ら使用するための設備を有する場合を除く。)は、運転者席の背あて後端から客室の後端までの中間点における車両中心線に直交する大部分の床面に平行な距離とする。 |
|
| |
最終改正(平成13年4月6日付け国自技第49号)の主文
現在、特種な用途に応じた設備を有する自動車を特種用途自動車として区分し、検査、登録において取り扱っているところであるが、近年、検査時にはその設備を装備して登録し、その直後に当該設備を取り外して乗用自動車等と同じ仕様で不正に使用する事例が多発している。また、特種用途自動車として不正に検査、登録を受けたとして、中古車販売業者が逮捕される事件も発生している。
このような不正使用の理由としては、1.特種用途自動車は、乗用自動車等に比べ税、保険料が安いこと、2.現在規定されている特種用途自動車の構造要件が抽象的であること等があり、一方、これらを背景として、検査時における自動車の用途の判定に当たって、申請者との間でトラブルが多発している状況にある。
こうした特種用途自動車の不正使用の防止及び検査時における自動車の用途の判定の適正化のため、特種用途自動車の各車体形状毎に構造要件を具体的、かつ、詳細に定めるべく、パブリックコメントを募集したところ、多くの意見、要望があった。
これらの意見、要望も踏まえ、「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(昭和35年9月6日付け自車第452号)(以下「用途区分通達」という。)の一部を別添新旧対照表のとおり改正することとし、平成13年10月1日からこれにより実施することとしたので了知されるとともに、関係者を指導されたい。
ただし、改正後の用途区分通達4-1-3(4)のキャンピング車については、平成15年3月31日までは、なお従前の例によることができることとする。 なお、平成13年9月30日(用途区分通達4-1-3(4)のキャンピング車については、平成15年3月31日と読み替える。)において、特種用途自動車として既に登録を受けている自動車又は特種用途自動車として車両番号の指定を受けている自動車にあっては、その自動車の構造・装置に変更がない限りにおいては、なお従前の例によることができることとする。
|