| 日時 : |
平成17年11月18日(金) 14時30分〜17時00分 |
| 場所 : |
国土交通省 低層棟共用会議室2A(中央合同庁舎第2号館) |
|
出席委員(敬称略) |
|
|
| ※五十音順 |
|
|
| |
〈委員〉 |
| |
井出多加子、金本良嗣、平井宜雄 |
| |
〈臨時委員〉 |
| |
石澤卓志、伊藤和博、岩原紳作、渋谷正雄、杉本茂、田村幸太郎、土田あつ子、濱口大輔、福士正 |
|
| 議事概要 : |
(1) |
開会 |
| |
|
(2) |
投資家が安心して参加できる不動産市場の在り方について |
| |
|
|
事務局から資料1の説明後、質疑応答、意見交換。 |
| |
|
|
事務局から資料2及び岩沙委員の意見書の説明後、質疑応答、 |
| |
|
|
意見交換。 |
| |
|
|
事務局から資料3の説明後、質疑応答、意見交換。 |
| |
|
|
事務局から資料4の説明後、質疑応答、意見交換。 |
| |
|
(3) |
今後の進め方について |
| |
|
|
事務局から今後の開催予定を説明。 |
主な発言内容:
- 投資家への説明方法を検討する際には、不動産投資においてなぜ対面説明を求めているのか、どのような点が対面でなくては説明できないのか等を一度きちんと整理する必要があるのではないか。
- 実物不動産の法定スキームである不動産特定共同事業法は、個々の不動産取引の際に詳細に説明を行い、意思確認する投資家保護を意識したスキーム。不動産を信託財産とした信託受益権の形で行う不動産投資は、信託受益権取引でありながらまさに実物不動産取引そのものであり、投資サービス法の枠内で議論するよりも、むしろ実物不動産投資スキームである不動産特定共同事業法と同じ考え方で捉えるべきである。
- 投資家からみると、不動産を裏付けにした金融商品のディスクロージャーについては、不動産固有のリスク等の情報が重要であり、今後はそれらの商品を横断的にカバーするディスクロージャー制度を整備する必要があるのではないか。米国でADCローン(買収型、開発型、建設型ローン)は不動産に区分されており、不動産と同一レベルの開示情報が必要とされている。
- 細かい法技術論はあまり気にせずに、まずは非代替性の強い不動産としての特性がある商品の規制内容についてのあるべき姿を検討すべきではないか。
- 5年程前から不動産の信託受益権化が始まり、金融と不動産が融合しつつあるが、不動産を裏付けにしたものについては、不動産に軸足をおいて考えた上で、必要に応じて金融の仕組みを取り込んで考えていくべきではないか。「不動産について相当の知識を有する者」に関する議論が必要である。
- 投資家の立場からすれば、投資対象の商品の裏付けが不動産だろうと航空機だろうと当該目的財産の固有のリスクを把握する必要があることには変わりなく、あえて不動産の場合を特別視して捉える必要はない。
- そもそも金融商品には何らかの実物の裏付けがある。不動産の特殊性を議論し始めたら出口がないのではないか。実物を並べてみて考えてはどうか。エクイティタイプのオペレーションはみな複雑。
- 個人投資家からすれば、金融商品の裏付けが何であろうが金銭を出していることにはかわりがない。金融から論じてほしい。個人投資家が不当にリスクを押しつけられるような制度は避けてほしい。
- 投資家からみて不動産は動かないから特殊ということはない。
- 不動産の特殊性を言いすぎないようにすることが大事。
- アセットマネジメント業者は行っている業務がバラバラで類型化しづらいので、参入規制というよりはむしろ行為や業務の内容に着目して分析していくべきである。
<資料3について>
- 不動産固有のリスクについて個別のファンドで自主開示を行っているところも多い。新しいファンドほど細かい。一方で情報開示されない事項もある。加えて、鑑定評価についても異論が多い。こういったことを考慮しつつ情報開示のあり方を検討すべきではないか。
- 例えば、1年前にはアスベストなど意識されていなかったというように、その時々の社会情勢によって投資家の関心を集めるリスク項目も変わっていくので、事情の変化によって開示内容をどうするか検討すべき。
- 地方の金融機関のように金融のプロであっても不動産についてはプロとは言えないことも多い。リスク項目を挙げて示さないと投資家の判断が及ばないこともある。
- 投資家と事業者をつなぐ仲立の者、例えばアナリストといった者についても制度の中で位置づけるべき。
- ディスクロージャーについて、時点に応じてどこまでの情報を開示するのか、また、開示された情報をどう判断して投資家にどのように伝えるかきちんと整理すべき。また、説明された情報について誰がどこまでの責任をとるのか、チェックできた情報について責任を取るのか、チェックできない情報は責任を取らないのか、投資家にとってわかりづらくなっている。実質的にはAMが決めているが。
- みなし有価証券化されたYK−TKについては、証券取引法の開示責任はオリジネーターまで負うのか、それとも販売者にとどまるのか。
- SPC法上は、みなし発行者であるSPCが開示義務を負っている。また、Jリートについては箱である投資法人が開示義務を負っている。こういった場合、全体を把握しているはずの運用会社は責任を負わなくてよい仕組みになっているが、それでよいのか。誰が責任主体であり、それが担保されているのか、投資家にとって分かりにくい仕組みになっている。
- アメリカでは、解釈によってオリジネーターに開示責任を負わせている。
<不動産投資市場の概況を4つの領域にわけていることについて>
- 商品分類の「流通性」については、商品の解約の可否も流通性を判断する上で考慮する必要がある。
- 不動産投資においては、基本的にプロとアマに分けて、プロについては自由にやらせてほしい。
- 証券取引法上のプロの要件と不動産特定共同事業法上のプロの要件との間のずれを存置すべきではない。
- プロ・アマの区分は情報の格差だけによって決まるわけではないのではないか。例えば、不動産取引についての知識・経験がなくとも財政的な余裕があれば不動産投資の専門家を雇うことによって情報の格差に伴うリスクを吸収できる。
- 「流通性」の意味を明確にしてほしい。
- 転売するのに承諾がいると聞いているがそのような細かいことも考慮すべき。
- マーケットの有無、規制の有無で考えていくべき。
- 不動産投資においても、消費者保護法との関係を整理すべき。
- 自主開示情報の項目は際限なく増えていくおそれがあり、きりがない。開示項目が多すぎると結局何が必要な情報なのか投資家からは分かりにくくなるため、投資家保護のために最低限必要な情報を法制度等で画定すべきである。
- アマチュアに売る商品について、プロが開示情報をチェックした場合、プロはどこまで責任を取るのか。
- プロ・アマ区分を保護の必要性の度合いによって判断すべき。保護の必要性の度合いの要素として、
 知識・経験の有無と
知識・経験の有無と 財政的な基準がある。
財政的な基準がある。
- オプトイン、オプトアウトの考え方を入れるのは基本。
- 不動産特定共同法と証券取引法におけるプロの概念は異なっている。仮に不動産特定共同事業法の枠組みが投資サービス法の枠組みの中に取り込まれるのならば、プロ・アマ区分の整合性が大きな問題になる。一部の金融商品については、全ての投資家がアマチュア。
<資料4について>
- PMには決定権限はなく、AMに対して、テナント募集や賃料などの提案をし、承認を得た上で業務を行っている。AMを取締役とすれば、PMは執行役員。PMは投資家と会うことすらない。
- この問題も誰がどこまで説明するのか、そして誰がどのような責任を負うかの問題であると考える。PMが投資家に対する責任を負うことはありえない。AMは実態的に支配しているが、責任を負わない。
- PMの能力は、物件の稼働率を向上させ、管理コストを削減するという点で投資商品の収益性に影響を及ぼすが、指標とはなっていない。PMの能力を評価基準として議論する余地あるが、投資商品の収益性に影響を及ぼす能力を検討しないと無意味な議論になる可能性がある。
- PMの管理はAMの収益の効率性、管理コスト削減につながるのでPMのクオリティの確保を図るためのしっかりとした基準が必要ではないか。
- スキームの設計段階において、誰がどのような義務を負い、どのような業務を遂行することとなるのかを詳細に規定し、実態がほとんどないビークルの責任ではなく、実態のある他の関係者が責任を負うスキームを組成することが重要である。
- TMKには法的ルールができていない。管理責任については、
 商品組成段階、
商品組成段階、 ビークル提供主体の段階、
ビークル提供主体の段階、 販売者の段階 の3段階でのチェックが考えられるが、いずれの段階でも管理責任をおさえられていない。米国では根本のオーガナイザーに管理責任がある。また、信託法、信託業法の改正によって事業信託が可能になるので、信託法が大幅に緩くなる。責任が緩やかになると金融の世界でも管理責任をとらえられなくなる。
販売者の段階 の3段階でのチェックが考えられるが、いずれの段階でも管理責任をおさえられていない。米国では根本のオーガナイザーに管理責任がある。また、信託法、信託業法の改正によって事業信託が可能になるので、信託法が大幅に緩くなる。責任が緩やかになると金融の世界でも管理責任をとらえられなくなる。
- 管理責任を厳しくすると誰もやらなくなる。米国のトラスティも責任をとらない。
- PMは資産運用会社の事務を履行しているだけであり、きつくしばるとかえってコスト高になる。また、清掃事務を行っている人が経営するPM会社もある。結局PMの位置付けをどうするのかの問題である。投資サービス法でYK−TKの登録制度を仮に導入したとして、生成段階での登録は規制のあり方としていかがなものか。
- PMによる管理の問題は他の信託受益権と違う不動産特有の問題という意識でよいか。
- 資料4の問題意識は、
 実物が信託受益権化されたのみでPMが信託会社と同じ執行義務を問われるのはどうか、
実物が信託受益権化されたのみでPMが信託会社と同じ執行義務を問われるのはどうか、 不動産の管理について特に登録規制がないがどうすべきか、の2点あり、主として
不動産の管理について特に登録規制がないがどうすべきか、の2点あり、主として にある。
にある。
(注)議事録については、後日、ホームページ上で公開されます。
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご参照下さい。
|

(ダウンロード)
|
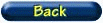
 All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport
All Rights Reserved, Copyright (C) 2005, Ministry of Land, Infrastructure and Transport