(1) 目的
官庁施設においては、膨大なストックの蓄積の一方で、ストックの老朽化が進行しており、修繕・改修等に要するコストの急激な増加が予測される。また、使用年数の長期化、行政需要の多様化、環境保全、コスト縮減等の要請への対応が急務となっている。しかし、少子・高齢化社会の到来などにより、投資余力の減少が予測されており、より一層効率的な保全の実施が求められている。 そこで、保全計画や保全情報を有機的に連携させて、保全を適正に行うシステムを、マネジメント技術として確立することにより、官庁営繕部による保全指導の充実を図るとともに、官庁施設の一層の有効活用を実現することを目的とする「官庁施設のストックマネジメント技術」について検討するため、「官庁施設のストックマネジメント技術検討委員会」を平成11年10月に設置した。本委員会は、平成11年度、12年度の2ヶ年で検討を行い、本報告書はその検討内容についてとりまとめたものである。
(2) 検討体制
建設省に「官庁施設のストックマネジメント技術検討委員会」を設置し、包括的な検討を行うとともに、(財)建築保全センターに分科会を設置し、具体的検討を行った。
官庁施設のストックマネジメント技術検討委員会
| 委
員 長 沖塩荘一郎 宮城大学デザイン情報学科教授
副委員長 今泉 勝吉 工学院大学名誉教授 委 員 小松 幸夫 早稲田大学建築学科教授 委 員 樫野 紀元 建築研究所第二研究部長 委 員 石神 隆 法政大学人間環境学部教授 委 員 佐藤 隆良 (株)サトウファシリティーズコンサルタンツ 代表取締役 委 員 松縄 堅 (株)日建設計取締役 委 員 後藤 志郎 (社)建築業協会 委 員 梶野 善治 (社)全国ビルメンテナンス協会 委 員 島田 高樹 (社)日本電設工業協会 委 員 遠山 精一 (社)日本空調衛生工事業協会 委 員 守屋 康正 (社)日本ファシリティマネジメント推進協会 委 員 岸本 孝一 郵政省大臣官房施設部建築企画課総括専門官 委 員 山本 康友 東京都財務局営繕部コスト管理室長 委 員 鈴木 正男 (財)建築保全センター審議役 委 員 塩原 壮太 (財)建築コスト管理システム研究所 審議役 専門委員 野城 智也 東京大学生産技術研究所第5部助教授 専門委員 柳瀬 正敏 (株)柳瀬建築総合研究所代表取締役 専門委員 丸尾 聰 日本総合研究所主任研究員 専門委員 関 幸治 日本IBM(株)FMS事業開発部FMコンサルティング部長 専門委員 吉岡 洋一 日本メックス(株)研究開発部担当部長 専門委員 石塚 義高 明海大学不動産学部教授 専門委員 伊香賀俊治 日建設計環境計画室長 専門委員 本橋 健司 建築研究所維持保全研究室長 専門委員 阿部 絋己 日本建築設備診断機構技術委員長 委託者側委員 野村 敬明 官庁営繕部管理課長 委託者側委員 横井 孝史 官庁営繕部営繕計画課長 委託者側委員 奥田 修一 官庁営繕部建築課長 委託者側委員 坂 智勝 官庁営繕部設備課長 委託者側委員 佐々木 良夫 官庁営繕部監督課長 委託者側委員 圓田 義則 官庁営繕部保全指導室長 |
分科会((財)建築保全センターに設置) | ||
| 保全計画分科会 | |||
|
|
主 査 佐藤 隆良
(委員会委員)
委 員 石神 隆 (委員会委員) 委 員 野城 智也 (委員会専門委員) 委 員 柳瀬 正敏 (委員会専門委員) 委 員 土屋 邦男 官庁営繕部営繕計画課建設専門官 委 員 林 理 官庁営繕部保全指導室建設専門官 委 員 岡野 雄 官庁営繕部保全指導室課長補佐 |
||
| 情報化分科会 | |||
| 主 査 沖塩荘一郎
(委員会委員長)
委 員 丸尾 聰 (委員会専門委員) 委 員 中津 元次 (有)中津エフ.エム.コンサルティング代表取締役 委 員 関 幸冶 (委員会専門委員) 委 員 吉岡 洋一 (委員会専門委員) 委 員 山田 稔 官庁営繕部特別整備企画室課長補佐 委 員 大町 徹 官庁営繕部保全指導室課長補佐 |
|||
| 保全技術体系化分科会 | |||
| 主 査 小松 幸夫
(委員会委員)
委 員 石塚 義高 (委員会専門委員) 委 員 伊香賀俊治 (委員会専門委員) 委 員 本橋 健司 (委員会専門委員) 委 員 阿部 紘己 (委員会専門委員) 委 員 川妻 二郎 (社)全国ビルメンテナンス協会 委 員 柊平 健 官庁営繕部建築課課長補長 委 員 鈴木 寿一 官庁営繕部設備課課長補佐 委 員 辻川 孝夫 官庁営繕部保全指導室施設管理官 |
|||
(1) 現状の保全の仕組み
(2) 保全指導行政の経緯
(3) 官庁施設の現状と将来予測
(4) 保全の実施状況
建設省官庁営繕部では、所掌施設(約4,700施設、約1,300万㎡)を対象に表1.1に示す内容の保全実態調査を行っている。この調査では、保全の実施状況を点数化して評価しており、60点以上を概ね良好と判断している。調査結果を図1.2に示すが、施設数では大多数を占める小規模庁舎を中心に、全体としてまだ改善を要する状況であると判断している。
| 保全責任者、設備概要、管理要員
保全業務実施状況 (記録整備、定期点検、測定、衛生、清掃) 保全状況および措置状況 (測定値、劣化状況、衛生・清掃状況) 保全関連経費 (維持管理費、光熱水費、修繕・改修費) |
(5) 施設管理者の現況
全国各地区における保全連絡会議等を通じて行った調査結果(図1.3)から、官庁施設の施設管理者の実態は、「保全業務の経験がほとんどない事務職が、他の業務のかたわら保全を担当し、経験も少ないために、保全に関する知識が十分でなく困っている。」という一般像が浮かび上がっている。
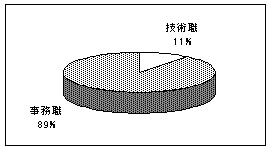 |
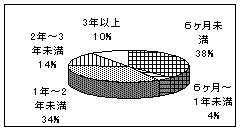 |
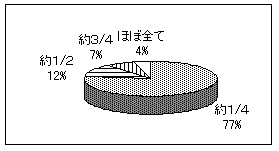 |
(1) 財政動向
現在の我が国の財政状況は、景気回復の諸施策に伴う歳出の増大や大幅な減税により、公債依存度が高まっており、平成12年度末の国と地方自治体をあわせた長期債務残高は645兆円に達すると予想されている。歳出については、経費の一層の合理化・効率化・重点化が図られ、官庁施設の保全に対する予算はますます厳しい状況になるものと考えられる。
(2) 人口動向
我が国の人口は、出生率の低下傾向から、2007年をピークに減少傾向に転ずると予測されているが、一方で平均寿命は延びていることから、かつてない少子・高齢化社会を迎える。あわせて、労働力人口の減少と高齢化が進むため、これまでのような経済成長は望むことができない。したがって、これまでに整備されたストックを有効な資産として21世紀へ引き継ぎ、次世代の経済的負担を低減することが大きな意味を持ってくる。
地球環境問題はいまや全世界に共通の課題であるが、特にCO2等の温室効果ガスは、1997年のCOP3京都議定書において、削減目標が定められた。しかし、その達成は困難視されており、また、図1.4に示すように我が国のCO2排出量における建築関連の割合は高く、建築物の運用段階における削減対策を率先して実行する努力が求められている。
以上の問題点をまとめると次の3点である。
① 官庁施設の膨大なストックと老朽化の進行
② 厳しい財政状況と地球環境問題等の社会的要請
③ 施設管理者は、技術的知識に乏しく、良好な保全に対する動機付けも少ない。
このような問題点と課題に対応する新たな保全システムとして、下図のように「官庁施設のストックマネジメント技術」を構築するものである。
(1) 体系図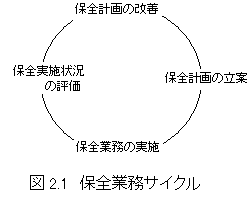
官庁施設の保全に関する課題に対応して、ストックマネジメント技術の体系は、保全計画の立案・実行システム、保全情報システム、保全技術体系から構成される。この体系では、保全に関わる各機関等の役割分担と、継続的な保全のためのサイクルを重視している。
① 各機関等の役割分担は次のとおりである。
・保全指導を行う「国土交通省」
・各省各庁において
・施設(群)の保全に責任を有する「施設保全責任者」
・各施設を直接管理する「施設管理者」
・業務を実施する「外部業者・コンサルタント等」
② 計画的、継続的な保全を行い、かつ状況の変化への対応も可能にするためには、図2.1に示すようなサイクルで保全が行われる必要がある。
官庁施設のストックマネジメント技術の体系図を図2.2に示す。図中、網掛けの部分が今後充実しなければならない業務である。
この体系は、各機関が、計画、実施、評価・改善の各段階でどのような役割を果たすべきかを「保全計画の立案・実行システム」として示し、同時に、そのシステムを円滑に実行するために必要な「保全情報システム」と「保全技術体系」の位置づけを示したものである。
(2) 保全計画の立案・実行システム
保全計画の立案・実行フローは図2.2に示す。
国土交通省は各省庁に対し、次の保全指導を行う。
図2.4 ガイドラインの構成
(1) 既存の現況評価手法
a.必要性
b.評価項目及び評価基準の設定
| 種別 | 重点管理項目 | 評 価 項 目 |
| 安全
|
安全性
|
外壁の剥落防止、漏水防止、
アスベスト、PCB等への対策、耐火、防火、防災 |
| 耐震性 | 耐震診断の実施、耐震改修の実施 | |
| 環境
|
省エネ・省資源
|
省エネ・省資源、廃棄物の削減、
電気使用量、燃料使用量、ガス使用量、水道使用量 |
| 品質
|
室内環境
|
光環境、熱環境、空気環境、衛生環境
情報設備設置環境 |
| バリアフリー
|
建築物の出入口、廊下、スロープ、階段、エレベータ
便所、駐車場、構内通路、サイン |
|
| 利用状況 | 狭隘度、利用度、満足度、アクセス、使いやすさ | |
| コスト | 維持管理費、光熱水費 |
表3.2 重点管理項目チェックシート記入例
(1) 概要
保全計画は、各施設の立地・用途・規模・特殊性等を考慮して、ライフサイクルにおける目標設定、長期的な修繕・改修計画、各年度ごとの点検保守計画を立案する。
①「ライフサイクル(LC)計画」
各施設ごとに設定する施設性能水準とその施設の目標耐用年数を明記し、ライフサイクル的視野に立った計画目標を立案するものである。性能の項目は「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準」及び「官庁施設基本的性能基準(案)」に基づき表3.3に示す項目を設定した。しかし、この各性能についてすべて水準を定め、それに対する施設の状況を把握することは多くの手間を必要とするところから、保全に際して重点的に考慮すべき項目として、性能項目に、利用状況、コスト等を加えた重点管理項目を設定し、それを基にLC計画を立案することとした。
表3.3 施設の性能項目
| 1社会性
|
1-1 地域性 |
| 1-2 景観性 | |
| 2 環境保全性
|
2-1 環境負荷低減性 |
| 2-2 周辺環境配慮性 | |
| 3 安全性
|
3-1 防災性 |
| 3-2 機能維持性 | |
| 3-3 防犯性 | |
| 4 機能性
|
4-1 利便性 |
| 4-2 バリアフリー | |
| 4-3 室内環境性 | |
| 4-4 情報化対応性 | |
| 5 経済性
|
5-1 耐用性 |
| 5-2 保全性 |
②「長期保全計画」
「LC計画」に基づき、各施設の20年間の修繕・改修・更新計画を立案するものである。
③「年度保全計画」
「長期保全計画」に基づき、年度ごとの維持管理、点検保守計画を立案するものである。保全計画書書式イメージを表3.4に示す。
(2) 保全計画作成指針
以上の計画の具体的な立案・作成方法を示したものとして保全計画作成指針(案)を作成し、合同庁舎等について保全計画立案の試行を行った。試行は各庁舎の施設管理者に地方建設局の営繕職員が協力して行ったが、保全計画を作成するためのデータの整理や修繕・更新時期の設定には、建築及び建築設備に関する技術的背景のあるインハウス技術者の関与が欠かせないことが明らかになった。
保全計画書 書式イメージ
(3) 簡便な長期保全計画作成手法の提案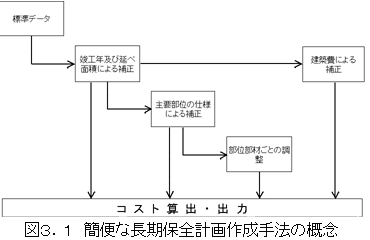
膨大なストックである官庁施設の長期保全計画を多くの施設について早急に整備し、全体像を把握することが今後の保全の適正化に重要なデータとなる。したがって、より簡便な手法を用意し、膨大なデータを早急に整理する必要がある。
優先度P= 評価点Q + 評価点R × 係数K
| 施設保全マニュアル | A庁舎保全実施マニュアル |
| 第1章「保全業務」
施設管理者が実施段階で行う保全業務について解説 施設概要の把握/保全実施計画の立案/保全業務の委託/保全業務の監督・検査/保全業務の記録 |
施設管理者は、左記に基づき、保全を実施する。 |
| 第2章「保全の手引き作成要領」
各施設について作成する「保全の手引き」について解説 |
左記に基づき「A庁舎保全の手引き」を作成する。 |
| 第3章「保全台帳作成要領」
各施設について作成する「保全台帳」について解説 |
左記要領に基づき「A庁舎保全台帳」を作成する。 |
(1) 保全業務委託のあり方
| 問題点 | 対応策 | 検討課題 |
| 現行制度の厳格な運
用による単年度契約 |
複数年度にわたる契約や数年間の随意契約の実施 | 会計法等の弾力的運用の検討
|
| 参加資格に制限をつ
けない一般競争入札
|
業者の技術力を参加資格要件に取り入れた競争入札の実施 | 競争入札における資格要件の設定の検討 |
| 業者の技術力評価の実施 | 業者の技術力評価手法の検討 | |
| 要求される性能が曖
昧な仕様による契約 と不十分な履行評価 |
要求性能を明確にした仕様書の確立 | 現行仕様書の見直し
|
| 確実な履行評価の実施 | 履行評価手法の検討 | |
| コスト縮減における
長期的視点の欠如 |
ライフサイクルコストなど長期的視点を考慮した業務委託の実施 | 施設管理マネジメント業務の検討
|
(2) 施設管理マネジメント業務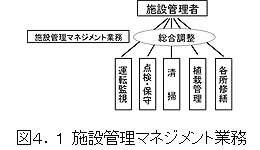
(1)保全業務評価の目的
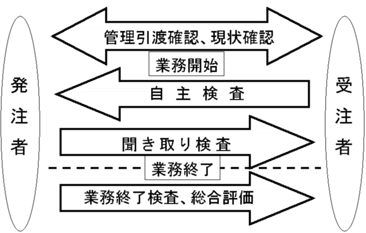
図4.2 業務評価フロー
保全情報システムは、情報を取り扱う立場から設定した情報カテゴリーに、必要な業務支援システムとデータベースのネットワークを対応させることにより、図5.1に示すように整理できる。
(1)システム形式
保全情報システムを構成するネットワークは、個別施設のコンピュータがそれぞれネットワークにつながって機能し、保全情報センターによってシステムの開発、運用、アプリケーションの更新等を行う統括型が想定される。図5.2にシステムの構成イメージを示す。
保全情報センターは、システム全体の運用・管理を行うだけでなく、施設運営上の指標となる、設備機器の更新周期、光熱水量、LCCO2などのベンチマークを提供する機能や、ネットワークにつながっている個々のコンピュータに組み込まれているアプリケーションのバージョンアップの対応を一括して行う、アプリケーションサービスプロバイダー的な機能を持つ。
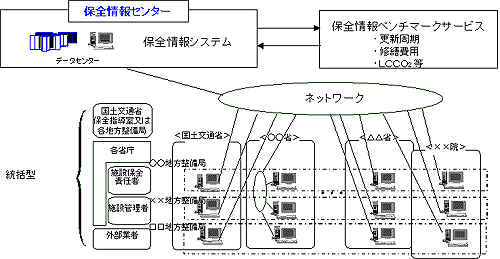
(2)業務支援システム
官庁施設の保全に関わる者(組織)の業務分析を行い、保全業務の実施を支援する業務支援システムを整理した。保全情報システムに含まれる業務支援システムを、表5.1に示す。各業務支援システムは、図5.3に示すように、複数の関係者にまたがって利用され、利用者によって、保全指導支援情報システムと施設管理者支援情報システムに分類する。
これらの業務支援システムとデータベースが、インターネットを含む省庁間ネットワークによってつながり、保全情報システムを構成することになる。
表5.1 業務支援システム
| 業務支援
システム |
Ⅰ 保全計画策定支援システム | Ⅱ 維持管理支援システム | Ⅲ 保全状況評価支援システム | Ⅳ 共通システム | Ⅴ 長期修繕需要予測支援システム |
| 主な機能 | ・LC計画/長期保全計画策定支援機能
・修繕優先度判定機能 |
・スケジューリング機能
・維持管理実施記録支援機能
|
・建物状況評価機能
・保全業務評価機能
|
・建物台帳ファイル管理機能
・定型グラフ・帳票作成支援システム |
・施設群の長期修繕計画策定支援機能
|
保全情報システムが、官庁施設の保全に携わる様々な立場から利用されるシステムであることから、保全計画の立案・実行システムとも対応させて各機関(担当者)の扱う情報を各々の立場から4つに分け、図5.1に示す情報カテゴリーとして設定した。 各情報カテゴリーごとに業務分析を行い、業務支援システムの検討に反映させた。
5.4 データベース
(1) データベースの位置づけ
データベースを整備するに当たって、データの入出力を誰が行うか、どこからデータを取り入れるかを検討するために、データベースに含むべきデータ項目ごとに次の項目との関係を整理した。対応表を表5.2に示す。
・保全関連業務
・データの登録・更新、入力代行及び参照をする者
・原データの所在(データの入手元)
データ項目には、1次データを加工して得られる情報や、定期的な調査によって得られるものがある。今後は、その算出方法及びデータ収集のしくみについて、建設省で実施している官庁建物実態調査及び保全実態調査の拡充を含めて検討する必要がある。
(2) データの入力
今後新築される施設については、施設整備を担当する国土交通省が、施設管理に必要なデータを整備して、竣工時に施設管理者に引き渡す必要がある。一方、膨大なストックとなっている既存施設については、大規模改修工事を実施した際に、順次必要なデータを整備していく。また、個別の施設で発生する保全データは、日常業務を遂行する中で無理なく自動的にデータが蓄積される仕組みを取り入れ、データ入力の省力化を図る必要がある。
表5.2 データ項目の整理表
個別施設の施設管理者が利用する情報システムを、施設管理支援情報システムとして位置づけ、情報システムの仕様書を作成した。
施設管理支援情報システムは、保全計画の作成を支援する機能、日常の維持管理業務を支援する機能、施設台帳を管理する機能等を持つ。また、主な利用者は、個別施設の施設管理者と保全業務を受託した業者である。(図5.3参照) 仕様書では、システム構成、支援システムの機能、操作メニュー、入出力項目等を規定した。
保全計画の立案・実行システムに対応して、保全の各段階(計画、実施、評価・改善)において必要となる技術・手法を体系的に整理した。(表6.1)体系化にあたっては、上記の各段階をさらに分類し、それぞれの技術・手法の利用者との関係を示した。
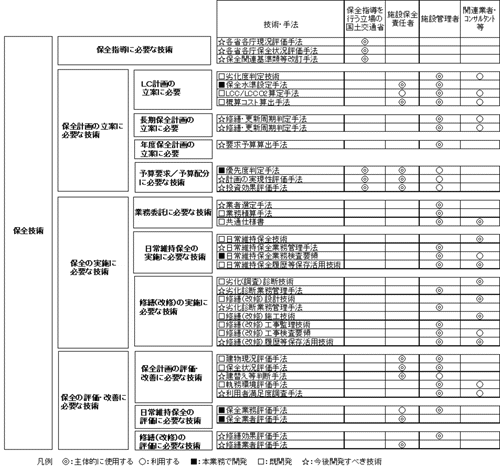
既存の技術についてみると、保全業務の実施のための技術は必要性も高く、よく整備されているが、保全計画の立案に必要な技術や、評価・改善に必要な技術は一部を除き、ほとんど整備されていない状況である。
(1) 目的及び検討対象
官庁施設においては、機器の点検・保守、清掃などの頻度や点検方法等は「建築保全業務共通仕様書(保全共仕)」に示されているが、施設の重要性や部屋の利用状況等に関係なく規定されている。このため、本検討では、施設の重要度、部屋の利用状況等に基づいた複数の水準を設定し、選択を可能とすることにより、限られた予算を適切に配分し、コスト上昇を抑えつつ保全レベルの底上げを図るため保全水準の設定の検討を行った。検討対象は、「運転・監視及び点検・保守」と「清掃」とした。
(2)運転・監視及び点検・保守
保全水準の設定にあたっては、個々の施設の重要度や部位・機器の故障の影響度等に応じて、各部位・機器別の「保全方式」を導入することとした。 保全方式の選択の流れは次による。
ステップ1:施設の重要度(Ⅰ~Ⅳ)を設定
ステップ2:部位・機器の劣化・故障時の被害損失の度合い(A~D)を評価
ステップ3:重要度の設定、被害損失の度合いの評価から各部位・機器をa~cに分類
ステップ4:コストや労力、劣化・故障の発見の容易性を判断基準に保全方式を選択
表6.2 保全方式の設定
| 保全方式 | 略称 | 具体例 | |
|
方式1 |
常時監視又は定期点検を行い、
不具合を未然に防止する。 |
「定期点検・未然防止」 |
24時間稼動の
設備機器 |
|
方式2 |
常時監視又は定期点検を行い、
不具合の発見を早期に行う。 |
「定期点検・早期発見」 |
受変電設備、屋根
防水層、外壁タイル |
|
方式3 |
不具合に対する迅速な対処体制
を整えることによって、点検を 省略できるもの。 |
「点検省略・迅速対処」 |
照明器具
建具類 |
|
方式4 |
不具合が生じても、
迅速な対処を要しないもの。 |
「点検省略・適宜対処」 |
人目につかない
外壁の汚損 |
(3) 清掃
表6.3清掃仕様の設定例
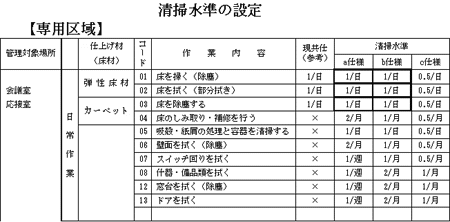
| 室の利用頻度 | |||||||||
| 窓口官署 | 窓口官署以外 | ||||||||
| A | B | C | A | B | C | ||||
| 室の重要度
|
共用区域 |
玄関ホール | Ⅰ | a | a | b | b | b | c |
| 廊下 | Ⅰ | a | a | b | b | b | c | ||
| 階段 | Ⅱ | a | b | b | b | c | c | ||
| 便所、洗面所 | Ⅰ | a | a | b | b | b | c | ||
| 駐車場、車路 | Ⅲ | b | b | c | c | c | c | ||
| 屋上 | Ⅳ | b | c | c | c | c | c | ||
(1) 目的
良好な保全を行うことにより、損失や危険の回避によるメリット、機器の効率の確保・延命によるメリットが考えられるが、保全を良好な方向に導くためには、保全の費用対効果を定量的に評価することが効果があるため、定量化の試みを行った。
(2) 定量評価の結果
今回試みたのは以下の3点である。
①機器の故障による執務能率低下の評価
機器の故障を想定し、それによる不便・不都合などをCVM(仮想市場法)を基本としたアンケート調査により行った。調査対象は、建設省職員と名古屋市内の設計事務所職員100名程度ずつとし、機器の故障による業務能率の低下の度合いで評価した。調査結果は、停電によるパソコン等の使用が不可能になった場合の業務低下率が75%、夏場の空調機器の故障の影響が48%という数字で表すことができた。
②機器の運転効率低下によるエネルギーロスの評価
保守状態が悪いために機器の運転効率が落ちた場合の想定では、空調機器の搬送動力のロスを対象とした。学術論文によるデータを用いると、一般的な庁舎で10年間で90.5kWh/㎡のエネルギーロスとなった。これは3,000㎡級の施設で500万円弱の電気料金に相当する。
③機器の延命効果
機器の寿命に関するデータは種々発表されているが、実際は使用状況により大きくばらついている。標準的とされている寿命に対し、しっかりした管理により寿命が30~50%延びた場合の効果を3,000㎡級調査をモデルに試算した。庁舎の供用期間を65年としてその期間トータルの更新及び修繕費用の低減率を求めると、13%という数字が得られた。
(2) 今後の検討課題