-
 1.外航海運とは
1.外航海運とは
-
外国との間の航海を「外航」といい、外航によって行われる輸送すなわち外航海運は、その対象により外航貨物輸送と外航旅客輸送に区分される。また、そのそれぞれは公表された日程表に従って船舶が運航される定期輸送とそれ以外の不定期輸送に分けられる。
我が国をめぐる外航貨物定期輸送においては、主に食料品、機械類といった貨物が輸送されており、1997年には、我が国発着貨物のうちの約10%に当たる8,690万トンが輸送されている。また、その91.5%の貨物がコンテナ化されている。コンテナ化が進展する以前は、その形状に応じて、大小の貨物が個々に外洋等を航海する本船に積み卸しされ、航海中に荷崩れを起こさないような本船への積み付け等特殊な技術も必要で、多くの時間と人手をかけて荷役作業が行われていたほか、貨物の管理にも労力を要していたが、コンテナ化とそのコンピュータ管理により、荷役時間が飛躍的に短縮されるとともに、輸送サービスの標準化や均質化が生じ、価格面における競争が激化した。こうした状況から特に、外航定期貨物輸送の分野においては、アジア・共産圏諸国の多くの海運企業が低コストを武器に市場に参入し、世界規模で激しい競争が行われるようになった。
我が国をめぐる外航貨物定期輸送のうちその大部分を占める定期コンテナ輸送における主要な航路としては、太平洋を経由してアジア・日本と北米を結ぶ北米航路、マラッカ・シンガポール海峡、スエズ運河、地中海を経由してアジア・日本とヨーロッパ間を結ぶ欧州航路などがある(図表1-1-1)が、荷主のニーズに応じて一週間に一度本船がそれぞれの港に寄港するというウィークリーサービスを実施するため、各社はそれぞれの航路に数隻の船舶を投入するのが一般的である(往復の航海に北米航路で約35〜42日、欧州航路で約56〜63日を要するのが一般的である。)。
また、外航定期コンテナ輸送に用いられる船舶は、5,000総トンから80,000総トンまで航海する航路等によって様々であり、中でも近年は60,000総トンを超える オーバーパナマックス クラスの大型コンテナ船が投入されるなど、大型化が進んでいる(図表1-1-2)。
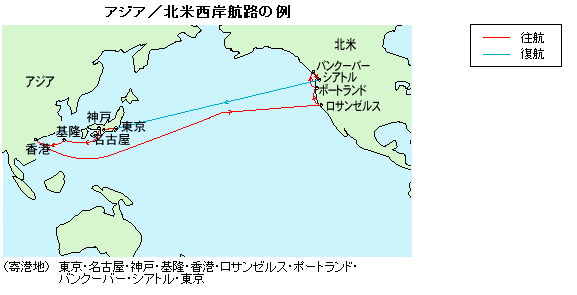 |
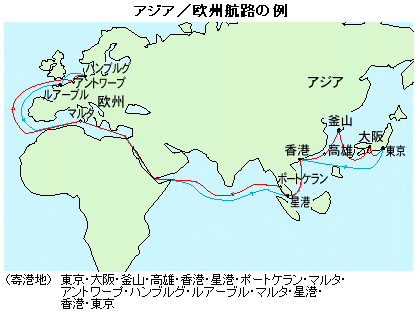 |
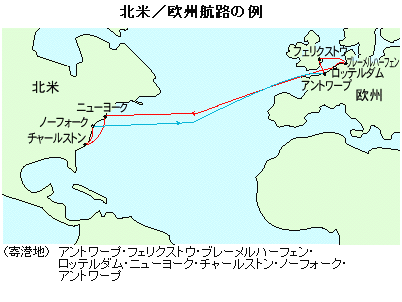 |
図表1-1-2 大型化するコンテナ船の代表船型の推移
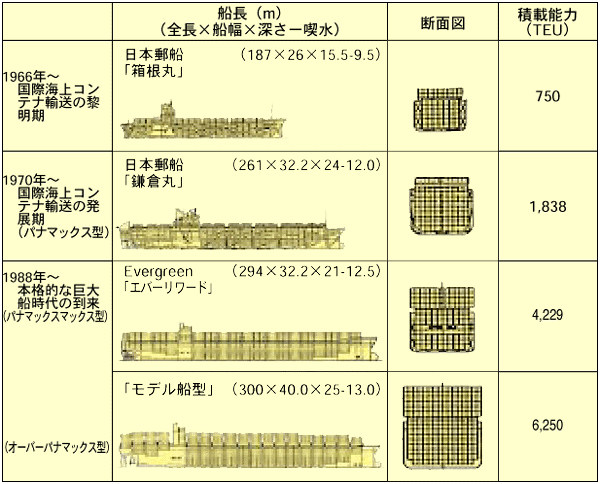
-
 一方、外航貨物不定期輸送は、主にLNG(液化天然ガス)、原油等のエネルギー資源、鉄鉱石等の原材料、小麦等の乾貨物が、個々の荷主の需要に応じて、主に、海外から日本向けに輸送されており、1997年には、我が国発着貨物のうち約90%の7億9,095万トンが輸送されている。
一方、外航貨物不定期輸送は、主にLNG(液化天然ガス)、原油等のエネルギー資源、鉄鉱石等の原材料、小麦等の乾貨物が、個々の荷主の需要に応じて、主に、海外から日本向けに輸送されており、1997年には、我が国発着貨物のうち約90%の7億9,095万トンが輸送されている。
不定期輸送に用いられる船舶は、輸送される貨物に応じてLNG船、オイルタンカー、自動車専用船といった専用船が用いられており、その大きさはハンディーサイズと呼ばれる約2〜4万重量トンクラスのものからVLCC(Very Large Crude Carrier)、ULCC(Ultra Large Crude Carrier)と呼ばれるそれぞれ20万重量トン超、30万重量トン超クラスのものまで様々である。また、鉄鉱石、小麦等のばら積み貨物は、そのままバルクキャリアと呼ばれるばら積み貨物専用船を用いて輸送されている。
-
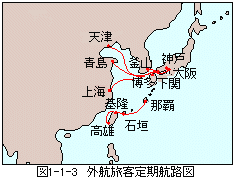 我が国をめぐる外航旅客定期輸送は、1998年5月現在、韓国、中国及び台湾の近隣国との間で、10社により7航路が運航されている(図表1-1-3)。1997年には約30万人が利用し、そのうち日本人乗客数は、前年に比べ17.4%増加し、約17万人となっている。
我が国をめぐる外航旅客定期輸送は、1998年5月現在、韓国、中国及び台湾の近隣国との間で、10社により7航路が運航されている(図表1-1-3)。1997年には約30万人が利用し、そのうち日本人乗客数は、前年に比べ17.4%増加し、約17万人となっている。
- 外航旅客不定期輸送としては、目的地への移動に加え客船による航海自体を楽しむことを目的とするクルーズがある。1998年5月現在我が国海運企業3社が運航する外航クルーズ船は6隻あり、1泊以上の外航クルーズに参加した日本人乗客数は、1997年には約8万人と前年に比べ11.5%増加している。
- 外航旅客不定期輸送としては、目的地への移動に加え客船による航海自体を楽しむことを目的とするクルーズがある。1998年5月現在我が国海運企業3社が運航する外航クルーズ船は6隻あり、1泊以上の外航クルーズに参加した日本人乗客数は、1997年には約8万人と前年に比べ11.5%増加している。
-
 2.外航海運の果たす役割
2.外航海運の果たす役割
-
我が国は、経済活動を維持していく上で必要なエネルギー資源や食糧の多くを海外に依存している(図表1-1-4)。また、我が国が基本的に原材料を輸入し、製品を諸外国に輸出するという貿易構造をもっていることを考えると、これらの物資輸送の99.8%を担う外航海運が、我が国の国民生活・経済活動を支える上で極めて重要な役割を担っていることがわかる。
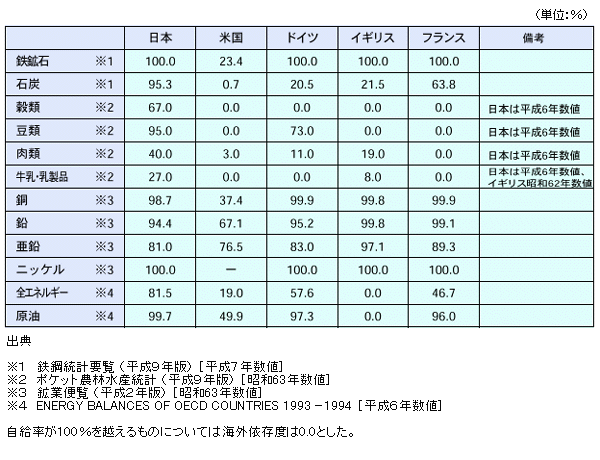
 最近では、アジア地域における工業化の進展、我が国製造業の海外現地生産により近隣アジア諸国との製品貿易もさかんになっており、輸出において、一般機械、電気機械の機械類がほぼ半分を占める一方、輸入では、事務用機械、テレビやVTR等の製品の輸入が増加するなど、地域別、品目別の貿易構造にも大きな変化が見られる。
最近では、アジア地域における工業化の進展、我が国製造業の海外現地生産により近隣アジア諸国との製品貿易もさかんになっており、輸出において、一般機械、電気機械の機械類がほぼ半分を占める一方、輸入では、事務用機械、テレビやVTR等の製品の輸入が増加するなど、地域別、品目別の貿易構造にも大きな変化が見られる。こうした輸出入構造の変化や我が国製造業の海外展開に応えてきたのも、我が国海運企業を含む外航海運であり、今後とも外航海運が、低廉で、信頼性が高く、質の高いサービスを提供することにより、我が国経済の発展に重要な役割を担っていくものと考えられる。
また、先般のインドネシアの政情危機における現地在留邦人の救出に際して、我が国外航海運企業は、必要な場合には即座に邦人救出のための輸送協力を行うことができるよう万全の準備を整えるなど、邦人の保護について全面的な協力姿勢で臨んだ。このことは、我が国外航海運企業の一つの重要な意義を再認識させる出来事であったといえる。