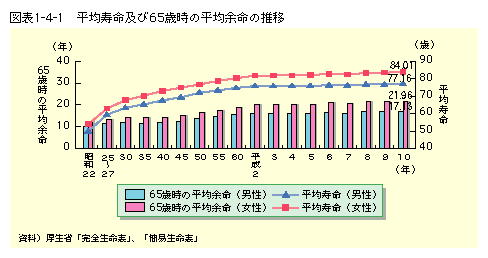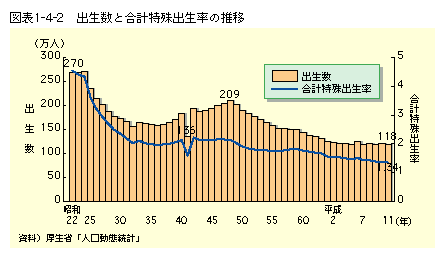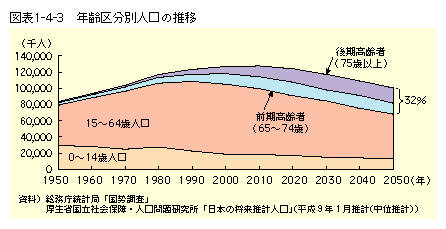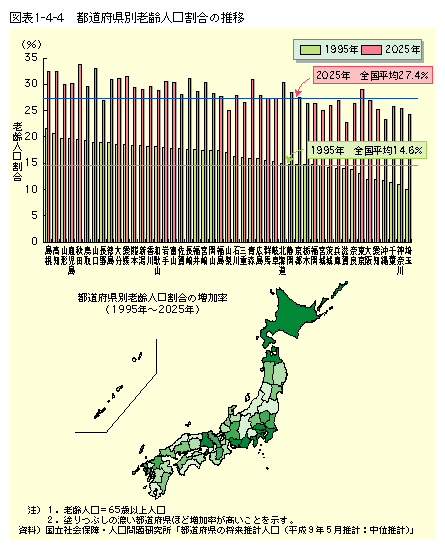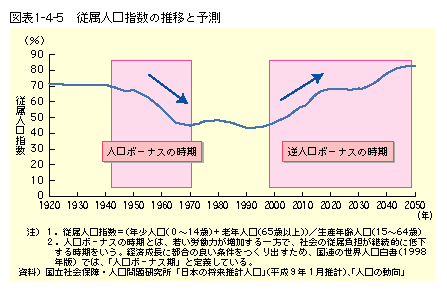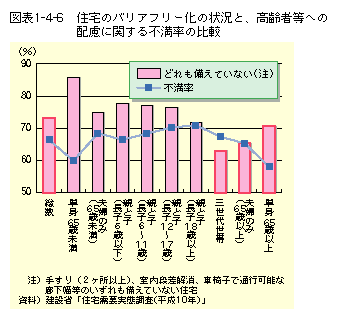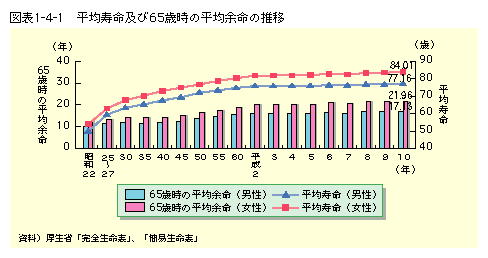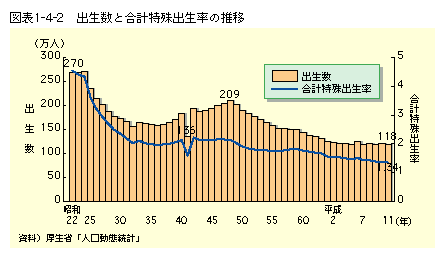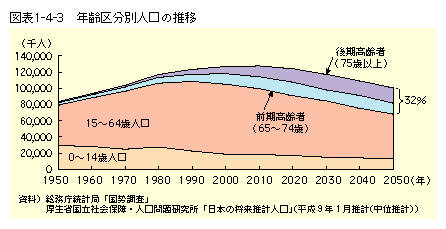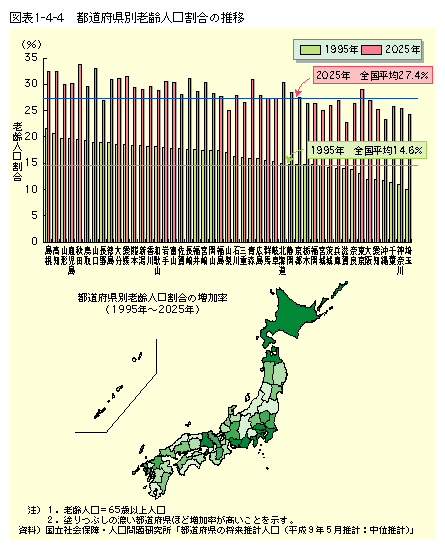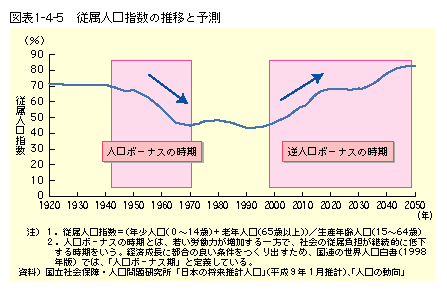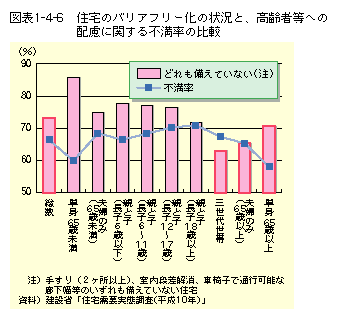(少子高齢社会への対応)
我が国は、大阪万博の開かれた昭和45年(1970年)、65歳以上の高齢人口の割合が7%を超え、「高齢化社会」に入った。それから四半世紀後の平成7年(1995年)には14%を超えた。高齢化社会へ向かうスピードは他の西欧諸国と比較して2倍も早く、国民の多くが長寿を享受できるようになるに伴い、長くなった高齢期を健やかに過ごせるための住宅・社会資本整備を進めることが課題となってきた。
(1)高齢社会の進展の様子
我が国の高齢化を促進する要因としての平均寿命は、一貫して伸びており、戦後直後の昭和22年には男性が50.06歳、女性が53.96歳であったのに対し、平成10年には男性が77.16歳、女性が84.01歳と長くなってきている(図表1-4-1)。これに対し、出生の状況を合計特殊出生率で見ると、昭和50年に2.00を下回ったのち、平成5年に1.5を割り、平成11年には1.34であった(図表1-4-2)。
これに伴い、我が国の将来の総人口構成は、大きく変化する。国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成9年)」の中位推計によると、65歳から74歳の前期高齢者人口は平成28年(2016年)にピークを迎え、その後減少していくが、75歳以上の後期高齢者人口はその後も増え続ける(図表1-4-3)。その結果、平成62年(2050年)には15〜64歳の生産年齢人口は3000万人以上減少し、65歳以上は約3200万人(総人口の32%)になると予測される。
地域別にみると、高齢化の進行は全国均等の動きではないことが分かる(図表1-4-4)。平成7年(1995年)時点での65歳以上の老齢人口割合についても最高の島根県の21.7%から最低の埼玉県の10.1%まで差異があり、平均14.6%である。これを平成37年(2025年)時点の老齢人口割合(平均27.4%)と比べると、老齢人口割合の平成7年から平成37年までの30年間での伸び率は、平均88%であるが、最高の埼玉県が140%、最低の長野県が42%と、差が大きく、高齢化の進展スピードは地域により異なることが分かる。また、老齢人口割合の伸び率の上位は、埼玉県(140%)、神奈川県(132%)、千葉県(128%)、大阪府(126%)、東京都(124%)、愛知県(113%)と、大都市圏に集まっており、高度成長期の生産年齢人口の移動による地域ごとの年齢構成のゆがみが、今後も影響を及ぼしてくることが分かる。
(2)「新人口ボーナス」の活用
昨年の「平成11年版建設白書 -人口の動きから見た住宅・社会資本-」では、戦後の大都市圏と地方圏の人口の動きから住宅・社会資本や国土構造の課題を分析した。要約すれば、戦後20年間の生産年齢人口のシェア拡大の時期(人口ボーナス期)(図表1-4-5)に大都市圏に若年人口移動が集中し、工業化による高度成長を支えたことから、住宅・社会資本はこうした人口と経済の動きに合わせて整備されたため、高度経済成長を支える一方で人口配置や土地利用にもゆがみをもたらし、過疎・過密や住宅・社会資本の総合的な機能の弱さなどの課題を残し、21世紀に持ち越すことになった。
さらに、今後急速な少子高齢化の進行の下で、地域別に見た人口減少社会の趨勢として、1)非都市圏における急速な人口減少(広大なる過疎化)、2)地方中枢都市の都市圏人口の増加等により長期的には東京一極集中から複数の極への分散傾向、3)三大都市圏について大幅な人口減少の中での高齢者の集中(静かなる集中)、を予測した。その上で、今後の住宅・社会資本の役割として、健康で自立し経験知を有する元気な高齢者の社会活動の可能性に注目し、これを「新人口ボーナス」として活用できる社会システムへの転換や住宅・社会資本整備の対応方向を提示した。今後、「新人口ボーナス」ともいえる高齢者を含めた貴重な人的資源を活かして、活力・創造力に満ちた安全で環境と共生した美しい国土づくりを行う必要がある。
(3)建設省の取組み
高齢化の進行は労働力人口や雇用慣行の動向、貯蓄の動向、社会保障に係る負担等我が国の経済社会に少なからずの影響を与えるものと考えられるばかりでなく、住宅・社会資本整備においても、エンドユーザーである国民の年齢構成の変化により、必要とされる社会資本の内容も大きな変化を迎える。
建設省においては、「生活福祉空間づくり大綱(平成6年 建設省)」により、「建設行政の視点を、高齢者、障害者はもとより、子供、女性等を含めた幅広いものへと転換し、多様な個人の幸福の追求という観点を住宅・社会資本整備の基本に据えた「厚み」と「幅」のある施策の展開を図る。」とされて以来、住宅・社会資本整備を進める上で少子高齢社会に対応することはその目標の一つとして内在化されてきている。近年においては、街のバリアフリー化を促進するために、特に鉄道駅と周辺道路、駅前広場等については「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(交通バリアフリー法)」の活用や、高齢者等が自動車交通に頼らない「歩いて暮らせる」コンパクトな街づくりを進めている。
・少子高齢社会に対応した「安心居住システム」の確立
住宅は、個人にとって、健康・生活の基盤であり、人生の大部分を過ごすという意味で極めて重要な、そして家族と暮らし、家族を育む、かけがえのない生活空間であり、ゆとりある住宅に安心して住むことが、生活の豊かさを実感する上での重要な要素となっている。
一方、少子高齢化の進展を受けて、老後の住まい方等居住に関する新たな不安をもたらしている側面がある(図表1-4-6)。今後の取組みに当たっては、高齢化の負の側面を必要以上に大きく捉え、弱者という視点のみから政策を講じるのではなく、社会活動へのアクセシビリティが高いまちなかでの活気ある居住、豊かな自然環境に囲まれた田園地域での悠々自適の居住やマルチハビテーション、子供、孫世帯との近居、同居によるやすらぎ居住など、高齢者の持つ様々な居住ニーズに的確に対応し、高齢者が末永く元気に社会活動を営むことができる環境を整備するという視点が重要である。
このため、高齢者が現に居住している持家資産を活用して、より自由な住替えを可能とするとともに、きめ細やかなバリアフリー改修相談体制の整備、バリアフリー化された良質な高齢者対応型民間賃貸住宅ストックの形成の促進を図ることにより、高齢者が安心、快適で自立して生活できる居住環境を整備していく必要がある。さらに、高齢者の自助努力、高齢社会の進展をビジネス・チャンスとして捉える民間活力を十分に活かしつつ、これらの取組みを市場を通じて実現するとともに、市場を通じた対応だけでは適切な居住を確保できない者に対しては、その者の身体状況に応じきめ細かく公共賃貸住宅の供給やサービスの提供を行っていくことが必要である。
また、少子化への対応としては、平成11年12月に策定された「少子化対策推進基本方針(少子化対策推進関係閣僚会議決定)」及び「新エンゼルプラン(大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治6大臣合意)」を踏まえ、仕事と子育ての両立に係る負担感や子育ての負担感を緩和・除去し、安心して子育てができるような環境整備を積極的に推進していくことが求められている。このため、特に都市居住の面からも、都心部における賃貸住宅供給により、職住近接のための都心居住、地域に必要な保育所等と賃貸住宅の併設を推進していくこと等を通じて、家庭や子育てに夢と希望が持てる社会の実現を図っていく必要がある。