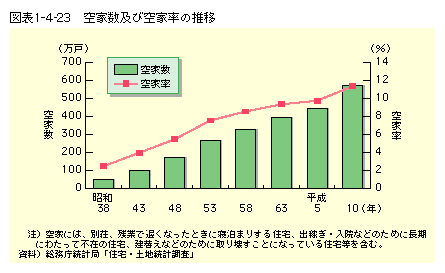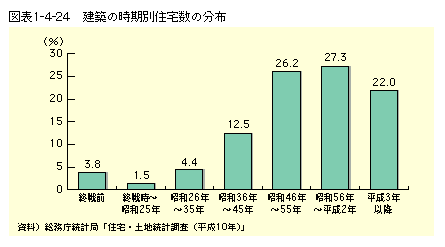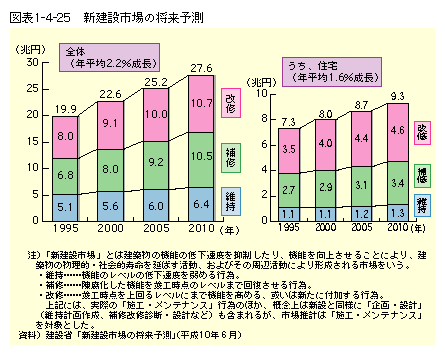(住宅リフォーム市場の推移)
我が国の住宅ストックに着目した「リフォーム」市場の将来推計を分析してみよう。
我が国の住宅ストックは、「住宅・土地統計調査(総務庁 平成10年)」によると、5,025万戸であり、そのうち居住世帯のある住宅(通常人が住んでいる住宅)の数は4,392万戸あり、それ以外の大半は空家(別荘、出稼ぎ・入院などのために長期にわたって不在の住宅等を含む。)となっている。住宅ストックに対する空家率は過去から一貫して増加しており、平成10年には約11%となっている(図表1-4-23)。
これまでの住宅取得は、「住宅双六」といわれ、借家からマンション、そして最終的には新市街地における戸建住宅の取得を目指すのが一般的であった。こうした住宅取得は、地価の上昇が続く中で、土地が非常に有利性の高い資産であったことから、必要な居住サービスを得るための住宅確保という観点よりも、土地取得に強い関心を置いたものであった。このため、上物としての住宅を重要な資産と考え長期的な視野に立ってより高い質を求めたり、適切な維持管理によりその質を維持・向上させることによって、自己の資産価値を形成・増進する、そしてそれを住替えの際に活用するというインセンティブに乏しく、既存の住宅の老朽化が進行するとともに、有効に活用するための中古住宅市場、賃貸住宅市場、リフォーム市場が未発達であった。
今後の住宅需要は、人口減少社会となると推計されることや、世帯数については高齢者世帯は増加するものの、それ以外の世帯は減少すると推計され、また人口移動も定住化の傾向を迎えることから、既に過去における住宅ストックの蓄積等に鑑みれば、新規住宅建設に対する需要は次第に減少してくるものと考えられる。
ただし、現存する住宅ストックは、昭和55年以前の高度成長期に住宅戸数の不足を補うことを重視して建てられたものが多く(図表1-4-24)、これらは老朽化が進むとともに、床面積等が最低居住水準や誘導居住水準を満たしていないものが多く、生活水準の向上に対応できず、陳腐化が進んでいるものも少なくない。(「21世紀の豊かな生活を支える住宅・宅地政策について」(平成12年6月 住宅宅地審議会答申))
これら高度成長期のストックの適切な更新を図る一方で、循環型社会への移行を目指し、限りある資源を有効に活用していくためにも、新しい住宅へのニーズに対応し、住宅を壊して建て直すことを繰り返すのではなく、耐久性の高い住宅ストックの形成を促進するとともに、適切な診断を踏まえ、今あるストックに必要な維持修繕を加えることにより良質な住宅ストックを維持管理し、長く大切に使っていく、という視点が必要となってくる。
「リフォーム」市場(
注)(住宅・非住宅計、ともに政府・民間を含む)の将来規模を「新建設市場の将来予測(平成10年 建設省)」でみると、「リフォーム」市場の規模は、平成7年(1995年)現在が19.9兆円であるのに対し、平成22年(2010年)には27.6兆円と、約1.4倍に拡大することが予想されている(図表1-4-25)。
特に、住宅についてみると、平成7年(1995年)現在が7.3兆円であるのに対し、平成22年(2010年)には9.3兆円と、約1.3倍に拡大すると推計される。また、「改修」市場の内容としては、間取りの変更等によるスペースの有効活用、外装・内装のリフレッシュ等の住宅イメージの向上、台所等の快適な水回り環境・空気環境等の実現、バリアフリー対応、マルチメディア対応、セキュリティーの充実、省エネルギー化対応等、個々の規模は必ずしも大きくないものの、様々な分野にわたることが予測される。
今後は、これらの新規分野であるリフォームを実施していくための環境整備を行い、住宅ストックを有効に活用することで、循環型社会にも対応した質の高い住まいづくりを推進することが必要となってくる。
(注) 「新建設市場の将来予測」においては、「維持」「補修」「改修」市場の動向について予測しており、これら3つを総称して「新建設市場」としているため、必ずしも「リフォーム」とは同義ではない。
なお、これらの推計は、建築物所有者等に対して実施したアンケート調査「リフォーム・リニューアル等に関する実態調査」の結果に基づいて算出している(現在市場規模の予測及び将来予測も基本的に同様である)。