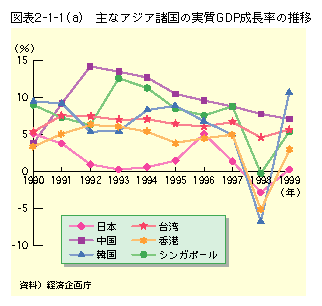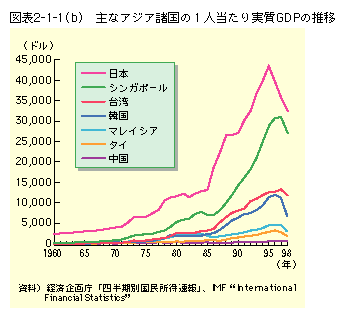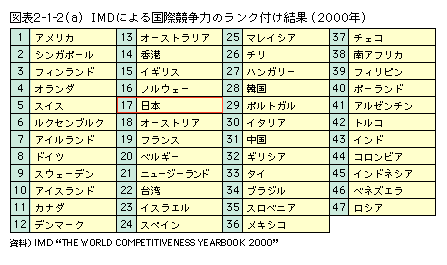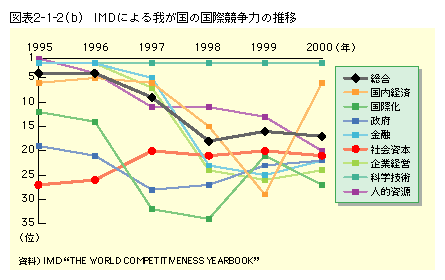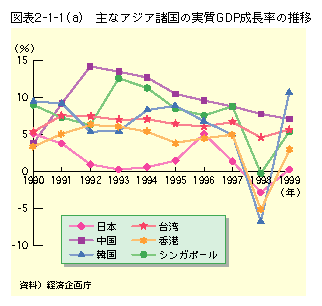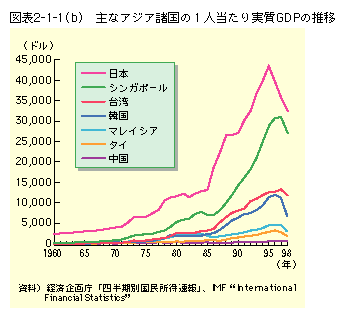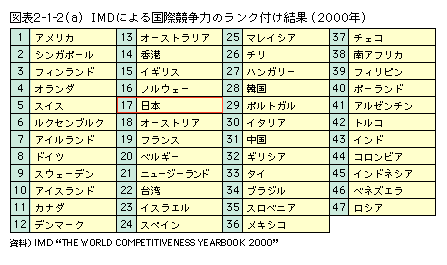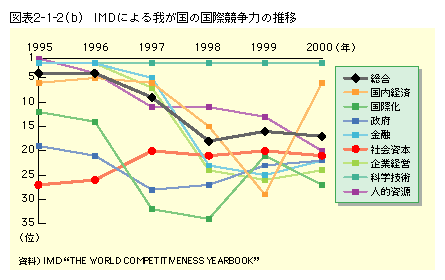(国際競争力低下の現状)
我が国は戦後の高度経済成長を通じ、高品質なモノを大量に生産する技術を有した輸出中心の工業国として国際競争力を確保した。しかし、バブルの崩壊を契機とした景気の低迷に加え、国際環境の変化を受け、我が国の国際競争力は低下を余儀なくされている。特に、労働コスト等の安いアジア諸国の工業化の成功によって、かつての我が国の輸出型工業国としての優位性は失われつつある。近年の国内総生産(GDP)の伸び率を比較すると、アジア諸国が着実に成長を遂げている一方で我が国は伸び悩んでおり(図表2-1-1(a))、1人当たりGDPでもシンガポールに追いつかれた状況となっている(図表2-1-1(b))。
国際競争力を数量的に示すことは「競争力」を測る指標の選び方で数値が大きく変わるため困難な作業であるが、よく知られている一例として、欧州有数のビジネススクールであるIMD(国際経営開発研究所)が、「世界市場の中で競争相手より多くの富を生み出す能力」を「競争力」と定義し、毎年国別の競争力を順位付けし発表している。経済統計などを基に、企業の競争力を維持する環境をどれだけ各国が提供できるかという視点から評価しているものであり、当事国の企業幹部等からのアンケート調査といった主観的な要素も多く含まれていることや、どの項目に重点を置いて評価をするかにより結果も異なってくることから一喜一憂すべきものではないが、どのような分野を改善していく必要があるのか検討する際の一資料となり得るものである。2000年版の報告によると、47ヶ国中我が国は17位となっており、1990年代前半では上位にあったことと比べると大きく低迷している状況にある(図表2-1-2(a)、(b))。
低迷の要因は様々であるが、その背景にあるのは従来の手法では国際環境の変化には対応し得ないということであり、特に現在競争力が優位にある国では見られるが我が国には不足している「海外の資本、人材、技術、さらには交流人口(観光客等)を呼び込む魅力」を高めるという視点が重要になる。産業面に限らず生活面を含め「魅力的な国」を創り上げていくことが、今後人口減少を経験していく我が国の活力創出のための一つの方向となり得るものであり、国土や社会資本においてもその方向に沿った整備・活用が求められる。