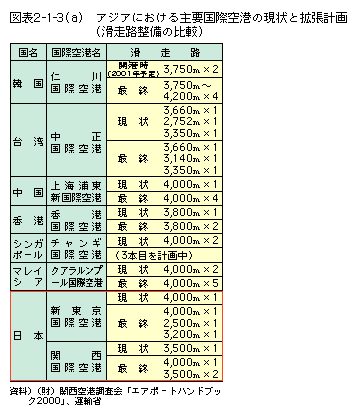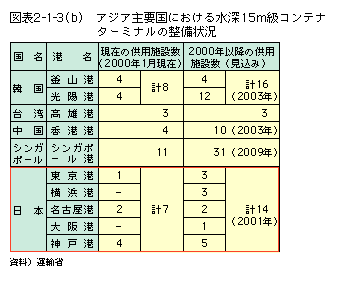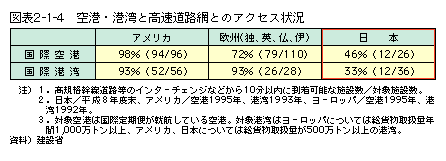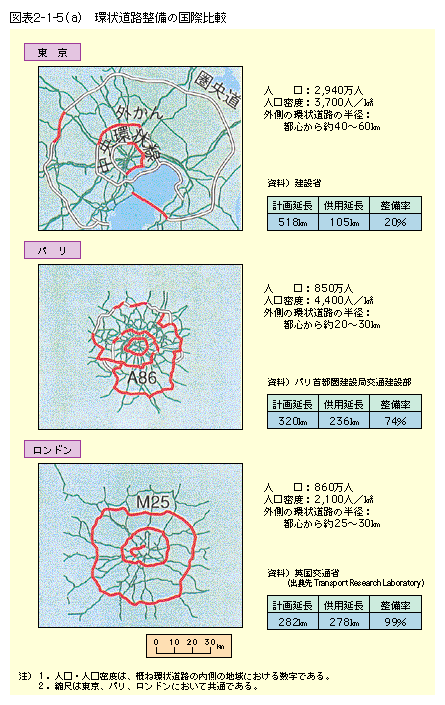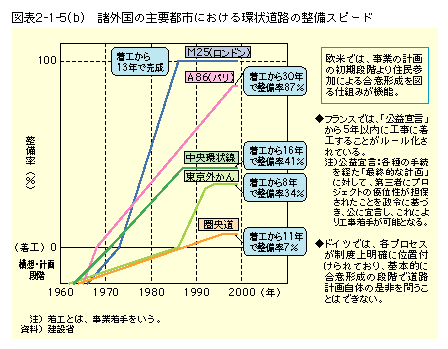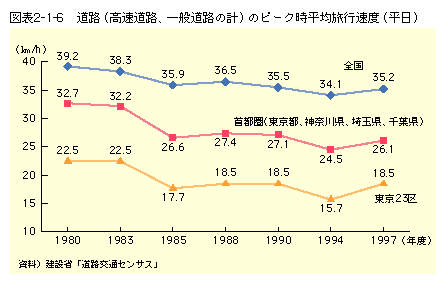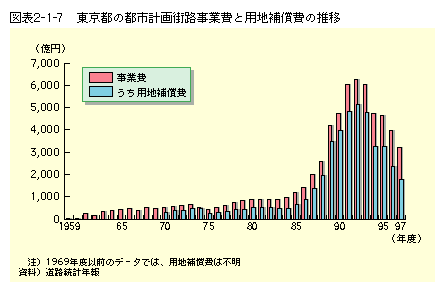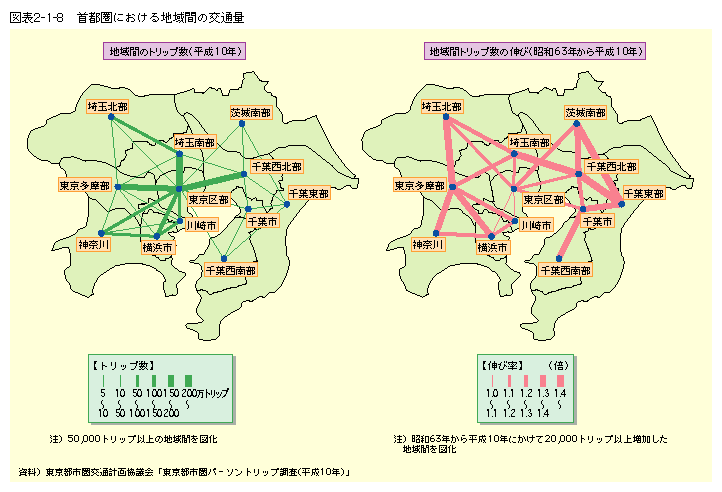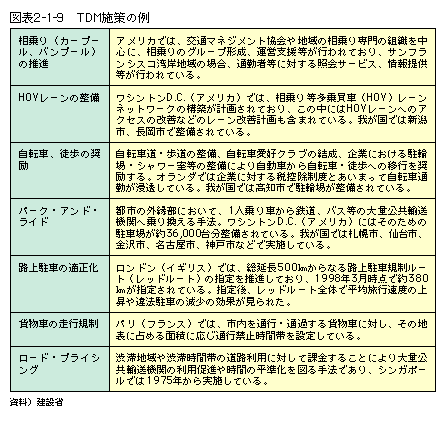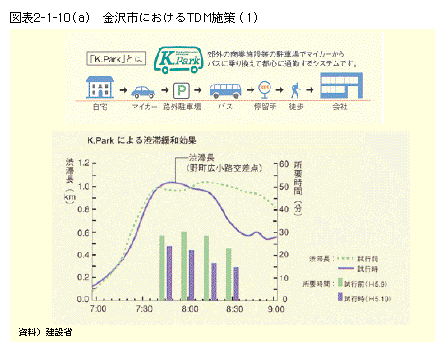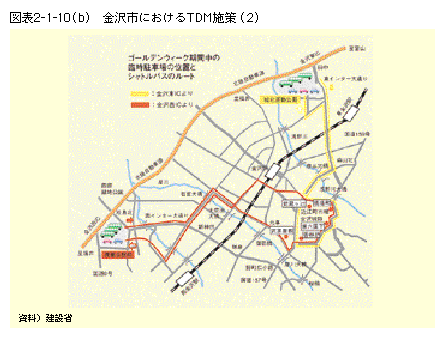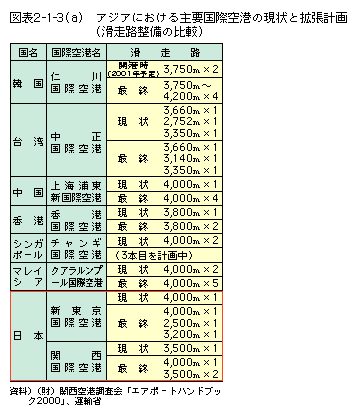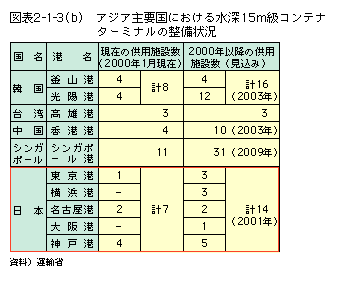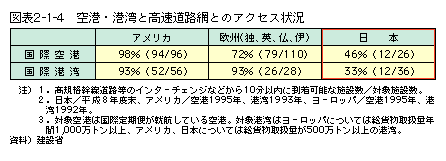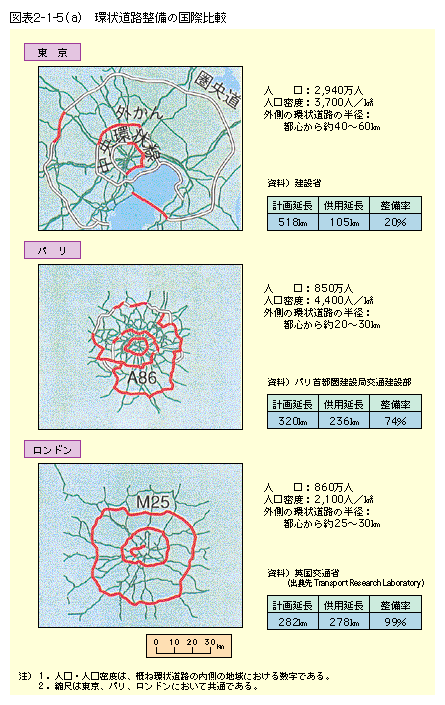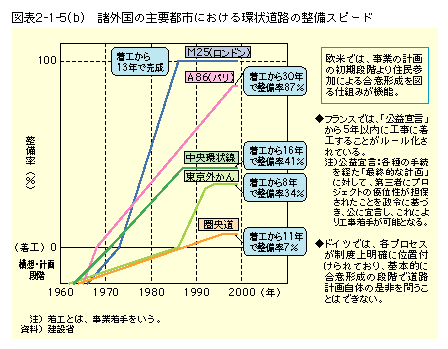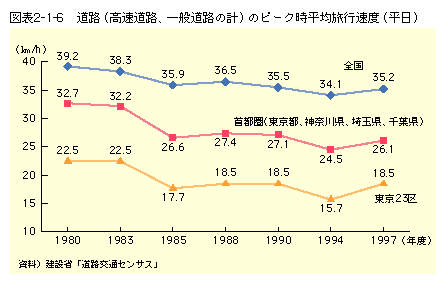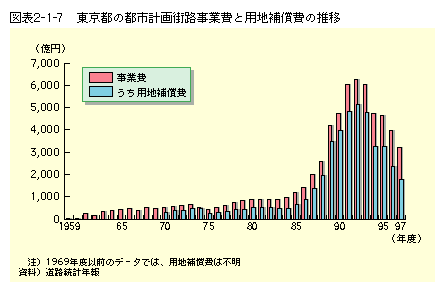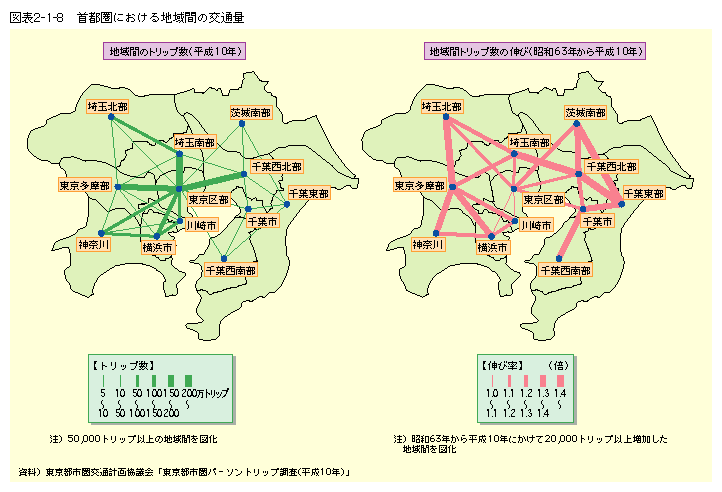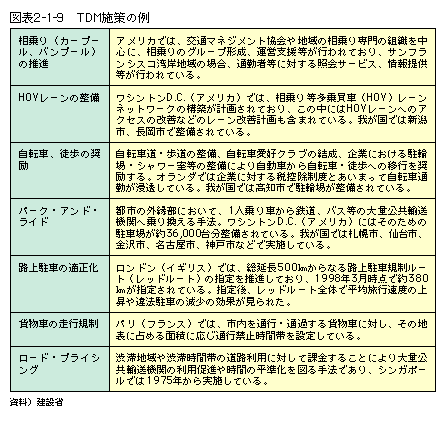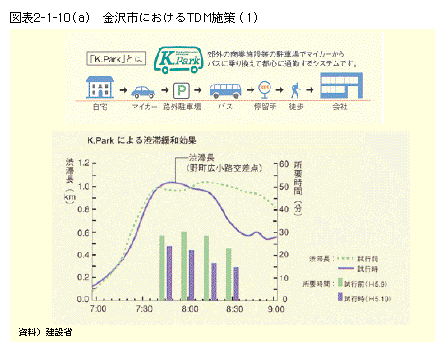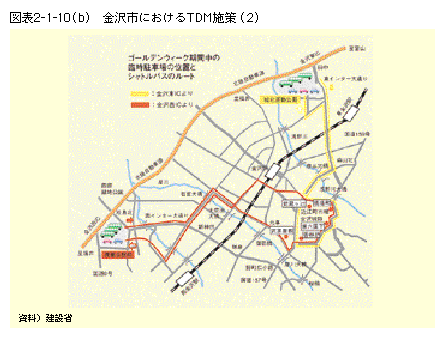(国際競争力のある国土構造の構築)
それではどのような国土づくりを行っていけばよいのだろうか。
一つの競争圏域であるアジア圏を見ると、各国は競争力確保のために国家戦略的に社会資本整備を行っている。情報化投資については後述するが、その他の国際空港や大規模コンテナターミナルの整備について見ると、必ずしも我が国が先行している状況にあるとは言えず(図表2-1-3(a)、(b))、その上に物流コスト等が高いことや地理的条件で我が国よりも有利な国もあることなどを考慮すると、アジアにおける物流拠点としての我が国の「魅力」は大きくはない。また、空港・港湾と高速道路網とのアクセス状況を見ても、欧米に比べ我が国は依然低い状況にあると言わざるを得ない(図表2-1-4)。このため、急増する航空需要に対応した国際拠点空港の整備、国際海上コンテナの需要増と船舶の大型化に対応した国際拠点港湾の整備はもとより、それらを連絡する国内幹線道路ネットワークの連携のとれた整備を行い、都市内物流を含めた物流システムの効率化と物流コストの低減を図ることが重要となっており、これらにより経済基盤が整備され我が国の産業の活性化を牽引することが期待される。また、国際競争の中で我が国の競争力を先導すべき首都圏をはじめとした大都市においては、高度成長期を通じて形成された過度な機能の集中や職住空間の遠隔化といった都市構造の歪みや、バブルの崩壊に伴う都心部の低未利用地の発生・増大や産業構造の転換に伴う膨大な工場跡地の発生といった都市空間利用の非効率性などの問題が生じており、我が国の発展に引き続き積極的に貢献していくことが可能か懸念されている。このため、道路ネットワークの整備と連携することにより、大都市の都心部に過度に集中している諸機能を周辺都市等に分散する構造を形成するとともに、都心部や臨海部に存在する低未利用地について土地利用転換や都市基盤の整備を通じ有効利用を図りながら、大都市の高次機能の高質化を推進する必要がある。また、一方で東京圏を中心に人口の都心回帰の動きも見られ、都心居住の観点も含めた、大都市への戦略的投資は今後の公共投資の一つのあり方であるといえる。
特に大都市圏における物流の効率化、交通の円滑化に関し、環状道路の整備の遅れによる影響が指摘されている。
東京圏を例にとってみると、放射道路の整備率が9割に達していることに対し環状道路(中央環状道路、東京外かく環状道路、圏央道の3環状をいう。)の整備率は2割にとどまっており、これはロンドンの整備率が99%、パリの整備率が74%であることと比較しても極めて低水準である(図表2-1-5(a))。この際問題となるのは「整備のスピード」であり、例えば同時期(1960年代)に計画が策定された環状道路を比較すると、ロンドンのM25が計画策定から20年で完成、パリのA86が計画策定から33年で9割が供用となっている一方、東京外かく環状道路は計画策定から約35年で供用延長が3割を超えたにすぎない状況となっている(図表2-1-5(b))。この結果、首都圏中央連絡自動車道の内側では、渋滞ポイントが約600ヶ所にも及び、また、東京圏の都市部では、都心部に発着点のない交通の流入等の影響により旅行速度が極めて低くなっている(図表2-1-6)。逆に、東京圏で計画されている3環状9放射の自動車専用道路網が完成すれば、これらの不経済な状況は改善され、その経済効果は年間約4兆円と推定されている。また、自動車から排出される二酸化炭素や窒素酸化物等も大幅に減少することが見込まれる。
では、早急な整備の必要性が叫ばれながら、なぜこれほどまでに遅れることになったのだろうか。確かに地形や耐震力、高い用地費など、我が国特有の事情から建設費が高くなっているという不可抗力的な理由もあるが、それだけではこの整備の遅れは説明しきれない。東京都について見ると、東京オリンピック(1964年)の後、1970年代から1980年代半ばを通じて必要な用地取得が進まず、その後地価の高騰も相まって事業費が膨大となり、道路整備の遅延を一層助長させた(図表2-1-7)。また、東京外かく環状道路(埼玉区間)の事業では、計画調整に約24年間の期間を要しており、特に都市計画決定をいったん行った後に17年を費やして都市計画変更を行っていることが大きい。いずれも、多くの関係者に対して、早期段階からの情報公開や意見聴取等、合意形成を得るための仕組みが必ずしも十分でなかったことが大きいと考えられる。欧米では事業の計画の初期段階より住民参加による合意形成を図る仕組みとなっており、合意形成がされた計画については拘束性を持つため、原則として覆されることはない。これは、事業の計画段階からその必要性(=公益性)、すなわち社会経済効果と、それがもたらす環境への影響等の外部不経済について住民と議論を尽くすというルールの下でなければ、事業の円滑な執行は困難になる可能性が高いことが欧米では認識されている証拠である。我が国でも事業の計画段階から情報公開や住民との対話等を一層積極的に進めることにより、当該事業の必要性について十分な理解を得ていくことが重要であり、その意味において、欧米の合意形成の仕組みは参考にすべき点が多いと思われる。
〈ドイツにおける道路計画・建設に係る合意形成プロセス〉
ドイツにおける連邦長距離道路の計画策定は、1)連邦全域にわたる交通網計画において道路需要に基づく一般的内容が定められる「需要計画」、2)大まかな路線を選定する「路線選定手続」、3)具体的な計画の確定を行う「計画確定手続」の3段階からなっている(1)及び2)は連邦議会、3)は州政府が行う)。住民が参加する実質的な合意形成の時期は計画確定手続時であり、聴聞手続が法定されている。それぞれの段階で法律にしたがい、連邦議会での議決などの手続きが進められており、決定された事項は法的拘束力を持つため、次の段階で変更されることはない。このため、需要計画で位置付けられる道路計画自体の是非をこの合意形成の段階で問うことはできない。なお、最終段階で行政裁判制度を利用することができることとなっており、道路計画策定プロセスにおける一定のチェック機能を果たしている。道路計画自体の是非を問うことはできないが、環境アセスメントの不備等のプロセスの妥当性について訴訟することができる。
また、環状道路の整備効果として、物流・交通の面だけではなく、近年、都市構造の再編の面においても期待が高まっている。つまり、環状道路は、過度に中心部に一極集中した構造から、周辺の拠点的な都市を中心に自立性の高い地域を形成し、相互の機能分担と連携・交流を行う分散型ネットワーク構造の構築に重要な役割を果たし得るものでもある。このように、東京圏をはじめ環状道路の整備は都市の魅力を高め競争力を確保するためにも重要であり、今後は環境や景観に対し一層配慮しつつ、構造・工法にも検討を加え早急に整備していく必要がある。
なお、東京区部以外の地域相互間の移動数の伸びが近年大きくなっているという調査結果からも環状道路の緊急性が高まっていると見られる(図表2-1-8)。しかしながら、環状道路の完成までには、なお相当の期間がかかるものと予想されるところであり、現在発生している慢性的渋滞などの不効用を一刻も早く改善することが不可欠である。このため、環状道路の早期整備と併せて、1)ITS(高度道路交通システム)の活用や、2)関係機関と連携して、交通需要の管理を行うことにより都市内の物流の効率化、交通の円滑化を図る必要がある。
まず、ITSの活用については、その実現・普及に伴い渋滞の緩和や事故の減少といった交通・物流の円滑化が図られるほか、経済速度での走行による排ガスの軽減等の環境対策、高齢ドライバーの運転操作支援による高齢者の活動の活発化や活動範囲の拡大等の高齢社会対応にも資する。特にETC(ノンストップ自動料金収受システム)については、平成12年度中に大都市圏だけでなく全国約580ヶ所の主要な料金所にもそのサービスが拡大されることになっている。
また、交通需要の管理を行う手法は、車の利用者の交通行動の変更を促すことにより都市又は地域レベルの交通渋滞を緩和する「交通需要マネジメント(TDM)施策」と呼ばれているものであるが、公共交通機関の利用促進やパーク・アンド・ライド等の手段の変更によるもの、時差通勤やフレックスタイム等のピークカット施策、ロード・プライシングや流入規制など様々な手法があり、世界各国や我が国の一部地方公共団体で取り組まれている(図表2-1-9)。特に、我が国でも早くから取り組まれているパーク・アンド・ライドについて金沢市の事例を、慢性的な大都市の渋滞解消策の一つとして我が国においても検討する動きのあるロード・プライシングについてシンガポールの実施状況を紹介する。
〈金沢市におけるパーク・アンド・ライドの取組み〉
金沢市では郊外の商業施設等の駐車場でマイカーからバスに乗り換えて都心に通勤する「K.Park」と呼ばれるシステムを平成8年度から実施している。平成5年の試行実験では5〜10分程度の所要時間短縮効果が見られた(図表2-1-10(a))。また、ゴールデンウィークには高速道路インターチェンジ周辺に臨時駐車場を設け、兼六園までのシャトルバスを運行することで市内の交通渋滞の緩和を図っている(図表2-1-10(b))。
〈シンガポールにおけるロード・プライシングの実施状況〉
シンガポールでは1975年からロード・プライシングを実施しており、当初は人手を使っていたが、多くの人手を要し人件費がかさむなどの問題があったため、1998年からERP(車両通行料自動課金システム)が導入された。平日のピーク時に市街中心部及び一定区域の高速道路に乗り入れる自動車(バス、緊急車両を除く。)に対して自動的に課金される。このERPによって常に交通量の動向が把握でき、混雑度の変化により料金を見直すことにより交通量をコントロールすることができる結果、円滑な走行が可能となっている。