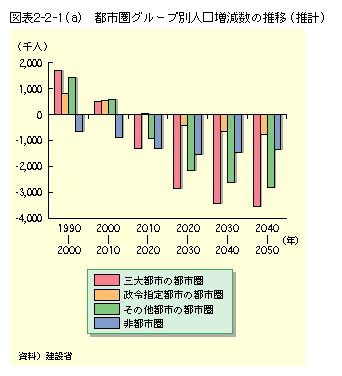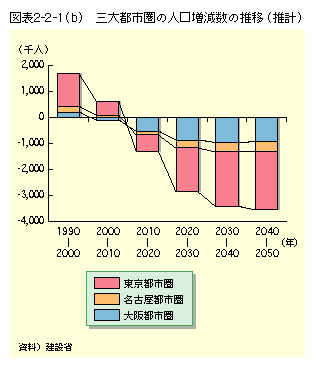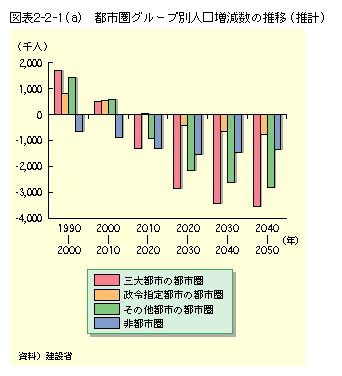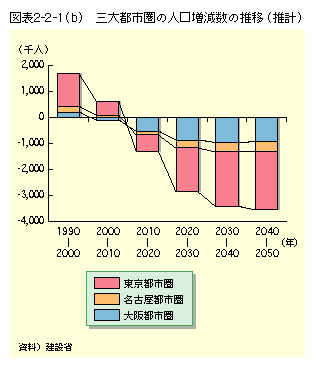(地域間競争時代の到来 〜魅力ある都市圏・生活圏への選択と集中〜)
昨年の建設白書において分析したように、21世紀は全国的に高齢化を伴った人口減少が進行し、特に政令都市や地方中心都市以外のいわゆる「非都市圏」においてそのスピードは速く、2050年には現在の6割程度にまで減少することが予測される。その結果、全国の面積の6割を占める非都市圏全体の平均人口密度は現在の過疎地域並みに低下し、国土の「広大なる過疎化」がもたらされることにより、我が国全体の活力が失われることが危惧されている。また、都市圏グループ別の人口増減数の推計を見ると、既に人口減少の始まっている非都市圏で今後10年間ごとに百万人単位の減少が続くとともに、三大都市の都市圏や県庁所在地の都市などの都市圏でも2010年をピークに大幅な人口減少が予測されており、人口減少は大都市においても深刻な問題となってくることがうかがえる(図表2-2-1(a)、(b))。一方で、高速道路網等が着実に整備されてきたことにより地域間の交流が活発化しており、今後さらに交通ネットワークが整備されていくことに伴い地域間交流は飛躍的に高まる可能性を有することになる。このような中で、居住・交流両面において『魅力ある都市圏・生活圏への選択と集中』の傾向が強まることが予想される。換言すれば、それぞれの地域が利便や魅力を求めて集まる定住人口・交流人口を確保するための一層の努力を余儀なくされる「地域間競争の時代」が本格的に到来しようとしている。
「広大なる過疎化」を中心とした全国的な高齢化を伴う人口減少は社会資本整備・管理の面においても大きな課題を投げかける。「非都市圏」だけでなく、住宅・社会資本がかなり整備されている「都市圏」においても人口減少が進行することにより、これら既存の住宅・社会資本ストックのうち活用されないものが生じるとともに、下水道等人口規模を考慮して整備された社会資本の管理の効率性の低下が懸念されるといった「人口規模と住宅・社会資本整備水準のミスマッチ」による国土管理の非効率性の問題や、財源の制約、さらには既存社会資本ストックの維持補修や更新費の増大などを考えると、今までのように全国各地においてフルセットの社会資本整備を目指すことは必ずしも効率的ではなく、その地域の発展にとって真に必要なものを戦略的に整備していくという姿勢が必要になってくる。その際、公共事業にはさらなる重点化・効率化・透明化が求められる一方、競争を通じた個性ある地域づくりによる活力や魅力の維持拡大の視点から、創意工夫をする地域に対するインセンティブを与えることも重要である。
以下、競争力を確保する「魅力ある地域」づくりについて、IT(情報技術)の進展の及ぼす影響について概観し、交流人口・定住人口それぞれを確保するためのまちづくりのあり方を検討した上で、最後に競争力を有するこれからの地域のかたちについて考えてみたい。