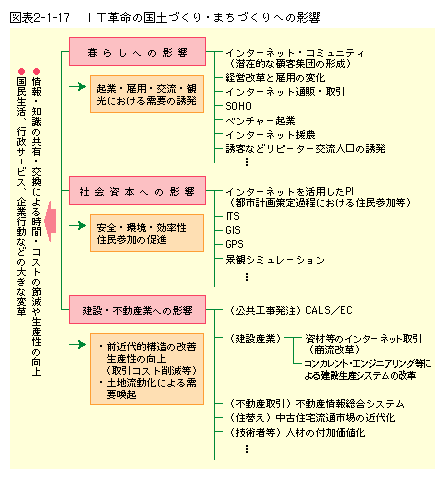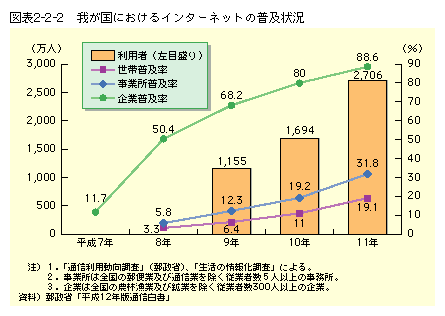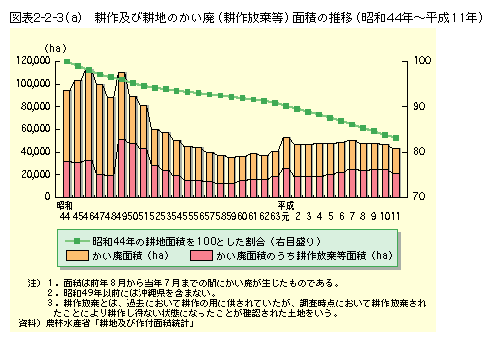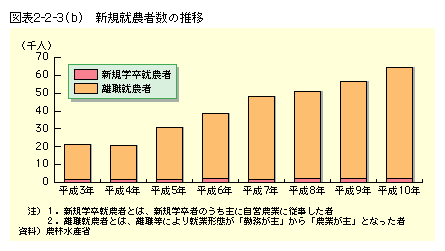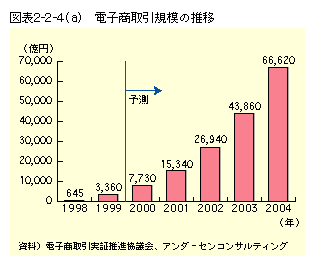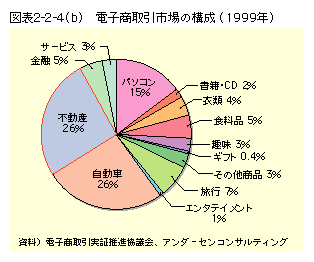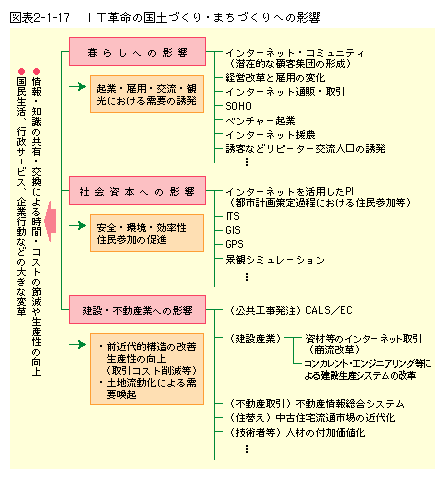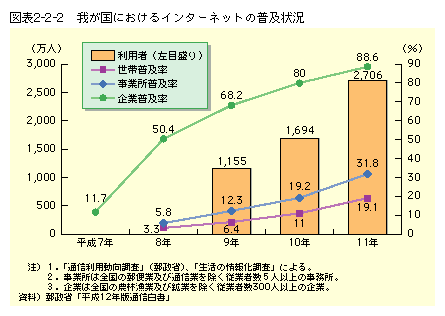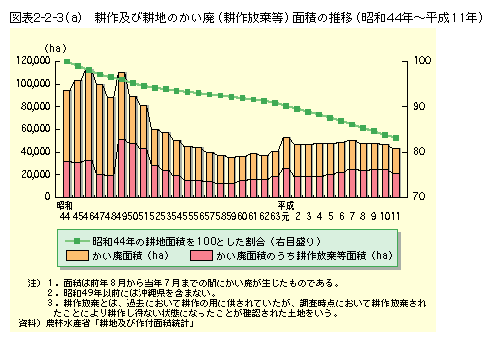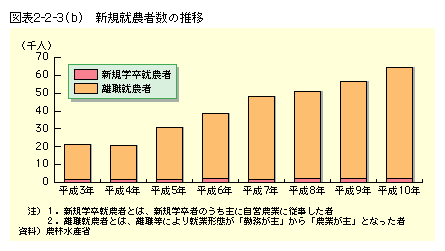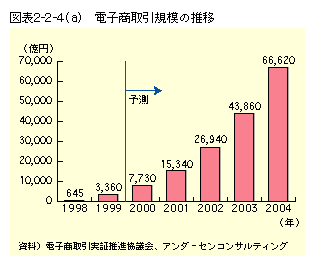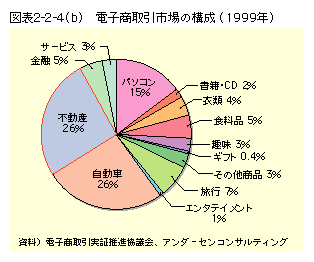(IT(情報技術)の進展の影響と活用)
前節でIT(情報技術)の進展による影響について「国際競争力の確保」の観点から概観したが、地域の発展にとっても大きな影響を及ぼし得るものであり、ここでは「地域の競争力の確保」の観点からインターネットを中心としたITの影響について考えてみたい(図表2-1-17)。
まず、インターネットや情報検索機能を備えた携帯電話の著しい普及により、行政や企業だけでなく個人が全国津々浦々で必要なときに必要な情報を収集・発信・交換できるようになった結果、その情報を活用した行動が消費者、旅行者等に見られるようになり、インターネット等を活用した情報発信への取組みが地域の活性化にとって重要な手段の一つとなりつつある(図表2-2-2)。
特に、個性ある地元情報を発信し、地域の魅力をアピールすることにより、交流人口が増加していく可能性がある。この観点からは、農山村の都市との交流の拡大による活性化が期待される。農山村では、農業者の高齢化の進行や農業の後継者の減少等に伴う耕作放棄が一因となって耕地面積の減少が続いており(図表2-2-3(a))、農業の担い手の確保等による耕作放棄の防止が地域農業の存続に関わる重要な課題の一つとなっている。一方、近年の新規就農者数は増加傾向にあり(図表2-2-3(b))、都市住民の中にも農業に魅力を感じる人は少なくないものと考えられる。このような中、稲刈りなど人手を必要とする繁忙期に、農家がインターネットを通じてボランティアを全国に呼びかけ、都市の住民が農業体験や農家とのふれあいを求めて集まる「インターネット援農」といった滞在・体験型の交流も生まれており、農業労働力の確保にも結び付いている。こうした個人・家族間の交流は、名所観光と異なり、滞在型の大きなリピーター交流人口となって、都市と農山村との間のヒトとモノの交流・循環を支えていく底流となる可能性がある。
また、インターネットの特徴として物理的距離をなくすことが挙げられるが、このことによる影響も見られ始めている。まず、インターネットによる通信販売が浸透しつつあることであり、情報提供のみである場合も含め何らかの形でインターネットに関わる「電子商取引(企業対消費者(B to C))」の市場規模は3,360億円(1999年)に達し、今後も急速に拡大すると予測されている(図表2-2-4(a))。この中で不動産関係の取引は約4分の1を占めているが、金融取引などと異なりそのほとんどが情報提供のみであり、契約・決済までを含めた厳密な意味での「商取引」とはいえない可能性もあるとはいえ、ITが不動産市場の活性化にも資することがうかがえる(図表2-2-4(b))。このインターネットによる通信販売という新たな手法により、地方部においても大都市に集中する消費者を対象として地元特産品・工芸品等の販売を行うことができるようになり、地域産業にとって重要なツールとなりつつある。ただし、先に見た交流の拡大を含め留意すべきことであるが、不便な交通・物流体系は交流の拡大やインターネット取引市場にとって制約条件になり得るものであり、インターネットで契約・調達した後の商品・資材など実物を運ぶ高速道路などの物流体系を併せて整備していく必要がある。次に、物理的距離の解消による影響として、個人や企業の経済活動を行う場所の選択の幅が拡大することが挙げられる。インターネットによる通信販売が可能となる業種であればあえて立地コスト等のかかる都心部に店舗を構える優位性がなくなる場合もあることも含め、前節においても見たように在宅勤務・SOHOといった職住近接・一体の形態が増加することが考えられ、生活環境に配慮したまちづくりの行われた地域が選択される可能性が高い。このSOHOに関しては、地域経済の活性化に資する産業の育成・支援という観点から、地域の活性化をにらみ各自治体においてその支援の動きが広まっている。特に住宅地の多い東京都三鷹市は、住環境と共存できる産業としてSOHOを積極的に支援しており、市が出資する(財)三鷹市まちづくり公社を通じ、情報通信施設が整備されたSOHO用オフィスの格安な賃料による提供等を行っている。
このようにITの進展は、地域の活性化にとって有用なツールとなるものであると同時に、人々の生活様式の変化に伴ったまちづくりを地域に促す大きな圧力となっているといえよう。