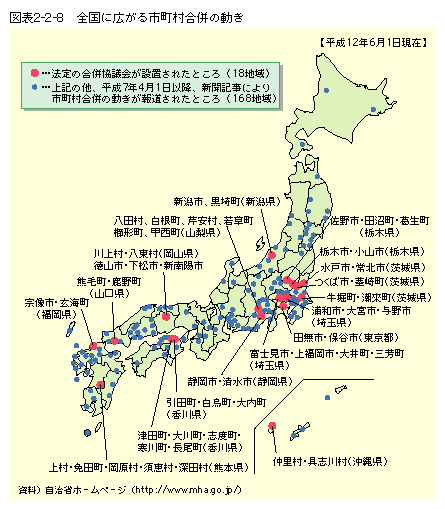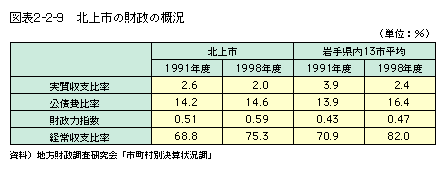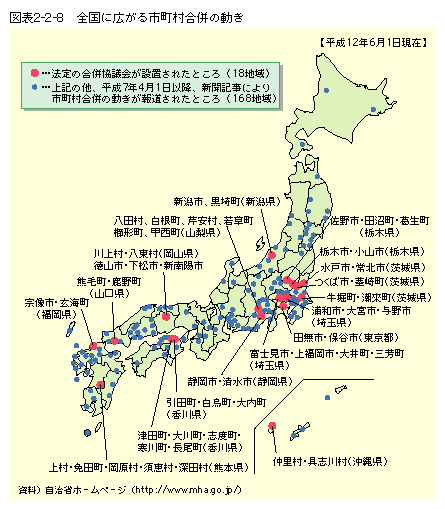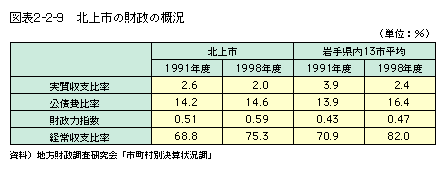(競争力確保のための地域のかたち-広域連携-)
以上に見てきたように、地域のコミュニティを持続させる「魅力ある地域」をつくるためには、地域の個性を生かした生活環境に配慮したまちづくりなどが必要であるが、単一地域だけでは高めるべき「魅力」の質・内容に限界があり、競争力の確保の観点からは地域の拠点都市を中心とした一定の広がりをもった都市圏レベル、広域的な生活圏レベルでの連携が必要になる。これは各地域の一体化へ向けた意識の向上、定期的な情報交換、地域間の人材・文化交流、イベントの同時開催、地域相互間の交通ネットワークの整備等によって図られていくものであるが、ごみ処理、し尿処理等の「環境対策」や在宅介護サービスの実施やデイサービスセンターの設置等の「福祉対策」など地方公共団体の抱える深刻な課題の局面では単なる連携では解決できない。このため、最近の地方分権の進展等に伴い、市町村合併や広域連合の自主的な動きが活発化している(図表2-2-8)。特に行財政の効率化等の観点から市町村合併や広域連合による共通課題への取組みがいわれているが、社会資本の効率的な整備・管理の観点からも歓迎すべきものといえよう。
すなわち、今後各地域においては、前述したように、人口減少の進行によって、人口規模と住宅・社会資本整備水準のミスマッチが生じることによる国土管理の非効率性の問題や、既存社会資本ストックの維持補修や更新費の増大による新規投資の圧迫の問題が懸案となり得るが、複数地域を一体として管理する体系(以下便宜的に「複合地域」という。)へ移行すればこれらの問題は緩和される可能性がある。むしろ、広域的視点から、戦略的なプロジェクトや公共施設の整備、土地利用などを行うことができるようになり、例えば複合地域内の地域で大規模で良質な施設を分担して整備しそれらを効率的に連絡できる交通ネットワークの整備を行うといったように、効率的な地域づくり・まちづくりを推進していくことが期待できるというスケールメリットが注目される。また、複合地域内で各地域が機能を分担する効果は、社会資本整備の効率化のみならず複合地域全体の魅力の深化にもつながり得る。なお、実際に市町村合併の効果があった事例として岩手県北上市の例を紹介する。
〈岩手県北上市の合併効果〉
1991年4月、和賀川流域に位置する岩手県北上市、和賀町及び江釣子村が合併して新「北上市」が誕生した。高速道路のクロスポイントを活かした県内陸部における中核都市づくりを目指したものであったが、そのねらいどおり、高速道路ジャンクション周辺への企業立地が進んだ。また、人口も大幅に増え、人口伸び率は北東北3県30市中でトップとなっている。さらに財政面について見ても、実質収支比率、公債費比率、財政力指数、経常収支比率のいずれの指標も県内13市の平均値と比べて相対的に良好に推移しており、合併効果のあったことがうかがえる(図表2-2-9)。