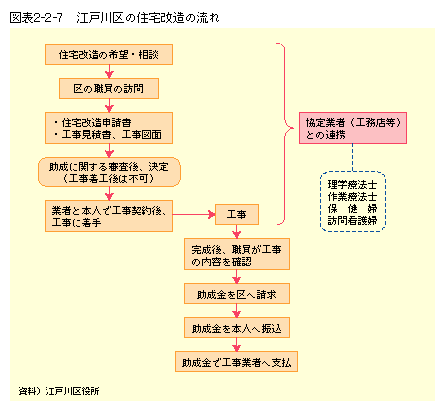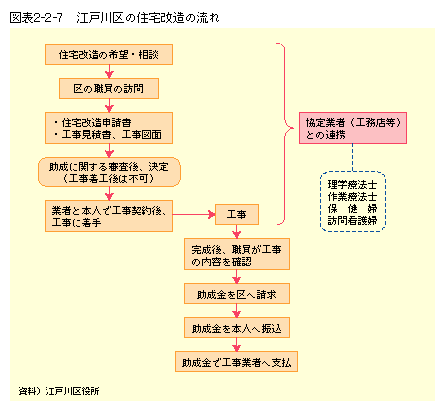(高齢者の「住」を支える新たなコミュニティ・マネジメント)
最後に地域全体から見た「住」環境の整備の重要性について考えたい。先にも触れたバリアフリー化のほか、美しい景観やリフレッシュできる公園等の「遊」空間、生涯学習や地域文化・歴史・産業と連携した「学」空間、拠点都市との交通利便性などが魅力的な「住」環境の重要な要素となる。このうち「美しい景観」づくりについては次章で詳細に検討していくこととする。
また、これからの高齢社会においては、このような魅力的な「住」環境の形成を図る上で、住宅や福祉に関する公的サービスだけでなく、地域の人的資源を活用しつつ、高齢者の自立支援をはじめ地域社会(コミュニティ)の「住」を支えるソフトな仕組みをつくっていくことが重要になる。これには公共コストを下げる副次的効果がある。地域のことを最も理解しているのは今まで地域づくりに携わってきた地元の各分野の専門家であり、これらのネットワーク化は地域づくりにおいて大きなメリットとなる。ネットワーク化とまではいかないが、良好な「住」環境を整備するに当たって地域の専門家を活用し効果を上げている東京都江戸川区の事例と、異業種ネットワークによる住宅改善への取組みを行っている特定非営利活動法人(NPO法人)の事例を紹介する。
高齢者や障害者の自立を支援するこうした地域の人的ネットワークは、個人の自主的な参加を通じて、地域で支える福祉社会づくりに寄与するだけでなく、社会に貢献しようとする「公たる自覚」を醸成し、コミュニティの新たな活力となろう。
〈東京都江戸川区における住宅改造への取組み〉
江戸川区では介護保険制度が始まる前から、介助を要する高齢者や身体障害者を対象に、住宅のバリアフリー化に関する改造費の助成を行ってきており(図表2-2-7)、平成11年度末時点でその実績は3,316件に上る。区は地元の工務店等と住まいの改造工事に関わる協定を結び、区の職員はこの工務店等と一緒に相談・訪問に当たっており、さらに工務店等は理学療法士、作業療法士や保健婦等と相談しつつ高齢者等個々の運動能力に応じた住宅改造を行っている。また、この副次的効果として、改造を施した住宅が高齢者等に喜ばれることによる建築職人自身のやりがいの復活、跡継ぎになる若者たちによるバリアフリー建築等に対する熱心なグループ研究会の開催も見られるようである。
〈特定非営利活動法人(NPO法人)による住宅改善への取組み〉
大阪市の「福祉医療建築の連携による住居改善研究会(福医研)」は、1989年以来、保健医療・福祉の専門家(医師、保健婦、看護婦、理学療法士、作業療法士等)と建築の専門家(建築設計者等)が連携して、住宅改善に関連する講演会、無料相談、設計監理業務、調査研究など住居改善についての活動等に取り組み、1999年には特定非営利活動法人(NPO法人)となった。福医研は、高齢者、障害者が安全で快適な社会生活を送ることができるかどうかを基本的人権に関わる問題と捉え、高齢者や障害者の自立を促し、併せて介護者の負担も軽減できる住環境の重要性を訴えている。