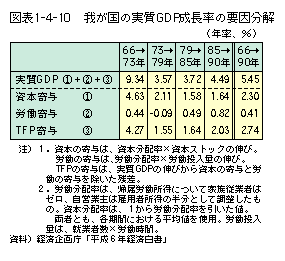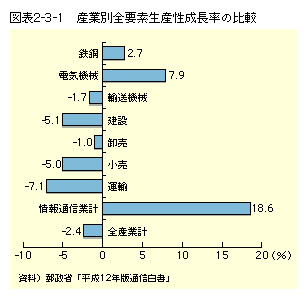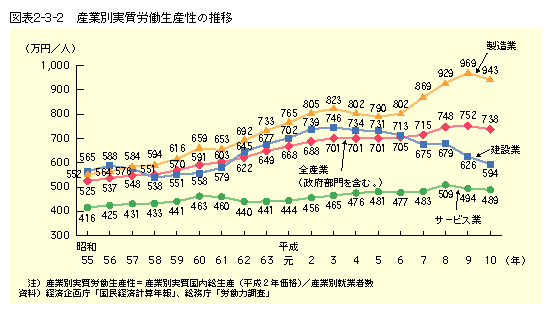第3節 良質な住宅・社会資本を生み出す建設産業の新たな競争力
我が国の住宅・社会資本整備を担う産業分野は建設産業である。
日本経済が長期間にわたり低迷し、産業競争力の強化が焦眉の急となっている現在、建設産業についても、建設投資の低迷と建設業者数の増加、コスト縮減の要請など公共投資を取り巻く環境の大きな変化、建設市場の国際化による競争の激化などから、その経営環境が極めて厳しくなっており、大きな構造変化に直面している。
我が国GDPの約15%程度、雇用の約1割を占め、住宅・社会資本整備の担い手として重要な役割を担っている建設産業のあり方は、国民・市場の大きな関心事であり、今後の我が国の経済社会に大きなインパクトを有するものと考えられる。このため、現下の厳しい環境を踏まえた建設産業の戦略的な取組みの方向について、明らかにすることが強く求められている。
このような状況を踏まえ、平成10年2月には、中央建設業審議会建議「建設市場の構造変化に対応した今後の建設業の目指すべき方向について」が示され、今後、技術と経営に優れた企業が伸びられる透明で競争性の高い市場環境の整備を進めていくことが急務であるとし、各企業の自助努力と市場原理を基本としつつ、1)技術力による競争の促進、2)連携強化など新たな企業経営の展開、3)入札・契約手続の透明性の向上、4)建設生産システムの合理化の推進などを積極的に進めていくとともに、技術と経営に優れた中小・中堅建設業者が伸びられる環境づくりを進めていく観点から、引き続き、公共工事の効率的な執行を確保しつつ、優良な中小・中堅建設業者の受注機会の確保対策を推進する必要があるとされている。
また、建設産業の将来ビジョンと建設産業政策の基本的方向に関しては、平成7年4月に「建設産業政策大綱」が策定されているが、我が国経済が低迷する中で、建設産業についても、競争力を強化し、21世紀の経済社会のニーズに応えられる創造力と活力を有する産業になることが求められている。
少子・高齢社会においても、環境と共生しつつ豊かで快適な生活を実現する上で、持続的な経済成長は不可欠である。経済成長を生み出す要因を分解すると、「労働力」「資本」「技術進歩その他(全要素生産性=TFP)」の要因に分解でき、社会資本の伸びがTFP(全要素生産性)の伸びに与える影響が大きいと前章において述べた。このように、社会資本の生産力効果以外にもTFP(全要素生産性)という経済成長への寄与度の中には、技術進歩などによる生産性や効率性の向上も含まれる。前章で述べたように近年TFP(全要素生産性)が資本や労働以上に成長に寄与しているとの推計があることからも(図表1-3-10)、生産性や効率性の向上によるTFP(全要素生産性)が経済成長の原動力となるよう改革を進め、経済社会の基盤を整備することが必要となってくる。
住宅・社会資本整備の分野において生産性向上のために採られるべき方策としては、
1) 社会資本のストック効果、公共投資のフロー効果の向上(
第1章第4節参照)。
2) 建設産業分野についての、労働力の質。例えば、経験知の集積による施工管理能力の向上などによる現場労働生産性の向上や、プレファブ等の新しい工法を活用する分野での新たに開発された技術や業態の変化による工法・工程改善、省力化などによる労働生産性の向上。
3) アメリカで先行しており、近年我が国でも始まった電子商取引、電子媒体による情報交換等のITを建設産業においても活用することによる生産性の向上。
などに積極的に取り組み、効率的な公共投資や住宅・社会資本の整備を通じて、2000年のIMDによるランク付けで世界第17位に低下した国際競争力の向上を牽引することが一層必要となってくる。
また、近年(平成2年から10年)におけるTFP(全要素生産性)の成長率を産業別に比較した場合、情報通信産業の18.6%、電気機械の7.9%、鉄鋼業の2.7%に比べて、建設業は-5.1%と、運輸業、小売業とともに低下しており(図表2-3-1)、これは、マクロでみた建設業の実質労働生産性の低下にも対応している(図表2-3-2)。本節では、建設業等の生産性向上について、どのような問題があり、労働・資材対策やITを含め、どのような対策が必要かを概観してみたい。