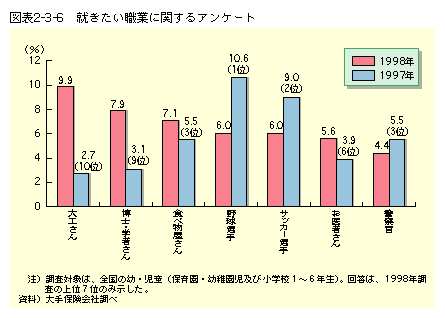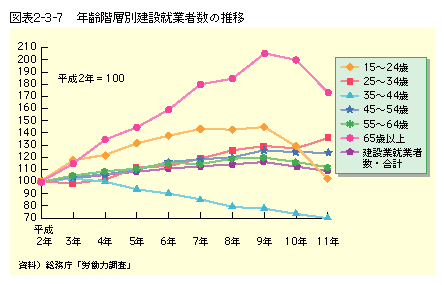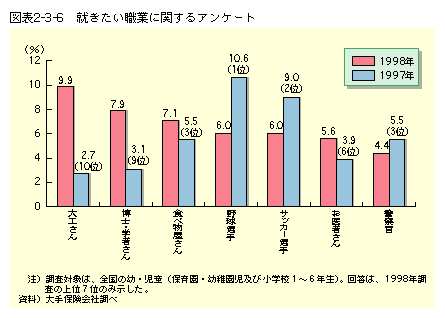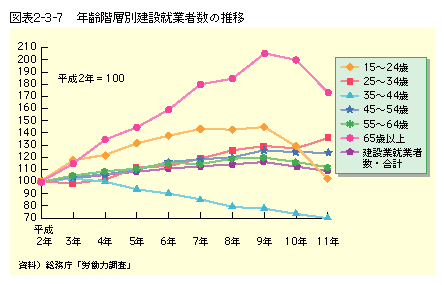(人に支えられる産業)
そこで、建設産業の現場の直接施工即ちものづくりに携わる人材について考えてみよう。
先に述べたように、より質の高い住宅・社会資本を整備する上では、建設産業が競争的環境の中で健全な市場を築いているばかりではなく、建設産業に働く人々、特に現場での施工に携わる人材が、建設産業で働くことに生きがいを感じ、また優秀な技能や技術が現場の中で蓄積されて、次の世代を担う人々に継承されていくことが重要である。
我が国における、建設業の就業者数は657万人であり(総務庁「労働力調査」(平成11年平均))、全産業就業者の約1割に相当する。そのうち、管理・事務部門に担う者や、建築士等の技術者などを除いた、現場での施工に携わる者は、432万人であり、これは建設業就業者数の約3分の2に相当する。建設業は確かに、労働時間、賃金等を見ても、他産業と比べて遜色のある面もあるが、最近、「ものづくり」に対する憧れや、会社人間ではなく「手に職」をつけて自分の財産となるものを身に付けたい、とする意識の変革があるからか、建設業は最近人気のある職業となっているという調査もある。例えばある大手生命保険会社が全国の保育園、幼稚園及び小学生を対象に行った調査(平成11年)によると(図表2-3-6)、「大人になったらなりたいものは何ですか。」という問いに対して、第1位になったのは「大工さん(9.9%)」であり、次いで「博士・学者さん(7.9%)」「食べ物屋さん(7.1%)」「野球選手・サッカー選手(6.1%)」であった。前年の調査では「大工さん」が10位であったことと比べると大躍進である。
建設省の建設労働需給調査によると、近年では建設投資の落ち込み等により技能労働者はやや過剰気味で推移していることが分かる。しかし、「少子・高齢社会に向けての建設業における労働生産性向上に関する研究会提言」(平成11年7月)によると、長期的には、少子・高齢化の進展や景気回復後に建設労働人口が他産業に流出する可能性などに鑑み、場合によっては労働力需給の逼迫が生じる可能性があるとの推測がなされている。
また、建設業就業者数の推移を年齢階層別に見ると(図表2-3-7)、建設業においては、全産業に比べ、35歳〜45歳の層の落ち込みが大きく、逆に65歳以上の高齢な労働力の増加が大きいことから、将来の建設業の中核を担う人材が不足することが予測され、「働き盛り」の層が弱体化していることが分かる。
建設産業についての「今その向こうにある危機」は、将来、後述する基幹技能者など有能な人材不足の時代がやってくる可能性が高いということである。
建設業にとって必要な人材は一朝一夕に育つものではなく、「一人前」の職人になるためには長い年月を要する。例えば、鉄筋工の「職業生涯モデルプラン((社)全国鉄筋工事業協会作成)」によると、18歳で鉄筋工として働きはじめてから、「班長」となって現場で作業集団を統率できるリーダーとして鉄筋作業の最前線に立てるまでは約12年かかる、と言うように、それまではいわば「下積み」「見習い」「修業中」である。修業年限は職種によって長短があるが、10年後の人間を育てる気概で、働く人に気持ちよく働いてもらう産業づくりや、よい人材を確保するための人材育成を行うことが今大切になっている。