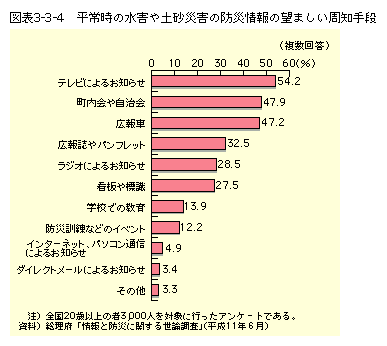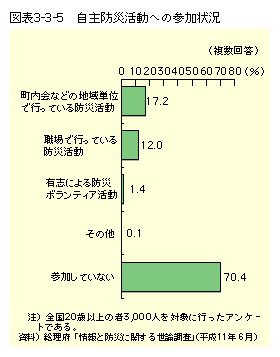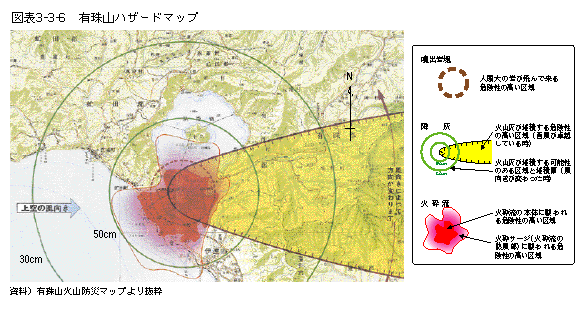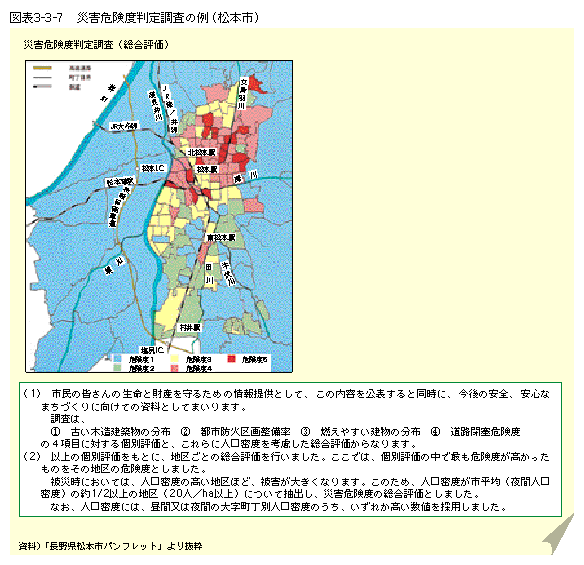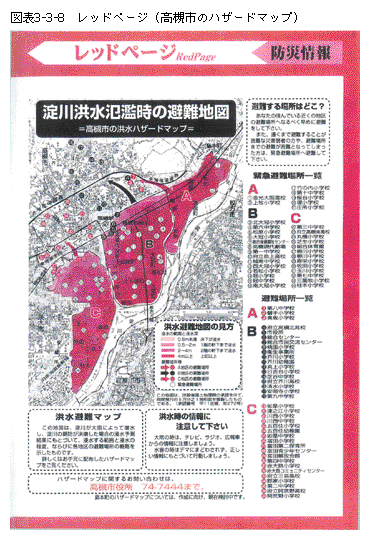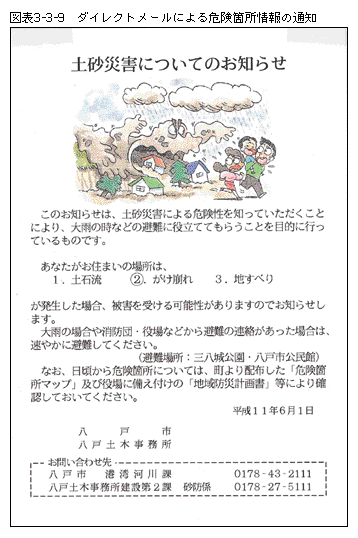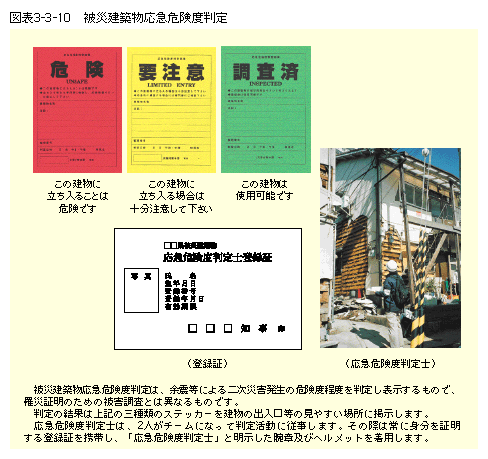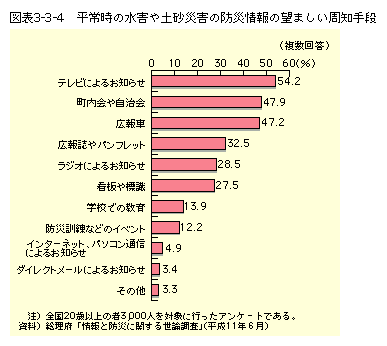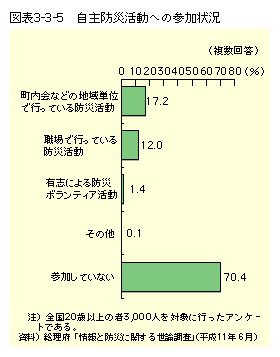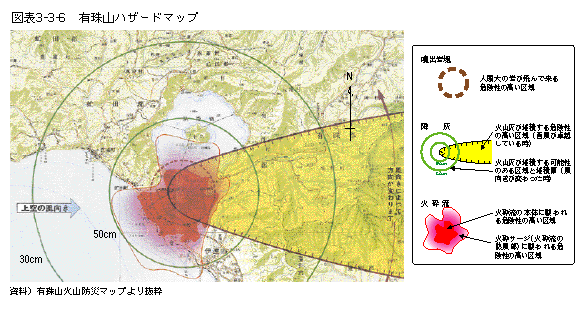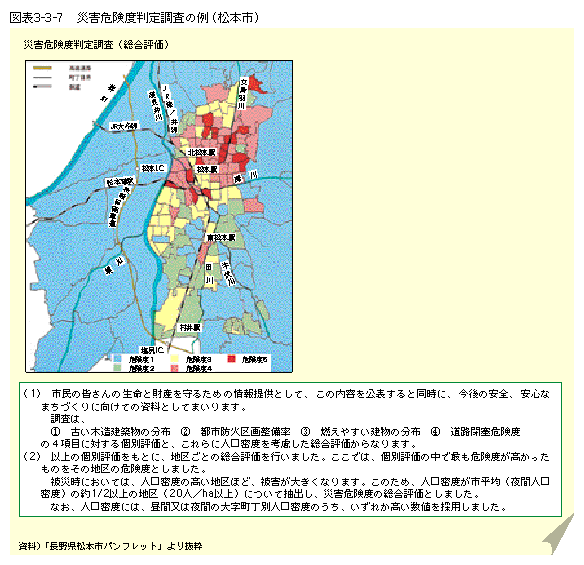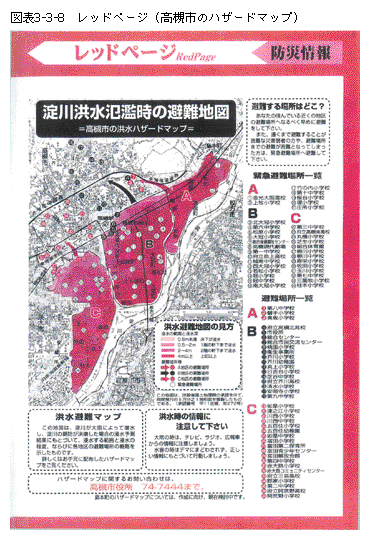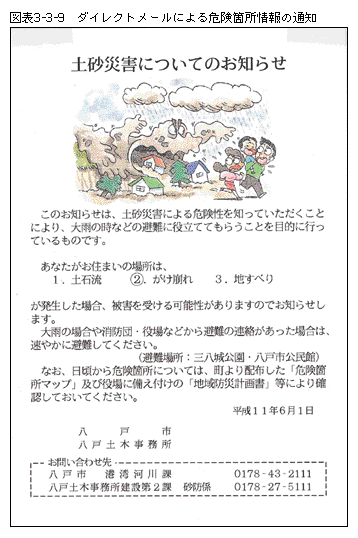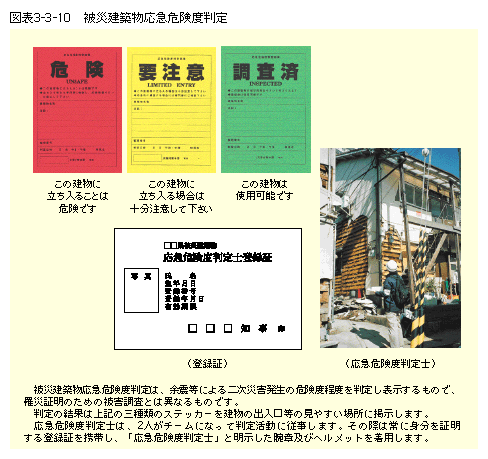(情報やボランティア等のソフト対策)
日本はその国土条件から、様々な形の災害に見舞われることが避けられず、また自然条件に起因する災害であることから、耐震性の強化や災害に強い国土づくり・まちづくりといったハード面の対策のみで対処することには限界がある。このような状況から、災害が発生した場合においても、被害を受けることをある程度容認した上で、被害を最小限に抑え、壊滅的な被害を回避するといった考え方を取り入れることの必要性が認識された。
このため、災害に対するソフト面での対応として、初動期の情報収集体制の確立、総合的な防災情報ネットワークの整備、住民の災害の危険性に対する認識の向上、住民との連携強化、災害の現場におけるボランティアによるきめ細やかな活動との連携、災害に対する調査研究体制の充実等により、災害を最小限に食い止めることの重要性が認識された。
「防災と情報に関する世論調査(平成11年6月)」によると、「地域での水害や土砂災害などの危険がある場所を、普段からお知らせするには、どのような方法がよいと思いますか。」という問いに対し、最も多い回答は「テレビによるお知らせ」(54.2%)であるが、「町内会や自治会」も47.9%と次いで多く、地域の災害情報を住民同士によって伝達しあい、地域での災害の危険に関する認識を共有しあうことに期待する声も大きいことが分かる(図表3-3-4)。一方で、「町内会や自治会などを単位として、消防団とは別に、住民などによる自主的な防災活動が行われています。あなたが現在参加している自主防災活動はどのようなものですか。」という問いに対しては、「参加していない」とする回答が70.4%であった(図表3-3-5)。阪神・淡路大震災においては地域住民の協力による自主的な防災活動の重要性が認識されたところであるが、都市化やマンション居住の進展は、一方で職場社会への単属傾向や高齢者の孤立傾向を強め、コミュニティにおける住民同士の交流・連絡を失わせている面もある。今後は、自主防災活動への参加を増やすことにより、地域で自立した個人として暮らすとともに、コミュニティの一員として一定の社会的責任を果たす「公」の意識も育むための防災における町内会・自治会等の役割に代表される「コミュニティの機能」が初期の情報収集面等において期待される。
(1)行政の知らせる努力と国民の知る努力
地域住民の日頃の災害に対する準備や災害時の適切な避難活動に資するため、防災情報を提供することは極めて重要である。
〈ハザードマップ〉
火山噴火や洪水、土砂災害を想定し、浸水や土砂災害等の危険区域、避難地・避難路の位置、避難の心得等を具体的に示したハザードマップを各市町村等が作成・公表している。
出水を想定したハザードマップ(「洪水ハザードマップ」)は、年々作成市町村が増加しており、平成11年度末までに74市町村が作成及び公表を行っている。さらに、検討着手済みや今年度内の着手予定市町村を加えると1年から2年以内で200市町村に近づく見込みである。建設省では、市町村のハザードマップ作成に対し積極的に情報提供を行っている。
北海道有珠山噴火の際、事前に配布してあった火山災害予想区域図(「有珠山火山防災マップ」)(図表3-3-6)が住民の迅速な避難に大変役立った。
近年の都市部における浸水による被害等に対応するため、地下空間のさらに浸水が発生する恐れのある地区について、浸水情報マップの作成・公表を推進している。
また、地方公共団体が現在の市街地の状況を評価し、まちの大規模地震などの災害に対する危険度をその要因を含めて明確にする災害危険度判定調査の実施及び結果の公表を行うことを推進している(図表3-3-7)。これは住民が容易に防災上危険な箇所を理解できるよう、町丁目単位などの地区単位で、地震などにより災害が起こりうる危険性を評価するものであり、住民の意識啓発やまちづくりの計画策定等に活用されている。
〈レッドページ〉
家庭内で防災に関する情報がすぐに取り出せるよう、電話帳(ハローページ)の冒頭部分に赤枠ページ(レッドページ)2ページを確保し、地域の実情にあわせた災害危険情報(ハザードマップ)や地震時の心得、土砂災害に関する前兆現象等防災・危険情報を掲載する取組みが始まっている(図表3-3-8)。
〈ダイレクトメール〉
土砂災害が発生するおそれのある危険箇所における災害防止施設の整備率は、約20%にとどまっていることもあり、尊い人命を守るためにハード対策と相まって警戒避難体制の充実が強く求められている。このため、平成9年度より土砂災害危険箇所周辺に居住する世帯を対象に「ダイレクトメール」による直接的な周知方法を行っており、全国で延べ約166,000世帯(平成11年6月現在)に危険箇所等の周知に関するダイレクトメールの配布を実施している(図表3-3-9)。土砂災害は雨などに伴い突発的に発生する特徴から、住民への平常時からの危険箇所等の周知が重要であるが、平成9年に住民の意識調査を行った結果、近くに土砂災害危険箇所があることを知っている人は49%にとどまる等、十分な周知がなされているとはいえない状況であったことから、この方法がとられたところである。
〈コミュニティ放送〉
コミュニティ放送局は市・町・村など限られたエリアを対象に地域に密着した生の情報を発信する放送局であり、通常は行政情報や地元商店街の情報、イベント情報等を提供しているが、災害時には地元住民に安心・安全のための情報を提供する緊急連絡手段としての役割を担う。行政との連携により正確な情報が迅速に提供でき、また地域住民とも身近なメディアとして関係が強いため、災害時の情報伝達手段としての役割を視野に入れて設立された例もある。平成12年度末現在で131局のコミュニティ放送局が開局している。
(2)災害時におけるボランティア活動
建設省においては、災害時におけるボランティアの果たす役割の重要性を認識し、公共土木施設等の被害情報の迅速な収集等をボランティアとして行う「防災エキスパート制度」を平成8年1月に発足させ、これまでに地方建設局、北海道開発局、沖縄総合事務局管内では約4,900名の方々が防災エキスパートとして登録されている。
「防災エキスパート」は、施設の整備や管理等に関して専門のノウハウを持っており、大規模災害が発生した場合に、河川管理施設及び公共土木施設の被災状況について、広範囲できめ細やかな情報収集活動を行い、迅速かつ効果的な対策に貢献し、被災地の一日も早い復旧を目指し活動を行っている。
さらに、土砂災害に関する知識の普及と斜面の亀裂等の変状の発見及び行政等への連絡、被災者の救助活動を行う「砂防ボランティア」が、阪神・淡路大震災を契機に全国各地で設立され、62団体、3,195名(平成12年6月現在)の方々が登録されている。
なお、これらのボランティアは平成8年12月の蒲原沢土石流災害を始めとして、現場作業の監視、情報伝達、行方不明者の捜索活動を行う等全国で活動している。
また、都道府県、建築関係団体及び建設省で構成する「被災建築物応急危険度判定協議会」では、余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生じる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災した建築物の状態を調査し、余震等による二次災害発生の危険の程度を判定・表示する「被災建築物応急危険度判定」の実施体制の整備を行っている(図表3-3-10)。この調査を行う応急危険度判定士は、都道府県知事が行う講習会を受講し、認定登録された建築技術者のボランティアで、全国で95,061人(平成12年3月31日現在)が応急危険度判定士として登録されている。阪神・淡路大震災では、延べ約6,500名の判定士が判定活動を行い、約47,000棟の建物を判定した。
さらに、平成9年5月には、大規模災害により被災した宅地の危険度を判定する「被災宅地危険度判定士」が創設され、全国で4,025人(平成12年3月31日現在)が登録されている。