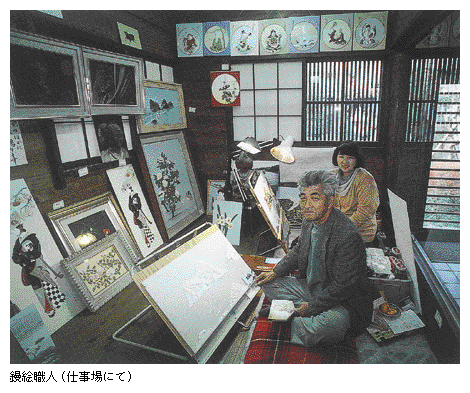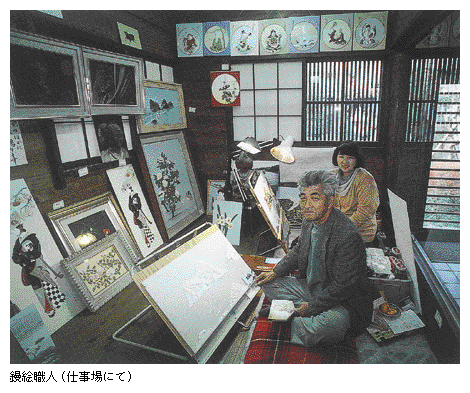現代に伝わる名工 鏝絵職人
鏝絵は江戸時代末期、伊豆松崎生まれの入江長八(通称 伊豆の長八 1815〜1889年)が、左官の弟子となり、狩野派の絵を学びながら、漆喰を使い鏝で壁面に絵を描く彫塑技術を大成して完成させた漆喰芸術である。「左官絵」「鏝掛け」「蔵飾り」とも言われる。長八の名は日本橋茅場町の薬師堂の建立に当たって柱に龍の彫刻を鏝で作成したことで一躍有名になった。以後この技法が全国の左官職人の間に広がって、腕のある左官職人たちは、漆喰で家壁に絵や家紋を描いては技量試しをしたとされる。また左官職人が2、3年の歳月をかけて完成した土蔵づくりの最後に、建築主の依頼により、家と家族を災厄から守り、健康で子孫の繁栄など庶民の願いをこめて、「波乗り兎」「雲龍」「鯉の滝登り」「恵比寿大黒」「お多福」「養老の滝」などの鏝絵を描いた。現在では、大分県をはじめ九州や四国の旧家などにその面影を見ることができる以外は、現代の建築物の中では鏝絵は姿を消し、また手間がかかることから左官職人の中でも鏝絵の仕事ができる者は数えるほどになってしまった。
近年、水と土という原始的素材を使い、凹凸のある豊かで温かみのある独特な鏝絵の味わいを求める人は多い。最近では室内のインテリアとしても鏝絵の作品が親しまれている。また、大分県では鏝絵をテーマとしたシンポジウムを開催するなど、鏝絵を現代から未来に継承するための試みを行っている。
静岡県在住の山本堪一さんは左官職人として左官業を営んでおられたが、55歳のときに長八の作品に触れ、以後長八の作品を研究することで独学により鏝絵を習得した。現在では、鏝絵の制作活動のほか、鏝絵の良さを理解してもらおうと自宅で鏝絵教室を開催したり、小学校で実演するなど、活躍されている。鏝絵の需要は少なく、職人も育ちにくいため、まずは人々に鏝絵の良さを分かってもらい、鏝絵の技術を後世に伝えていくことが今後の課題である。