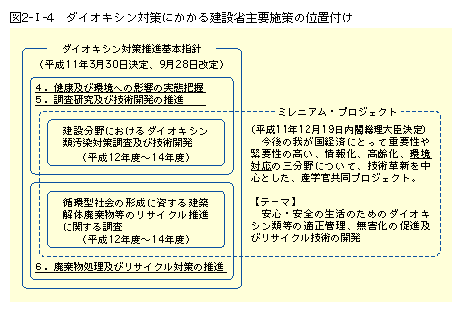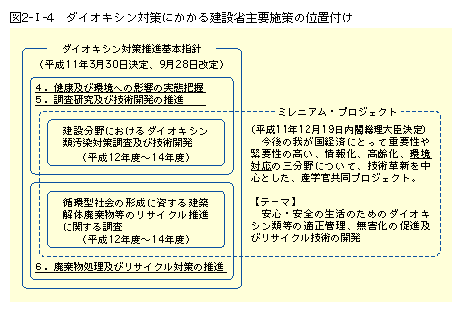(4)新たな化学物質問題への対応
イ ダイオキシン問題への対応
ダイオキシン類は、試験研究用途で作られる以外には意図的に作られるものではなく、炭素、酸素、水素、塩素が熱せられるような過程で自然にできてしまう副生成物である。現在の主な発生源は、ごみ焼却による燃焼であるが、そのほかにも様々な発生源がある。我が国における平均的な環境中での濃度は、平成10年度の調査によると、大気中では1立方メートル当たり約0.23pg-TEQ(ピコグラム=1兆分の1グラム)、土壌中では1グラム当たり約6.5pgである。日本人の一般的な食生活で取り込まれるコプラナーPCBを含めたダイオキシン類の量は、1日に約100pg、人の平均体重を50kgと仮定して体重1kg当たり約2.0pgと推定されている。その他呼吸により空気から取り込む量が約0.07pg、手に付いた土が口にはいるなどして取り込まれる量が約0.0084pgと推定され、人が1日に平均的に摂取するダイオキシン類の量は合計で、体重1kg当たり約2.1pgと推定される。この水準は、耐容1日摂取量(4pg/kg/日)を下回っており、健康に影響を与えるものではない。
しかしながら、ダイオキシン問題は、将来にわたって、国民の健康を守り、環境を保全するために政府を挙げて取り組んでいくべき重要な課題である。このため、政府は、ダイオキシン類による環境汚染及び人の健康をめぐる諸対策について、関係省庁相互の緊密な連絡を確保し、その効果的かつ総合的な推進を図るため、平成11年2月にダイオキシン対策関係閣僚会議を設置し、同年3月に「ダイオキシン対策推進基本指針」を決定したところである。また、同年7月には、「ダイオキシン類対策特別措置法」が成立し、平成12年1月から施行された。
建設省としては、これら法律及び指針に基づき、関係省庁とも協力しつつ、建設廃棄物のリサイクル、対策に必要な技術開発・調査研究、所管施設の適切な維持管理等の施策の的確な執行を図り、ダイオキシン問題の解決に資するよう適切に対応していくこととしている。
これまでの主な取組み及び今後の取組みは次のとおりである。
・建設廃棄物のリサイクルの推進
・調査研究・技術開発(河川におけるダイオキシン類汚染実態調査、汚染土壌処理工法、建設廃棄物発生抑制に関する技術開発)の推進
・官庁施設における廃棄物の発生抑制・適正処理
ロ 内分泌攪乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)問題への対応
内分泌攪乱化学物質の問題は、生態系や人の健康に様々な影響を及ぼすことが懸念される重要な課題である。
このため、建設省においては、平成10年度より、健全な水環境(河川・下水道)、住環境(住宅)の構築のために必要な調査研究を推進している。
これまでの主な取組み及び今後の取組みは次のとおりである。
(水環境関係)
1) 平成10年4月に「流域水環境研究会」(座長:楠田哲也 九州大学教授)を設置し、関係省庁と連携を図りつつ調査を実施
・全国の主要な河川における水質、底質及び魚類の調査
・下水処理場への流入水・放流水調査
2) 平成10年度に「下水道における環境ホルモン対策検討委員会」(委員長:松尾友矩 東京大学教授)を設置し、調査・検討を実施
・下水性状に応じた分析手法の開発
・水処理、汚泥処理工程における実態把握
・高度処理工程における実態把握
3) 人や生態系に対する安全性を高めるための研究施設として、下水・河川における水系リスクマネジメント実験施設を整備
(住環境関係)
4) 内分泌攪乱化学物質等の物質や温室効果ガスの排出量の評価手法に関する研究のレビュー、実態に関するデータの収集
5) 住宅の構造・工法・材料の別等による物質の排出量の評価手法の確立のための検討
6) 物質の排出量を低減するための方策の検討