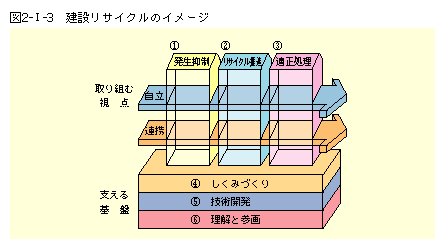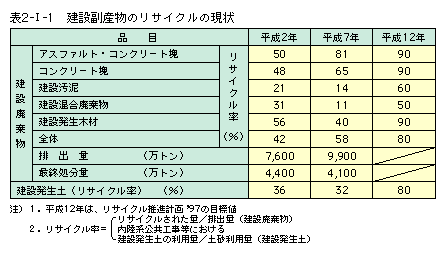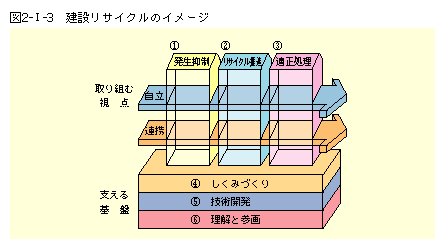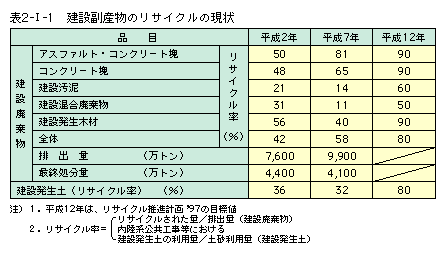(3)建設リサイクルの推進
建設リサイクルは、発生抑制、リサイクル推進、適正処理の3つの基本施策と、これを支える仕組みづくり、技術開発、理解と参画の3つの基盤施策の具体化実施により、建設リサイクル推進計画'97(平成9年10月策定)の目標値の達成を目指している(図2-I-3、表2-I-1)。
イ 建設リサイクルの理念・基本目標
「建設リサイクル」とは、建設副産物の発生を抑制するとともに、リサイクルの徹底を図り、新材投入量の可能な限りの削減に努め、処分量ゼロを目指すことで、建設資源の省資源化及び循環利用を推進することを基本目標とする概念である。
ロ 建設副産物の現状
建設副産物実態調査の結果によれば、平成7年度の建設廃棄物の排出量は約1億トンで全産業廃棄物の約2割を占め、建設発生土の排出量は約4億4,000万立方メートルとなっており、リサイクル率は、建設廃棄物で58%、建設発生土は32%となっている。
品目別では、アスファルト・コンクリート(いわゆるアスファルト)塊とコンクリート塊はリサイクル率が上昇している。しかし一方で、そのほかの品目は、低迷しているのが現状である(表2-I-1)。
ハ これまでの建設リサイクルに向けた取組み
建設省では現在まで、「再生資源の利用の促進に関する法律」(リサイクル法)の施行(平成3年10月)後、経済性にかかわらず、工事現場から一定の距離以内に他の建設工事及び再生資源がある場合に再生資源の利用及び再資源化施設の活用を原則とする措置(リサイクル原則化ルール)の周知徹底や、建設副産物適正処理推進要綱の策定(平成5年1月)と遵守の徹底など、様々な側面から建設リサイクルを推進する施策を講じてきた。
その結果、公共工事から特に多く発生するアスファルト・コンクリート塊とコンクリート塊のリサイクル率の上昇につながっている。
平成12年度は、上記施策の一層の徹底を図るとともに、リサイクル関連技術の開発の推進等を図り、他省庁との連携を図りつつ、建設リサイクルの基本施策・基盤施策のより一層の推進を図る。
ニ 建設リサイクル推進計画'97
建設省では、以上で示した状況等を踏まえ、建設リサイクルの推進に向けた基本的考え方、目標、具体的施策を内容とする計画として、「建設リサイクル推進計画'97」を策定した。
本計画の中では、リサイクル率を平成12年度に80%とすることを目標としており、この計画に基づき、建設副産物の発生抑制、リサイクルの促進及び適正処理の推進に際して、必要な施策を取りまとめている。また、重点的に検討を進める課題としては、1)建設工事における適正な解体・リサイクル促進のための新たな仕組みづくり、2)再資源化施設及び最終処分場等の適正な立地促進方策等の2点について、主要課題と検討事項を整理している。
今後は、重点的に検討を進める課題の検討状況や行動計画の実施状況をみながら、必要に応じて本計画を見直すことにしている。
ホ 工事発注者の責務の徹底
公共工事発注者の責務を徹底するため、計画・設計段階でのリサイクル計画書の策定義務付けなどの行うべき事項を平成10年8月に「建設リサイクルガイドライン」として取りまとめ、公共工事発注者に対してその徹底を図っている。
また、平成9年度の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正等も踏まえ、平成10年12月に建設副産物の適正な処理に当たって必要な基準を定めた「建設副産物適正処理推進要綱」を改定し、民間工事も含めて発注者及び施工者に対し、その徹底を図っている。
さらに、公共事業におけるリサイクル事業を推進するため、建設発生土の再利用促進のための情報交換システムを平成11年4月から運用開始している。
ヘ 建築解体廃棄物の分別・リサイクルの推進
建設廃棄物のなかでもリサイクルの取組みが特に遅れている建築解体廃棄物の分別・リサイクル推進方策について、平成11年10月「建築解体廃棄物リサイクルプログラム」を取りまとめた。このプログラムを踏まえて、建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付けや解体工事業者の登録制度を創設することを内容とする「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が制定された。
ト 建設汚泥のリサイクル推進
建設汚泥は、リサイクル率が14%と低迷しており、そのリサイクルを推進するため平成11年3月に建設汚泥再生利用基準、平成11年10月に建設汚泥リサイクル指針を作成している。