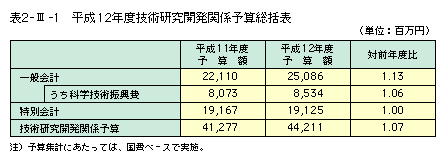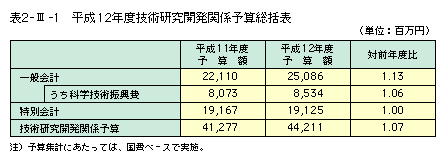2 平成11年度、12年度の主要施策
(1)建設技術研究開発について
イ 建設技術開発会議
建設技術開発会議(建設大臣の私的懇談会)においては、現在、建設省における今後の技術研究開発のあり方について審議を行っており、ここでの審議を踏まえ、新たな技術研究開発を推進することとしている。
また平成11年3月に設置された建設技術開発会議評価部会は、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月7日内閣総理大臣決定。以下「大綱的指針」という)を踏まえ、建設省の附属研究機関等の運営全般の評価を厳正に実施するため、平成12年3月に第1回部会を開催し、技術研究開発の評価の基本的枠組みに関することや、機関評価の実施に関すること等について審議を行った。
ロ 建設産業技術戦略
建設分野の産業技術力強化を目指して、土木、建築、測量等の分野における産学官の代表者で構成される「建設産業技術戦略検討会」が発足し、平成11年11月から4回の検討会を開催し、平成12年3月に「建設産業技術戦略」が策定された。
当該戦略においては、「ものの豊かさと心の豊かさを両立しうる社会の実現」を21世紀の目標として掲げ、これを実現するための建設産業技術の革新を推進するため、1)技術研究開発システムの改革、2)建設市場の改革、3)技術研究開発支援の強化、4)国際競争力の強化、5)人材育成システムの改革、6)人文・社会科学を取り入れたソフト技術革新の加速化、という6つの総合戦略が打ち出されている。
ハ 建設省における技術研究開発の取組み
1) 技術研究開発関係予算
平成12年度の建設省における技術研究開発関係予算としては、総額412億円を計上しており、厳しい財政状況のもと、対前年度伸び率で7%の伸びを示している。特に科学技術振興費については、6%増と高い伸び率を示している。
2) 技術研究開発の評価の実施
科学技術基本計画に基づき決定された大綱的指針を踏まえ、建設省として実施すべき技術研究開発の基本的枠組み(評価の基本理念、評価対象、評価事務局・体制、評価時期・事項等)を明確化するとともに、省内関係部局等における研究課題の評価を適切に実施している。
3) 総合技術開発プロジェクト等による研究開発
イ)総合技術開発プロジェクト
建設技術に関する重要な研究課題のうち、特に緊急性が高く、対象分野の広い課題を取り上げて、産学官の連携により、総合的、組織的に研究を実施する制度として「総合技術開発プロジェクト」を実施している。
平成12年度は、「GISを活用した次世代情報基盤の活用推進に関する研究」「建設分野におけるダイオキシン類汚染土壌対策・廃棄物発生抑制技術の開発」の2課題について新規着手し、10課題について継続実施する。
ロ)建設技術の先導研究による研究開発
建設分野の先端的独創的研究開発は、技術的熟度等の問題から、直ちに本格的な研究開発を実施することが困難なテーマが存在する。建設技術の先導研究は、このような研究課題について、体系的、効果的に研究開発を推進していくため、本格的な研究開発の前段階で、予備的、基本的な内容の調査、研究等を実施する制度である。
平成12年度は、「都市型建設技術の開発」「住宅・市街地計画における総合的な環境負荷低減最適化手法の開発」の2課題について新規に着手し、3課題について継続実施する。
ハ)官民連帯共同研究による研究開発
総合技術開発プロジェクトが広範な範囲を総合的、横断的に研究するのに対し、官民連帯共同研究は、単一分野の課題について、早期の成果を期待したい場合に利用する制度である。特に民間に革新的な技術の芽がありながら、単独での技術開発では、リスクが大きい場合などにおいて、その促進を図ることが可能な制度である。
平成12年度は、「既存コンクリート構造物の高度診断技術の開発」「用途複合型集合住宅の建設システムの合理化」「先進的なリサイクル技術の開発」の3課題について新規着手し、4課題について継続実施する。
ニ 附属機関等における技術研究開発の取組み
1) 土木研究所
土木研究所は、土木技術に係る我が国唯一の総合研究機関として、現在及び将来における国民のニーズ、行政ニーズに対応した建設技術の研究開発とその成果の普及に努めている。
平成11年度には「第5次土木研究所研究五箇年計画(平成11年度〜平成15年度)」を策定し、21世紀に向けた今後5年間の研究開発の基本方針、具体的な研究課題及び研究開発を円滑かつ効果的に行う方策について規定した。
ここでは、土木研究所の使命と役割を、1)国土マネジメントに必要な技術体系を提示し、その研究体制を構築する(研究開発の体系と体制のコーディネーション)、2)関係研究機関との連携を保ちつつ、自ら行うべき研究を実施する(研究活動)、3)これらの活動によって得られた知見、成果を基に関係機関に対して技術支援を行う(技術支援活動)としている。また、土木研究所が実施する研究課題を56の研究群にまとめ、1)国土マネジメントの方向性に関する研究、2)安全で安心できる国土の形成のための研究、3)自然生態系と地球環境の回復・保全に関する研究、4)多様性に富んだ社会、快適な地球環境の創出に関する研究、5)経済活力の維持と効率的な建設行政の執行に関する研究の5つの分野に整理し、研究の全体体系を提示した。
具体的な研究の実施に当たっては、研究の性格を、社会・行政ニーズが極めて高く、関連分野を体系化し、ソフト面での対応も含めて、組織横断的、重点的に取り組む「プロジェクト研究」(28課題)と、事業部門毎、研究部門毎の課題を解決するために実施し、研究ポテンシャルの向上に必要な「基盤研究」に大きく分類し、進めることにしており、特にプロジェクト研究については、社会的・行政的な緊急性等を考慮し、優先度の高いものから順次「重点研究プロジェクト」に採択して実施する。
平成12年度は、前年度以前から既に実施している12課題に加え、以下の新規3課題に取り組むことにしている。
1)国土マネジメントの方向性に関する研究
2)総合的な流域土砂管理に関する研究
3)快適な冬期交通を確保するための道路管理水準に関する研究
また、これら重点研究プロジェクトに対し、学識経験者や専門家等の第三者による外部評価を実施し、適切かつ効率的な実施に努めている。
2) 建築研究所
建築研究所は、建築・住宅・都市の分野での我が国唯一の国立試験研究機関として、国民のニーズや社会的変化に対応した技術の研究開発、及びその成果の普及に努めているところである。
平成11年度に「建築研究所研究開発五箇年計画」を改定し、これに基づいて研究開発を進めている。研究開発の目標として、1)国民の生命・財産への安全・安心の確保、2)市場の技術的基盤の整備や社会の誘導、3)長期的社会動向への対応、4)豊かで質の高い国民生活の実現、5)国際活動への貢献を設定している。
平成12年度における主な研究開発課題等は以下の通り
イ)国民の生命・財産への安全・安心の確保
用途複合型集合住宅の建設システムの合理化
高層部を集合住宅、低層部を商業施設等とする複合用途建築物は、都市部において合理的な形態である。このような建築物を、構造安全性の視点から、合理的に計画・設計・施工するためのシステムを開発する。
ロ)市場の技術的基盤の整備や社会の誘導
性能を基盤とした建築物の設計・評価及び関連社会基盤に関する研究
建築基準法が仕様規定から性能規定に移行していることを踏まえ、建築物の性能基準、評価基準、評価方法等を研究し、またそれを誘導するための社会制度の整備に関する研究も併せて行う。
ハ)長期的社会動向への対応
住宅・市街地計画における総合的な環境負荷低減最適化手法の開発
住宅・市街地において、省エネルギー、省資源、廃棄物の抑制等、環境負荷の低減を進めることが必要である。それぞれの環境負荷低減目標は、お互いに相反する要素があり、それらを総合的に評価する手法を開発する。
ニ)豊かで質の高い国民生活の実現
投資効率向上・長期耐用都市型集合住宅の建設・再生技術の開発
豊かで質の高い国民生活を実現させるためには、長期耐用可能な都市型集合住宅の供給を促進する必要がある。このため、1)スケルトン・インフィル分離による長期耐用型の集合住宅の建設・供給技術の開発、2)既存ストックの長寿命化技術の開発、3)円滑な建替手法の開発を行う。
ホ)国際活動への貢献
i)国際共同研究
国際共同研究として、多国間共同研究(性能を基盤とした建築物の設計・評価及び関連社会基盤に関する国際共同研究)や日米共同研究(木造住宅の動的崩壊挙動の解明と制御に関する日米共同研究)を行うこととしている。
ii)国際地震工学研修の推進
ヘ)研究開発に係る評価への取組みについて
平成10年度より建築研究所研究評価委員会において、主要な研究課題について、事前評価・事後評価を行っている。加えて、平成12年度は機関評価を実施し、効果的かつ効率的に研究を進めていくこととしている。
3) 国土地理院
国土地理院は、測量・地図を所掌する国家行政機関として、測量に関する基本的施策の企画立案、測量に関する各種技術基準の制定、測量事業、測量に関する国際協力、公共測量の指導・調整等を実施するとともに、これらの測量行政を支援するため、基礎から応用にまたがる幅広い研究開発を行っている。国土地理院が行った研究開発の成果は、自らの業務の遂行に利・活用されるだけでなく、我が国の測量技術の発展にも大きく貢献してきた。
測量を取り巻く近年の技術の進展は、情報技術、宇宙技術の発達により非常に目覚ましいものがある。また、測量が対象とする分野が単に位置を測るものから、測量技術の応用により地殻変動観測や環境調査等の周辺分野へ拡大されてきた。さらに、地域的にも、地球規模の広がりをもった観測・解析が必要となってきている。このような変化も踏まえ、国土地理院では、「国土地理院研究開発五箇年計画」に基づき、地殻変動、宇宙測地及び地理情報解析分野等の研究を推進している。また、その推進に当たっては、国土地理院研究評価委員会等による適切な評価を受けるとともに、研究成果の公開と政策への反映を通じた国民への還元に努めている。
平成12年度は、以下の課題に重点をおいて研究開発を実施する。
イ)日本列島周辺のスローアースクエイク(ぬるぬる地震)の地殻変動データによる検出に関する研究
これまで蓄積されたGPS連続観測データを精査し、地震計等その他の連続観測データと比較検討することにより、日本列島の周辺で発生しているスローアースクエイクを検出し、その発生様式を解明するとともに、応力分布、活断層分布などとの関連について研究する。
ロ)合成開口レーダの解析モデルに関する研究
高速処理のためのデータ処理技術の改良と処理ソフトウエアの開発及びGPS連続観測データを用いて、干渉SARの視線方向の変動を上下成分と水平成分に分離する手法の開発並びに航空機搭載型SARによる地殻変動量の計測技術の可能性について研究する。
ハ)多次元GISによる地理情報解析に関する研究
多次元GISの実用化を目的として、地震による液状化や土砂崩壊等の自然災害に対する地盤災害危険度評価を例として、多次元GISによる地理情報解析技術の適用手法について研究する。
ニ)火山性地殻変動のダイナミックモデルに関する研究
火山活動による災害を最小限に食い止めるため、火山のダイナミックな活動をモデル化し、火山地域におけるGPS連続観測等の地殻変動データを準リアルタイム解析して火山活動の推移を逐次予測するシステムの開発について研究する。
ホ)VLBIとGPSの高精度コロケーションに関する研究
VLBIとGPSの両観測網を高精度に結合するコロケーションに関する調査研究を実施するとともに、解析法の違いによる系統的変動量を検討し、mmレベルでの両技術の互換性の確立について研究する。
ヘ)ニューラルネットによる画像情報の判別手法に関する研究
脳内の情報処理を模したニューラルネットワークの手法を用い、分光情報と形状やパターンの情報を同時に処理し、土地利用を分類する方法について研究する。
ト)GPS連続観測による上下地殻変動検出手法開発に関する研究
全国にほぼ均一に配置されているGPS連続観測データを用いて、全国の上下方向の地殻変動の進行状況を解明する手法を開発する。
4) 技術事務所
技術事務所においては、地域に根ざした技術開発を行うことにより、各工事事務所が抱える技術的諸問題を解決し、各地方建設局における事業の円滑な実施に資するため、施工・維持管理技術の改善、建設機械の開発・改良及び技術的な基準の作成等を各工事事務所と連携をとりながら実施している。特に建設省技術五箇年計画や各分野技術五箇年計画に定められた技術開発テーマについては重点的に取り組んでいくこととしている。
ホ 民間技術開発の支援制度
1) 新技術の審査証明制度
建設技術評価制度は、行政ニーズに基づいた、個別分野の研究課題について、官側で技術開発目標を示し、これに対し、民間が研究開発を実施し、開発された新技術の評価を官側で行う制度である。昭和53年度の創設以来、ここで開発された多くの技術が公共事業等で積極的に活用されている。しかし、平成9年度以降当制度は休止しており、現在は「公共事業のための新技術活用システム」の運用へと移行している。
技術審査・証明事業は、民間が自主的に開発した技術について、建設大臣が認定した機関(平成12年4月1日現在で14団体)において、技術開発の内容を審査・証明するものである。審査証明された民間技術に関する情報はJACIC NET((財)日本建設情報総合センターが管理運営している建設情報ネットワーク)等の新技術情報システムを利用して現場技術者に伝達している。
2) 融資・税制等
建設事業に関する技術開発を民間において実施するには、多額の資金と長い投資期間が必要とされる。
このため、平成元年度より国の研究機関と共同で実施する建設新技術研究開発に対して、また平成6年度より安全の確保・省エネ推進等の政策的意義の高い民間企業の建設新技術研究開発に対して、日本開発銀行による低利融資を行い、建設新技術の開発促進を図ってきた。
平成11年度からは、新技術開発にかかる日本開発銀行融資制度の整理・統合が行われた。
また、平成11年10月に日本開発銀行は廃止され、新たに設立された日本政策投資銀行が上記の融資制度を継承した。
なお、我が国の産業構造を高付加価値化していく上で不可欠なリスクの高い先端的事業に対して超低金利が適用される「先端産業育成特別融資制度」は平成12年度まで延長措置された。
税制面からの民間技術開発支援としては、従来より増加試験研究費の税額控除、中小企業技術基盤強化税制があり、建設産業における積極的な技術開発の促進に貢献している。平成11年度からは、増加試験研究費の税額控除は、比較試験研究費の額を過去5年間の各期の試験研究費のうち多い方から3期分の平均額として、当期の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分を特別税額控除とすることとなった。
3) 共同研究・研究者の交流等
民間、学界、行政の関係機関等の相互の連携や異分野、諸外国との連携など、各種の連携・交流を促進するため、体制整備、制度改正等を行う必要がある。
そのため、共同研究より相応の貢献が認められる民間企業等の知的財産権の保護を強化し、共同研究への民間企業への積極的な参加を図るため、平成9年度には、共同研究の成果として得られた特許等に係る当該相手先民間企業等への優先実施権の付与について、その期間を従来の「共同研究終了後から5年を超えない範囲」から「特許出願日から10年を超えない範囲内」に拡充した。
また、産学官の連携・交流の促進のため、国・公立大学と国立試験研究機関等との連携を推進することとしている。
ヘ 公共事業における新技術活用・普及の推進
新技術活用促進システムの推進
新技術活用促進システムは事業を直接行う地方建設局が、統一的な基準、体制により、広く民間等からの新技術情報を随時収集し、その現場適用性等の確認を行い、有用な新技術の公共事業への円滑かつ的確な活用・普及を図る体系的システムである。
具体的には、全ての地方建設局において、窓口を設置し、いつでも情報の提供を受けつけており、特に重点的に収集したい情報について、インターネット等により発信している。そして、最寄りの地方建設局に提供された情報は、電子情報ネットワークにより、全ての地方建設局工事事務所等で新技術情報として共有化している。
次に、収集した新技術のうち、政策ニーズや現場ニーズの高いものから新技術の成立性、現場における適用性、技術基準類の整備の必要性等に関する評価を行い、新技術を活用する事業方法(試験フィールド事業、技術活用パイロット事業、一般工事)を明確にしている。
さらに、地方自治体、公団等にも必要な情報の提供を行い、公共事業全般における有用な新技術の積極的な活用を図っている。
最後に、活用した新技術のフォローアップを適切に行い、特に優れたものについては、全国的な活用展開、各種技術基準等への反映を図っている。