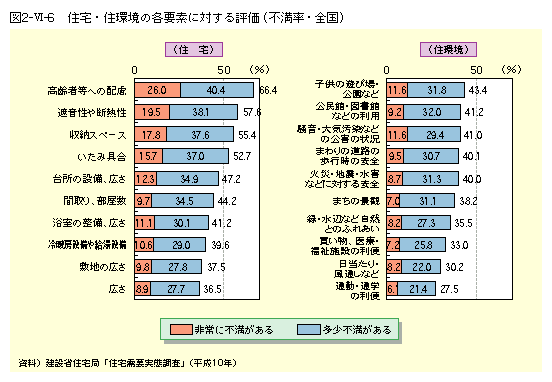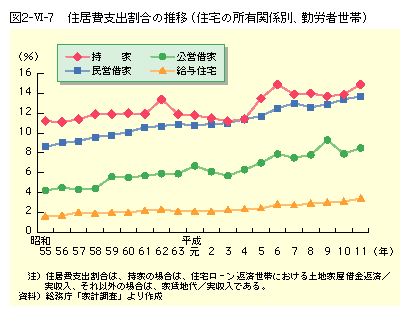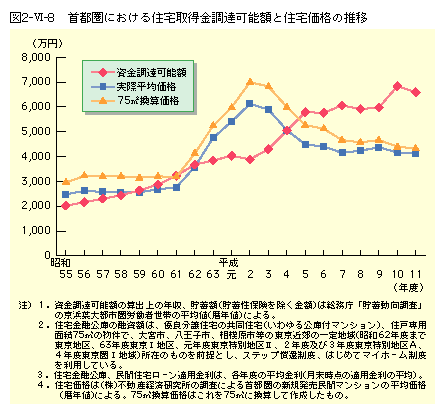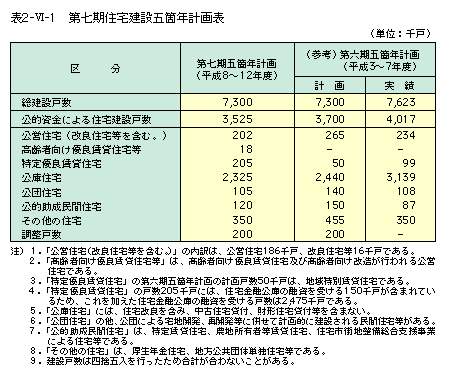(2)住宅・宅地政策の課題と展開
イ 住宅事情の現況と問題点
1) 住宅事情の現況
終戦直後の420万戸の住宅不足を背景に、戦後の住宅政策は住宅の量的確保の推進に力点がおかれた。その結果、昭和40年代には1世帯1住宅の目標を達成し、量的不足は解消された。昭和50年代以降、居住水準の目標を設定し住宅の質的向上を図っているところである。
平成10年の住宅・土地統計調査によれば、全国の住宅数は、総世帯数4,436万世帯に対して5,025万戸となり、この結果、1世帯当たりの住宅数は1.13戸に達し、戸数面での充足は進んでいる。
住宅の質的な面については、1戸当たりの平均床面積が92.4m
2に達し、全体として着実な向上が見られるものの、その内訳をみると、持家122.7m
2、借家44.5m
2と差が生じており、依然として、標準的な世帯向けの賃貸住宅ストックは極めて少ない状況にある。
また、世帯と住宅との対応関係を示す居住水準についてみると、全世帯が確保すべき目標である最低居住水準に満たない世帯は、平成5年の7.8%から平成10年には5.1%となり、着実に最低居住水準未満世帯率は減少している。
しかしながら、平成10年住宅・土地統計調査によれば、三大都市圏の最低居住水準未満の世帯は、7.0%であり、全国平均5.1%よりも高い。特に所有の関係では借家が13.9%、さらに借家に住む3〜5人の世帯では、19.4%と高くなっている。
また、平成10年住宅需要実態調査によれば、約3分の1の世帯が住宅及び住環境に不満を感じている。特に、住宅の広さに限らず、住宅性能、住環境についての不満が高くなっている(図2−VI−6)。
2) 家計の住居費支出の現況
世帯の収入に対する住居費支出(住宅ローン返済額・家賃等)の割合は、過去ほぼ一貫して漸増しており、勤労者世帯の平均で9%台となっている。ただし、住居費支出割合は地域別・住宅の所有関係別の格差が大きい。京浜葉大都市圏をはじめとした大都市圏域では値が高くなり、住宅の所有関係別では、民営借家に比べて公営借家・給与住宅の値が著しく低くなっている(図2−VI−7)。
3) 住宅取得能力の推移
住宅の取得しやすさの指標としては、住宅価格と年収倍率の対比(いわゆる年収倍率)が用いられることが多いが、より正確には貯蓄額や住宅金融公庫等の融資条件等を加味した資金調達可能額でみることができる。首都圏で75m
2(3人世帯の都市居住型誘導居住水準)の新規分譲マンションを取得する場合で試算した結果が、図2−VI−8である。平成3年以降、公庫融資の拡充や金利低下により資金調達可能額が上昇しており、住宅価格の下落と相まって、住宅取得能力が概ね向上していることがわかる(図2−VI−8)。
ロ 新たな住宅宅地政策の方向性
第七期住宅建設五箇年計画が平成12年度をもって終了することに鑑み、新たな計画の策定に当たって、住宅・住環境の現況及び社会経済状勢の変化に、より的確に対応するため、平成10年9月「21世紀の豊かな暮らしを支える住宅・宅地政策はいかにあるべきか」について、建設大臣から住宅宅地審議会に対して諮問がなされ、平成11年9月にその中間報告がなされた。
同中間報告では、今後の住宅宅地政策の方向性を考えるに当たって、次の要素が重要であるとされている。
1)これまでは土地取得に強い関心を置いた住宅宅地資産の形成が行われてきたが、成熟社会においては、居住サービスを生み出すものとしての住宅宅地の確保の側面が強調されること
2)国民の価値観、家族形態の多様化に対応して、「居住」ニーズが多様化すること
3)成熟経済への移行、環境制約等から限りある資源を有効に活用していく必要性が高まること等から良質な住宅宅地ストックを適切に維持管理し、長く使っていくという視点が必要となること
こうした点を踏まえ、的確な住宅宅地政策の転換を図るに当たっては、次の2つの視点が重要であるとされている。
1) 市場重視
国民の価値観、家族形態の多様化に対応して、国民生活の基盤である「居住」についても競争を通じた適正な価格の下で、多様な選択が可能となるようにしていくことが必要である。これらの多様な選択は市場機能の活用により実現することが最も効率的である。このため、市場の歪みにより自由な選択が阻害されている場合には、その阻害要件を除去し選択の幅を拡げていく等の取組みが必要である。
2) ストック重視
成熟社会において、自由に住替えを行うことにより、ライフスタイル、ライフステージに応じた適切な住宅を選択したいという要望に対応するため、社会全体に備わっている住宅ストックを有効に活用していくことが必要である。
以上を受け、新たな住宅政策、宅地政策の基本的方向性は以下のように示されている。
ハ 住宅政策の基本的方向性
今後の住宅政策の基本的方向性は、「市場を通じて国民が共用しうる良質な住宅ストックを形成し、管理し、円滑に循環させることのできる新しい居住水準向上システム」の確立を目指していくことである。このため、
1)少子・高齢社会、人口減少社会の本格的到来を目前に、現在の住宅ストック・居住環境を、長期的な視点から良質なものにいかにして再生していくか
2)既存ストックを活用しつつ国民の多様なニーズに対応するため、ストックの流動化を如何にして実現するか
という課題を市場の機能を活用しつつ、解決していくことが必要となっている。
以上のことから、
1)ストック重視、市場重視の住宅政策体系を支える計画体系の再編
2)高度経済成長期ストックの更新等を契機とした住宅ストック・居住環境の再生
3)既存ストック循環型市場の整備による持続可能な居住水準向上システムの構築
4)少子・高齢社会に対応した「安心居住システム」の確立
5)成熟社会の住宅政策を支える公民の役割分担
によって住宅政策体系の再編を進めていく必要がある。
ニ 宅地政策の基本的方向性
経済社会環境の変化を背景としつつ、従来からの宅地の大量供給の推進の方針に代わる、新しい宅地政策の理念は以下のとおり。
1) 消費者・生活者志向型の宅地供給支援
これまでの、大都市圏の都心通勤可能圏内で一定量の宅地供給をとにかく確保するという大量供給至上主義から、職住近接、都心居住による利便性の向上、ゆとりある生活空間の確保等のニーズに即した良質な宅地供給、消費者・生活者志向型供給に対する支援を重視する。
2) アフォーダブルな住宅宅地取得等への支援
ライフステージに応じたアフォーダブルな住宅宅地の取得、買替え、住替えが活発化するよう条件整備をする。
3) 環境と安全性の重視
環境面を重視した宅地供給の推進を図るとともに、環境負荷の抑制を図る。造成宅地の土砂災害に対する防災性の向上等を支援する。
4) 既存の宅地の有効利用
新規宅地開発の重視にかえ、既成市街地内の工場跡地、市街化区域内農地、既存住宅地等の活用による宅地供給の推進と宅地の細分化防止、老朽木造密集市街地の改善等による良好な市街地形成を重視する。
5) 高齢社会への対応
宅地供給の時点から、バリアフリーの視点を取り入れるとともに、高齢社会に対応したコミュニティの維持・形成を図る。
ホ 第七期住宅建設五箇年計画の推進
平成8年3月に策定された第七期住宅建設五箇年計画においては、人生80年時代において、国民一人一人がそれぞれの人生設計にかなった住まい方を選択し、実現できるよう、21世紀初頭に向け、国民の住生活の質の向上を目指した住宅政策を積極的に推進することとし、平成8年度以降5年間の住宅・住環境整備の目標を以下の通り定めている。
1) 基本的目標
イ)国民のニーズに対応した良質な住宅ストックの整備
良質な住宅ストックの整備のため、住宅金融公庫融資や住宅税制による住宅取得の支援、公営、公団、公社住宅等の供給、住宅リフォームの推進、住宅流通基盤の整備、建て替えの促進等を図る。
ロ)安全で快適な都市居住の推進と住環境の整備
21世紀に向かって都市に住む多数の人々の住生活の質の向上を図るため、良好な環境空間を備えた住宅市街地の整備、都心部における共同住宅の供給、地震等の災害等への対策として老朽住宅密集市街地等の整備等を推進する。
ハ)いきいきとした長寿社会を実現するための環境整備
人生80年時代において、いきいきとした長寿社会を構築するため、バリアフリー仕様の住宅の整備、高齢者に対する公共賃貸住宅の重点的な供給、福祉施策等との連携の充実等を推進する。
ニ)地域活性化に資する住宅・住環境の整備
定住人口の増大やふるさとづくりなどの地域の活性化、地域独自の需要に応じた住宅地づくりを推進するため、地方公共団体による住宅マスタープラン策定の推進、地域活性化に資する公的住宅等の供給及び宅地の開発等を図る。
2) 居住水準等の目標
居住水準等については、以下の目標を達成することとする。
長期的視点に立って、住宅全体の質の向上を誘導するための広さや設備について定めた指針である誘導居住水準(4人世帯 共同住宅91m
2、一戸建123m
2)については、平成12年度までに全国で半数の世帯が、その後できるだけ早期にすべての都市圏で半数の世帯が確保できることを目標とする。
このため、平成12年度において住宅1戸当たりの平均床面積を約100m
2とすることを目標として良質な住宅ストックの形成に努めるものとする。
また、すべての世帯が確保すべき住宅の広さや設備について定めた指針である最低居住水準(4人世帯 50m
2)については、大都市地域の借家居住世帯に重点をおいて水準未満の世帯の解消に努めるものとする(
資料2−2−3参照)。
性能及び設備の目標については、本格的長寿社会となる21世紀の住生活に対応するために住宅が備えるべき段差の解消等のバリアフリー性能、遮音や断熱性能、耐久性能等を盛り込む等、所要の拡充を図り、その着実な改善を図る。
3) 住宅建設戸数
計画期間中における民間を含めた総住宅建設戸数については、世帯の形成、住み替え、建て替え等による住宅需要を充足するため、適正な規模、構造及び性能・設備を備えた730万戸を見込んでいる。
また、公的資金による住宅建設の量としては、居住水準等の目標を達成するため、住宅金融公庫を用いて持家取得を行う中堅所得者、民営借家の家賃を支払うことが困難な低所得者、子育てを行う中堅所得者等を対象として公的援助を行うこととし、所要の戸数352.5万戸を見込み、これらの着実な建設を図ることとしている(表2−VI−1)。
なお、この戸数は、計画策定当初360万戸を見込んでいたものを、財政構造改革の趣旨等を踏まえて平成10年1月に変更したものである。
ヘ 公的住宅制度の見直しによる市場の誘導、補強・補完
第七期住宅建設五箇年計画期間における諸施策の推進に当たっては、公的住宅供給を、民間との適切な役割分担の下、住宅市場を補強・補完するものとしてその推進を図ることとしているが、公団住宅、住宅金融公庫融資の主要制度について、事業の重点化と政策誘導機能の強化を図る方向で所要の見直しを行ってきている。
1) 都市基盤整備公団の事業の展開
イ)住宅・都市整備公団が果たしてきた役割と公団改革
住宅・都市整備公団は、昭和30年の日本住宅公団の設立以来、都市への人口の急速な集中に伴う住宅不足の解消という観点から、住宅事情の改善の必要性が特に著しい大都市地域等において住宅・宅地の大量・直接供給を中心的な目的として業務を展開し、これまでに約150万戸の住宅と約12,600haの宅地供給、135地区における都市再開発事業を実施してきた(平成11年度末実績)。
このように、住宅・都市整備公団は、国民の住生活の安定向上等に多大な貢献をしてきたところであるが、近年の民間住宅市場の成長により、公団による分譲住宅の直接供給は概ねその目的が達成されたと考えられる。その一方、我が国の大都市地域等においては、都市の基盤が充分整備されることなく人口や諸機能が集中した結果、都心居住・職住近接の促進、防災性の向上、拠点市街地の形成、土地利用の整序等、市街地の整備改善が大きな課題となっており、またファミリー向けの良質な賃貸住宅は依然として必要量が供給されていないといった状況にあり、真の豊かさを実感できる都市生活が確保されていない大きな原因となっている。
これらを踏まえ、「特殊法人等の整理合理化について」(平成9年6月閣議決定)において、住宅・都市整備公団については、平成11年の通常国会において法律改正を行い廃止し、分譲住宅業務からは適切な経過措置を講じた上で撤退し、都市開発・再開発業務、政策的に特に必要とされる賃貸住宅業務及び賃貸住宅の管理業務について業務内容を調整した上で新たに設立する法人に移管することとされた。これを受け、都市基盤整備公団法案が国会に提出され、平成11年6月に都市基盤整備公団法が公布、同年10月に新たに都市基盤整備公団が設立された。
ロ)都市基盤整備公団の役割
都市基盤整備公団は、地方公共団体、民間事業者等との協力及び役割分担の下に、人口及び経済、文化等に関する機能の集中に対応した秩序ある整備が十分に行われていない大都市地域等において、居住環境の向上及び都市機能の増進を図るための市街地の整備改善並びに賃貸住宅の供給及び管理に関する業務を行い、並びに都市環境の改善の大きい根幹的な都市公園の整備を行うこと等により、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし、これまでの「住宅事情の改善のための住宅宅地の大量供給」から「健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動の基盤整備」へと業務の重点を移行した。
具体的には、市街地の整備改善に関する業務として、
イ)都心居住・職住近接を実現するための住宅市街地の整備
ロ)土地の有効利用の促進と良好な市街地の整備
ハ)都市構造再編のための拠点市街地の整備
ニ)密集市街地の整備改善
ホ)防災公園と周辺市街地の一体的整備
ヘ)地方公共団体のまちづくりへの支援
賃貸住宅の供給及び管理に関する業務として、
イ)大都市地域における良質な賃貸住宅の供給
ロ)既存賃貸住宅ストックの適切な活用
ハ)賃貸住宅の適切な管理
を重点的に実施している。
2) 住宅金融公庫融資制度の改善
住宅金融公庫融資制度については、良質な住宅ストックの形成を誘導しつつ、居住水準向上を推進するため、基準金利適用要件の見直し、割増融資制度の簡明化・重点化などを行ってきたところである。
さらに、平成12年の通常国会において、住宅金融公庫法を改正し、
イ)新築住宅について、一定の耐久性を要件化することと併せ、償還期間を35年に一本化
ロ)良質な中古住宅に対する融資の充実
ハ)計画的な共同・協調建替えを支援する「都市居住再生融資制度」の創設
を行うなど、成熟社会に向け、良質な住宅ストックの形成、維持・管理の促進、中古住宅の流通促進等の観点から、公庫融資制度の総合的な見直しを行った。
ト 密集住宅市街地の整備
老朽木造住宅等が密集している市街地は、大規模地震時に市街地大火が生じるおそれがある等、防災上危険な状況にあるため、従来から密集住宅市街地整備促進事業等により、老朽住宅等の除却や建替えの促進、道路・公園等の整備、従前居住者用住宅の建設等を総合的に進めてきたところである。また、平成9年11月には「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」が施行され、防災再開発促進地区の指定などにより、密集市街地の整備の一層の推進が図られることとなった。今後は、これらの法制度や補助制度の活用による集中的な事業の実施により、可能な限り早期に密集市街地の防災性の確保と居住環境の改善を図ることが重要である。
チ 少子・高齢社会に対応した住宅政策
本格的な高齢社会の到来に対応し、安心、快適で自立した高齢者居住を実現することが重要な課題となっている。このため、建設省においては、平成12年4月に「総合的な高齢者居住政策の基本的方向」を発表し、以下の方向性に基づき施策の推進を行うこととしている。
1) 高齢者の安心、快適で自立した生活を支える住宅・住環境整備の推進
特に民営借家についてバリアフリー化が遅れていること等を踏まえ、今後、高齢者に配慮された住宅ストックを形成するためには、次の3つの課題が重要である。
イ)高齢者世帯等が安心、快適で自立した生活を確保する基盤として、バリアフリー化され、高齢者の入居が確保された住宅ストックを社会全体として形成することが必要
ロ)必要なバリアフリー化レベルやバリアフリー化された住宅ストックに関する目標を掲げるとともに、社会全体の民間住宅ストック形成・更新にインパクトを与えうる政策の検討を行うことが必要
ハ)医療、職場、文化など、様々な生活機能がコンパクトに集約され、活気に満ちたまちなかでの生活等、いろいろな社会活動へのアクセシビリティの確保された高齢者の安心、快適で自立した居住を支える環境整備を推進することが必要
2) 公民の適切な役割分担による高齢者の多様なニーズに応えた居住選択の支援
イ)少なくとも高齢者というだけで入居に支障が生じない民間賃貸住宅市場の環境整備や高齢者の持家資産を活用した住替えをスムーズなものとする仕組み作りが必要
ロ)公共賃貸住宅の整備や既存ストックの有効活用により、民間賃貸住宅市場では適切な住宅を確保できない住宅困窮高齢者に対し、的確な支援を行うことが必要
3) 地域における高齢者を支える福祉と連携した生活環境の整備
イ)今後、高齢者関連施策が展開される場として、住宅の役割が大きくなることを勘案すれば、福祉施策との的確な役割分担に基づいた福祉施策と住宅施策の連携が必要
ロ)このため、例えば、在宅介護の場として活用可能な高齢者の身体状況に応じたきめ細かなストック形成、サービスの提供等を推進するととともに、総合的な情報提供体制の構築等が必要
一方で少子化問題に対応して、平成11年12月に少子化対策推進関係閣僚会議において策定された「少子化対策推進基本方針」においては、ゆとりある住生活の実現により子育てがしやすい環境を整備するため、良質なファミリー向け賃貸住宅の供給を促進するなど、子育て世帯の広くゆとりある住宅の確保を支援するとともに、夫婦で仕事や社会活動をしながら子育てがしやすい環境の整備を推進するため、職住近接した都心居住や、住宅と保育所等の子育て支援施設の一体的整備等を推進することとされている。
リ 住宅・建築物における環境対策
地球温暖化問題をはじめとした地球規模での環境問題の深刻化に伴い、住宅・建築分野においても、様々な環境問題への対策が必要となっており、平成10年6月、建築審議会において、住宅・建築分野の環境対策のあり方についての「建議書」が取りまとめられた。
この建議書では、住宅・建築分野に関する環境問題の現状と問題点として、
1)住宅・建築物の使用段階でのエネルギー消費量は増加しており、特に家庭部門のエネルギー消費増加が著しいこと
2)最終処分場の新規立地が困難となる一方で、産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理の多発が指摘されていること
3)近年、住宅室内のホルムアルデヒドをはじめとする化学物質等による健康影響への適切な対応が不可欠となっていること
があげられている。
このように、多岐にわたっている住宅・建築物に関わる環境問題については、的確な現状と問題点の把握が課題であるとともに、公的主体、住宅・建築生産者、消費者の各主体が、それぞれの立場で実効性のある環境対策を総合的かつ計画的に講じることが重要である。
ヌ 住宅建設コストの低減
我が国の住宅政策においては、豊かさを実感できる住生活の実現に向け、土地価格の安定、良質な住宅・宅地の供給促進、住宅取得能力の向上に関する従来の施策の充実に加え、住宅建設コスト(住宅建設費)の低減のための施策が不可欠である。
近年、我が国の住宅建設コストが米国に比して高いとの指摘があり、その低減に関する社会的要請が高まっている。また、消費者のコストに対する意識の高まりに伴い、住宅に本来必要な性能、機能等を問い直す動きも強まっている。
住宅建設コストを低減することは、国民の住宅取得の負担軽減に資するだけでなく、住宅規模の拡大や設備の充実といった国民の居住水準の向上意欲に応えるとともに、規模増に伴う家具等の関連需要の喚起など、広い分野での経済効果も期待できるものである。