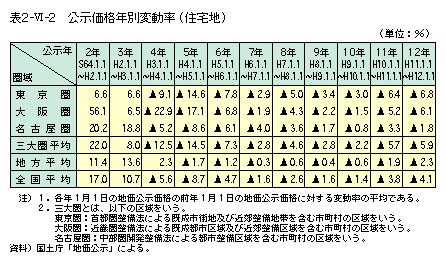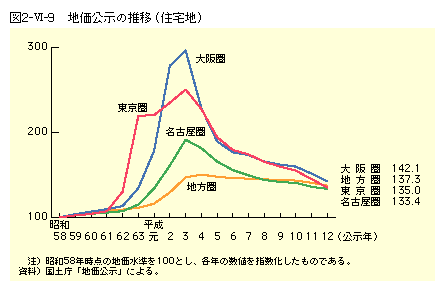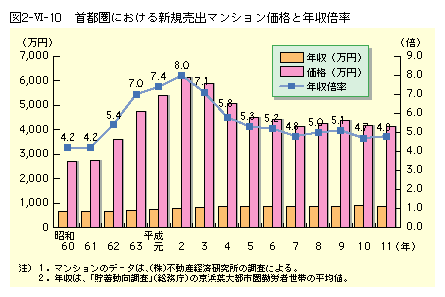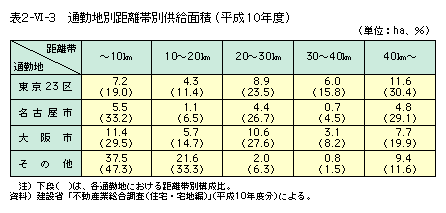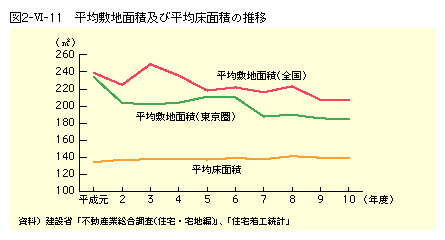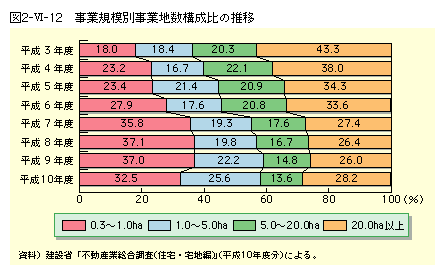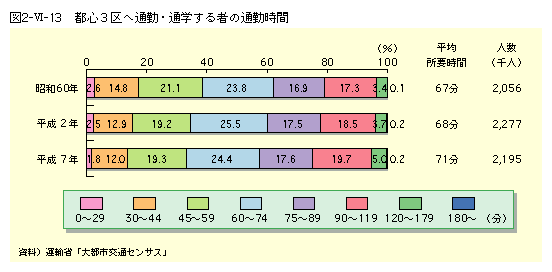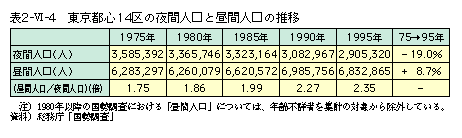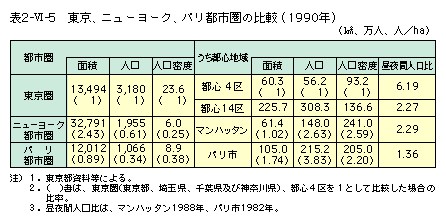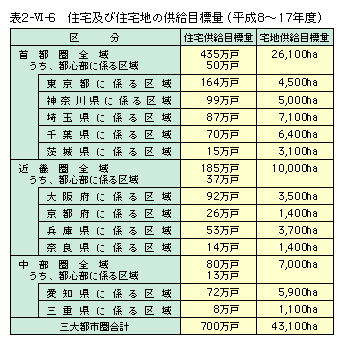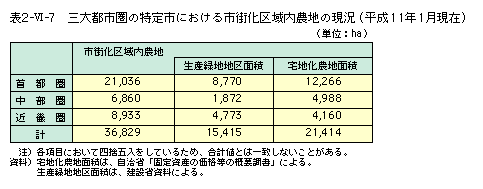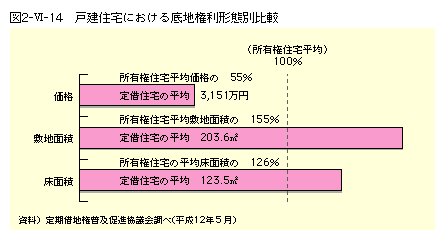(3)大都市地域における住宅・宅地問題
イ 大都市地域における住宅・宅地問題の現況
1) 地価の動向
国土庁の平成12年地価公示によると、三大圏における住宅地の地価は、対前年変動率▲5.9%と平成4年以降9年連続の下落となり、下落幅は前年と比べ拡大している(表2-VI-2)。
なお、地価高騰が始まる前の昭和58年公示を100とする住宅地の地価変動率の累積値をみると、平成12年公示においては、東京圏135.0、大阪圏142.1、名古屋圏133.4となっている(図2-VI-9)。
2) 住宅の分譲価格、年収倍率、供給戸数、家賃
昭和50年代末に東京都心部の商業地で端を発した地価高騰等により、大都市地域を中心に住宅価格は大幅に上昇した。例えば、首都圏の新規民間分譲マンションの平均価格の指数の推移をみると、地価高騰前の昭和58年を100とした場合、平成2年には239.5にまで上昇した。その後、地価の沈静化等に伴い下落し、平成11年には161.8となっている。
この平均価格の勤労者世帯の平均年収に対する倍率は、昭和60年頃まで4〜5倍で推移していたが、地価高騰に伴って上昇し、平成2年には約8倍に達した。その後低下傾向にあり、平成11年には4.8倍となっている(図2-VI-10)。
また、同じく新規民間分譲マンションの供給戸数については、昭和60年以降は概ね40,000戸前後で推移してきたが、平成3年及び4年には26,000戸程度に減少した。その後、住宅ローン金利の低下やローン減税の大幅拡充等による市場の好況を反映し、平成11年は約90,000戸となっている。
民間賃貸住宅の家賃についても、新規入居時の家賃は地価高騰に伴ってかなりの上昇をみせたが、平成3年頃をピークとして最近は下落傾向が続いている。
3) 住宅立地の状況
平成10年度に新規供給された宅地分譲と戸建て分譲の合計を、通勤地からの距離帯別にみると、三大圏では約6割が20km以遠に立地しているのに対し、その他の地域では約8割が20km圏内において供給されており、若干都心回帰の傾向がみられるものの、地方と比較して大都市地域の住宅立地状況が依然厳しいことを示している(表2-VI-3)。
4) 住宅・宅地供給の動向
住宅供給の動向をみると、平成11年度の新設住宅着工戸数は、公庫融資制度の拡充、税制改正等の政策効果により、3年ぶりに前年水準を上回った。しかしながら、住宅着工の3〜4割を占める貸家については、その約半数が50m
2以下のものであり、必ずしも良質な住宅ストックの形成が進んでいるとはいえない。
一方、宅地供給の動向をみると、宅地分譲・戸建住宅による新規供給宅地の平均敷地面積は若干低下傾向がみられる(図2-VI-11)。また、宅地開発事業の事業規模は、近年小規模なものの割合が多くを占めている(図2-VI-12)。
5) 居住水準
居住水準目標のうち、規模要因に関する達成状況をみると、平成10年時点で、主世帯のうち最低居住水準未満世帯率は全国で224万世帯(5.1%)であるが、三大都市圏で156万世帯(7.0%)、京浜葉大都市圏で99万世帯(7.8%)存在しており、また、誘導居住水準以上世帯についても、全国で2,041万世帯(46.5%)、三大都市圏で913万世帯(40.7%)、京浜葉大都市圏で477万世帯(37.7%)となっており、大都市地域における居住水準向上の遅れが目立っている。
6) マンションストックと建替えの状況
我が国における分譲マンションの供給は、昭和30年代以降本格的に始まり、平成11年末のストック総数は約369万戸と推計され、都市型居住形態として定着してきている。初期に建てられたマンションの中には物理的、機能的な老朽化が進行しているものもある。
このような状況の中で、実際に建替えが完了した事例は、(財)マンション管理センターの調べでは50数件(平成11年3月末現在)となっている。建替事例の多くは昭和30年代前半に都市基盤整備公団又は地方住宅供給公社により分譲されたものであり、容積率に余裕があるため、従来のマンションよりも増床を行い、余剰床を売却して建替え費用に充てる方法が採られている。
ロ 都心居住の推進
1) 都心居住推進の必要性
大都市地域においては、住宅立地の遠隔化により通勤時間が長時間化し、職住近接のニーズが高まっている。
一方、都心地域においては、人口減少による居住空間の空洞化やコミュニティの崩壊等の問題が生じている。
東京圏と諸外国の大都市地域を比べてみても、東京圏は圏域全体の人口密度が高いにもかかわらず、都心地域の人口密度が低く、中心部と周辺の人口密度の差の少ない都市構造となっている。近年は、都心の地価が一時期よりも下落したため住宅立地の都心回帰のきざしもみられるが、職と住のバランスのとれた都市構造を実現し、職住近接によるゆとりある生活の実現を図るには、政策的に都心地域における土地の有効高度利用と積極的な住宅供給を促進することが必要となっている(図2-VI-13、表2-VI-4、表2-VI-5)。
2) 都心居住推進の考え方
都心居住の推進に際しては、都心地域の居住者が単身世帯に偏っている現状を改善し、多様な人々が豊かな都市生活を享受することができるよう、
イ)住宅価格について、中堅ファミリー層を含めた多様な世帯が住むことのできる価格、家賃にすること
ロ)利便性や眺望を重視して、日照条件にとらわれないといったようなニーズの変化に対応して、新しい都市的な住まい方を確立すること
ハ)道路の幅員や建物のセットバックなどによって良好な空間を創出しつつ、土地の有効高度利用を図ること
ニ)共働き世帯の増大や女性の社会進出に伴い、都心居住者のライフスタイルに対応した生活支援施設やサービスの提供を確保すること
等に留意することが重要である。
ハ 広域的計画体系に基づく住宅・宅地供給の促進
供給基本方針等の策定
大都市地域における住宅・宅地需要は、ひとつの都府県を超えた範囲にわたるため、広域的な観点からの取組みが不可欠である。
このため、「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)」に基づき、三大都市圏の大都市地域について、平成8年4月、10年間を目標として国が「住宅及び住宅地の供給に関する基本方針(供給基本方針)」を、関係各都府県は同方針に即して「住宅及び住宅地の供給に関する計画(供給計画)」を策定した(表2-VI-6)。
現在、国及び関係公共団体は一体となって、既成市街地の有効利用、市街化区域内農地の計画的宅地化、新市街地の計画的開発、都心の地域その他既成市街地内における住宅供給の促進等を推進し、適正な価格での良質な住宅・宅地の供給を図るとともに、住宅取得能力の向上等の総合的な施策の展開を図っている。
ニ 既成市街地における住宅供給の促進
1) 都心の地域その他既成住宅地内の住宅供給の促進
都心の地域その他既成住宅地内では、居住水準の向上、土地の有効・高度利用、職住近接の実現、公共公益施設の有効利用の観点等から中高層共同住宅の供給と、建替えによる住宅供給を推進する必要がある。
このため、都心の地域及びその周辺の地域については、住環境の整備を図りつつ、用途別容積型地区計画等の制度の活用により住宅供給を誘導するとともに、都心共同住宅供給事業、住宅供給に資する市街地再開発事業等を推進する。これらの施策により住宅を適切に確保し、都心の地域等における居住機能の回復を図ることとする。なお、地方公共団体、都市基盤整備公団、地方住宅供給公社等の公的主体は、住宅市街地整備の推進と住宅供給の拡大を図るとともに、それぞれの役割に応じた家賃により、適正な家賃の住宅供給に努めるものとする。
老朽木造住宅地区においては、各地区ごとの明確な整備目標の下に、公共施設の整備と敷地の共同化等による土地の有効・高度利用を図り、利便性の高い良質な住宅の供給を促進することとしている。その際、密集住宅市街地整備促進事業、特定優良賃貸住宅供給促進事業等による共同建替え、中高層化及び基盤整備を推進する。また、賃貸住宅の建替えの促進を図るため、一括借り上げ、定期借地権その他の借地方式、土地信託、事業受託等を活用する。さらに、これらの円滑な実施を図るため、地方公共団体を中心とした事業推進のための体制を整備する。
2) 老朽マンション等の建替えの円滑化
老朽マンションの建替えは、複数の区分所有者について建替えの合意を形成しなければならない等、困難な問題を有している。このため、合意形成を円滑に進めるという観点から、分譲マンション建替えマニュアルを作成・普及するとともに、良質な住宅供給と市街地環境の形成という観点から、マンションの建替え事業について補助を行う優良建築物等整備事業を推進していくこととしている。
3) 低・未利用地の有効利用
三大都市圏の既成市街地等において工場跡地等の低・未利用地で一定規模以上のものについては、早急にその状況を点検し、住宅地としての利用に適するものについては、有効・高度利用を図ることにより周辺市街地整備と併せた住宅供給を行っていくことが必要である。このため、市街化区域内の低・未利用の状態にある一定規模以上の土地について地区指定し、その有効利用を促進する遊休土地転換利用促進地区制度、同地区内の一定の土地に対して課する遊休土地に係る特別土地保有税及び基盤施設整備を条件に用途制限、容積率制限等の特例を認める再開発地区計画制度等を活用していくこととしている。
ホ 大都市地域での良好な宅地供給の推進
市街化区域内農地の住宅地等への転換の促進、定期借地権を活用した住宅・宅地供給の促進等に重点を置き、大都市地域内における職住近接の実現に向けて、公共施設が適切に整備され、良好な居住環境を備えた住宅市街地の整備を図る。また、常磐新線・新駅の周辺における鉄道整備と一体となった宅地開発や緑・景観、高齢者等に配慮した良質な宅地開発を推進する。
1) 市街化区域内農地の計画的利用
三大都市圏の市街化区域内農地については、良好な都市環境の形成に資するとともに、その積極的な活用により住宅・宅地の供給が期待される。
このため、特定市における市街化区域内農地は、生産緑地地区内の農地を一般農地として課税し、生産緑地地区以外の農地である宅地化する農地を宅地並み課税としている。平成11年1月現在で、特定市における市街化区域内農地の面積は約36,829ha、うち宅地化する農地は約21,414haとなっている(表2-VI-7)。
特定市における市街化区域内農地の分布をみると、地区によっては生産緑地地区と宅地化する農地が混在していることに加え、宅地化に必要な道路が必ずしも十分に整備されていないところも見受けられる。これらの課題に適切に対処し、公共施設整備を伴った良好な住宅・宅地供給を推進するため、都市再生区画整理事業、特定優良賃貸住宅供給促進事業等の各種事業制度や、基盤整備を伴う優良な賃貸住宅を建設した場合の固定資産税の減額等融資・税制上の措置の活用を図ることとしている。また、(財)都市農地活用支援センターによる都市農地の計画的利用促進の支援、関係公共団体における関係部局の連携等庁内体制及び農協等との連携体制の整備等を推進しているところである。
2) 定期借地権の活用
平成4年8月に施行された借地借家法により創設された定期借地権制度は、借地契約の更新がなく、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了する借地権である。定期借地権付住宅の供給実績は、平成11年末までに約25,000戸に上っている。
定期借地権付住宅は、土地の資産価値ではなく利用価値を重視し、比較的少額の初期負担で取得でき、中堅勤労者にとっても職住近接でゆとりある居住の実現に資するものであり(図2-VI-14)、多様化する国民のニーズに対応してその促進を図っていく必要がある(
2(12)、
(17)イ参照)。
3) 良好な住宅市街地の整備
都市基盤整備公団、地方公共団体等の公的主体による宅地開発については、まちづくりと一体となった都市開発事業など民間では対応が困難なものを中心として、引き続き長期的、安定的に良好な宅地供給の推進及び健全な市街地の整備を図る。
また、民間事業主体による宅地開発については、地域の実情に応じて市街化調整区域における計画的開発の規模要件を緩和する都道府県の規則(いわゆる5ヘクタール規則)の活用、宅地開発等指導要綱(
2(23)ロ参照)の適正な見直し等により事業環境の改善を図るとともに、優良な計画的宅地開発事業を建設大臣が認定し、税制、財政等の特例措置を講じることを内容とした「大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法」を積極的に活用することとしている。
さらに、適正な土地利用、良好な宅地供給のため、官民の適切な分担のもとに宅地供給を行うものとし、このため、宅地開発等指導要綱の行き過ぎ是正について引き続き指導を徹底するとともに、住宅宅地関連公共公益施設の整備を積極的に推進する。