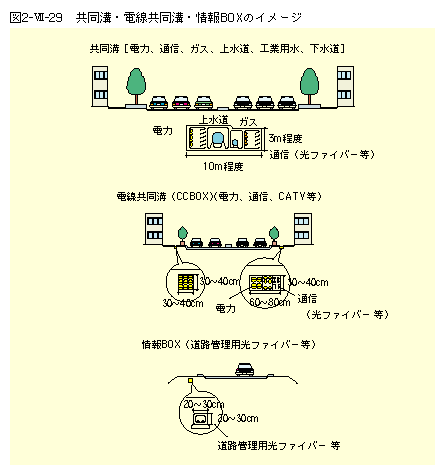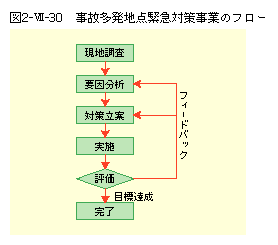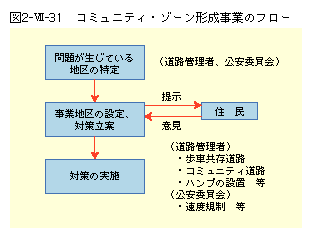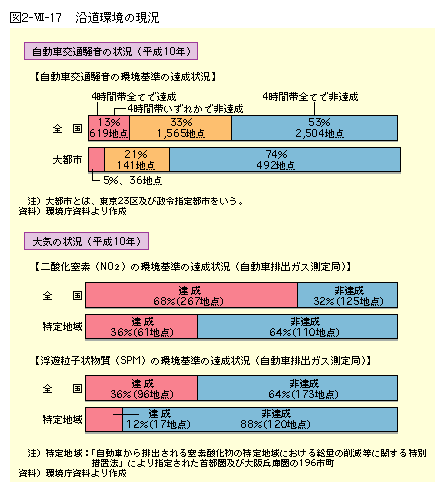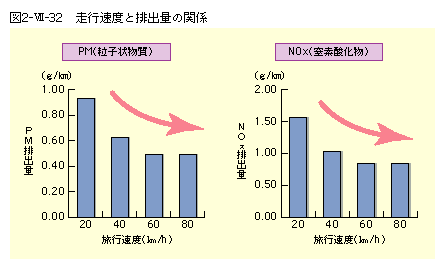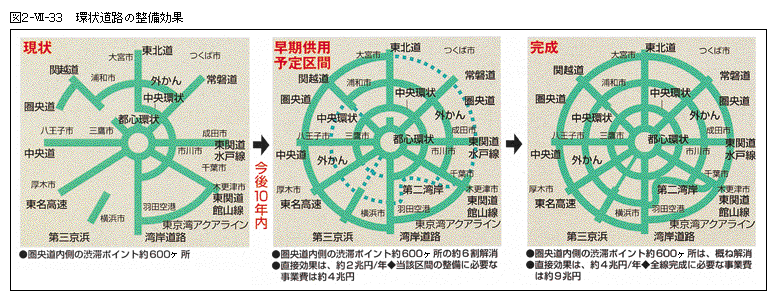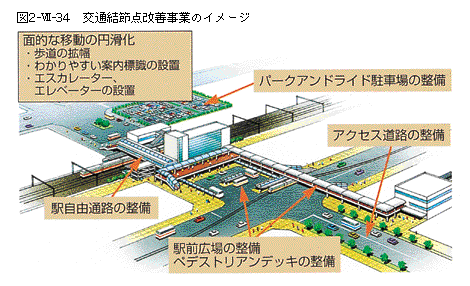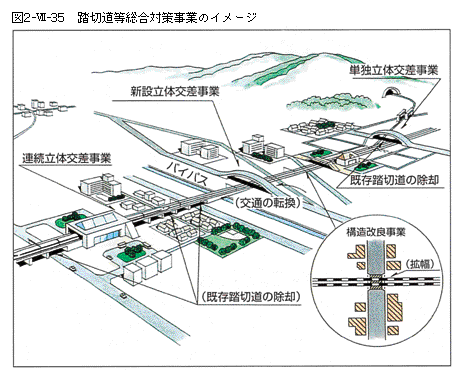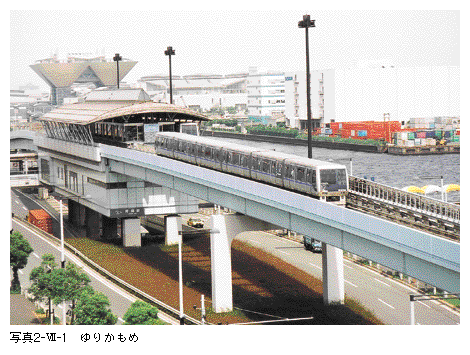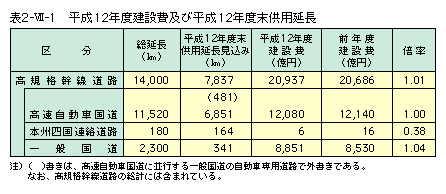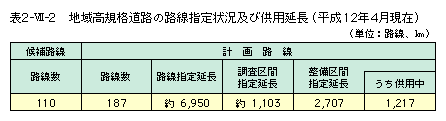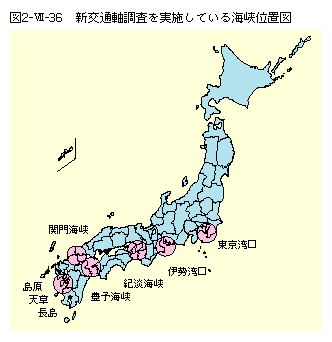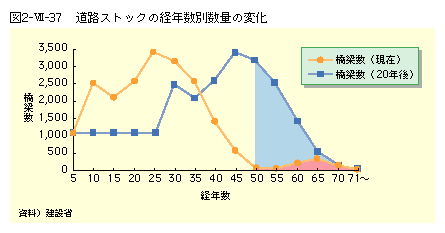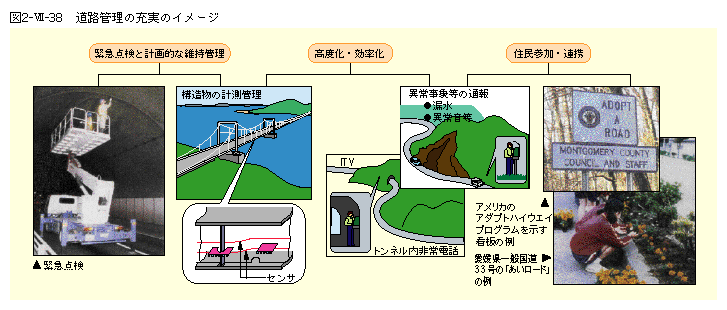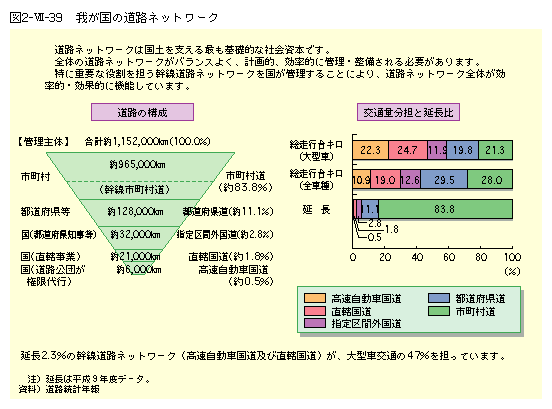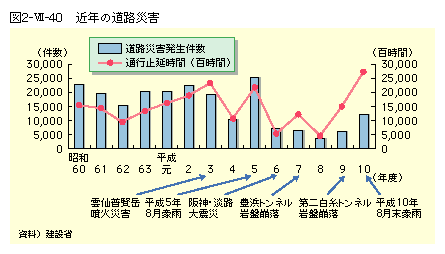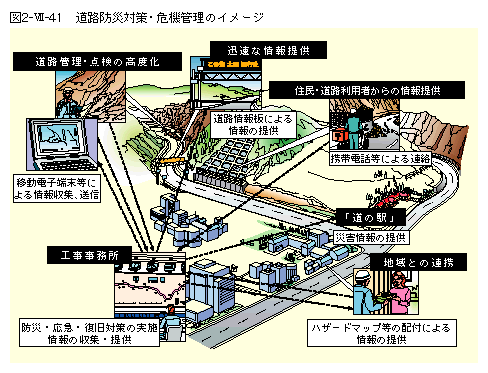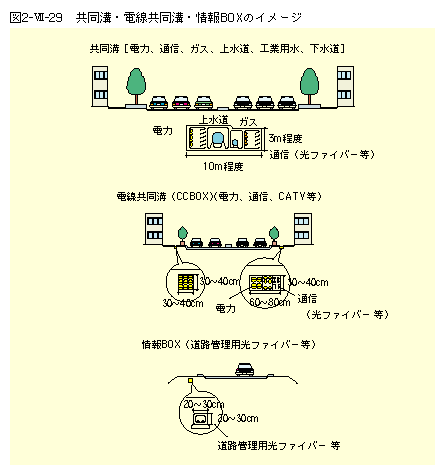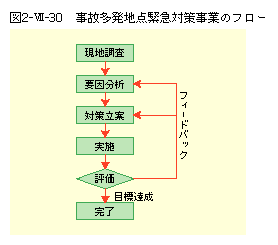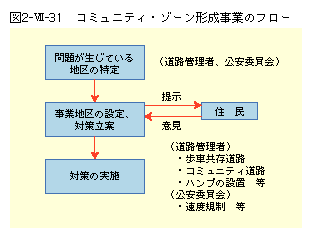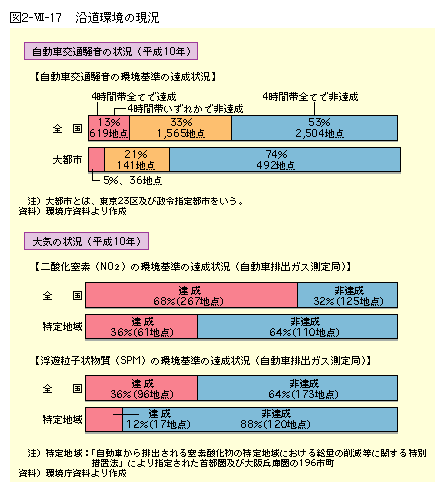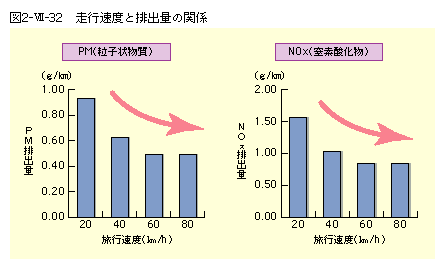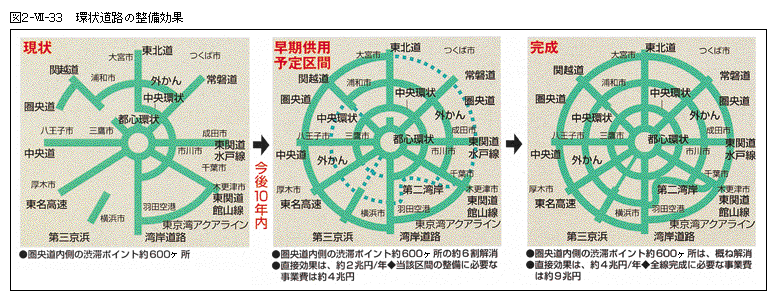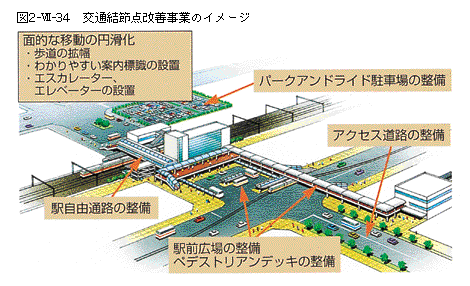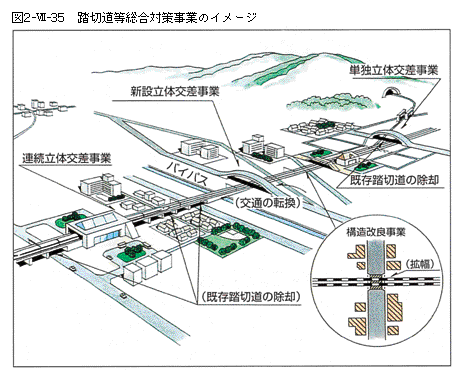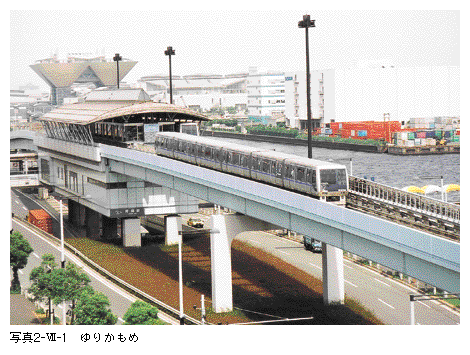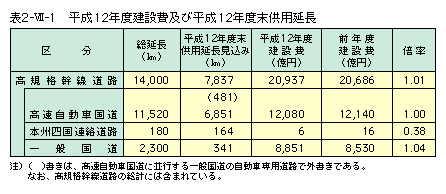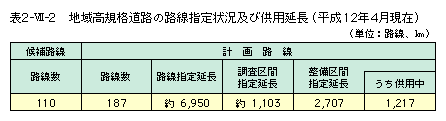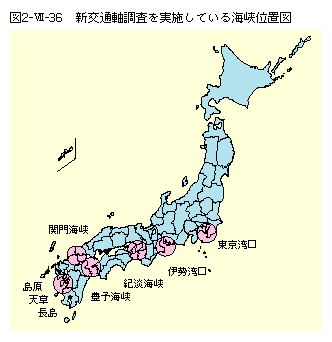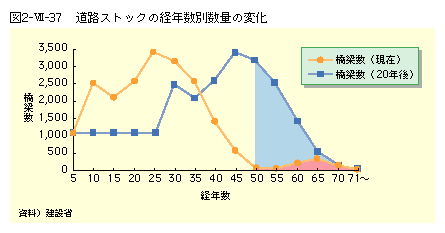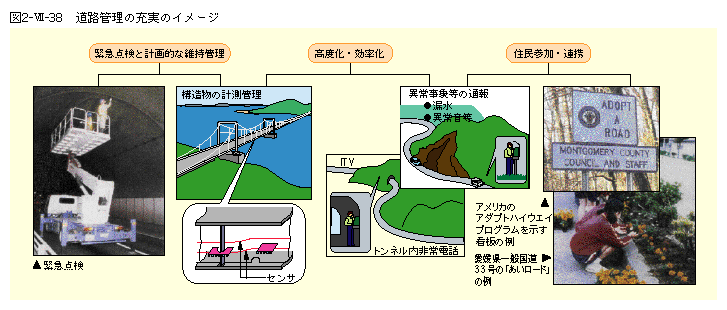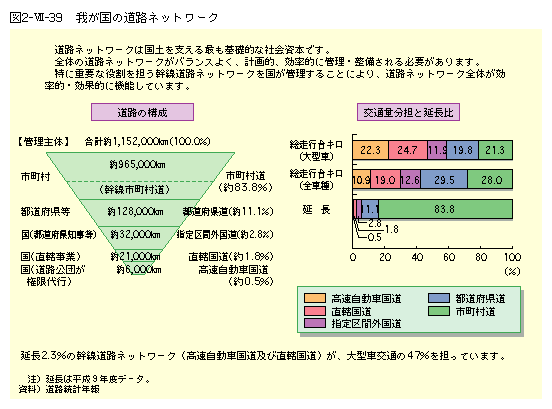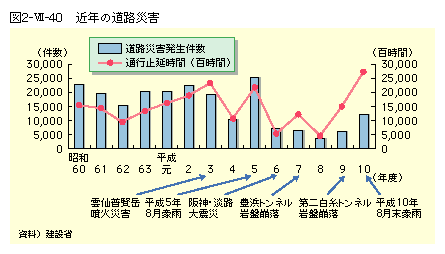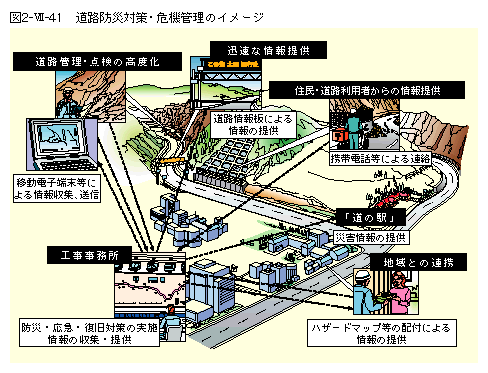(2)平成12年度の主要施策
世紀の節目となる平成12年度は、以下の視点で道路政策を展開し、新世紀にふさわしい豊かで活力ある経済社会の構築を目指して取り組む。
・高度情報通信社会推進に向けた道路の情報化
・少子・高齢社会に対応した生活空間の形成
・地球環境の保全と沿道環境の改善
・都市構造の再編を図る環状道路の整備
・都市圏の交通円滑化
・個性豊かな地域・まちの形成
・地域連携と物流効率化の支援
・更新時代を見据えた安全性・信頼性の高い道路空間の確保
イ 高度情報通信社会推進に向けた道路の情報化
1) 道路交通システムの高度化(ITS)の推進
建設省では、関係各省庁と連携して交通渋滞・交通事故等の低減や利用者の快適性の向上を目的に、最先端の情報通信技術等を活用して創り出す新しい道路交通システムであるITS(Intelligent Transport Systems)を積極的に推進している。
イ)ITSの個別サービスの展開
カーナビゲーションシステムにリアルタイムな道路交通情報等を提供するVICS(Vehicle Information and Communication System:道路交通情報通信システム)について、平成12年6月現在、全国の高速道路及び19都道府県においてサービスを実施しており、引き続き情報内容の充実やエリアの拡大を図るべく施設整備等を実施していく。また、有料道路における料金支払いを無線通信により自動的に行うETC(Electronic Toll Collection System:ノンストップ自動料金収受システム)について、平成11年度には東関東自動車道、京葉道路等、千葉地区を中心とする首都圏の主要な料金所において路側機器の整備を行い、平成12年4月からサービス開始を開始した。平成12年度中には、サービス区間を約580ヶ所まで大幅に拡大するとともにETCの普及を図り、平成14年度末までに全国の主要な料金所(約900ヶ所)に導入を図る。さらに、研究開発プロジェクトとして、交通事故の削減を目指すため、道路と車の協調によりドライバーへの危険警告や運転の補助を行うAHS(Advanced Cruise-Assist Highway Systems:走行支援道路システム)について、自動車や電気・通信等の先端企業から成る「技術研究組合 走行支援道路システム開発機構(AHSRA)」との連携により、研究開発を推進している。本年10月には運輸省との連携の下、走行支援システムの実証実験(「スマートクルーズ21」)を行い、実用化を目指す7つのサービスについて評価・検証を行う。
ロ)スマートウェイの推進
VICS、ETC、AHS等を始めとする多様なITSサービスの本格的な展開を支えるITS仕様の道路「スマートウェイ」の実現に向けた取組みを平成10年度から開始している。このスマートウェイを実現するには各分野における横断的な連携、産学官の連携、国際的な協調が必要となることから、平成11年2月に、産業界、関係省庁等から構成される「スマートウェイ推進会議」(委員長:豊田 章一郎(社)経済団体連合会名誉会長)を開催し、平成11年6月にはスマートウェイのあり方や実現方策等について幅広い見地からの提言を頂いた。この提言に基づきスマートウェイ実現に向けた本格的な取組みを推進し、平成13年を目標に必要となる制度や基準類の整備を図り、平成14年以降、逐次、スマートウェイの整備を進めていく。
地域レベルでもITSの積極的な導入を図るため、平成12年度にITS関連施設整備事業を創設し、地方公共団体が円滑な道路交通の確保、道路利用者の利便性向上等を目的に、一般国道及び都道府県道等において、道路の改築事業等と一体的に行うセンサー類等のITS関連施設の整備に対して補助を行っていく。
その他、ITSを構成するシステム間や地域間の互換性を確保しITSの統合化を図るための道路管理者間の通信規約(プロトコル)等、システムの共通的基盤に関する調査研究を推進するとともに、また、日本のシステムを国際標準と整合の取れたものとするため、ITU(国際電気通信連合)、ISO(国際標準化機構)等における国際標準化活動を支援し、ITS世界会議やAHSワークショップ等を通じた国際交流・協調を進めている。
2) 情報ハイウェイの構築
地震等の大規模災害時における即応体制の確保など、公共施設の管理の高度化による道路の安全性・信頼性の向上を図るため、道路管理用光ファイバーを整備するとともに、その収容空間として、情報BOX、電線共同溝、共同溝の整備を図り、道路地下空間の有効活用を推進する。
なお、道路管理用光ファイバーを収容するとともに、民間の全国的な光ファイバーネットワークの構築にも資するよう配慮し、その予備空間に電気通信事業者、有線放送事業者等の光ファイバーも収容可能な情報BOXについては、平成12年度末までに、青森〜鹿児島間の基幹網が完成する等、全国で約16,000kmの整備を予定している(図2-VII-29)。
ロ 少子・高齢社会に対応した生活空間の形成
1) 豊かな生活空間づくり
誰もが安心して社会参加でき、快適に暮らせる豊かな生活空間を創造するため、歩行者や自転車、高齢者や障害のある方など様々な人の利用する視点から、地域と連携して安全・快適で利用しやすい道路空間づくりを推進する。
イ)バリアフリーで快適な歩行空間の整備
i)バリアフリーで快適な歩行空間ネットワークの整備
高齢者、身体障害者等を含めた誰もが安全かつ円滑に通行できるよう、幅の広い歩道(幅員3m以上)の整備、既設歩道の段差・傾斜・勾配の改善、スロープ付き・昇降装置付き立体横断施設の整備、電線類地中化、歩行者案内標識の整備等により、歩行空間のバリアフリー化を推進してきた。
特に、平成11年9月にはバリアフリー化に対応した歩道の構造基準(「歩道における段差及び勾配等に関する基準」)を策定するとともに、平成12年度からは「歩行空間ネットワーク総合整備事業」を創設し、市街地の駅、商店街、病院、福祉施設等の周辺等において、バリアフリーで快適な歩行空間をネットワークとして整備する。
また、駅等の公共交通機関の旅客施設の周辺については、運輸省、建設省、警察庁、自治省を主務省庁とする「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」が平成12年5月に制定されたことを受けて、公共交通機関のバリアフリー化と連携した整備を推進する。
さらに、ITS技術を活用し、高齢者、身体障害者をはじめとした歩行者等の移動円滑化を支援するためのシステムの開発を推進する。
ii)道路交通環境改善促進事業の推進
道路交通環境改善促進事業により、沿道建築物や駅の上下空間等を活用して、歩行者通路等の快適な歩行空間を確保する。
ロ)都市における自転車利用環境の整備
日常的な都市交通モードとしての自転車利用を促進するため、「自転車利用環境総合整備事業」を創設し、平成11年度までに自転車利用環境整備モデル都市として指定した19都市(群馬県前橋市等)において、当該都市の道路管理者等が策定する基本計画のもと、都市において快適かつ安全に自転車が走行できる自転車道等のネットワークとそれをバックアップする自転車駐車場の整備を重点的に推進する。
ハ)うるおいある生活空間の創造
i)人とくらしの公共空間の再生
住民参加のもと、地域の個性を活かしたイベントなどの利用に配慮した道路空間の活用計画を作成し、試行的に実施する。
ii)ウォーキング・トレイル事業の推進
歩くことを通じた健康・福祉活動や魅力ある地域づくりを支援するため、豊かな景観・自然、文化的施設等を連絡する質の高い歩行空間の形成を推進する。
2) 安全な道づくり
イ)交通安全施策の推進
基本施策として道路網の体系的整備を進めるとともに、緊急に安全を確保すべき道路について「特定交通安全施設等整備事業七箇年計画」等に基づき、都道府県公安委員会と連携して、以下の事項に重点をおいて交通安全施策を推進する。
i)事故多発地点緊急対策事業の推進
幹線道路における事故多発地点(約3,200ヶ所)について、交通事故の特性に即した事故削減策(交差点改良、歩道等の整備、道路照明の設置等)を集中的に実施し、事故多発地点の解消を目指す。
対策の実施後においては、講じた対策の効果を評価し、必要に応じて、事故発生要因分析・対策立案段階にまでフィードバックしつつ、的確に対策を講じる(図2-VII-30)。
ii)安全な歩行空間の形成
住居系地区等において、通過交通の進入を抑え、地区内の暮らしの安全を確保するため、「コミュニティ・ゾーン形成事業」を推進する。この事業では、地域の人々の参加のもとに策定される計画に基づき、都道府県公安委員会によるゾーン規制等と併せて、道路管理者によるコミュニティ道路、歩車共存道路等の面的整備を行う。
また、安全かつ快適に通行できるよう、歩道の整備を進めるとともに、歩行者優先の空間としてコミュニティ道路や歩車共存道路の整備を実施する(図2-VII-31)。
iii)交通安全総点検の推進
誰もが安心して利用できる道路交通環境を形成するため、都道府県公安委員会と連携し、地域住民等の主体的な参加のもと道路交通環境の点検を行い、点検結果を踏まえて道路交通環境の改善を行う「交通安全総点検」を推進する。
iv)わかりやすい道路案内標識の整備の推進
道路利用者の意見を道路標識の整備・改善に反映する仕組み(標識BOXなど)を充実させ、わかりやすい道路案内標識の整備を推進する。また、POINTERプロジェクトを推進し、交差する道路の路線番号を表示する案内標識を一般都道府県道以上の道路が相互に交わる交差点において整備する。
ハ 地球環境の保全と沿道環境の改善
1) 沿道環境改善への取組み
イ)沿道環境の状況
我が国の幹線道路の沿道環境は、騒音については全国の騒音測定地点の約9割で環境基準を超え、また大気汚染については大都市圏の沿道の測定局において、二酸化窒素(NO2)は約6割、浮遊粒子状物質(SPM)は約9割が環境基準を超えるなど、非常に厳しい状況が続いており、対策が急務となっている(図2-VII-17)。
ロ)沿道環境改善への取組み
沿道環境の改善を図るためには、経済・社会活動を支えている幹線道路の役割と沿道の生活環境の保全の両立を図ることを基本理念に、自動車単体対策、低公害車の普及、交通流対策、道路構造対策など総合的な取組みを関係機関等が協力して進めることが必要である。
走行速度の向上によりPMやNOxの排出量の縮減が図られることから、道路行政における対策としては、特に自動車交通の円滑化を図ることが必要である(図2-VII-32)。
・幹線道路ネットワークの整備
自動車交通の分散・円滑を図るため、環状道路・バイパスなど幹線道路ネットワークを整備する。
・交通流対策、道路構造対策
騒音や大気質の現況が継続的に環境基準を超えている地域において、交通の円滑化を図り沿道環境への影響を軽減するボトルネック対策や、沿道環境への影響を緩和する低騒音舗装・遮音壁・環境施設帯の整備等を行う。
・「幹線道路の沿道の整備に関する法律」の活用
「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づく沿道整備道路の指定や、沿道整備計画の決定を促進し、緩衝建築物の建築物の負担、防音工事の助成等を行う。
なお、沿道環境の改善を図るため、全国約20ヶ所において沿道環境改善プログラムを策定する。また、全国の直轄国道等において、道路交通騒音の現状を調査・公表し、調査結果を踏まえて対策を計画的に進める。
2) 地球温暖化対策の推進
イ)道路審議会答申
近年、地球規模での環境問題の深刻化が指摘されており、なかでも、地球温暖化問題は、人類の生存基盤に関わる重大な問題となっている。平成9年12月に京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議においては、京都議定書が採択され、我が国には2008年から2012年までの間の温室効果ガスの排出量を1990年比で-6%に削減するという厳しい目標が位置付けられた。
そこで、道路審議会では平成7年9月に建設大臣より諮問された「今後の道路環境政策のあり方」に基づき、平成9年6月に道路環境対策全般についての基本的方向を示す中間答申を行い、この基本的方向を受けた各論の一つとして、平成11年11月29日に、「地球温暖化防止のための今後の道路政策について」をとりまとめ、建設大臣に答申した。
答申では、環境と調和した循環型の持続可能な経済社会を実現し、未来によりよい環境を引き継ぐことを理念に、道路利用を地球環境への負荷の少ないものとすることを目指し、道路行政を転換していくことが必要であるとし、地球温暖化防止に取り組むに当たって、「地球環境への負荷の少ない道路利用への転換」「よりよい環境創出のための道路空間・ネットワークの実現」「創意と連携による取り組み」の3つの観点から、基本的な方向が示された。
ロ)地球温暖化防止に向けた施策展開
地球温暖化防止に向け、効率的な国土利用や環境負荷の小さな地域構造を支える環状道路やバイパス等の道路ネットワークを整備するとともに、良好な環境を形成し、二酸化炭素の吸収に資する緑豊かな道路空間の創出と緑のみちのネットワークの形成、自転車利用の促進による環境負荷の軽減、天然ガス車などの低公害車の普及のためのSA・PAへの燃料供給施設の設置に向けた調査の実施、道路維持管理車両への低公害車の導入等を進める。
3) 緑化・自然環境対策等の推進
緑化等景観に配慮し、地域の街並みや歴史・文化等と調和したうるおいのある道路空間の創出を図る。
事業の計画、設計段階から、貴重な自然環境のある場所はできるだけ回避し、回避できない場合は、影響の最小化や代替措置を講じることを基本とし、環境の保全・回復を図る。このため、調査・設計・施工・管理・フォローアップの各段階における自然環境保全・回復のための考え方や具体的な方法に関する指針の策定を進める。
また、道路ののり面等を緑化し、河川や公園等と一対となったビオトープネットワークを構築する。
4) 廃棄物の削減・適正処理・リサイクルへの取組み
事業の計画段階からリサイクル計画書の作成や建設発生土情報交換システムの活用等、発生抑制、適正処理、リサイクルを進める。
また、道路の維持管理作業で発生する剪定枝などの発生木材等についてチップ化、木質ボードとしての利用等、技術開発を含めて減量化・再資源化を図る。
ニ 都市構造の再編を図る環状道路の整備
都市圏をはじめとする交通渋滞の緩和や国民生活・社会経済活動の効率化を図るために、大量の高速交通需要を処理するために最も効果的である自動車専用道路ネットワークの整備を進めることが必要である。これにより、交通渋滞が解消・緩和され、円滑な道路交通が実現され都市機能が向上し、旅行速度の増加は、自動車から排出される二酸化炭素の削減にもつながるなど、地球環境の保全が図られることに加え、二酸化窒素(NO2)や浮遊粒子状物質(SPM)が減少するなど沿道環境の改善に資する。
このうち、都心部に集中する交通を分散・導入させ、都心に起終点をもたない交通を迂回させるなど、都市圏の交通混雑を緩和することを期待されているのが、環状道路である。
しかしながら世界の主要都市の環状道路の整備率を比較すると、ロンドン、パリがそれぞれ99%、74%であるのに対し、三大都市圏は、東京や名古屋では未だ約2割と低水準である。
また、例えば東京圏(首都圏)における自動車専用道路の環状道路である首都圏中央連絡自動車道や東京外かく環状道路などは、その計画策定が1960年代と、ロンドンのM25やパリのA86とほぼ同時期であるのに対し、その完成は東京が大きく遅れているのが現状であり、その早急な整備が課題である。
また、道路の機能は多様であり、交通の円滑化、交通安全などの交通機能面のみならず、空間機能や市街地を誘導する機能、国土や都市の骨格を形成する機能も有していることから、環状道路の都市構造の再編に対する役割なども明確化しつつ、建設省においては、平成12年度予算においても国費助成の充実、償還期間の延長など有料道路制度の活用等により都市圏の環状道路の整備を重点的に推進している(図2−VII−33)。
ホ 都市圏の交通円滑化
道路交通需要の大きな伸びや非効率な自動車の使われ方の増加等により、道路交通渋滞の状況は深刻化しており、全国で年間に発生する渋滞損失は約12兆円、国民1人当たり年間約42時間にのぼり、環境問題、経済効率の低下等を引き起こしている。また、地球温暖化防止や沿道環境改善の観点から渋滞対策の推進によって自動車燃費効率の高い走行環境を確保することによる二酸化炭素や窒素酸化物、浮遊粒子状物質の排出量削減対策や、自動車利用の適正化等が求められている。そこで渋滞の緩和・解消を図るために、各都市圏において都市規模、交通特性に応じてバイパス、環状道路の整備などの交通容量拡大策、関係機関と連携して、交通需要の調整・抑制策である交通需要マネジメント(TDM)施策、各種交通機関の連携及び公共交通機関の支援策であるマルチモーダル施策を組み合わせて総合的な都市交通施策を実施する。
1) 渋滞緩和のための抜本的対策や局所的・緊急的対策の推進
首都高速都心環状線の交通のうち約6割が通過交通であり、通過交通の都心部への流入により渋滞が発生している。一方、東京の放射道路の整備率は約9割に達するが、環状道路は約2割と整備が遅れている。このため、抜本的な対策としてバイパスの整備や、三大都市圏、中枢・中核都市を中心に渋滞緩和に効果の高い都市環状道路の整備を重点的に推進する。
また、局所的・緊急的な対策として立体交差化や交差点の改良、料金所におけるETCの導入等を推進する。
2) 交通需要マネジメント(TDM)施策の推進(交通需要の調整・抑制策)
自動車の利用者の交通行動の変更を促すことにより道路交通混雑の緩和を図るため、フレックスタイム、時差通勤などのピークカット施策やパークアンドバスライド等のTDM施策を実施する。また、行政のTDM推進体制の整備に併せ、NPO法を活用した交通マネジメント協会(TMA)の設立を支援する。またTMA組織が実施する調査、社会実験、さらに循環バス運行やパークアンドライドなどのTDM活動を支援する。
3) マルチモーダル施策の推進(各種交通機関の連携及び公共交通機関の支援)
利用者のニーズに応じた効率的な輸送体系を確立し、良好な交通環境を創造するため、道路のみならず航空、海運、水運及び鉄道等複数の交通機関の連携による総合的、効率的な交通施策(マルチモーダル施策)を推進する。
鉄道駅等交通結節点の機能強化として、大都市ターミナル駅等乗降客概ね5,000人以上の駅(約2,400駅)を対象として駅周辺総点検を3年間で実施する。そして、総点検の結果を踏まえ、乗り継ぎの改善や歩行空間のバリアフリー化を行う「駅周辺交通環境改善計画」を策定し、創設した交通結節点改善事業等の活用により、駅前広場、歩道、パークアンドライド駐車場等の整備を短期・集中的に実施する(図2−VII−34)。
また、連続立体交差事業等によるボトルネック踏切の除却や鉄道の立体化を契機とした一体的なまちづくりを促進するとともに、踏切除却による地域づくりと併せて鉄道高速化を支援するため、「踏切道等総合対策プログラム」に基づき、踏切改良等を計画的かつ重点的に実施する「踏切道等総合対策事業」を創設・実施する。その際、連続立体交差事業や踏切除却事業の採択基準を緩和する(図2−VII−35)。
次にバス関連結節点の機能強化として、高速道路バス停近傍や郊外部の拠点地域におけるバス交通広場整備等により、バスを中心とした効率的な交通ネットワークを形成するため、「バスの駅」としてバス交通広場を重点的に実施する。また、都市及び近郊の通勤・通学等に利用されるバス路線において、バス交通の定時性確保及び利便性向上を図るため、道路拡幅、交差点改良、バスレーンのカラー舗装化、パークアンドバスライド駐車場整備、バス停のハイグレード化等を推進する。特に、バス路線フレッシュアップ事業として、多くのバス路線が集中しバスの運行本数が多い区間で、これらの整備を重点的かつ総合的に実施する。さらに、オムニバスタウン構想として警察庁や運輸省が実施するバス事業への支援施策等と連携し、上記バス利用促進策を推進する。
また、都市モノレール、新交通システム及びガイドウェイバスシステムのインフラ整備を推進するとともに、車両の小型化、インフラコスト等の整備等の事業費低廉化に資する技術開発を行い基本仕様等を見直す。さらに、路面電車の新設、延伸を行う場合に、マルチモーダル施策の一環として路面電車の整備を支援する路面電車走行空間改築事業を推進する。
4) 総合的な都市圏の交通円滑化対策
都市圏の交通円滑化を図るため、交通容量拡大策に加え、交通需要マネジメント(TDM)施策及びマルチモーダル施策を組み合わせて推進する「都市圏交通円滑化総合計画」を都道府県警察、地方公共団体の他、企業、市民等の参画を得て共同で策定し、渋滞の著しい地区や交通結節点等で、重点的かつ総合的に実施する都市圏交通円滑化総合対策事業を実施する。
また、平成10年度から開始した第3次渋滞対策プログラムに基づき、全国の約3,200ヶ所の主要渋滞ポイントについて、道路整備に加え、公安委員会等と連携を図ることにより、平成14年度までの計画期間内に約1,000ヶ所を効率的・効果的に解消を図る。
5) 路上工事の縮減対策の推進
東京都区部の場合、路上工事の約8割は、電気・電話・ガスなどの公益事業者が自らの料金収入等により実施する占用工事であり、これらは市民生活にとって不可欠ではあるものの、大きな交通渋滞原因の一つであることから大幅な縮減が必要である。そこで、各地域毎に道路管理者や公益事業者等からなる協議会を設置し、施工時期や施工方法を調整し、複数の工事をまとめて実施したり、年末・年度末の工事を抑制するなど、工事件数の削減と年間を通じた平準化を推進する。また、さらなる路上工事縮減のため、共同溝の整備、非開削工法の採用、埋設物件の浅層化などの施策を推進する。
ヘ 個性豊かな地域・まちの形成
1) 都市の再生・再構築の推進
都市活動を支える放射・環状道路等の体系的な整備を進め、沿道の民間建築投資を誘発し、土地の有効高度利用を促進する。また、連続立体交差事業の拡充や、拠点的な交通結節点の整備等により、都市を支える交通機能を強化し、都市構造の再編を進める。さらに、大都市都心部や臨海部の大規模低未利用地等において土地区画整理事業や市街地再開発事業等の面整備により土地利用転換を進める。
2) 地域連携機能の強化
公共・公益施設の共同利用・整備等地域住民等の利便性の向上や地域固有の魅力ある観光資源を活用した観光による地域づくりを支援するため、複数の市町村が地域自らの発意に基づき作成した計画に位置付けられた道路事業を重点的に支援する「地域連携強化支援道路事業」を推進する。また、観光資源等へのアクセス道路の整備に加え、拠点となる地域振興施設の整備や、地域イベントの開催を、国土庁と連携し一体的・総合的に支援する「地域連携総合支援事業」や、地形的な制約により相互の交流が遅れている都道府県間、市町村間等を大規模なトンネル・橋梁で直結する「交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業」を一層推進し、都市と地方の交流、市町村間の連携等を支援する地域間連絡道路等の整備を進める。
3) 地域の活性化支援
追加インターチェンジの整備により地域の活性化を促進するため、地方公共団体が、一般道路事業と有料道路事業を組み合わせて高速自動車国道のインターチェンジの整備を行う「地域活性化インターチェンジ制度」を創設した。また、駐車場等の休憩施設と地域振興施設が一体となって道を介した地域連携や、交流の核を形成するため「道の駅」の整備を進める。
4) 中心市街地の活性化の支援
バイパス等の整備に併せ、現道沿線地域が実施する地域づくりと一体となって現道を再生し、中心市街地に相応しい街並みを地域とともに創出できるよう歩道空間の整備、駐車場の整備等を進める。また、中心市街地の関係者と地元地方公共団体が一体となって策定する活性化計画に基づき、各種の道路整備(商店街の通過交通を迂回させるバイパス、電線類の地中化、モール化、ポケットパーク等)を総合的かつ短期集中的に実施する「賑わいの道づくり事業」推進する。
5) 地域・まちづくりの支援
地域の主体的な計画に基づいて、複数の事業を一括して採択し補助を行う「まちづくり総合支援事業」を創設し、地域づくり・まちづくりを支援する。また、まちづくりと一体となった面的な道路整備を行う「くらしのみちづくり事業」を推進する。
6) 電線類地中化の推進
安全で快適な通行空間の確保、都市景観の向上、都市災害の防止、情報通信ネットワークの信頼性の向上等を図るため、新電線類地中化計画(平成11年度〜平成15年度、約3,000km)に基づき、従来の大規模商業系地域に加え、新たに中規模商業系地域や、住居系地域の幹線道路等も対象として、電線類地中化を一層強力に推進する。
7) 自動車駐車場の整備
路上駐車の著しい商業業務地区等において、道路空間の活用や官民共同整備等により自動車駐車場の整備を進める。
ト 地域連携と物流効率化の支援
1) 幹線道路網の構築
イ)高規格幹線道路と地域高規格道路の重点的整備
高規格幹線道路については、国土空間の有効活用を図り、地域ブロックの自立的な発展や、物流の効率化などを強力に支援するため、平成10年3月に閣議決定された全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」等での位置付けを踏まえ、21世紀初頭までに14,000kmのネットワークの概成を目標に整備を進める。
平成11年度末の供用延長は7,548kmであり、平成12年度についても、都市圏の環状道路、地域ブロックの循環型ネットワークの重点的整備を推進して289kmの供用を図り、年度末の供用延長を7,837kmとする予定である(表2−VII−1)。
例えば、平成11年度に四国縦貫自動車道(井川池田〜川之江東ジャンクション)の供用により、四国横断自動車道と直結し、四国四県の県庁所在地が高規格幹線道路で結ばれるなどネットワークの進展を図っており、平成12年度も東北横断自動車道酒田線(湯殿山〜庄内あさひ)の供用により、日本海側と太平洋側が月山道路を介して直結されるなど一層の整備促進を図る。
また、第32回国土開発幹線自動車道建設審議会(平成11年12月)の議を経て新たに整備計画が策定された区間を含め、整備計画区間のうち施行命令が出されていない278kmについては、日本道路公団において行う所要の調査を踏まえ逐次事業着手する。
本州四国連絡道路については、平成11年5月に尾道・今治ルートの海峡部橋梁の供用により、3ルートが概成している。平成12年度は、尾道・今治ルートの島嶼部にある未開通部の工事及び神戸・鳴門ルートと四国横断自動車道との接続工事を継続する。
併せて、東京外かく環状道路、首都圏中央連絡自動車道及び東海環状自動車道等の大都市圏の環状道路の整備を重点的に行い、都市圏の再構築を支援する。
一方、高規格幹線道路とこれに次ぐ全国的な幹線道路ネットワークである一般国道のサービスレベルには、大きな格差が存在する。このため、全国総合開発計画「21世紀の国土のグランドデザイン」等の位置付けを踏まえ、高規格幹線道路と一体となって、地域発展の核となる都市圏の育成や地域相互の交流促進、空港・港湾等の広域交通拠点との連結に資する路線を地域高規格道路として整備を進める。
平成12年度は、計画路線に指定されている187路線(約6,950km)について、調査区間・整備区間の指定(表2−VII−2)を踏まえて、14区間77kmについて新たに着工準備を行うとともに、6区間24kmについて新たに事業に着手するなど整備を推進し、福島空港・あぶくま南道路((主)矢吹小野線)等の供用を図る予定である。
ロ)広域的な幹線道路網の整備計画の策定手続等の明確化
国と地方の役割を明確にし、広域的な幹線道路網が効率的・効果的に機能を発揮するように、その整備計画の内容及び手続等を明確化する。
ハ)高規格幹線道路等の整備及び利用の促進を支援する制度の創設
高速自動車国道と一体的に地方公共団体により実施される側道整備等において、地方負担の平準化を図ることにより高速自動車国道事業の円滑な実施を確保するため、その用地取得費に対して道路開発資金による低利融資制度を創設した。また、追加インターチェンジの整備により地域の活性化を促進するため、地方公共団体が、一般道路事業と有料道路事業を組み合わせて高速自動車国道のインターチェンジの整備を行う「地域活性化インターチェンジ制度」を創設した。
ニ)新交通軸の形成
「新しい国土軸」「多様な地域連携軸」の形成に向けた構想が各地で提唱されており、併せてその根幹となる基盤として海峡横断道路等のプロジェクトが提唱されている(図2−VII−36)。また、平成10年3月に閣議決定された「21世紀の国土のグランドデザイン」においても、海峡横断道路プロジェクトが盛り込まれたところである。これらのプロジェクトは新たな交通軸として、新たな交流圏の形成による地域活性化、振興を図るものであり、阪神・淡路大震災の教訓も踏まえてその形成に向けた調査を推進している。
平成12年度は、コスト縮減に資する技術開発を一層推進するとともに、各プロジェクトが、地域振興に及ぼす効果などを含めた費用対効果や事業手法についての検討を引き続き行う予定である。
2) 物流効率化の支援
物流コストの削減やユーザーニーズに対応した物流サービスを提供するため、総合物流施策大綱(平成9年4月4日閣議決定)に基づき、関係省庁連携のもと社会資本整備、規制緩和、物流の高度化・効率化の推進を図る。
イ)広域物流ネットワークの整備
広域的な視点での交通基盤の利用効率の向上を図るため、「広域交通基盤連携強化計画」を策定し、アクセス強化、交通結節点の改善、情報提供の推進を図るなどの施策を展開する。
具体的には、高規格幹線道路等の道路ネットワーク、国際空港・港湾、広域物流拠点等の国際交流基盤を総合的・重点的に整備する「国際交流インフラ推進事業」を推進する。また、複合一貫輸送を推進するため、内貿ターミナルと高規格幹線道路等との連絡を強化する道路等、主要な物流拠点とのアクセスを強化する道路整備を重点的に推進する。
物流拠点、重要港湾等を連絡する高規格幹線道路、一般国道等を中心とする約6万kmのネットワークのうち、約3.9万kmについては平成11年度末までに車両の大型化(車両の長さ及び軸距に応じ総重量最大25t)に対応した橋梁の補強等の整備を完了しており、残る約2.1万kmについては平成14年度までに整備を行う。平成12年度は約3,000kmについて橋梁の補強等を行う。
この大型化に対応した道路ネットワークにおいて、総重量最大25tの車両は自由走行が可能となり、フル積載したISO規格海上コンテナを運搬する車両は、特殊車両通行許可により通行が可能となる。
ロ)都市内物流対策
都市圏交通円滑化総合計画等を踏まえつつ、中心市街地等において、複数箇所の小規模な駐車スペースを整備し、一体的に運営するトラック荷捌き効率化事業等を推進する。また、都市圏におけるこれからの物流施設整備のあり方について、東京・丸ノ内地区をケース・スタディとした検討を平成12年度より開始する。
ハ)物流拠点の整備支援
高速自動車国道法等の一部改正を受け、民間事業者等が高速道路と連結する物流拠点の整備を行う場合、連結通路等の整備に対し、道路開発資金制度及び日本政策投資銀行による融資を行う。また、高規格幹線道路のIC周辺において、広域物流拠点の整備について、関連道路の一体的整備等により支援する。
ニ)研究開発の推進
ETC等ITSの実用化・展開と併せ、ITS関連情報を活用した物流の効率化や、新物流システムについて、研究開発を進める。
チ 更新時代を見据えた安全性・信頼性の高い道路空間の確保
1) 更新時代を見据えた道路管理
道路ストックの増加と老朽化に伴い道路維持管理費は増大しており、橋梁で言えば、全国約66万橋の建設後の平均供用期間は、約22年であるが、21世紀初頭には米国なみの約35年となる見込みであり、道路投資に対する維持管理費の比率が現在の約2割から倍増するとの試算もある。
21世紀には国民的資産である道路の修繕・更新の時代を向かえることとなるが、これら増大する維持管理や修繕更新コストを抑制しつつ国民のニーズに応え、道路ストックの健全性、信頼性を維持し、次世代に良好な資産として引き継ぐための「道路ストック管理」が求められている。
イ)緊急点検と計画的な維持管理
本格的な修繕・更新時代をひかえ、構造物の長寿命化技術や修繕・更新工法等の経済化、交通への影響を軽減する工法・技術の開発などを推進することが求められている。また、コンクリート構造物等の破損による道路利用者等への被害防止の観点を重視した緊急点検・緊急対策を実施するなど、一層の管理の強化を行うとともに、老朽化する道路ストックの急増に対処するために、計画的な維持管理を行う。
特に、トンネル等の構造物や道路付属物の安全性・信頼性の確保に向け、有識者からなる検討委員会を設定し、これまでの損傷事例を調査して、必要な点検手法や補修方法の検討を行い、適切な管理を実施する。
ロ)道路管理の高度化・効率化
さらに、国民が快適に安心して道路を利用できるよう、道路利用者の求める道路情報を提供し、災害時や異常気象時において危機管理のために迅速に降雨量、積雪、風速、震度等の道路情報を収集・提供することが求められている。そのため、道路管理用光ファイバーやGPS、ITV等情報通信技術を活用して橋梁や岩盤斜面等の状況を把握して変状に即応できるシステムを構築するなど、より信頼性の高い道路管理体制の構築を推進する。また、特殊車両の通行に関し、インターネットを利用した特殊車両通行許可の申請支援システムを導入するとともに、車両計測装置等を活用した車両制限令違反車両の指導・取締りの効率化に取り組む。
ハ)住民参加・連携による道路管理
これらの道路ストックを効率的に、確実に維持管理するため、老朽化に対応した構造物の定期点検及び健全度評価、これに基づく計画的維持管理を実施する仕組みの構築に合わせて、地域に相応しい道づくりを進めるために、地域に密着した道路の清掃や植樹管理等についての支援等、積極的な住民の参加・連携の強化などのパートナーシップを背景とした取組みを進める(図2−VII−37、図2−VII−38、図2−VII−39)。
2) 道路の防災対策・危機管理の充実
我が国の国土は地震、豪雨、豪雪、急峻な地形、脆弱な地質等、厳しい自然環境下にある。
最近では、平成7年の阪神・淡路大震災をはじめ、平成8年2月の豊浜トンネル岩盤崩落等多くの災害が発生しており、平成11年においても6月の広島の土砂災害や福岡の地下街水没災害、8月の豪雨によりキャンプ客が孤立する等の災害があったことは記憶に新しい。
このように多くの災害が発生する中で、災害を未然に防止し、さらに迅速な復旧を図ることは重要であり、特に国民の生活を支える道路の防災対策を積極的に推進する必要がある。
イ)防災・震災対策の重点的な実施による安全と信頼性の確保
i)道路利用者の立場から、高次医療機関へのアクセス性や生活必需物資の安定供給の確実性等を重視し、災害に強い広域幹線道路ネットワークの形成を進め、安全で安心できる生活を支える道路空間を確保するための防災・震災対策を進める。
ii)道路防災総点検、岩盤斜面等の緊急調査を受けた防災対策を進めるとともに、治山事業と連携した落石対策を進める。
iii)阪神・淡路大震災等の災害の経験を踏まえ、緊急輸送道路に係る橋梁等を中心に耐震補強を実施する。
iv)災害時のライフラインの安全性に資する共同溝等の整備を進める。
v)安心できる市街地の形成に資する土地区画整理事業、市街地再開発事業等及び避難路の整備を進める。
ロ)地域との連携の強化・情報の提供
i)地域の住民の方、郵便配達や宅配便など日常的に道路を通行している道路利用者からの情報収集により、よりきめの細かい防災管理を行う。
ii)インターネットを活用した路面状況の提供など道路管理の情報化を図り、地域と連携した防災管理体制を構築する。
ハ)冬期道路交通確保の推進
国土面積の約6割、都道府県数の約4割、人口の約2割を占める積雪寒冷特別地域において、生活の安定の確保や地域の振興を図るとともに、国民に広く諸活動の場を提供するため、地域の特性に応じた適切な冬期道路交通対策を推進する必要がある。
このため、新積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画に基づき以下の事業を推進する。
i)広域的な交流機能を維持し、社会活動の安定を図るため、拠点間を結ぶ主要な広域幹線道路について、除雪、防雪事業を重点的に推進する。
ii)冬期の交通支障箇所となっている凍結路面箇所等において消雪施設を重点的に整備するとともに、中心市街地や通学路、福祉施設周辺等における歩行空間の確保、市街地内における流雪溝の整備、地域と連携した雪処理を進める。また、老朽化した雪寒施設の計画的な維持保全及び更新を図る。
iii)気象情報等の収集装置の整備を進めるとともに、きめの細かい気象情報・路面情報の提供を行う。チェーン着脱場では道の駅等の機能を備え、情報提供機能の強化を図る。また、除雪機械の省力化・省人化、冬期の安全な走行を支援する技術等の新たな雪寒技術を積極的に活用し、より効果的、効率的な雪寒対策を推進する(図2−VII−40、図2−VII−41)。