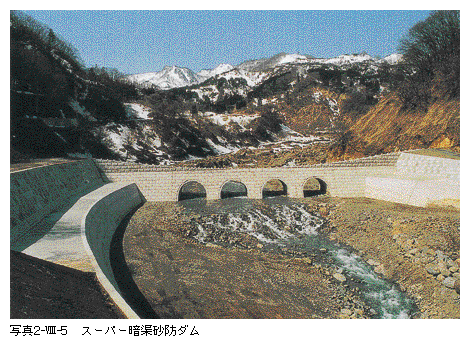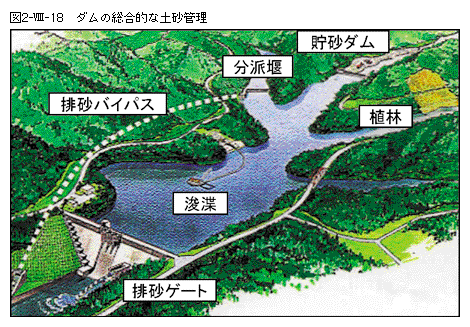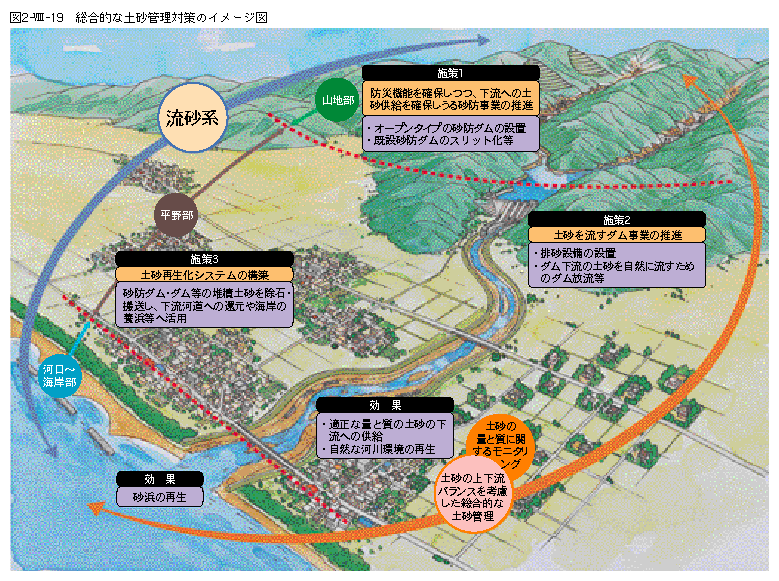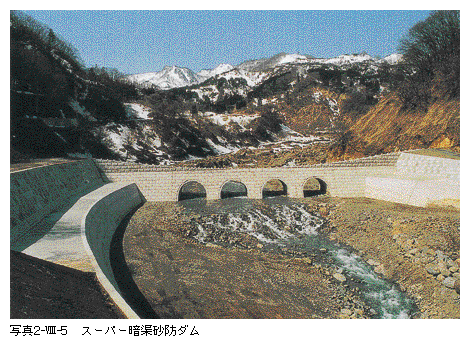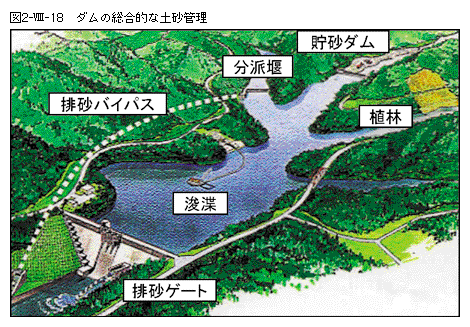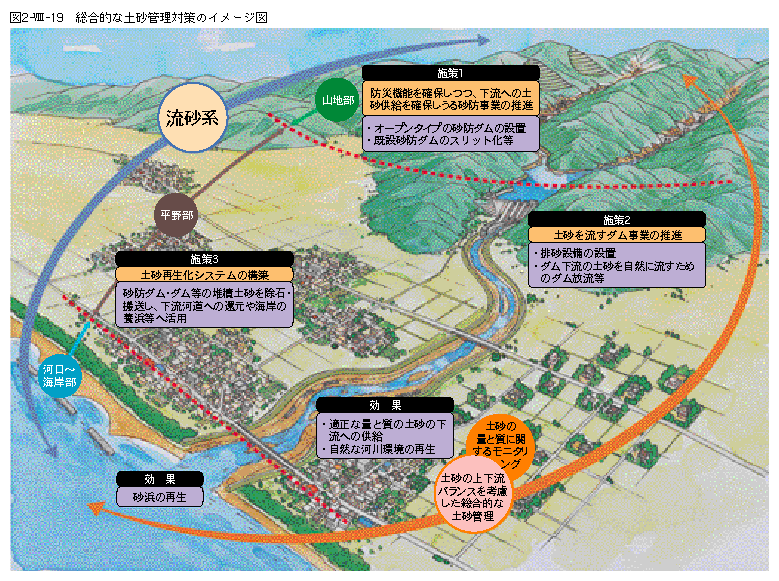(4)信頼感ある安全で安心できる国土の形成
イ 洪水や高潮による災害を防止する治水事業
平成12年度の河川事業は、事業費総額約1兆942億円で実施する。
事業内容として、洪水や高潮に対して安全で安心できる国土をつくるため、利根川等の大河川及び中小河川の整備を推進する。
また、土地利用や経済社会活動が高度化した都市部においては、都市計画、下水道整備、住宅などまちづくりに関連する施策と調整・統合を図りながら治水対策を実施し、さらに、都市化により治水安全度の低下の著しい河川について、流域全体での保水・遊水機能の確保や土地利用の誘導などの総合的な治水対策を実施する。
1) 治水施設の信頼性の向上の推進
大都市地域を大洪水時の破堤から守り、併せて良好な水辺空間の形成を図る高規格堤防(スーパー堤防)整備事業を荒川、利根川、江戸川、多摩川、淀川及び大和川において引き続き実施する。
2) 流域と一体となった総合的な治水対策の推進
特に都市化の進展が著しい流域や市街地が大部分を占める流域においては、治水施設の整備のみでは流域全体の十分な治水安全度の早急な確保が困難な場合がある。このような流域において、流域の保水・遊水機能の確保・増進を図るため、流域の適正な土地利用や流出抑制対策等を総合的に実施する総合治水対策を推進し、都市の発展と成熟に対応した治水安全度の確保を図る。
さらに、学校、公園等を貯留若しくは浸透機能を持つ構造とすること等により流出抑制を図る流域貯留浸透事業や、総合的な治水対策と地下水かん養による水環境対策とを併せて実施する流域水環境総合整備モデル事業等を推進する。
3) 再度災害防止対策の推進
上下流一体となった抜本的な治水対策として、河川災害復旧等関連緊急事業を推進するとともに、激甚な水害の再発を防止する河川激甚災害対策特別緊急事業を実施する。また、床上浸水被害の頻発地域、浸水域の高齢化率の高い地域、及び都市機能の進んだ地域において、築堤、排水機場の整備等、河川事業を集中的に実施し、概ね5年間で被害の解消を図る。
4) 都市河川事業の推進
都市河川事業としては、総合的な治水対策のための治水施設の整備及び流域対策を推進するほか、通常の河道改修に加え、公園等の都市施設と一体となった遊水地、大規模宅地開発等に対応して実施する防災調節池等の整備を重点的に実施する。また、安全で快適なうるおいある都市づくりのため、改修に際して親水性の確保や景色に配慮する。
低地河川については、高潮対策、耐震対策、地盤沈下対策等を行う低地対策河川事業を推進する。また、既成市街地及び周辺地域等において、河川整備と一体となって行われる盛土等の事業により堤防の強化及び河川空間を活かした良好な市街地整備を図る特定地域堤防機能高度化事業を推進する。
さらに、土地利用が高度化した都市における治水対策の一手法として、東京地下河川(東京都)、寝屋川南部地下河川(大阪府)等、地下空間を利用した治水施設の整備を推進するとともに、河川立体区域制度の活用により、河川事業用地の円滑な取得と河川事業の進捗を図る。
5) 下水道関連河川事業の推進
河川の流下能力の不足のため、下水道事業による雨水対策効果が十分に上げられない地域に係る治水事業や、公共用水域の水環境の改善のため、下水道事業と協調して行う治水事業である下水道関連特定治水施設整備事業を実施する。
6) 構造物の機能確保・改善対策の推進
特定構造物改築事業等を直轄管理河川において推進するとともに、補助事業として、老朽化等により治水上著しく支障となっている大規模な河川管理施設等や、鉄道橋の改築を進める河川構造物改築事業及び鉄道橋緊急対策事業等を促進する。
ロ 水資源の安定供給への取組み
1) ダム等建設事業の推進
広域的かつ抜本的な治水対策と、国民生活の向上及び産業の発展に不可欠な水資源の安定的な確保を目的として、多目的ダム、河口堰、流況調整河川等多種多様な手法を用いて水資源開発を推進する。このほか既設のダムの有効利用を図るためのダム群連携事業、消流雪用水の確保を図る雪対策ダム事業、地域に密着した局地的な治水・利水対策を行う生活貯水池整備事業等、地域特性を考慮したきめ細かいダム事業を推進する。さらに、地域の創意工夫を活かし、地域へダムの一層の開放を図る「地域に開かれたダム」事業を実施すること等により、地域の活性化を図っている。
また、良好なダムサイトの減少、熟練労働者の減少・高齢化等により、より合理的、経済的なダム建設のための技術開発が課題となっており、そのための新たな技術開発を推進するとともに、堆砂対策、濁水・富栄養化対策等ダム水源地域の環境整備に関する調査・研究の推進を図る。
平成12年度の河川総合開発事業は、共同事業費6,332億円(公共費4,935億円、利水者負担金1,397億円)であり、平成12年度完成予定事業をはじめ、渇水が頻発している地域において早期に整備効果が期待される宮ヶ瀬ダム等や、農山村等の生活用水の早期安定確保を図る生活貯水池整備事業を重点的に推進する。また、ダムを水源とした新たな工業団地造成や宅地開発などが計画されている地域において、民間投資を誘発するために安定的な水供給を可能とするダムを緊急的に整備する。
2) 異常渇水対策の推進
被害を最小限にとどめるべく異常渇水(計画上10年に1回発生する渇水を上回る渇水)の際に必要最小限の水を確保するため、渇水頻発地域における水資源開発施設の整備、渇水対策ダムの整備、水系間水融通等を推進している。渇水対策ダムの整備については、平成12年度は、木曽川・徳山ダム(岐阜県)等10事業を推進し、また、流域内外の河川水を緊急的に導水し、必要最小限の水を確保する河川の広域ネットワークの形成を図るため、現在実施中の流況調整河川3事業等を推進する。
3) 水源地域対策等の推進
ダム建設事業を円滑に進めるためには、水没関係者の生活再建、水源地域の整備等の推進が必要であり、補償措置に加えて、水源地域対策特別措置法に基づく整備事業の実施、水源地域対策基金による事業の実施等により総合的な対策を行っている。平成12年3月末現在、同法の適用指定ダム等として、建設省所管のダム等では86ダム等が指定され、このうち74ダム等で水源地域整備計画の決定が行われている。
4) 水利用の適正化と合理的な水利調整
都市用水の需給が逼迫している地域において、既存の水利使用を合理化し、余剰水を都市用水に転用することにより水利用の適正化を図っている(一級河川における昭和40年度〜平成11年度の転用許可140件、転用量62m3/s)。
また、河川環境の保全のため、水利使用許可に当たり、河川維持流量の確保、水質、魚道の設置等に十分配慮した審査を行っているほか、発電水利使用で、河川維持流量の確保が不十分なものについて、許可更新時に河川環境の改善のために必要な流量を放流することとしている(平成12年3月現在、301発電所について措置済み)。
また、平成7年度より全国的な規模で主として慣行による農業用水の実態調査を農林水産省と共同で行い、農業用水の利用実態等の把握に努めている。
異常渇水時には、関係利水者間の調整を円滑に行うことが重要であり、渇水が予想される重要水系について常設の渇水調整協議会の設立を指導してきたが、平成12年3月末現在で、一級河川109水系のうち、66水系において69組織の常設の協議会及び22組織の非常設の協議会が設立されており、渇水調整の円滑化に寄与した。また、必要に応じて地方建設局に渇水対策本部を設置し、渇水情報の収集、連絡及び関係利水者間の調整を行うこととしている。
ハ 土砂災害から人命・財産を守る砂防事業の推進
平成12年度は、第9次治水事業七箇年計画の4年目として、安全で安心できる福祉社会の実現に向けて、災害弱者関連施設に係る総合的な土砂災害対策をハード・ソフト両面から強力に推進していくとともに、土砂災害の発生の危険性が高い都市域のうち、緊急に整備が必要となる都市域の山麓部について一連の樹林帯の形成を図り、住民の生命、財産を土砂災害による壊滅的な被害から防御することを目的として都市山麓グリーンベルト整備事業を引き続き推進する。
1) 砂防事業の推進
平成12年度は、事業費3,228億円をもって、重荒廃地域における根幹的な土砂災害対策、総合的な土砂災害対策、総合的な火山砂防事業の推進等の激甚な土砂災害から人命・財産を守る土砂災害対策を強化推進するとともに、野外活動拠点の整備等の生活関連の社会資本整備を推進する。さらに、水系一貫した総合土砂管理対策の推進、総合的な流木災害防止緊急対策(林野庁)、郵便局との連携による地域防災体制の強化(郵政省)等の他省庁との連携施策など効果的・効率的に事業を推進する。
また、砂防設備の整備に当たっては従来の流路工のような画一的な施設計画をやめ、各地の渓流に見合った安全を確保するため、安全で地域環境に調和した整備を推進する。
2) 地すべり対策事業の推進
平成12年度は、事業総額460億円をもって事業を実施するとともに、豪雨等により被災した地域など緊急に対策を実施する必要のある区域、病院、老人ホーム、幼稚園等の災害弱者に関連した施設を保全対象とする地区、主要な国道・鉄道が並行している等の交通網集中地域、同時多発的な土砂災害の危険性の高い都市山麓部など、社会的経済的影響の大きい地域における対策を推進する。
また、地すべり対策に伴って創出される安全な斜面空間や排出される地下水の有効利用によって地域の活性化と生活環境の改善の支援や、情報基盤整備など警戒避難体制の整備等を含めた総合的な対策を推進する。
3) 総合的な土砂災害対策の推進
昭和57年の「総合的な土石流対策の推進」(事務次官通達)、さらに昭和63年の河川審議会での「総合的な治水対策の実施方策についての提言」等を踏まえ、土石流、地すべり、がけ崩れに対処するために砂防設備等の整備を強力に推進するとともに、人命保護の立場から土砂災害危険箇所図や土砂災害氾濫(予想)区域図の作成・公表、表示板の設置、広報紙等を利用した住民への危険箇所の周知等の警戒避難体制の整備を推進しているところである。また、近年頻発する激甚な土砂災害に対して警戒避難体制の一層の強化を図るため、平成10年7月10日に「総合的な土石流対策の推進」(昭和57年、事務次官通達)の一部を改正し都道府県知事等に対して、i)都道府県、市町村の地域防災計画に土石流危険区域、警戒避難基準に関する資料を掲載すること、ii)土石流危険区域及びその周辺の地域住民からなる土石流に関する自主的な防災組織を育成するよう指導すること、iii)保全対象人家戸数1〜4戸についても、5戸以上の土石流危険渓流と同様の土砂災害対策に取り組むこと等を旨とする通達を発出した。
平成12年度は引き続き、上記通達の一部改正を踏まえて、各都道府県土木事務所等、市町村役場における土砂災害110番の開設、雨量情報表示板の設置、ダイレクトメールの送付、土砂災害危険区域図の作成・公表、警戒避難基準の設定等の土砂災害防止、軽減に資する諸施策を強化推進する。
また、昭和58年より毎年6月を土砂災害防止月間と定め、「みんなで防ごう土砂災害」をテーマに土砂災害防止に関する関心を深めるとともに知識の普及等を図っている。平成12年度は6月1日〜2日、栃木県宇都宮市等において「土砂災害防止月間推進の集い(全国大会)」を開催するとともに、同月間の主旨を幅広く広報するため小学生や中学生を対象とした絵画・ポスター・作文を募集・表彰、土砂災害防止功労者の表彰等を実施している。
4) 火山砂防対策の推進
火山砂防事業としての砂防設備の整備等を推進する。また、噴火等の恐れのある火山においては、住民の警戒避難体制の整備に資するため、火山災害予想区域図の作成、雨量計、ワイヤーセンサー、監視カメラ等の設置を行う火山噴火警戒避難対策事業を実施するとともに、火山活動が活発で、現在警戒避難体制の整備に取り組んでいる火山について、大規模火山泥流対策施設等の整備を重点的に実施し、火山災害予想区域図の作成・公表を推進する。
ニ 安全で災害のない斜面づくりの推進
1) 急傾斜地崩壊対策事業の推進
平成12年度は、事業費980億円をもって、災害発生箇所等の施設整備を推進するとともに、土砂災害の犠牲者となりやすい高齢者、幼児などの災害弱者に関連した施設(病院、幼稚園等)を保全対象に含む急傾斜地崩壊危険箇所等を重点的に整備する。
2) 警戒避難体制の整備とボランティアとの連携
土砂災害に関する情報を住民から受け付ける「土砂災害110番」制度の充実やボランティア団体と連携して「斜面カルテ」を整備するなど、いち早くがけ崩れ等の危険性を把握し住民が早期に避難できる体制の整備を図る。
ホ 雪崩及び雪対策事業の推進
1) 雪崩対策事業の推進
集落における雪崩災害から人命を保護するため、平成12年度は事業費48億円をもって雪崩防止施設を整備するとともに、警戒避難体制の整備等ソフト対策を実施する総合雪崩対策モデル事業を引き続き実施する。
2) 雪対策事業の推進
豪雪地帯においては、融雪時の出水や雪崩に伴う土砂流出防止に資する砂防ダム及び流雪機能を発揮できる低水路等の整備を総合的・包括的に実施する。
ヘ 美しく、安全で、いきいきした海岸を目指して
平成12年度は、建設省所管海岸事業費586億円をもって事業の推進を図る。
我が国は台風の常襲地帯にあり、地震多発地帯で津波の来襲も多いという厳しい地理的・自然的条件にあり、海岸侵食も全国的に顕在化してきている。
平成12年4月に改正海岸法が施行されたことに鑑み、多様な海洋性レクリエーション需要の増大に伴う海浜利用や生物の生息・生育地の確保、景観に配慮していく「防護」「環境」「利用」の調和した海岸保全を今後は一層推進する。
具体的には、人工リーフ、養浜、緩傾斜護岸等の複数の施設で波浪エネルギーを分散して受け持つ面的防護方式による整備や漁港事業等と連携し漁港等の港内の浚渫土砂等を海岸侵食が顕著な海岸に輸送する「渚の創生」等により砂浜の保全・回復を主体とした整備を推進する。
また、他の事業との連携も積極的に進めており、海岸保全対策とあわせて公園等の建設省所管公共事業及び民間活力を積極的に導入した施設整備を一体的かつ計画的に行う「コースタル・コミュニティ・ゾーン(CCZ)整備」や水産庁所管の沿岸漁場整備開発事業との連携による「魚を育む海岸づくり」により一体的な整備を行い、水産生物との共生を目指した海岸事業を推進するとともに、厚生省と連携し、海岸浴による人々の健康増進を図るため、周辺の砂浜の保全・復元、遊歩道の整備を図るなど、健康増進のために利用しやすい海岸づくり等を行う「海と緑の健康地域づくり(健康海岸事業)」を推進する。
さらに、文部省所管の教育関連施設と連携し、海岸保全を図りつつ、海辺における野外学習等を支援する「いきいき・海の子・浜づくり」を推進する。
平成12年度からは、海岸事業と治山事業の連携による「自然豊かな海と緑の整備対策事業(白砂青松の創出)」を推進し、自然環境と利用に配慮した海岸整備を実施する。
一方、平成7年1月の阪神・淡路大震災の被害に鑑み、地盤の軟弱な地域やゼロメートル地帯での海岸保全施設の耐震性強化や、地盤液状化への対応など、被害が想定される地域での安全性の向上を図る。さらに、津波による壊滅的な被害を回避するため、海岸4省庁所管の水門等の施設を一元的に遠隔制御する「津波防災ステーション」の整備を推進するとともに、堤防等の新設、改良等の津波対策の総合的な推進を図り、津波に対する安全性の向上を図る。
近年の著しい侵食により堤防の倒壊等大きな災害が発生している仙台湾南部海岸については、平成12年度より建設大臣が代行して事業を進める。仙台市から福島県境に及ぶ長大な砂浜海岸の背後には、政令指定都市である仙台市、JR常磐線等があり、交通輸送上も重要な地域である。このため、特に侵食の激しい区域について平成12年度より直轄化し、防災機能を強化するため、砂浜の保全・創出を主体とした抜本的な侵食対策を実施する。
我が国最南端の島である沖ノ鳥島については、周辺に沖ノ鳥島を基線とする巨大な排他的経済水域(日本の国土面積よりやや広い約40万km2)が存在する極めて重要な島であるため、平成11年の海岸法の改正により直轄管理海岸とし、沖ノ鳥島の保全をすべて国の費用により実施することとした。沖ノ鳥島の保全に万全を期すように、引き続き維持管理に努めている。
現在、海域については様々な機能に着目した保全や利用がなされており、また年々利用の形態が増えており、海域はより輻輳した空間となりつつある。そのため、国内及び諸外国における海域の公物管理や保全、利用の実態、最新技術による新たな利用の可能性を把握し、現状における課題の抽出や、望ましい海域の公物管理のあり方に関する検討を進めている。
ト 平成11年発生災害と災害復旧事業等の実施状況
1) 平成11年発生災害に対する施策
平成11年建設省所管公共土木施設に係る被害報告額は6,108億円であった。これに対し災害復旧事業費4,957億円(直轄事業費1,220億円(709箇所)、補助事業費3,737億円(39,579箇所))、災害関連事業費1,090億円(174箇所)(うち関連費602億円)、災害関連緊急事業費894億円(直轄277億円、補助617億円)を決定し、早期復旧を図ることとした。
2) 公共土木施設災害復旧事業等
イ)災害復旧事業
平成11年度は、当初事業費436億円に加え、4,231億円の公共事業等予備費、補正を行い、平成9年災害に係る事業の完了、平成10年災害に係る事業の一層の促進を図った。また、平成11年発生災害について約86%の復旧を図ることとした。
ロ)災害関連事業
再度災害防止の見地から、災害復旧事業のみでは十分効果を期待できない被災箇所について、改良費を加えて一定計画等に基づく改良復旧を図るため、平成11年度は、当初事業費115億円に加え、373億円の補正を行い、平成10年梅雨前線豪雨災害等に係る事業の一層の促進を図るとともに、広島県を中心とした平成11年6月末梅雨前線豪雨による土砂災害、9月下旬に熊本県で発生した台風18号による高潮災害等に係る事業に着手した。
ハ)降灰除去事業
火山の爆発に伴う道路の降灰被害に対処するため、平成11年度は、桜島に係る鹿児島市及び桜島町で事業を実施した。
3) 災害関連緊急事業
再度災害の防止を図るため、災害復旧事業と関連して一定の復旧改良を緊急に行い、豪雨等により生じた土砂の崩壊等の危険な状況に緊急に対処するものであり、平成11年度は、当年発生災害に係る事業の完了を図った。
4) 激甚災害に対する特別財政援助
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)」に基づき、平成11年発生災害のうち「平成11年9月14日から同月24日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」など22災害が局地激甚災害として指定され、関係する114市町村(延べ124市町村)に対し、その財政負担の軽減を図った。
このうち、建設省所管の公共土木施設災害復旧事業等については、富山県利賀村等40市町村(延べ41市町村)の特定地方公共団体に対し、約27億6,000万円の特別財政援助(国庫負担率の嵩上げ)が行われた。
チ 総合的な土砂管理の推進
砂防、ダム、河川、海岸等の各領域で個別になされてきた土砂対策について、生態系、景観等の環境面を含めた土砂移動に係る問題を解決するため、森林を含む山地部から海岸までの土砂の運動領域を「流砂系」という概念で捉え、海岸侵食、河床低下など土砂管理上問題が顕在化している流砂系において、総合的な土砂管理の推進を図るため広域的・長期的な視点から土砂移動状況について、流砂系の一貫した土砂の量と質に関するモニタリングを実施するとともに、既存のデータも活用して分析を行う。
また、適切な量の土砂を供給するための「スーパー暗渠砂防ダム」の整備、「ダムの排砂設備」の設置等により自然な土砂の流れを再生するとともに、砂防事業と海岸事業が連携して行う海岸侵食対策のための養浜等を実施し、良好な環境の保全・再生を実現する(写真2−VIII−5、図2−VIII−18、図2−VIII−19)。
リ 震災対策等の拡充
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災を踏まえた、河川管理施設等の耐震設計のあり方等に関する検討結果を受けて、ゼロメートル地帯等における耐震性の高い河川、海岸堤防の整備等、必要に応じた既存施設の耐震性の点検及び耐震対策を実施している。
また、消火用水等の確保に資する河川整備、災害時における輸送手段の確保を目的とした緊急用河川敷道路及び河川舟運のための船着場等の整備、大河川と緊急輸送道路との結節点に設置され緊急時の人員・物資の広域的輸送支援等を担う内陸防災拠点の整備、緊急時の救援活動の拠点やヘリポート等として活用できる河川防災ステーションの整備、水門等の一元的な遠隔制御を図る津波防災ステーションの整備、地震による崩壊等が多発する危険性の高い流域における重点的な砂防設備の整備、危険箇所が集中している都市部における急傾斜地崩壊防止対策、災害対策用機械の整備等の推進を図っているところである。
さらに、平成8年1月に発足した「防災エキスパート制度」を拡充し、地震により被災した公共土木施設等の被害情報の迅速な収集等を行うための体制の充実強化を図るとともに、地震に関する観測・調査・研究として、GPS連続観測による地殻変動監視の拡充・強化、断層等の活構造調査や耐震対策に関する各種調査研究等を推進している。
平成7年6月に成立した地震防災対策特別措置法に基づき都道府県知事が作成した地震防災緊急事業五箇年計画に基づき、河川管理施設、海岸保全施設、砂防設備、地域防災拠点施設等の整備を推進している。なお、東海地震に係る関係6県においては、地震対策緊急整備事業計画に基づき、河川管理施設、海岸保全施設、避難地・避難路等の整備も行っている。