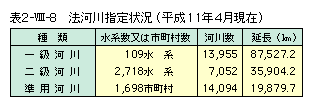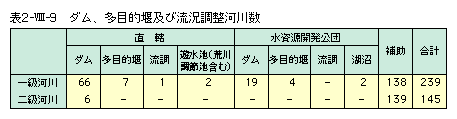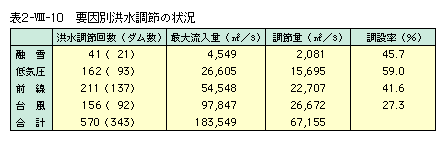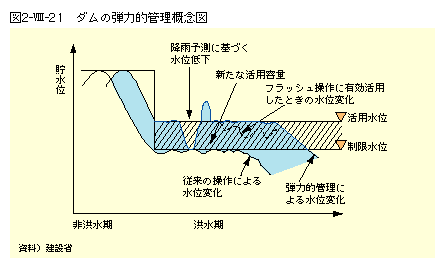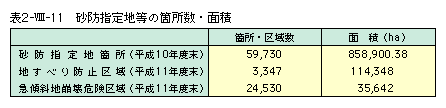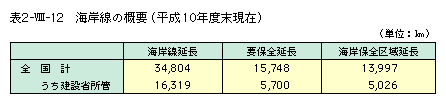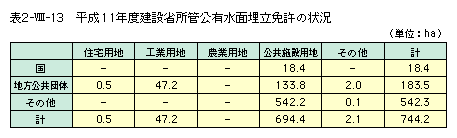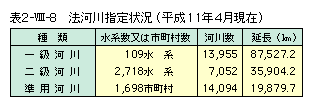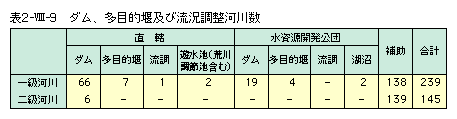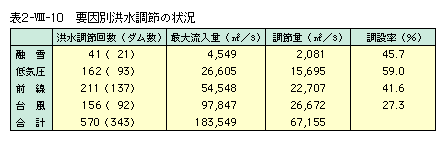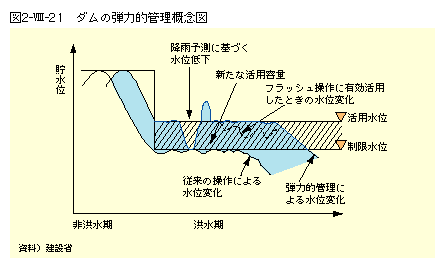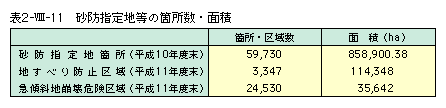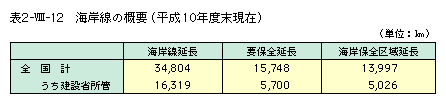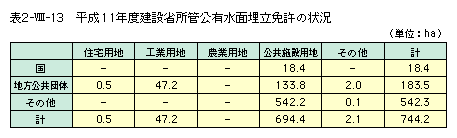(8)河川管理等の充実
イ 河川管理の充実
河川法により指定されている河川の状況は、表2-VIII-8のとおりである。
毎年7月を河川愛護月間として定め、河川愛護思想の普及と河川美化の促進等の運動を展開しているほか、「河川砂利基本対策要綱」に基づく規制計画の策定及び特定採取制度の導入等により総合的な河川砂利対策を推進している。
平成9年の河川法の改正により、河川の管理は、治水、利水及び環境の整備と保全が達成されるよう総合的に行うべきこととされた。河川敷地の占用許可制度についても、これに対応した見直しを行い、河川審議会の答申を受け、平成11年8月に河川敷地占用許可準則(事務次官通達)の改正を行い各河川管理者に通知した。
従来の占用許可準則からの主な改正点は、次のとおりである。
・占用許可申請について、地元市町村等の意見を聴くこととしたこと。
・占用主体に、市街地開発事業を行う者並びに水面利用調整協議会等で認められた船舶係留施設等の整備を行う者を追加したこと。
・占用施設に、遊歩道、階段等の親水施設、堤防の天端若しくは裏小段又は地下に設置する道路等を追加したこと。
・地元市町村が占用許可後に河川敷地の具体的利用方法を決定することができる「包括占用許可」の制度を創設したこと。
係属中の訴訟は、平成12年4月1日現在106件である。平成11年度の主な判決としては丸山町賤機山損害賠償請求上告審判決、九十九里浜(一宮町)建物収去明渡請求上告審判決があり、いずれも国等が勝訴した。
ロ 不法係留船対策の促進
河川区域内の不法係留船は、洪水の流下の阻害、船舶が流出した場合の河川管理施設の損傷、河川工事の実施の支障等の治水上の支障のほか、一般公衆の自由使用の妨げ、騒音の発生、景観の阻害等様々な面で河川管理上の支障となっている。このため、平成7年及び平成9年に河川法が改正され、簡易代執行制度の創設により不法係留船の撤去手続の整備を図っているが、不法係留船の増大に加え、マリーナ等恒久的な係留・保管施設の建設が十分に進んでいないことから、一挙に強制的な撤去措置を執ることが困難な状況にある。
このため、平成10年2月、「計画的な不法係留船対策の促進について」(河川局長通達)を地方建設局長等及び都道府県知事あて通知し、今後は河川管理上の支障の程度に応じて計画的に不法係留船対策を促進していくこととした。
ハ 安全な生活と環境を守るダム等の管理の充実
1) ダム等の管理の充実
建設省所管の管理ダム数は、表2-VIII-9の通りである。
これらのダムは、平成11年度に全国でのべ705回の洪水調節を実施し洪水被害の軽減に寄与したが、これを洪水の要因例にみると表2-VIII-10のようになる。
一方、利水面では、建設省所管ダムより流水の正常な機能の維持のために約70億m3、都市用水のために約80億m3、農業用水のために約14億m3の放流を行ったほか、発電のために約680億m3(流水の正常な機能の維持約23億m3、都市用水約8.4億m3、かんがい約25億m3を含む)が使用された。
ダム貯水池内の堆砂状況については、全国的には総貯水容量に対して7%程度となっているが、ダムごとにみると地質が脆弱な一部のダムで堆砂の進行の早いものもあり、今後とも積極的に堆砂対策を進める必要がある。
ダム管理については、洪水時、渇水時におけるダム機能の十分な発揮等、ダムの的確な管理を行うため、管理設備の維持及び整備の推進に努めている。
また、利水ダム管理主任技術者の認定等の実施や、ダム管理技士制度の活用によるダム管理の一層の強化を図っている。
2) ダムの弾力的運用の取組み
近年のダム管理技術や各種データの蓄積を踏まえ、平成9年6月からダムの弾力的管理を試行している。洪水調整を目的として建設されているダムでは、台風や梅雨等の洪水期の出水に備えるため、通常、ダムの容量の一部が空けられている。これに対し、今回試行されたダムの弾力的管理では、気象予測等により洪水が予想される場合、直ちに放流して洪水調整のための容量が安全に確保できる水位(活用水位)を新たに設定することにより、洪水期の通常の水位を従来より1〜2m高く維持する。これにより、従来に比べダムに新たな水量を確保し、清流回復や流況改善に活用するものである。ダムの弾力的管理は、平成9年度から寒河江ダム(山形県)をはじめとする全国7つのダムで試行している。例えば、寒河江ダムでは、洪水期間の貯水位を通常の水位より高く管理することにより、新たな容量を生み出し、平成9年から11年度の3年間で約860万m3の容量を活用することができた。この結果、洪水期間に1回/週を基本としたフラッシュ放流を35回実施し、河川の浄化等に役立てることができた。この他のダムについても、河川の流量の増量等により、ダム下流の清流回復に役立つなどの効果が報告されている(図2-VIII-21)。ダムの弾力的管理については、ダムが位置する河川及び流域状況の違いもあるため、安全管理に配慮しながら試行を積み重ねている。
ニ 砂防指定地等の管理の充実
治水上砂防のため、又は地すべり及び急傾斜地の崩壊による災害を防止するために、砂防設備、地すべり防止工事及び急傾斜地崩壊防止工事を要する土地、及び一定の行為を禁止又は制限する必要のある土地については、引き続き砂防指定地等の指定を促進し、管理の一層の強化を図る(表2-VIII-11)。
ホ 良好な海岸空間を求めて
津波、高潮等による災害が頻発しており、全国的に海岸侵食も顕在化していることから、施設整備による防護が必要な区域について海岸保全区域の指定を進めている(表2-VIII-12)。一方、海岸は優れた自然景観を有し、多様な生物の生息・生育の場であるとともに、国民の様々な利用にも供されている。平成12年4月に施行された改正海岸法において目的に「防護」に加え「環境」及び「利用」が追加され、これまで財産管理のみ行われていた海岸保全区域外の国有海浜地についても防護・環境・利用の調和のとれた海岸管理を行うよう一般公共海岸区域として海岸法に位置付けられ、海岸保全区域と併せて海岸管理者によって管理されることとなった。
さらに、改正海岸法を施行するに当たり、海岸法施行令、海岸法施行規則等の整備を行うため、海岸の占用及び海岸における制限行為に関する許可基準並びに海岸における禁止行為を定めることにし、その内容について広く国民のご意見をお聴きするためパブリック・コメントの募集を行った。
また、7月を海岸愛護月間として定め、地域住民等による清掃活動の実施や海岸愛護思想の普及と啓発を行っている。
へ 公有水面埋立ての適正な実施
我が国では埋立てが歴史的に大きな役割を果たしてきたが、埋立てに伴う自然的、社会的、経済的影響は重大であることから、免許に際しては国土利用上適正かつ合理的であるか、環境の保全や災害の防止に十分配慮されているか、埋立地の利用が適正に確保されるか等について慎重に検討し、処理することとしている。
平成11年度建設省所管公有水面埋立免許状況は、表2-VIII-13のとおりである。
ト 地下水管理の充実
地下水の保全と適正な利用を推進するため、地下水観測、水準測量、地盤沈下状況等の調査及び、流域の水循環を構成する地下水と河川を一体としてとらえ、その水収支等の適正化を図る地下水管理計画等策定調査を実施するとともに、地盤沈下防止等対策要綱対象地域等における適正な地下水管理を推進していく。また、地下水のかん養を図り、健全な水循環や治水安全度を確保するため、流域貯留浸透事業を拡充し、事業のより一層の推進を図る。
さらに、地盤沈下対策として、地下水の代替となる水源確保を行うダム等建設事業、地盤沈下が生じた地域における治水機能の回復を図る堤防の嵩上げ等の河川事業や、地すべり対策事業と地下水の有効利用を総合的に推進する特定地下水関連地すべり対策事業を実施する。
チ 河川行政の高度情報化
1) 河川情報伝達体制の整備の推進
洪水時等災害時において、建設省等の河川管理者が有する雨量、河川の水位等の河川情報を市町村や水防関係団体等に迅速かつ的確に伝達するため、(財)河川情報センターにおいて河川情報の収集、処理、加工を行い、全国情報ネットワークを通じた情報提供体制の整備を推進している。
また、一般住民に向けて迅速に情報提供を行うため、NHK等報道機関を通じた情報提供体制の整備も併せて進めている。
なお、平常時から河川及び流域に関する情報について、全国共通で使いやすく誰でもアクセスできる公開型河川情報データベースを構築し、防災情報を含む多様な情報の一般への提供を推進する。
2) 高度情報基盤の整備
洪水や渇水等の災害時には正確な情報を地域住民に提供し、被害の最小化を図るなど、的確かつ効率的な河川管理を行うため、関係機関との連携を図りつつ、新たな高度情報通信システムを構築し、高度情報の活用を推進する必要がある。このため、光ファイバ、河川GIS等の高度情報基盤の整備を推進し、さらに、光ファイバ収容空間を開放することにより、民間通信事業者の多様なネットワーク構築に資する。
また、河川水辺の国勢調査の結果について電子化をはかり、GISで利用できるシステムを構築するとともに、水文・水質に関する情報について、情報公開型データベースを構築し、インターネットによる一般への情報提供を行う。