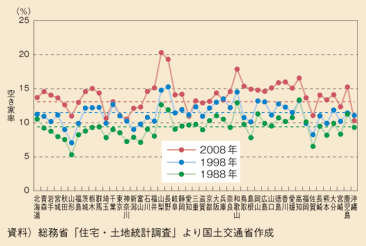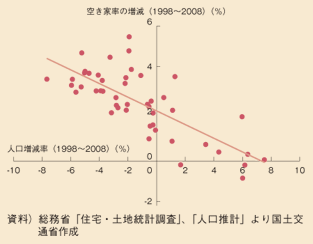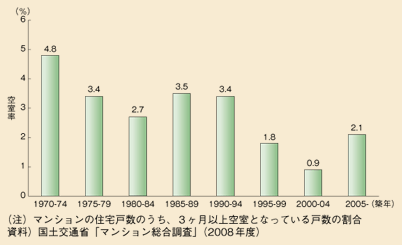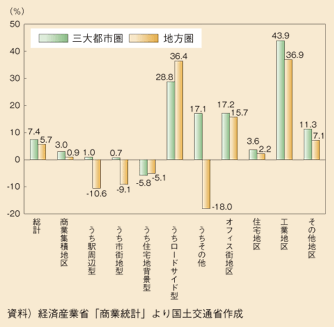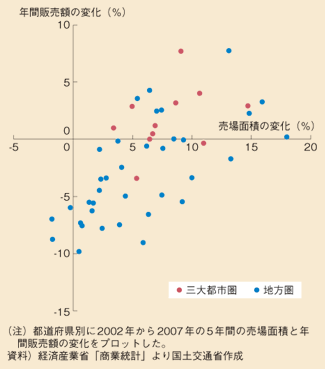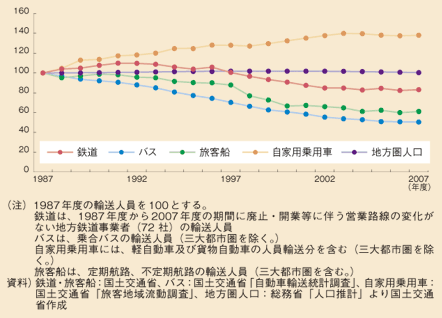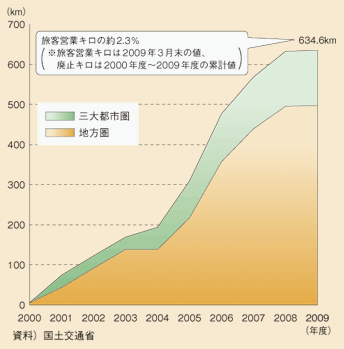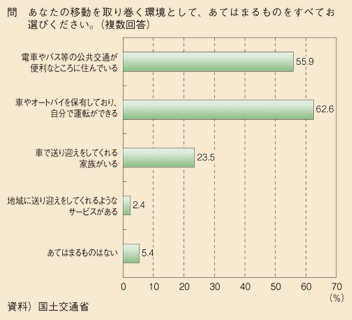2 地域を支える基盤の変化
地域に住む人々の生活を支えてきた各地域の様々な基盤、例えば住宅やまち、公共交通にも変化がみられる。
(空き家の増加)
人の生活のもっとも基礎である住宅については、個人の資産であるとともに全体でみればまちを形成する社会基盤でもある。
これまで住宅のストック数は一貫して増加し、1960年代後半以降世帯の数を上回っている。一方で、空き家率をみると、日本全体で1988年に9.4%であったものが2008年には13.1%となり、これまでで最も高くなっている。図表29は、1988年、1998年、2008年について都道府県別に空き家率をみたものであるが、全体として空き家率が増加するとともに、地域によりその水準や増加のスピードに差があることがわかる。また図表30は人口の増減と空き家率の増減をみたものであるが、人口の減少しているところで特に空き家率も増加していることがわかる。社会的な基盤でもある住宅が、人口減少により利用されなくなっている状況がうかがえる。
図表29 都道府県別の空き家率
図表30 人口の増減と空き家率
また、現在では4割以上の人がマンションやアパートなどの共同住宅に居住するが(注1)、図表31はマンションの空室率を築年代別にみたものである。建設から年が経つにつれ空室率が上がる傾向がうかがえる。
図表31 マンションの築年代別空室率
(まちの中心部の衰退)
個々の住居だけではなく、まちについても、特に中心部の空洞化が進んだ。商業機能についてみると、図表32は2002年から2007年(注2)の間の小売業の立地ごとの売場面積の増減をみたものであるが、特に地方圏で駅周辺型や市街地型の立地が減少するとともに、全国で、ロードサイド型やさらには工業地区への立地が進んだことがわかる。なお、図表33は都道府県別の小売業の売場面積と販売額の変化をみたものであるが、ほとんどの地域では売場面積が拡大している一方で、地方圏を中心に販売額が減少している様子がうかがえる。
図表32 小売業の売場面積の立地別の増減(2002年→2007年)
図表33 小売業の売場面積と販売額の変化
(公共交通の衰退)
人の移動を支える公共交通機関についても、地方圏を中心に衰退する傾向がみられる。
図表34は、地方圏における移動手段別の輸送人員数の推移をみたものであるが、鉄道やバスなどの公共交通機関の利用者が減少し、自家用乗用車の利用が増えていることがわかる。また図表35は、廃止された鉄道をみたものであるが、公共交通事業者が不採算路線から撤退することなどにより、特に地方圏で公共交通のサービスレベルが低下していることがわかる。
図表36は、移動に関する環境を尋ねている。6割以上の人が「車やオートバイを保有しており、自分で運転ができる」とし、また、2割以上が「車で送り迎えをしてくれる家族がいる」と答えているが、高齢者の増加や次節でふれる世帯構造の変化・単身世帯の増加を考えると、今後、自分で運転できなくなった時や送り迎えしてくれる家族等がいなくなった時について、移動手段の確保がより必要になると考えられる。
図表34 移動手段別輸送人員の推移
図表35 全国の廃止された鉄軌道の累計
図表36 移動に関する環境
(注1)2008年の住宅・土地統計調査によれば、居住世帯のある住宅の総数は約4,960万戸、そのうち共同住宅は約2,068万戸。
(注2)2007年11月に改正都市計画法等が施行されており、大規模集客施設の郊外立地規制が強化された。