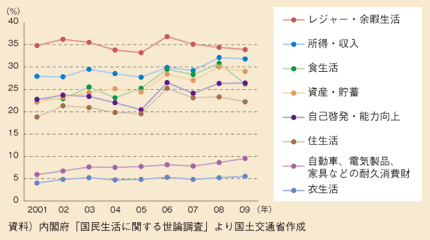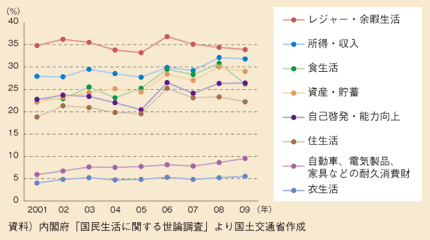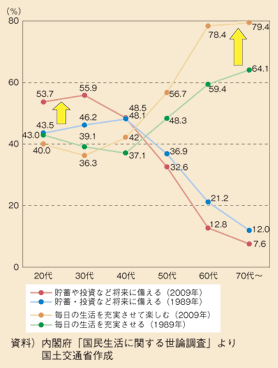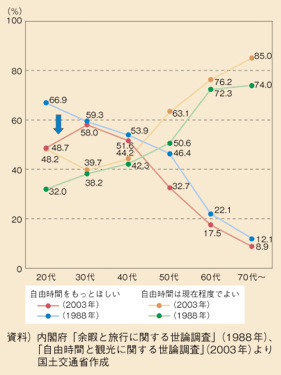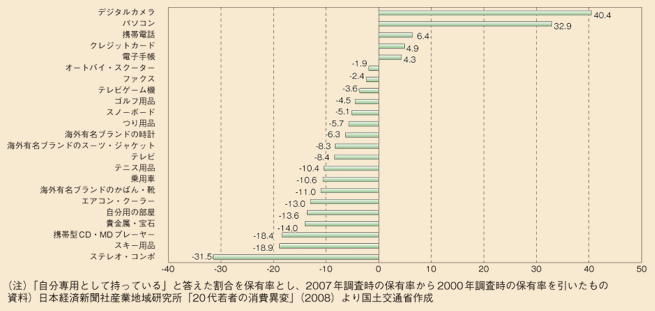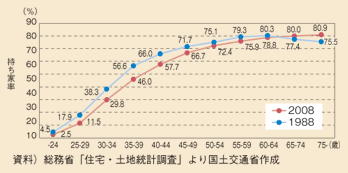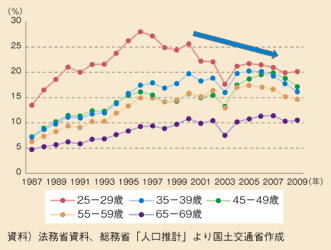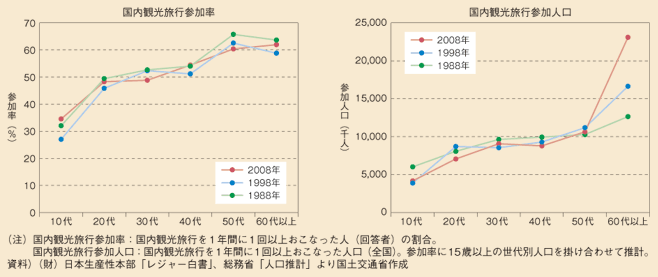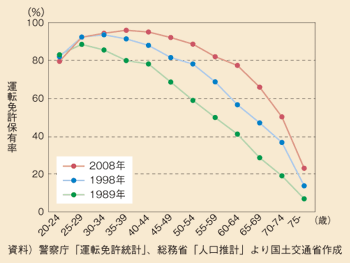2 変化する意識や活動
(変化する意識)
個人の生活に関する意識や時間の使い方に対する考え方も変わってきている。
図表47は今後の生活の力点について尋ねたものであるが、レジャー等が常にトップとなっている。全体として、生活の中でゆとりを求める意識が常に強いことがわかる。
図表47 今後の生活の力点
しかし、世代ごとにみれば、別の傾向がうかがえる。図表48は、貯蓄や投資など将来に備えるか、毎日の生活を充実させて楽しむかについて、世代別に2時点間で比較したものである。1989年と比べて2009年は、20代と30代で「将来に備える」が増加し、他方で特に60代以上で「毎日の生活を充実させる」が増加している。また図表49は、自由時間に対する意識について、やはり2時点間で比較したものであるが、1988年には若い世代ほど自由時間をもっと欲しいと感じていたものが、2003年では特に20代で減少している。若い世代で、将来に備える意識が強くなり自由時間の要望が弱まる一方で、高齢者では、毎日の生活を楽しもうとする姿勢が強くなっていることがうかがえる。
図表48 将来に対する意識
図表49 自由時間に対する意識
(変化する若者の生活活動)
若者の消費活動等の生活活動にも変化がみられる。
図表50は若い世代のモノの保有率の変化をみたものであるが、全般的に保有率が下がっており、モノをもたない傾向がうかがえる。図表51は世代別に持ち家率の推移をみたものである。全体の持ち家率はほぼ横ばいである中(注1)、30代後半を中心に比較的若い世代で持ち家率が減少していることがわかる。また、図表52は世代別に海外への出国率をみたものである。20代の海外旅行は、1990年代中頃までは大きく伸びたが、2000年代は特にこの世代が減少している。前述した意識の変化に加え、晩婚化の進展や伸びない所得、価値観の変化など様々な要因が重なって、若い世代を中心に消費等が変化している様子の一端がうかがえる。
図表50 20代若者のモノの保有率(2007年と2000年の比較)
図表51 世代別持ち家率の変化
図表52 世代別出国率の推移
(イメージが変わる高齢者)
一方で、高齢者の行動にも変化がみられる。
図表53は世代別の国内観光旅行の参加率と参加人口である。年齢が進むほど参加率は高くなるのは過去からあまり変わらないが、参加人口をみると高齢者で顕著に増加していることがわかる。高齢者が生活を楽しもうとする積極性は変わらず、それが高齢者人口の増加とあいまって参加人口を大きく増加させていると思われる。
図表53 世代別国内観光旅行の参加率と参加人口
また図表54は、世代別の運転免許保有率である。次に高齢期を迎える50歳代の運転免許保有率は84.9%であり、現在の60歳代の保有率71.9%と比べて高くなっている(注2)。これは、将来の高齢者世代は、現在よりも自分で移動する手段を持ち身動きが軽くなることが推測される。また、情報へのアクセスを考えても、例えばインターネットの利用率は、60〜64歳について、2003年の39.0%に対し2008年は63.4%と大幅に高くなっている(注3)。移動の面でも、情報へのアクセスの面でも、高齢者の自由度が増しつつあることになる。
図表54 世代別運転免許保有率
高齢者は、従来のイメージを変えつつあるとともに、その増加により普段の活動で存在感を増していることがわかる。
(注1)持ち家率は1988年61.1%、2008年60.9%(総務省「住宅・土地統計調査」より)
(注2)なお、運転免許保有者に占める65歳以上の者の割合は、1989年が4.2%であるのに対し、2008年は14.7%と約3.5倍となっている。
(注3)総務省「通信利用動向調査」(2008年)による。インターネット利用率とは、過去1年間にインターネットを利用したことがある者の割合