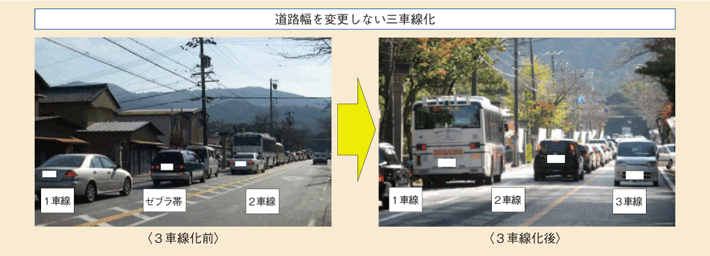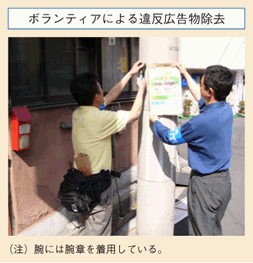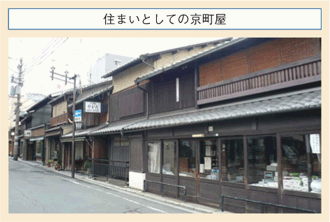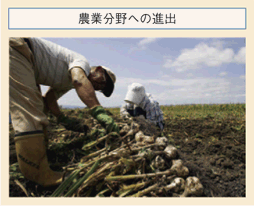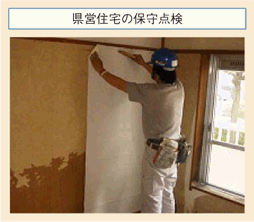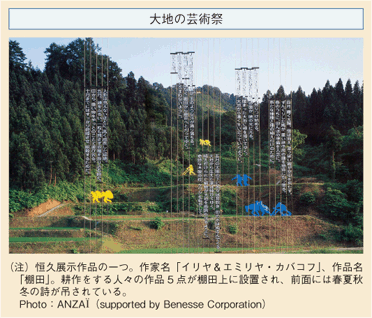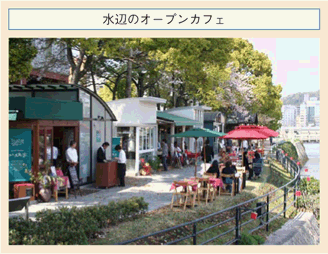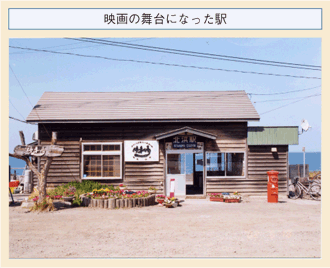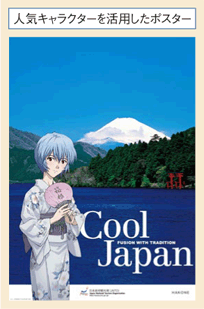1 地域で芽生える様々な取組み
(1)人口減少・少子高齢化社会を支える地域の工夫
1)既存のものを再構築して利用
厳しい財政状況においては、限られた資源を活用して効果を上げるという考え方がより重要になってくる。既存のものを見直し、再構築することで、コストを抑えた効果的な施策を行うことができる。
【官民共同運営によるコミュニティバス】
北海道当別町、約420平方kmの土地に約2万人が生活するこの町において、一般住民が利用できる路線バスは2路線23便に限られていた。一方で、地域にはこれらのバスの他に、医療機関や大学等による送迎バスなど、異なる主体が運営する路線が存在していたことに着目した当別町は、関係者に路線の統廃合を提案し、2006年4月より、提案に合意した関係者とともにコミュニティバス(乗合バス)「ふれば」の運行を開始した。これにより、一般住民が利用できるバスは8路線95便となり、利便性が大幅に向上した。
「ふれば」は行政と民間の共同事業であるが、行政の出資可能な予算は限られているため、運営においては様々な工夫が行われている。例えば、路線の統廃合の後も定期的に路線の見直しを行い、利用者の少ないものについては便数の削減を、要望が強いものについては便数の増加や路線の延長を行い、効率的な運行を実現している。また、退職まで大型車の運転手をしていた地元の高齢者を採用することで、人件費を抑制している。これは、「自分の経験を活かして地域のために貢献できる」と、雇用される側にも大変好評である。
これらの継続した努力の結果、運行経費は初年度から2008年度にかけて約100万円の削減に成功した。

【知恵と工夫による渋滞緩和】
三重県伊勢市では、伊勢神宮前の国道23号における慢性的な渋滞により沿道住民の生活等に支障があった。これに対し、道路の幅を広げる工事をすることなく、もともと2車線だった道路について、中央分離のゼブラ帯を除去するとともに路面標示を変え、3車線化するといった既存の道路の再構築によって対応した。この結果、道路の幅を広げる工事に比べ、10分の1程度の費用にて、通常数年かかる場合もあるこのような工事を1箇月にて終えることができ、短期間かつ低費用にて住民の円滑な交通が実現するなどの成果があった。また、年末年始やゴールデンウィークなど伊勢神宮への参拝客が極めて増大する時期にはパーク&バスライドも合わせて実施するなど、交通需要に合わせた対応を行っている。
2)当地にフィットした新しい仕組みを導入
さらに、地域の実情を把握しそれにフィットするよう仕組みを変えたり、新しい仕組みを導入したりすることにより、地域のニーズに効果的に応えることができる。
【オンデマンド交通】
長野県安曇野市は、市域約332平方kmに約10万人の人が暮らしているが、ごく一部の路線をのぞいて民間路線バスが廃止されているなど、公共交通の再構築が課題であった。このため関係者が協議会を立ち上げ、アンケート調査やワークショップにより住民の要望をまとめ、定時定路線運行とオンデマンド運行を組み合わせた乗り合いタクシー「あずみん」を導入した。オンデマンド運行では、事前の予約により自宅から目的地までなどを直接結んでおり、利用者の利便性は高い。一日あたり延べ約350人が利用し(2009年度の平均)、約8割は60歳以上であるなど、特に高齢者を中心に利用されている。
【子育てを支援する交通サービス】
子育てしやすい環境づくりに向け、子育てニーズに柔軟に対応した交通サービスを提供しているタクシーもある。香川県高松市では、2004年よりNPOとタクシー事業者が連携して、一定の研修を受けたドライバーがチャイルドシートを備えた車両で乳幼児を伴っての外出に対応したり、保護者の代わりに保育所へ送迎するなど子どもだけの利用にも対応したりするなど、想定される場面に応じたきめ細やかな対応を行ってきた。現在では、県外にもこの取組みが広まっており、子育て世代をサポートしている。
3)行政だけに頼らない支えあい
行政だけではきめ細やかな対応にはもはや限界がある。地域の内外の人が連携して、高齢者等の生活を支えたり、地域の活力を維持したりしていく必要がある。
【雪下ろしボランティア】
岩手県西和賀町は秋田県との県境に位置し、人口約7,000人、高齢化率約41%(2010年3月)のまちである。豪雪地帯にあり、高齢者世帯などの雪かきは大きな問題であった。それまでも青年会が一部で行っていたが限られた地域であったため、社会福祉協議会が事務局となり、雪かきボランティア「スノーバスターズ」を組織した。民生委員等の協力による対象世帯の把握、広報等による町民全体へのボランティアの呼びかけ、班の編成など、全町をカバーするような体制で活動している。
ボランティアには、町内だけではなく町外からの参加者も増えている。このような取組みは、現在では県内13市町村まで広まっている。
【耕作放棄地の新たな担い手】
耕作放棄地は、高齢化等による労働力不足などを背景に増加傾向にあり、担い手の確保が課題となっている。新潟県糸魚川市は、農地が中山間地域にあるなど耕作に不利な環境にあり、耕作放棄地は深刻な問題であった。このような中、地域で建設業を営んでいた企業が、工事量の少ない時期に保有する重機・資材や建設業に従事する人材等を活用して、耕作放棄地の復元や防止に取り組んだ。現在では、作業受託した田んぼや休耕田で稲作を始め、ナス、蕎麦、ブルーベリーなどを栽培している。この取組みによって、農地の荒廃に一定の歯止めがかかるとともに、中山間地域の棚田などが耕作されることにより、地滑り防止など防災面での効果も期待されている。
【違反広告物除去ボランティア】
市民が主体的に行動することで、町の景観を守ることが可能となる。広島市は、快適で住みよいまちづくりを目的として活動する市民団体の増加を受け、2003年10月、指定の腕章を着用した市民の手によって違反広告物の除去を行う「広島市路上広告物除去推進員制度」を創設した。これにより、迅速な広告物除去が可能になり、また、こうした活動を通じて市民の景観への意識が高まるにつれ、違反広告物は徐々に減少していった。その結果、制度導入時には約3万5千件除却されていた違反広告物が、2008年度には約4千件にまで減少した。
(2)困難を乗り越え地域に新たな活力
1)空いているものの活用
人口減少により空き家や廃校が増えており、これは地域の活力をそいでいる。見方を変えることにより、新たな利用が始まるとともに、それが外から人を呼び込むなど活力の基にもなる。
【NPOと協働した空き家バンク】
空き家の増加は各地で大きな課題となっているが、地方公共団体が、その地域の空き家を他地域の住民などに紹介する“空き家バンク”の取組みが始まっている。
佐賀県武雄市の若木町、武内町、西川登町は、市の中心部からは離れた田園地帯にあり、過去30年間で人口が2割以上減少し空き家や空き地が目立つなど、過疎化が進んでいる。このため武雄市ではNPO団体と協働して、空き家情報登録制度(空き家バンク)を開始した。市は、空き家を貸したい人・借りたい人を募集する窓口になるとともに、建築関係の技術者が中心となったNPOがその知見を活かして状況調査を行っている。NPOはホームページ上で物件を紹介するとともに、希望者との相談に対応するなど、貸し手と借り手のマッチングを行っている。これまでに10世帯が空き家バンクを利用して移り住んでいる。
2)これまで気づかなかった価値の利用
これまで気づかなかったものでも、何かをきっかけにその価値を再認識したり、また、別の地域の人にとっては非常に魅力的であったりすることがある。地域に新たな価値を発見して活力の基にする。
【地吹雪体験による観光振興】
青森県津軽地方は、冬の積雪が多く厳寒の地であり、特に地面に積もった雪が強風で舞い上がる地吹雪は、車の視界を奪うほどの“厄介者”である。この雪という北国の日常を、旅行のテーマの一つでもある非日常体験へと転換させた地吹雪体験観光ツアーが青森県五所川原市で行われている。
観光客は、まずモンペ、角巻といった昔から津軽に伝わる防寒服を着用し、白一色の真冬の津軽平野の雪原に降り立って地吹雪の中をひたすら歩く。ただでさえ強い風に、雪が舞い上がり1メートル先すら見えなくなる本物の地吹雪に驚くツアー客も多いという。今年まで23年続いているこのツアーは、特に台湾、ハワイといった南国からの観光客が多く、体験者総数は一万人を超えている。
【町家がもつ価値への再評価】
町家は、日本らしい生活の面影を残す住居であり、特に京都市内には約5万件の京町家が現存しているといわれている。しかし、その古さ、気密性の低さなどから町家は不動産査定額がほぼゼロとみなされ、開発が進む京都市にあっては年間約1000件ベースで取り壊されてきた。他方で、町家は、気密性の低さが風通しの良さとなって、住む人々に四季の移ろいを感じさせ、雨音や土の匂いを運ぶなど、その住まいは日本古来より培われてきた感性を残すものである。
そこで、2002年から京都市のNPOが中心となって、近代的な暮らしにあっては気づかれにくい“京町家に住むという価値”を広めるべく活動を行った。その良さを伝えるのみならず、町家一つひとつがもつ特徴や、実際に住むにあたっての費用や改修等へのアドバイスを提供するなど町家暮らしのサポーターとなり、約120件の契約へとつなげた。
この結果、“京都に住むなら町家がいい”といった考えの人々も徐々に増え、一般住宅における快適性を超えた価値が再認識されつつある。また、町家を改築したカフェや旅館が観光客を惹きつけたり、町家の風情が景観としてまちの魅力になったりと、新たな活力源ともなっている。そして、京町家は中古住宅市場で評価されるようになるなど、経済的価値も見直されるに至っている。
3)技術をもとに新たなニーズに対応
地域の産業は厳しい状況にあるが、その技術、ノウハウや人材を活かせば地域に貢献することもできる。
【建設業の地域総合産業化】
地域に根ざした建設業がその技術を活かして、農林水産業や公営住宅の管理など他の分野に進出している動きがある。
北海道旭川市の建設業者は、緑化工事で培った土壌改良技術を活かし、ニンニク生産者の悩みである連作障害に強く、そして、寒冷地でも耕作可能なように、−25度にも耐えることができる無農薬有機ニンニクの栽培に成功している。
また、福島県福島市では、建設業者がNPO法人と連携して、県営住宅等の保守管理・修繕や、駐車場管理などの業務を行い、建設業の技術力や管理ノウハウを活かして地域に貢献している。このように、各地では、既存の技術、ノウハウや人材を活かして地域の地場産業がきめ細やかなニーズに対応する取組みが行われている。
(3)新しい成長を築き元気を取得
1)生活にプラスアルファをもたらす大小のアイデア
ちょっとした・これまでにないアイデアによって新しいことが生まれ、地域や人々の生活にプラスアルファをもたらすことができる。様々な分野で大小の取組みが行われている。
【大地を舞台にした芸術祭】
棚田やブナ林が広がる里山といった日本の原風景が残る越後妻有地方(新潟県十日町市、津南町)では、3年に1度アートを探しながら里山を巡る「大地の芸術祭」が催され、人々を惹きつけている。第4回展となる2009年の芸術祭は、NPOと自治体が共催し、40の国と地域358組の作家により365作品が出展され、入込み客数約38万人、経済波及効果35億円という盛況ぶりであった。
運営は、集落の住民はもちろん、首都圏の学生等を中心としたサポーターが大きな力となり、作家とともに地域に入り込み協働で作品づくりを行うなど交流を深めた。アートの表現方法も、13の廃校が舞台となったりブナ林という空間に作品が展示されたりなど、越後妻有らしいものとなっている。また、恒久展示作品も150を超え、廃校美術館も開設されるなど、通年での誘客も行われている。さらに、アジア・欧米等の人々や機関と各集落とが芸術祭以降も交流を深め、アートの持つ力を通して地域を盛り上げようと取り組んでいる。
【水辺のオープンカフェ】
市街地に占める水面積の比率が約13%にも及ぶ広島市、中心部を流れる京橋川・元安川沿いでは、河川空間を活かすため、規制緩和により民間事業者がオープンカフェを設置している。
川辺の木々など周辺に調和するようカフェを設置したり、一年を通じて遊歩道をライトアップしたりすることにより、水辺に心地よい空間が創出され、テレビや新聞等でも話題となり、広島市の新しい観光スポットとして定着している。遠方からも人々が訪れるようになり、かつて利用者がまばらであった河川の周辺に交流やにぎわいが生まれた。また、民間事業者が周辺河川敷の清掃等を行い河川美化に貢献しているところである。
【上毛電気鉄道サイクルトレイン】
群馬県前橋市を走る上毛電気鉄道は、利用者にとって駅から目的地までの移動手段が不便である状況を踏まえ、2003年、自転車をそのまま持ち込むことができるサイクルトレインを実施した。
当初は限定的であった時間帯や利用可能な駅は徐々に拡大され、2005年4月には全駅で、ほぼ終日利用可能となった。導入時には約500人にとどまっていた利用者は、2009年度には約3万人にまで増加した。また、有人駅においては無料レンタサイクルも合わせて実施するなど、総合的な取組みが行われている。
2)新しいまちへの取組み
既存のものを活かしつつ新しいまちを形づくり、暮らしやすく豊かな生活空間を創造していく。
【人にやさしい、歩いて暮らせるまちづくり】
住む人の視点にたったまちづくりによって、人口減少・少子高齢化に備えるとともに、誰もが快適に暮らすことができる環境づくりが可能となる。
富山県富山市では、これまで、郊外開発により薄く広い市街地が形成され、中心部の人口密度が低下するとともに公共交通が衰退し、車を自由に使えない市民が生活しづらくなり、都市の活力が低下することが懸念された。
このため、公共交通を軸とした“拠点集中型”のコンパクトなまちづくりの実現のため、公共交通の活性化とまちなか居住への支援により沿線人口密度を高めるとともに、商業、業務、文化等の都市の諸機能を集積させることにより、過度に自動車に依存することなく、徒歩や自転車、公共交通などを組み合わせて生活できる歩いて暮らせるまちづくりに向けて、総合的な取組みを行っている。
特に、まちづくりの軸となる公共交通は、衰退した既存路線をLRT(次世代路面電車)化したり、環状線化を図ったりすることで、便利で魅力的なネットワークづくりに取り組んでいる。
また、まちなかにて自転車の貸出しを行うコミュニティサイクルも始まっており、新しいまちづくりへの取組みが行われている。
【駅と直結した病院や保育所】
東急電鉄の大岡山駅(東京都大田区)では、駅の上の空間を有効利用して病院が開設され、駅構内から出ることなく来院できるようになっている。さらに、壁面緑化を行うなど、景観や環境にも配慮し、周辺のまちづくりとの調和も図られている。また、小田急電鉄喜多見駅(東京都世田谷区)では、送迎に便利な駅近くの高架下を活かして保育所が設置され、時間的ゆとりのない子育て世代等のニーズにあったサービスが提供されている。
このように、鉄道駅を単なる通過点としてではなく、人々が集まる拠点と捉えて生活機能を集積することで、利便性を高めることが可能となる。
3)魅力や能力を見出して外へ発信
地域の資源を見出して積極的に外部に発信し、活力を取り込んでいく。
【網走の中国人呼び込み】
中国で北海道ブームがおきている。2008年12月に公開された映画「非誠勿擾」(邦題「狙った恋の落とし方。」)が中国で大ヒットした。この映画の舞台の一つである北海道網走市を訪れる中国人は前年に比べて急増した。映画に取り上げられることにより、これまで観光資源としてあまり注目されていなかった場所にも、中国人観光客が訪れるようになった。
これを機に、網走市は映画の舞台に関する中国語の看板の設置やパンフレット等の作成等をおこなった。また、一時的なブームで終わらせないために、自治体が中心となって網走市に住む中国人とともに、中国人を惹きつけるような地域づくりについて検討し、映画の舞台とともに宣伝を行った。この結果、中国人が作成する北海道専門誌において、映画の舞台以外の風景等も紹介されるようになり、地域の魅力をより一層海外へ発信することができた。
【アニメを利用した観光戦略】
神奈川県箱根町、この町が世界的に有名なアニメ(新世紀エヴァンゲリオン)の舞台になっていることに注目した箱根観光協会は、2009年6月、アニメの印象的なシーンの舞台となった場所が一目で分かる地図を作成した。この地図は、テレビ、新聞等で話題になった。観光協会は、2010年3月より、日本政府観光局(JNTO)と協力してアニメの人気キャラクターを活用したポスター、マップ等による海外への宣伝を始めており、広く世界から人を呼び込んでいく効果が期待される。